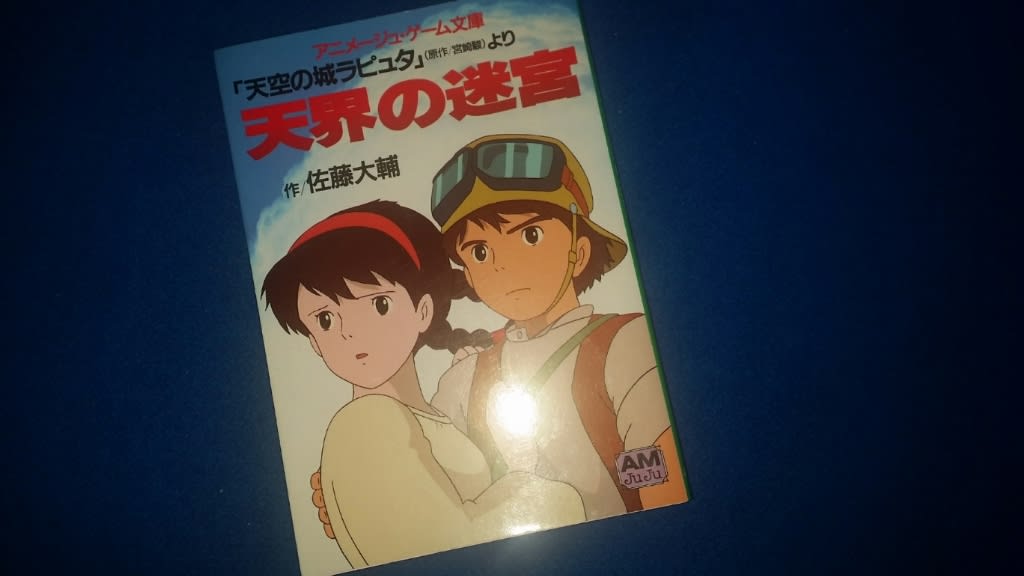●Wikipediaで調べるの禁止。ネタバレの嵐だから。
●最近、『大砲とスタンプ』を読み切った。左のリンク先のには第一話が載っている。
これは速水螺旋人の代表作の一つになるに間違いない。
●東欧、トルコっぽい地域での兵站(=補給)軍に所属する女性が主人公のマンガ。
ちなみに作者は現在のウクライナ侵攻を嘆き、ロシア批判をしている。
●兵器や戦争、工業技術などに詳しくないけれど、1950年~1960年くらいが舞台かなあ。
一話につき、1ページの架空の兵器の紹介から推理すると。
この解説が詳しく、面白い。
コミックスでは文字が小さいので、1ページでは見にくいと思ったのか、2ページで紹介しているコーナーもある。
●初めは一話完結型だが、9巻あるので、徐々に大河ドラマ調となってくる。
●決して戦争賛美マンガではなない。
ユーモアのあるマンガである。
●戦争の悲惨さ描いている場面も多いけれど。
●この時期にこの地域を舞台にしたマンガに、ましてや戦争を舞台にしたマンガに抵抗感がある人も多くいらっしゃると思うが、おすすめのマンガである。