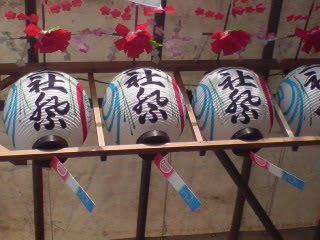(黄菖蒲 赤塚植物園)
釈迦堂の夕べふちどる黄の菖蒲
黄菖蒲の憂しと思ふはわが影や
昨日せっかく万太郎の句を揚げたので少しお勉強を・・
①秋風や水に落ちたる空のいろ
②短日やされどあかるき水の上
③短夜のあけゆく水の匂かな
④ゆく年や草の底ゆく水の音
⑤古暦水はくらきを流れけり
この五つの句に共通する水以外のものが有ります
お分かりでしょうが、それは明かりです。
これも常套でありながら、こうして詠みわけが出きる
のは写生眼に他ならないのでしょうね。
カメラレンズと違って、人間は心と眼と両方のレンズで行う
ために、その写生は立体的になると思うのです。
机上、机前俳句というのがありますが、それがけして悪い
わけではなく、過去の体験(既視)を元に頭の中で組み立てる
という作業をします。結果で言えば、机上であろうと、写生で
あろうと秀作であれば良いのです。
机上が駄目なら、病床俳句も駄目ということになります。
これが言いたかったことですが・・・話がそれました。
試しに①~⑤の季語を入れ替えてみましたが、同じ水と
明かりを詠んでも季は動かないのです。それは確かな
作者の眼前の景色を読者に伝えることが出来た秀作
だからでしょう。ではどこが秀でているのか?
それは措辞が決め手だと思うのですが、どうでしょう?
① 水に落ちたる空の色
色が水面に落ちたという発見。
② されどあかるき水の上
水の上とはなんでしょう?水面でもなく、中空でもない空間
を作者は見たようです。
③ あけゆく水の匂かな
「におい」は「匂い」であるように「い」という送り仮名がありま
すあえてそれを取り去り「水の匂」という一個の物にしました
④ 草の底ゆく水の音
草の底。この措辞が私には一番インパクトがありました。
⑤水はくらきを流れけり
「水は暗いところを流れた」と解釈するのが普通です。
しかし季語の「古暦」でその明暗でないことを暗示しています。
このように措辞こそ、昨日のブログに書いた「語彙の蓄積」
の上にあるのです。
以上の事は私の体験的な感想で、俳論ではありません。