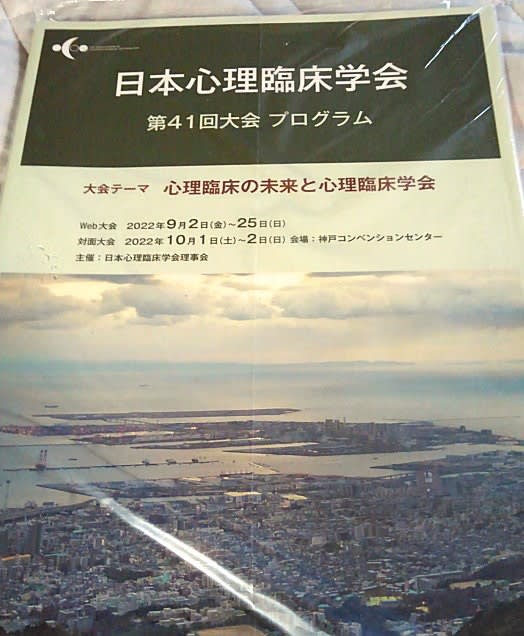お盆休みに、親友の山下と飲んだときのことだ。

彼のまだ十一ヶ月の長男がつかまり立ちやハイハイするようになったという微笑ましい話から一転して、彼の顔色が曇った。
「あのよ・・・。なんだかムスコがよ、最近、ぶきみでなぁ・・・」
「エッ、なんで?」
「毎晩、十二時過ぎるとパッチリ目ぇ開けてよ、
もそもそフトンから這い出すんだ」
「・・・んなの、どってことねーじゃん。
赤んぼのときは、よくあるって。
ウチだってあったもん」
「そっかなぁ・・・。
でもよ、ウチのは最近、毎晩だぜ」
「えーっ? 二、三回じゃねーのか」
「そうなんだ。
だからよ、カミさんも気味悪がって・・・。
医者に連れてこーか、って言うんだ」
「ほぉぉ・・・。
なんだか、気持ちワリーな、たしかに・・・」
「だろッ・・・」
「・・・んでも、ハイハイしてどこまで行くの?」
「いやぁ、ふとん抜け出ても、せいぜいフスマにぶち当たってそっから先にゃ行けないんだけど・・・」
「ふーん・・・」
「あ、そうだ。
いっぺんだけ、フスマ蹴ったことあんだよ」
「ほんとかよー?」
私は赤ん坊が小ちゃな足でキックしてる様を思い浮かべると、思わず笑ってしまった。
「ほんとだって」
山下は笑ったが、嘘じゃなさそうだった。
「なんで、フスマ蹴ったんだろ?」
「知らねーよ、んなの・・・。
おまえ心理屋だから、なんか知らねーの?」
「ま、乳幼児心理学っつーのはあるけんども・・・。
フスマ蹴っぽるヤヤコの話なんざ聞いたこともねーべさ」
山下はゲラゲラと笑った。
「んだね・・・」
話は、不気味なんだか、笑い話なんだか酔いも手伝って、段々ワカンナクなった。
「じゃよぉ、こーすべー」
「ん? どーすんの?」
「今夜さぁ・・・、ヤヤコが這い出したらよ、おめえも寝てねーでさ、フスマをよ、いっぺん開けてみれッ」
「あぁー。なるほいど・・・」
「そしたら、ヤヤコのやろ、どごさいぐのが、わがっぺした・・・」
酔いが回ってきたのか、ふたりとも段々と呂律がまわらなくなり地金がはがれて田舎ことばが出てきた。
「んだなすッ!」
山下は単純に感心したかのように酔いに濁らせた目を一瞬、キラリと光らせた。
「今晩、やってみっぺ・・・」
次の週の土曜。
私たちは、ホルモン焼きのうまい店で待ち合わせた。
「どしたい? お坊っちゃん」
私は開口一番に尋ねた。
気のせいか、山下はいくぶん緊張したような面持ちで言った。
「あのよぉ・・・。やったのよ」
「おう」
「そしたらよ、あいつ・・・
ハイハイ、ハイハイ、ふすま超えて行くんだわ」
「ふんッ」
「廊下ぁ、真っ暗なのに、平気でハイハイ行くのな・・・」
「ほぉ」
「で、行くとこまで行かせようと、もう手ぇ出さねーで後ろにくっ付いていったんだ」
「ふんふん。ほんで?」
「そしたら、玄関の方に行くのな。
真っ暗なんだぞ。玄関だって・・・」
私は段々と面白くなってきて、からだを前にのり出した。
山下は、目の前のビールを一口流し込んだ。
「そんでね・・・。
玄関のタタキにおっこちると大変だから、真うしろから、いつでも手ぇ出せるように構えてたらよ・・・」
「はん」
「あいつ、何したと思う?」
「さあ・・・なんだべ」
「いいから、当ててみれッ」
「んだよぉ・・・。クイズはいいからよ」
「ハハハ・・・。吠えたんだよ」
「えーッ?! ガオーってか?」(笑)
「ちがわいッ!」
山下も噴き出し笑いをした。
「エテカーッ! ・・・って」(笑)
「なんじゃ、そりゃーッ!」
私は松田優作節でツッコンだ。
「な、笑うだろッ!
なにもんやねん、おぬし・・・って、俺だってツッこんだもん」(笑)
「なんなの? そのエテコーって・・・。
猿公のことかいな?」
「違うって。エテコーじゃなくて・・・
エテカ、エテカー・・・っつうのよ」
「エテカぁ・・・?
ナスカの宇宙人の子か? おまえんとこの」
「違う、っつうの」(笑)
「ほんで、どーしたの?」
「なんだか、ぼっこれテープみたいに、エテカ、エテカ、ばっかり言うもんだからワケわかんなくて、
『はいはい。
もう、お寝んねちまちょーね』
って、ふとんに連れてったんだ」
「バッカだなぁ。おめぇ・・・」
「えっ、なんでよ?」
「その先、続きがあったんじゃねーの?」
「なんの続きよ?」
「だからよぉ、ヤヤコがまだなんか言いたかったか、どっかへ行きたかったかの・・・」
山下は少し呆れたような顔をして言った。
「だって、お前、真夜中なんだよ。
俺だって、会社あるもん・・・」
私は笑った。
「だよな・・・。俺みたいな暇人じゃねーもんな」
「んだでば・・・」
焼き上がったホルモンをコリコリ噛りながら山下がふと洩らした。
「そーいやよ・・・
あいつ、玄関の先っつーか、外の方向いて、吠えてんだよ。目線がな・・・」
「ふーん。
じゃ、外に出ていきたいんだべ、たぶん」
「んなこと、あるわけねーべ・・・」
「なんで?」
「んだって・・・」
そう言うと、山下は急に、ブルッと身震いした。
「なんだか、気持ちワリーッ」
「何が?」
「んだって・・・なんだかよぉ、玄関の外さ誰かいたら、どーすんだば・・・」
「はぁー。なるほいど・・・。そっかぁ・・・」
「なにがよぉ・・・」
山下は独り合点している私の顔を怪訝そうにのぞいた。
「あのよぉ、お前、また、実験してみる気ぃ、ねーかい?」
「ウチの子でか?」
「んだ」
「なにをーッ?」
私はその場で実験デザインを語って聞かせた。
「あのね。お前さ、会議用のボイス・レコーダー持ってんべ」
「ああ」
「それでさ、今夜もヤヤコ追跡して、録ってほしいのよ」
「吠えてっとこを?」
「んだんだ」
「どーすんだい?」
「心理学の研究に使うんだべさ」
「ちゃっかりしてからに・・・。
ウチのセガレ実験に使うてっか・・・」
「んだんだ。(笑)
今日は奢っからさ・・・」
山下は快諾とはいかないまでも乗りかかったナントカで、やってみると言った。
サンプリング・データの回収は、また土曜の晩だった。
例によって寿司屋で飲んでいた。
「ほら、これ・・・」
山下はレコーダーを通勤バッグから取り出した。
「どうだった?」
「んー・・・」
と言ったっきり、彼はコハダを一貫パクリとやった。
「ちゃんと入ってるけんど・・・。
なんだか、こんどは違うのよ・・・」
「なにが?」
「エテカじゃなかった。ゆんべのは・・・」
「でも吠えたんだろ?」
「おお。吠えた」
「なんて?」
「なんだか、よくわかんねーの。
だから、あとで、聞いてみれッ」
「ほーん。そりゃ、楽しみだない」
山下は寿司とビールを交互に口中に放りこんだ。
「荒木兄すごむ・・・」
「はーッ? なに言ってんの?」
「いや、ゆんべのが・・・アラキアニスゴム・・・って
俺には聞こえたんだな、これが・・・」
「せがれのセリフか?」
「んだ」
「ほだにハッキリべしゃくったのか?」
「いや・・・。なんとなく、そー聞こえるんだわさ。
荒木のアンちゃんが凄んだ・・・って、覚えやすいべぇ」
「なーるほいど」
目の前のカウンターに私の好物の煮穴子がトンと置かれたので、すかさず手を伸ばした。
「ほいで、おめさ、玄関開けんかったの? やっぱし・・・」
山下は、鼻でフンと笑うと
「なんだか、やっぱおっかねぇんだわ・・・。
なんでだべ・・・」
「このやろ。臆病なんだべぇ」
「ほだず・・・。おら、オクビョーだず。
んだげんと、真夜中に、赤んぼのくせして、ほんとに誰か呼んでるみてーなんだもん。
目線がよぉ、ちょーど人の顔のあたりなんだず。
気持ちワリーぞ、おめぇ・・・」
翌日、私は講義の合間に研究室のパソコンにさっそく録音データを取り込み音声解析ソフトを駆使して、あーでもない、こーでもない、と試行錯誤していた。
その時、ノックの音がした。
院生の奈保子が修論の下書きを持ってやってきた。
「先生。どうにか、やっとゆうべ書き上がりました」
「あ、そ・・・。ちょっと待っててね・・・」
と言ってマウスを何気なくクリックした。
すると、突然、パソコンから子どものような叫び声が出た。
「もう しないからッ!・・・」
「ウワーッ! なんですか? 今の・・・」
奈保子がビックリして言った。
私もドキンとした。
慌てて慌ててパラメーターを確認すると「逆行」発声の操作をしたらしい。
再度リターンすると
「もうしないから・・・」
という女の子の声がハッキリ聞き取れた。
私は奈保子にも確認した。
「そう言ってるよね・・・」
「はい。そう聞こえます・・・。
けど、何なんですか? これ・・・」
私はハッとして目の前のホワイトボードに
「MOUSINAIKARA」
と横文字で書いてみた。
奈保子がそれを声に出して読んだ。
「モウシナイカラ」
「じゃ、反対から読んでごらん」
「あらきあにすおむ」
「そう・・・。
荒木兄凄む、じゃなかったんだ」
私はすかさず赤いマーカーで
「ETEKA」
と書いてみた。
そして背筋がゾッとした。
「エテカ・・・?
なんです、これ?」
奈保子は不思議そうな顔をした。
「反対に読んでみな」
「あ・け・て・・・」
そう。
そうなんだ・・・。
「あけて。あけて。
あけて。あけて。
もうしないから・・・」

私は奈保子におかまいなしに、すぐに山下の会社に電話を入れた。
「どしたの?」
のんびりしたその声とは正反対に私は高ぶった声で訊いた。
「お前んちってたしか借家だったよな」
「そうだよ」
私も彼も、職場では決して方言を使わなかった。
「あのさ、前に住んでた家族って知ってるのか?」
「ああ」
「どんな?」
「叔父さん夫婦だよ。今は、別のところに新築したから移ったけど・・・」
「叔父さんちに子どもいたか?」
「ああ。いたよ三人」
「死んだ子っていたか?」
「死んだ子ぉ・・・? いねーよ。んなの・・・」
「そっかぁ・・・」
私は当てが外れてちょっとガッカリした。
私の突飛な空想はどうやら空振りに終わったようだった。
「あっ・・・
あのな、そーいや、叔父さんたちの前にも、別な夫婦が住んでたんだよ・・・」
受話器の向こうで語る山下は、私の推理小説まがいの空想なぞ、想像もつかないはずであった。
「ほんでな・・・、たしか、まだ三才くらいの、小っさい女の子がいたんだけど、病気で死んだんだって・・・。
いや・・・。
近所の噂では、折檻っていうの?
酷かったらしいぞ。
今なら児童虐待か・・・。
なんでも、真冬でも、裸足で玄関の外に、閉め出されたりしたらしいぜ・・・。
あんがい、病死じゃなく凍死だったりしてな・・・
アハハ・・・」

*