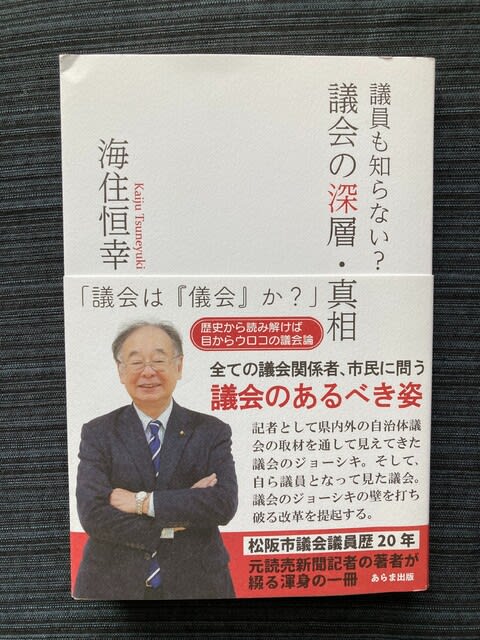ノーベル文学賞を受賞した韓国の女性作家、ハン・ガンさんの『すべての、白いものたちの』を読み終えた。書店で訊いたら、「ウチにはこれしか置いてないです」と言われて買って来たが、この本が受賞作品なのか分からない。
読み始めて、頭が混乱した。難しい言葉は無く、とても読みやすいのに、何が何だか分からない。まるで、詩なのだ。1ページから2ぺージごとに書かれた詩を読み進むような感じで、どうなるのと思いながら読んでいった。
最後まで読んでみて、これは詩の形をした小説なのだと理解できた。この作品を書く前に、執筆していたという『少年が来る』という作品を読んでみたい衝動に駆られた。作者があとがきに、「(『少年が来る』)が無事に刊行された後、しばらくどこかへ行って休むのはよさそうに思えた」と書いていたからだ。
それほど、心血を注いて書かれた作品を読まないことは無いと思った。『すべての、白いものたちの』には、韓国だけでなくポーランドの街の風景も出て来る。『少年が来る』は、韓国の民主化を象徴する「光州事件」を扱ったものらしい。
ポーランドの街は、ナチスドイツに破壊されたワルシャワのようだが、生まれ変わっている。今、韓国は大統領支持の人々と、野党を支持する人々に二分されている。GDPでは日本を抜いた韓国なのに、国の行先は混とんとしている。
アメリカもヨーロッパ諸国も、自国優先を主張する人々が多勢になってきている。みんなで仲良く助け合っていこうと、ならないのはどうしてなのだろう。ハン・ガンさんはこの世界をどう見ているのだろう。
『すべての、白いものたちの』は、詩のような展開だけど、哲学的でもある。「しなないで、しなないでおねがい。それを力をこめて、白紙に書きつける。死なないようにと。生きていって と」。
詩のような形の小説。小説家志望の中学からの友だちに読ませたい。