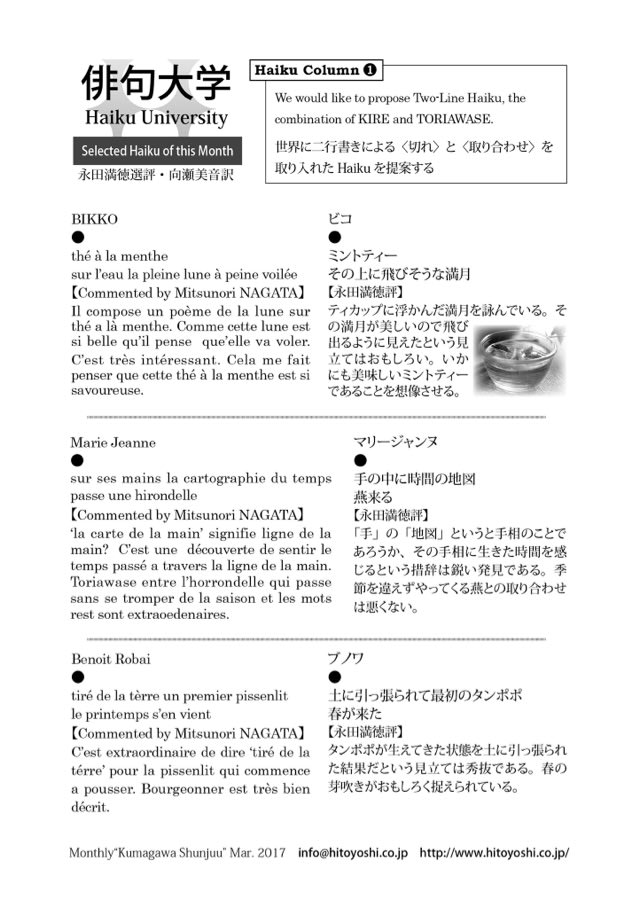〜俳句大学 Haiku Column 「今月の秀句」①〜
『くまがわ春秋』(2017年3月発行)に俳句大学 Haiku Column 「今月の秀句」の連載を開始しました。
Facebook 俳句投句欄
Facebook Haiku Column
今月の秀句
Selected Haiku of this Month
世界に二行書きによる〈切れ〉と〈取り合わせ〉を取り入れたHaikuを提案する
We would like to propose Two-Line Haiku ,the combination of KIRE and TORIAWASE
永田満徳選評・向瀬美音訳
Selected and Commented by Mitsunori NAGATA/Translated by Mine MUKOSE
①
BIKKO(ビコ)
●
Thé à la menthe
sur l'eau la pleine lune à peine voilée
ミントティー
その上に飛びそうな満月
②
Marie Jeanne(マリージャンヌ)
●
sur ses mains la cartographie du temps
passe une hirondelle
手の中に時間の地図
燕来る
③
Benoit Robail(ブノワ)
●
Tiré de la terre un premier pissenlit
le printemps s'en vient
土に引っ張られて最初のタンポポ
春が来た