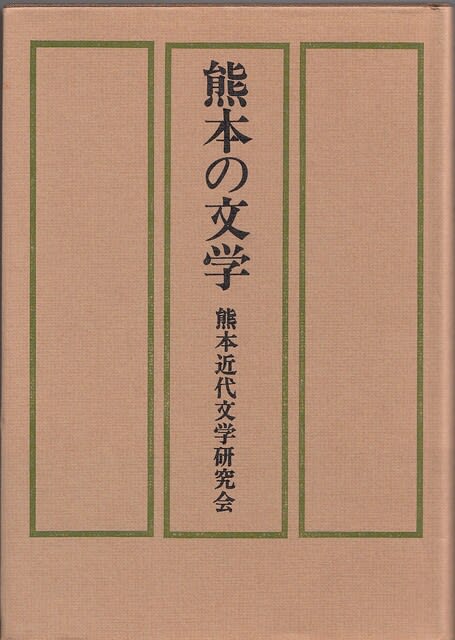柴田翔『鳥の影』論
(初出 「方位」10号 三章文庫 1986.12)
永田満徳
初めに
「烏の影」は、昭和四十六年十一月に筑摩書房より刊行された作品集『鳥の影』の巻頭作品である。初出は文芸雑誌『人間として』(昭和四五年三月・筑摩書房)であるが、この雑誌は現代社会とそこに生きる人間の追求という課題をになって発刊されたものである。時期としても現代の問題が最も先鋭化した時期で、三島由紀夫の自決とそれがもたらした問題、公害とそれが人類に及ぼす影響の問題、それに大学の制度改革を叫ぶ全共闘運動の問題などの切実な問題が重なり起こっている。「鳥の影」の魅力のひとつは、柴田翔のその他の作品にも云えることだが、登場人物のすべてに現代という時代の刻印が色濃く刻み込まれていることである。それは、柴田翔の文学姿勢そのものの中にみとめられることで、「柴田翔が作品で追求する課題は、時代そのものの、すなわち私たち自身の課題である」(真継伸彦『立ち盡す明日』解説、新潮文庫)からであり、さらに云えば、「作家柴田翔氏が現在と現実を深く受けとめている」(大橋健三郎『燕のいる風景』解説、新潮文庫)からに他ならない。
一 作品について
「鳥の影」は破滅小説である。その中で横切る〈鳥の影〉は、同期のトップを切って課長代理に昇進した第一線級のビジネスマン則雄一家の破滅を象徴している(1)。主人公則雄がエリートの常道をいとも簡単に踏みはずして破滅する過程は次のように五つに箇条書きすることができる。
① 級友山本の誘いで「潮田古稀祝賀会」に参加する。
② 潮田の通夜に出席した夜信江と出合う。
③ 信江と再度の交渉をもつ。
④ 街で出合った少女といっしょに連れ込み宿に入いる。
⑤ 逮捕後、自分の行為を素直に述べて自殺をする。
なお、この小説はこのように、週刊雑誌の特別記事に掲載されてもおかしくないような、ある意味では通俗的でありふれた筋書きになっている。そこで、柴田翔のその他の作品についてではあるが、大岡昇平が「人物は類型的、筋は通俗的」(『朝日新聞』夕刊、昭42・6・29)だと批判しているのも一概に否定できない。だが、〈現代の知的エリート、知識人の苦悩を努めて描こうとする柴田翔の文学姿勢にこそ、福永武彦同様「こういうロマネスクな小説を書こうという意志は認めてやりたい」(『群像』創作合評、昭40・7)という気持ちを持っている。
柴田翔は、主人公則雄の〈自己破滅〉が性格破綻や金銭的トラブルによるものでなく、あくまでも正常な知的エリートのそれであったことを強調して描いている。そして、ここで特に注目したいのは、則雄が本来、理智的で、どちらかというとニヒルな人物であって、時として兆した心の動揺不安までも自分の心の「弱さの反映にしか過ぎない」と割り切るような「得体の知れぬ不安にかかずらわるのを好まない性質」だと規定されているところである。にもかかわらず、その則雄は高校の恩師潮田の古稀祝賀会に向う途次、行手に立ちはたかる母校の体育館を見たとき、「さびた鉄骨がむき出しに並んでいるその様子に、感動とも不安ともつかない感情に襲われ」、〈建物〉に対する初めての〈不安〉を表明することになる。これはさらに「何故今日の会合のことを覚えていたのだろうか。少し早足で、新しい生徒集会所への道を急ぐ今、則雄はふと不安にかられるような感じで、そのことを考えた」ことと連関していて、〈不安〉の原因が潮田の祝賀会への参加にあったことはまちがいない。従って、今まで通り流れ始めた生活の「平穏さのなかで則雄自身もよく気づかぬうちに、あの祝賀会の日以来彼の心の底にきざしたある種の不安めいたものは、次第に着実に拡がり始めていた」というのも当然であって、〈建物〉に対する当初の違和感〈不安〉は潮田の古稀祝賀会への参加が契機となって拡大されつつあることを証明している。それはそして、則雄がのちに現代杜会の完全なアウトローになったときには〈建物〉そのものが〈絶望〉の象徴となって、「数知れぬ自動車が流れる広い通りをへだてて、彼が十数年を過ごしてきた会社の高い、明るい、大きな建物が、晴れた秋の午後の光のなかに、棲惨な美しさをもって輝いていた。彼は、その美しさの前に息を呑んだ。それは彼をはねつけるもの、彼にとって完全に無縁なるものであった」というように決定的な瞬問を向えることになる。このように、現代社会に屹立する〈建物〉に対しての〈不安〉の拡大が則雄の自己破滅の伏線として、あるいは象徴として描かれているのである。
二 自己破滅の原因
それにしても、誰しも「鳥の影」を一通り読み終えて感じることは、順風満帆にエリートの道を進んでいた主人公がなぜあのようにあっさりと破滅しなければならなかったかという疑問であろう。
そこで、まず考えてみたいことは、則雄が自分の能力と勤め先との関係について「思い違いしも「幻想」も懐いておらず、むしろ大事業のサブリーダーという社内の地位も「代替可能な一部品にしか過ぎぬこと、自分がいなくなっても、すぐそこに代わりの部品がはめ込まれ、数瞬間ののちには、全体がまた何の支障もなく動き続ける」ことを自覚していることである。このことから、資本主義的生産のメカニズムのなかで人間の労働が相互の交換可能性によって〈商品〉としてのみ扱われるというマルクス主義の自己疎外の規定を思い起こすことができる。従って、則雄の〈自己破滅〉を現代日本の資本主義における〈自己疎外〉の問題として解釈できない訳ではない。
しかし、この論文では先程箇条書きにした⑤の部分の、詳しくは則雄が逮捕直後の調べに対して「すらすら」と住所氏名・勤め先さえも述べ、未青年である少女との行為を認め、再度の取調べに対しても「憔悴していたが、静か」に受け、さらに改築中の警察署の窓から「何気なく」飛び降り自殺をするところに注目し、その一連の行為の必然性を考えてみたい。
○ 自己に〈正直〉たらんとしたものの悲劇
最初に、柴田翔の世代に親しまれた『異邦人』の作者力(2)ミユが「『異邦人』の悲劇は、自分に正直であろうとしたものの悲劇」であり、「そのためにあえて一切の行為を説明せず、社会の名において殺された」(「カミュ会見記」『朝日新聞』昭27・1・15)と語っている主人公のルムソーの行為と、「鳥の影」の結末にみられる主人公則雄の行為との類似性を思わずにはいられない。だからと云って、「鳥の影」の主人公が不条理の人間であり、「鳥の影」という作品は柴田翔が彼なりの不条理の哲学を展開するために書いたものであるといいたい訳ではない。ただ、両作品に共通するもの止して、主人公がきわめて自分の行為に対して〈正直〉であったということを指摘して置きたいだけである。さらに、カミュがルムソーの「問題とする真理は、存在することと、感じることとの真理である」 (英語版自序、一九五五・一)と言っていることをも考え合わせれば、則雄もまた現存在としての自己とその自己の実体験に〈正直〉であろうとした人物だったといえないだろうか。
前に「鳥の影」の問題をマルクス主義の自己疎外の概念で解釈しようとしなかったのは、資本主義の生産過程にプライベートな問題までも還元し、社会体制にその責任を転稼してしまう恐れがあるからである。そうなれば、則雄の〈自覚的〉になされた行為の真意が捉えられなくなるであろう。仮に現代日本の資本主義制度にかかわりがあったとしても、則雄がく自覚的〉におこなった行為はことの善し悪しをこえて責任をとるべきことである。なぜなら、自己に〈正直〉であることは自己の行為に対しても責任をもつことの別の謂であるからである。その意味で、信江との再度の交渉に対しても「今度こそ、自分がすべてを知りつつ、自覚的に饗宴のなかに身を浸して行」こうとし、少女との関係にしても「自分の行為を認め」ることにいささかも躊躇しなかったのは、則雄が自己に〈正直〉であったとともに、明確に責任の持てる人物であったことを証明している。
ところで、『異邦人』が日本に初めて紹介されたとき世に名高い「異邦人」論争が起こったことは周知のことである。異を唱えた広津和郎が「自分の感じた以外のことは言いもせず、やりもしない」ルムソーの不条理な行為に対して一つの理解不能を表明したのはリアリズム作家として当然の帰結である。というのは、絶対的な感覚、ないし体験は代替不可能なかけがえのないものであり、そのために主観的な要素が他人の理解を拒むほど強いからである。逮捕直後の場面のなかで則雄のことが「男」という表現になっていることの秘密はここにある訳で、つまり則雄がこの場面のみ不特定人称に表現されている分、自己に〈正直〉たらんとして得た感覚、ないし体験の絶対化の表現をみてとることができる。そして、このような体験の絶対化こそ、この両作品に共通するモチーフであり、主人公が裁判官によって、あるいは自らの選択によってともに悲劇にいたる根本的な原因であったといえる。
○ 〈瞬間の王〉に殉じようとしたものの悲劇
次に、柴田翔自身が「創作論覚え書」(『われらの文学21』昭44・10・12、講談社)において「私にとって小説は、自分が見てしまったことを、ただ自分がそれを見たということのためにだけ書く場所なのである」と述べていることを考えてみたい。柴田翔がその作家的デピューをかざった『されどわれらが日々――』の作品さえも、その作品の中にある言葉〈歴史の重大な一場面〉を「生きて見たから書いた、あるいは生きることによって見てしまったから書いた」と強調しているように、〈見る〉という五感のうちで最も強裂な体験に裏打ちされた作品だった。ここにこそというべきか、柴田翔の自己における体験の絶対化の思想を読み取ることができるし、自己の体験の絶対化をモチーフとする柴田翔の小説作法がうかがえるというものである。
柴田翔がこれほど自己の体験に固執するのはどうしてか。思えば、自己史においても、人類史においても、ある歴史的な瞬間のなかで生死にかかわるかけがえのない体験をした人々がいる。それは、戦後の日本では革命運動、および学生運動に一画期を期する昭和三十年前後に大学生活を送った人々であった。柴田翔もまた、その一人である。柴田翔の〈時代体験〉は「のちに彼の文学に素材を提供するのみならず、作家としての立場を決定することにもなる」(宮内豊『日本近代文学大事典』講談社)という指摘を待つまでもたい。しかしながら、戦後日本における社会変革の成就という歴史の瞬間に最も高揚した精神の一瞬を経験した人間にとって、その革命の幻想、ないし夢想が明瞭なかたちで挫折したのちの足取りは決して平担な道を歩くようではなかった。例えば、『贈る言葉』の中で、主人公の女子学生が理想にもえて嬉々としてメーデーに参加している学友たちを見ながら、「私たちは決してそんな明るい社会になんか暮らしてはいないってことに」気づいた時、「自分を捨てて、死んだように生きて行くほかはないのよ」と言っていることを思い出すならば、柴田翔においても、東京大学入学後に「やや深入り」したといわれる学生運動とその運動の挫折の深さを感じない訳にはいかないし、その〈時代体験〉は個人的体験の絶対化をうながすほど強烈なものであったはずである。
歴史のうちで各人の生死にかかわるかけがいのない体験内の〈瞬間の王〉ともいうべきものを経験した人々は、このように時代体験があまりにも強烈な痕跡を残こして通り過ぎていったため、その後に訪れる生様(いきよう)にも重大な影響をうけることになる。そこで、考えられる生様は二つしかない。一つは、命運をかけた〈瞬間の王〉の無意味さに気づいたとき、蛇の抜け殻のように「自分を捨てて、死んだように生きて行くほかはたい」生き方である。二つめは、生の火花を散らした〈瞬間の王〉の体験に固執するあまり新たな〈瞬間の王〉を求めて絶えず緊張を強いながら張りつめた生活を送らざるを得ない生き方である。しかし、いずれにせよ、平凡で一般的な生活など保障できない生き方であることはまちがいない。もちろん、〈瞬間の王〉を体験したものの辿るもう一つの生き方、二つめの生き方に近似しているが、充実した生にあふれていた〈瞬間の王〉の幻影にすがりつつ自己を慰撫して生きる生き方もある。しかしこれは、「時間を浪費する余裕」もなく、従って「懐古することで現在の生活の空しさを慰める必要」もない則雄のような現代人には無縁である。
それでは、則雄の場合どうかというと、二つめの生き方に属しているといえる。三十代半ばの一流企業に勤める有能な社員である則雄は、年齢にしては早すぎる課長代理という地位についていたが、それは、「その地位を保持し、足をひっぱる同僚たちを振りはらい、次の地位に進み、私と私の妻子の人生を危げないものにするためには、一刻も気を許すことができない」もの、「休むことのできぬレース」のようなものであった。まさしく「つねにトップを駈け続けなければならない宿命を負っていた」のである。ただ、注意すべきことは、則雄の場合〈仕事〉に対する態度が〈仕事〉によって「短い一生を更に短く駈け抜けようとしている」ことである。つまり、そのせっかちな生き急ぎの背景には、人生の目的というよりも手段にすぎないとする〈仕事〉に対する認識がある。そして、人生の本当の目的は生き急ぎを促すものということになるが、それは、〈仕事〉の中味の問題として、「自分の考えを打ち込むべき場所と時期||それを的確に測り、行動に移る時」のまさに「一種スポーツの緊張に似た快さ」にあったのである。それだからこそ、則雄はそこに「誇り」と「人生の充実」を感じることができた。従って、ここに表現されているのは、緊迫した歴史の〈場所と時期〉に際会しながら社会変革というマクロ的な仕事をなしえなかった作家柴田翔がごく、ミクロ的な一企業のある大型プロジェクトに見出した〈瞬間の王〉を追体験しているのに他ならない。
ところが、〈瞬間の王〉に生きることは何も〈仕事〉だけに限ったことではない。挫折の誘因となった「異質な世界」を持った信江との交渉もまた、則雄に「そこに身をまかせたい強い欲求」を促し、〈瞬間の王〉を体験させるものであった。則雄にそれを気づかせたのは、「人間は馬鹿なことをすることがある。が、その馬鹿なことのなかに人生はあるのだ」と呟いた潮田や、「結局、人生は女につきるかもな」と言った級友の山本たちの存在である。彼らは、「仕事に充たされている現在の生活こそが、人生の真面目な部分なのだ」と考えて、仕事以外に向けることのなかった〈瞬間の王〉ヘの欲求を「女」に向けさせ、堅実なエリート社員であった則雄を破滅にひきずり込んだ張本人だったといえようか。しかし、三者の人間関係をもう少し詳しくみると、おもしろい構図ができあがるのである。年下の同僚の奥さんに手を出して国立大学の教授の椅子を棒に振った潮田は、まだしも「執する光」「ある狂気」「狂にも似た偏執」「狂気と偏執」とか「奇怪な執念」などと表現されるような日常をつき抜ける〈狂気〉を孕んでいた点で、「狂気の波」のなかで信江と交渉した則雄に近い存在である。それに対して、仕事を手段だと考えていることでは恐ろしく近似している山本は、やはり「つまらない人間だからって、その人生がつまらないか、どうかってのは、別のことなんだぜ」と言いながら「そういういい方で居直ろうとする」だけの弁解がましい人物である。つまり、則雄ら三者の違いは、すべてをまかせても晦いない〈瞬間の王〉に殉じようとする〈狂気〉を持っているか否かであり、その〈狂気〉を持っていたことから、潮田は地位を失い、則雄は自殺するという不幸を招いた訳である。
ここで、誤解を防ぐ意味で云えば、則雄の〈狂気〉が本人の自己破滅のすべての原因だったと捉えるのはまちがいである。確かに、二度にわたる信江との情交が「狂気の波」や「狂暴さと甘美さ」のなかで行われている。が、よく見ると、その信江との情交においてさえも、最初のそれが「すべては、漠然としてい」て、無意識のうちでの逸脱であり、そのためにこそ、再度の情交の時には「今度こそ、自分がすべてを知りつつ、自覚的に饗宴のなかに身を浸して行くのだ」と念じている。則雄にとって〈瞬間の王〉に生きるとは、物事に一心になることによってまったくの〈自己放出〉とか〈忘我〉とか呼ばれる類いの状態になることとは程遠いものである。それは、「我を忘れたようにはしゃぎまわる裕太の顔を、何か見慣れぬものを見るかのように見つめ」る態度に、あくまでも一個の覚醒した意識的な人間であったことを読み取ることができるのと同じことである。しかし、かといって、意識の人則雄の内面に時として浮かぶ心の陰影〈自己放出〉が見え隠れするのを無視することはできない。例えば、潮田の古稀祝賀会の会場に足を運ぶため降り立った則雄は、この部分が「鳥の影」の最初の場面だけに何かしら暗示的であるが、「午後の静かな風景のなかに立って、ぼんやりと遠くを眺め、次第に身が軽くなって行くのを感じた。時間が、彼から遠のいて行った。あたりの透明な大気が、彼の指の先から、やがて腕、四肢、身体にしみ通ってきて、彼を解き放った」ような気がする。息子裕太の誕生日の贈り物を買うために立ち寄った玩具売場の亀のおもちゃに、則雄は「思わず立止って、暫くの間、その動きをじっと見ていた。不思議な幸福感が、玩具売場の喧噪のなかに立つ則雄の心に拡がっていった」ことを感じる。これらはいずれも、『贈る言葉』のなかで、主人公が一枚のマチスの絵に感じる「ある種の安らぎであり、解放であり、恍惚であり、忘我であ」るところの〈自己放出〉である。それは、これもまた『贈る言葉」のなかの言葉を借りて云うと、「ぼくをある狂暴な衝動へと揺さぶる」何ものかである。つまり、これらは、「一刻も気を許すことができない」日常生活であればあるほど意識的であろうとした則雄の意識の網目からこぼれ落ちる無意識の表れとでもいうべきか。そのことから考えてみると、則雄があれほど故郷の「忘れていたその町へ、その祖父のところへ、戻っていくことを、明らかに恐怖していた」のは、「今の彼の生活にまったくなじまないものであった」からだが、意識された生活の裏返しとして、むしろ故郷的なものの持つ無意識の領域にはまり込んでしまうかもしれないという恐れがあったからである。
時折訪れたこのような〈自己放出〉が引き起こすある種の狂暴への衝動〈狂気〉は、信江という「異質な世界」へいざなう働きを一度は果たした。が、そのほんのしばしの〈狂気〉から覚めたとき、信江との二度目の交渉も、少女との交渉も、意識的に〈正直〉であろうとし、意識的に〈瞬間の王〉に殉じようとした。その結果、則雄は自分の破滅をも「戻って行く意志も、まったくないことを、はっきりと自覚していた」ように意識しなければならなかったのである。そこには、〈狂気〉の跡など微塵(みじん)もなく、「彼の心には、苦しみにひきつる潮田の渋紙の仮面のような表情、短い泥まみれのユニフォームで彼らの脇をゆっくりと駈け抜けて行った疲れて不機嫌な少年の姿、教師はつまらぬと眩いた中年の男、死の床の祖父を見守る暗い母の姿などが、何の連関もなく、ばらばらに現われ、交錯し合い、そして、あの少女の抑えた低い笑い声がいつまでも響き続けていた」のを忘れてはならない。
ところで、「鳥の影」の主人公則雄が過去においてどんな〈瞬間の王〉というべきものを経験したのかは小説中どこにも記述がないので不明である。しかし、体験の絶対化をモチーフとすむ柴田翔の小説作法から類推すれば、昭和三十年前後の日本社会の〈瞬間の王〉を体験した〈瞬間の王〉的心象の歩みが投影されていないはずはない。投影していたからこそ、「鳥の影」の作品が唐突のように見えながら、単なる女につまずいたエリートの悲劇にとどまることなく、かけがえのない〈瞬間の王〉に殉じようとしたものの挫折をもののみごとに描くことになったのである。
○ 〈死からの逆照射〉を受けたものの悲劇
思うに、則雄が何かと「挑発的」なもの言いをする山本にことごとく反発しているのは、前に述べたように生き方や気質の相違からして、所詮互いに相入れない間柄だったことを意味する。だが、粘っこくからむように「人間、やがて死ぬんだぜ。潮田のじいさんのようにね」と言った山本の言葉に対して、則雄は異様な反応を示し、自分「のなかで、うねりが高ま」るのを覚え、「今、どうしようもなく流れ出そうとしている自分を感じ」る。そして、その数時間後には、則雄自身がこれまであれほど強く思っていた「仕事に充たされている現在の生活」の「人生の真面目な部分」から逸脱していくのである。これは、『十年の後』の康子が「私たちは、いずれは死ぬのよ。としたら死にのぞんで、心安らかにふり返れぬ仕合せなど本当の仕合せであるはずはないわ。私たち人間にとって、何かを求めるに値するものがあるとしたら、それは死に耐えうるものだけであるはずだわ」と詰問している言葉や、遡っての『されど われらが日々――』の佐野が自分の老いを先取るかたちで「死の間際に何を考えるか」と問う姿勢との関連を考えずにはおられない。ここに、よく指摘される柴田翔文学の早老性の問題があると思うのだが、「死に臨んで、何を思い返すか」という〈死からの逆照射〉にあてられる人生とはとどのつまり、振り返って見ても悔いのない心安らかな生き方をしたかどうかを問うのと同じ意味である。従って、過去に何らかの重大な傷をもつ康子や佐野の場合、〈死からの逆照射〉という生の検証を行えば否定的な結果しか出てこないのは明らかで、佐野のようにその苦悩に耐え切れずに自殺してしまうのは当然のことである。しかも、それは自らの内部でなされる行為なので、ごまかしようもない査問審査のようなもので、それこそ自らを縛る荒縄のような働きをする。一方、過去にさして傷を持たない人間の場合、〈死からの逆照射〉に耐えうる生き方が〈瞬間の王〉に生きようとする気持ちと重なったとき、一瞬一瞬のかけがいのない瞬間に生き、そのことによって少しでも後悔を残こさぬようにしようとする、いわゆる積極的な生き方を生み出すのである。そういう生き方をしようとしたものに、『されど われらが日々――』の節子がいる。例えば、節子の最後の手紙には、「ただひたすら、執拗に自分の過去の自己展開を見守りつづけるばかりで、それに新しい道筋をつけてみようと」しない主人公「私」とは違って、「これからの生き方を、過去の規制によってではなく、過去の否定の上につくり変えようと試み」ながら、今を生きること、そしてそのことによって「生きたと言える日々」の生活をいかに見い出すかという切実な人生の希求が述べられている。これは、強く「心の動揺」を誘ったという佐野の遺書の言葉「死に臨んで、自分は何を思い出すか」に対する節子なりの結論であったのである。また、そこに、時代の挫折を背負わされている登場人物のなかでただ一人、その「世代を抜け出る」可能性、つまり新しい生き方を示しているといわなければならない。そこにあるものは、一瞬のうちに過ぎ去る今を充分に生きることが最も大切にすべきで、過去も現在の自分を形作っている以上の意味はなく、「何をもたらすか知ることのできない明日」という未来までも今を精一杯に生きた上に築かれるもの以外の何ものでもないという生き方である。
この生き方は、「鳥の影」の主人公則雄に継承されていると考えたい。なぜなら、則雄にとっては、信江や少女の関係も〈死からの逆照射〉にあっても悔いることがないという意識があったからこそ、「狭い階段を再び上る時も、暗い常夜燈の下で裸の信江をさいなみながらも、彼は、今度こそ、自分がすべてを知りつつ、自覚的に饗宴のなかに身を浸していくのだと、くりかえし考え」ることができたし、少女の不透明な笑いに「彼は今、すべてのものから解き放たれ、いまだかつて知らなかった、のびやかな、無制限の自由と幸福の、漂うような感覚」を味わうことができたのである。そして、則雄は破滅しつつある自分に後悔の念はさらさらなく、あっさりと少女との行為を認め、二度目の取り調べを静かに受け、これまで住んでいた日常の世界に「戻って行く意志も、まったくないことを、はっきりと自覚し」ながら、仮取調室の窓から空間に身を躍らせて自殺するのである。
終わりに
「鳥の影」の主人公則雄の生の軌跡は特異ではあるが、めまぐるしく変動してやまない現代社会に生きるものの一つの典型ではないか。しかし、破滅して悔いはなかった則雄本人はともかく、窓から身を躍らせた直後、そこに通り合わせたタクシーの乗客は巻き添えを食って死ななければならなかったし、何よりも彼の妻子は「これからの暮らし向きのことを考えて、胸を痛め」なければならなかった。則雄の生き方はややもすれば本人を含めた数多くの人々の犠牲なしには成り立たないことを柴田翔はしかと見抜いている。
そして、そのような生き方をした則雄に対して、人一倍「病とか事故とか死に関係することに神経質」な妻宏子は、「世をはばか」るようなことをした夫の死に立ち合いながら、「まだ暖かい骨壷を膝に抱」いて、もうすでに「これからの暮らし向きのことを考え」ることのできる女性である。ある意味では、堅実で、決して現実の枠を越えない人物である。この宏子の存在こそ、何一つ展望のひらけない「鳥の影」において、唯一の光明、そう云って悪ければ救いのような気がする。
このように日常性に回帰して終結するのは、「鳥の影」という作品だけでなく、『立ち盡す明日』という作品にもみられるが、それは、柴田翔がどんな生き方をしても結局は日常性の網の中にかすめ取ってしまうその強靭な時の流れを善しくも悪しくも描こうとしたからではないかという思いがしてならない。
この稿は昭和六〇年熊本近代文学研究会十一月例会で発表したものを加筆訂正したものである。
註(1) 加賀乙彦『鳥の影』解説(新潮文庫、昭49)参照
(2)『贈る言葉』には次のような文章がある。「カミユだとかサルトルだとかマルクスだとかいう、当時の学生にとってきわめて正統的な、やや事大主義的なといってもよいようなもの」