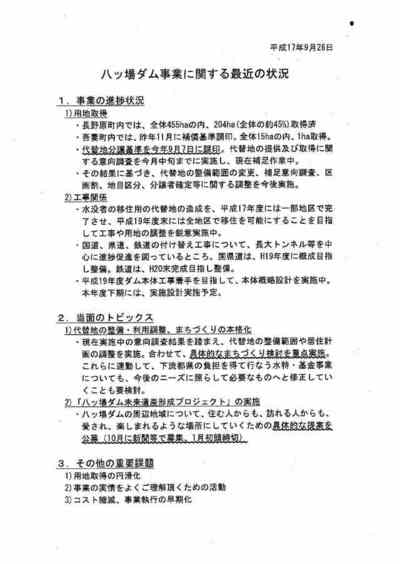■足掛け3年もの間、安中市の岩野谷地区の住民に迷惑をかけ、不安に陥れてきた東京ガスの高圧導管敷設工事は、岩井地区の県道下のトンネル部分のパイプ挿入と設置も済み、残るのは縦穴の埋め戻し、および、若宮橋から市道を横切る箇所の最後の接続部の埋め戻し工事です。

↑岩井地区の県道に明けた縦穴の底部には配管済みの高圧ガス導管が見える。(9月5日撮影)↑

↑若宮橋右岸で実施中の、岩野谷地区における最後の配管接続作業。(9月5日撮影)↑
おそらく、岩野谷地区の道路交通規制は、今月中にほぼ解除される見通しですが、東京ガスからは、もう地区回覧用チラシによる工事予定の情報提供はなく、いったい道路の下で、いつまで、どんな工事をおこない、仮舗装された凸凹の道路がいつ本舗装されるのか、まるでわかりません。
また、高圧ガス導管工事が12月末に完了したあと、導管内の清掃や、内面処理、防錆措置、耐圧試験など、パイプラインの機能確認を行い、来年4月の運転開始となるのでしょうが、もはや、東京ガスはそうした予定についても、今後一切、地元住民には公表しないものと思われます。なぜなら、地元住民が切望している災害防止協定の締結には、まるで無関心だからです。
そうした中で、東京ガスの情報公開に消極的な体質が、またもや示されました。

↑東京ガス本社ビル全景。ガスパッチョの親しみやすさのイメージに惑わされないようにしたい。↑
■当会は、東京ガスから、平成21年8月1日付けで「上から目線」的書面が到来したので、平成21年8月6日付で、反論と再質問を兼ねた回答書を東京ガスに提出していました。東京ガスからの誠意ある回答を心待ちにしていたのですが、なかなか返事がありません。
そして、ちょうど1ヶ月が経過した平成21年9月7日付けで、次の内容の書面が送られてきました。いつもは、予めFAXで送信してくるのですが、今回は、書面での送付のみでした。
**********
平成21年9月7日
小川賢 様
東京ガス株式会社 群馬幹線建設事務所
平成21年8月6日付貴状に対する弊社見解
拝復 初秋の候、貴殿ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
さて、平成21年8月6日貴状について下記のとおり弊社見解を回答申しあげます。 敬具
記
弊社は平成21年7月31日付文書にて貴殿に対し『誠意あるご対応』を要望いたしましたが、同年8月6日付貴状から判断する限り、貴殿は弊社の意を汲み取っていただけていないものと認識し大変遺憾に感じております。
弊社は貴殿のご理解を賜るべく2年以上にわたり真摯に対応して参りましたが、見解の相違に属する部分については如何ともしがたく、これ以上の対応は控えさせていただきます。
なお、貴殿管理のホームページ上における、弊社員の顔写真の無断掲載及び弊社ホームページ掲載写真の無断転載ならびに弊社員を評し『ドロボーと大差のない』との記載等につきましては、一般常識に照らした良識あるご対応のほどを再度要望いたします。 以上
連絡先 渉外課 課長○○○○ 電話 027-324-5438
**********
■驚きました。当会のブログに対して、さまざまな視点でクレームをしてきた東京ガスに対して、誠意をもって当会の見解を書面で伝え、さらに、当会の見解に対する東京ガスの回答も要請していましたが、結局、東京ガスからは誠意ある説明責任をいただけないまま、「これ以上の回答は控えさせていただきます」として、見解の相違を埋める努力を放棄した内容の文章となっています。
そこで、CSRが機能しない東京ガスのため、仕方なく同社の群馬幹線建設事務所長に対して、次の書面を送付するとともに、FAXでも送信しました。東京ガスでは、高圧パイプの敷設工事が完了すれば、もう沿線住民には要はないのでしょうが、地元住民としては、今後、殆ど未来永劫、70気圧の超高圧ガス管が埋まった生活道路を使って、通勤、通学、買い物のため往来しなければならず、住居の目の前の生活道路下に敷設された高圧パイプと共存していかなければなりません。しかも、災害防止協定の締結にも東京ガスが応じないため、高圧ガス導管施設の運用や維持面での情報が入手できないので、将来への不安は尽きません。だから、東京ガスから、「これ以上の回答は控えさせていただきます」と、三行半を突きつけられても、沿線住民としては、今後とも東京ガスから誠意ある回答をいただける余地を残してもらわなければなりません。万一の事態を考慮して、ステークホルダーの住民としては、地元住民とのパイプの構築を、引き続き、東京ガスにお願いしていく必要があるからです。
そこで、次のレターを群馬幹線建設事務所長宛に、FAX及び郵送で送付しました。
**********
平成21年9月13日
東京ガス株式会社 群馬幹線建設事務所長 殿
〒379-0114安中市野殿980番地 小川賢
平成21年9月7日付貴状に対する弊コメント
拝啓 初秋の候、貴社いよいよご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、平成21年8月6日弊状について、平成21年9月7日付書面で、貴社見解をご連絡賜り厚く御礼申し上げます。貴見解について、下記のとおり、弊コメント申し上げます。 敬具
記
私は、貴社が当地において、天然ガス高圧導管敷設計画を立案し、その現地施工に際して、地元関係者のことをステークホルダーと見なしていただき、情報開示及び説明責任の重要性を重ねてお願いして来ました。
しかるに、誠に遺憾ながら、貴社の説明姿勢は高慢で消極的であり、地元として要望したルート変更にも一切応じていただけず、地元との災害防止協定についても、全く関心を示していただけませんでした。
日本におけるエネルギー転換において、今後、貴社の果たす役割が大きいことは十分承知をしており、そのため、貴社には、今後の天然ガスのネットワークの充実にむけた導管敷設の円滑な工事のためには、周辺住民への理解を得ることが、最重要な要素であることを、理解していただきたいと念じつつ、これまで、再三にわたり貴社に対して「誠意ある対応」を要請してきました。
しかし、結局、貴社は、地元住民の要望に真摯に耳を傾けることなく、地元に多大な迷惑と不信感を残したまま、今年12月中の工事完了と、来年4月の運用開始に向けて、既に、地元住民の迷惑など眼中にないご様子です。
また、私が何度もご質問してきた事項についても、誠意あるご回答をいただけないまま、今回の書面で、一方的に、「見解の相違に属する部分については如何ともしがたく、これ以上の対応は控えさせていただきます」との一文を寄せられたことは誠に残念です。
貴社では、そのような方針で今後は対応をお取りになられるようですが、私としては、今後とも貴社の設置した導管施設のすぐ近傍で生活を余儀なくされることから、今回の貴社の対応を風化させることのないように次代に継承するため、当会のブログも引き続き維持してゆきます。
また、貴社に対して、地元との災害防止協定の締結や、施設維持情報の開示など、懸案事項について、貴社のご理解を得るための努力を今後も惜しまない所存です。 以上
**********
■東京ガスでは、最近、大阪ガスや韓国のガス会社と一緒に、オーストラリアと30年間にわたる長期の天然ガス供給契約を締結しました。一方、群馬県の今回の群馬幹線Ⅰ期工事のあと、計画されているⅡ期工事については、現時点で、計画の実現性については白紙だといわれています。その理由は、沿線の大規模なガス消費者としての企業業績が、昨年秋のリーマンショックを契機として景気減速だとされています。
今回の安中市磯部の信越半導体から、高崎市下小塙町までの群馬幹線Ⅰ期工事では、途中に東邦亜鉛や、NSKなどの大口消費家がいたので、57億円もの工費を投じる気になったのでしょうが、一番宛にしていた東邦亜鉛との交渉が足踏み状態となると、このⅠ期工事の採算性に黄色信号が点くことになります。だから、Ⅱ期工事の着手に踏み切れないのかもしれません。なお、どっちにしても、安中市民がCO2削減に役立つクリーンエネルギーの恩恵にあずかれるのは、いつになるのかわかりません。
■東京ガスの体質について、わかりやすい事例を示します。当会では、東京ガスの本社の写真を読者の参考のために撮影しようとしたことがあります。JR浜松町駅で下車して、立派な廊下のような越線橋を渡ると、左手に東京ガス本社への渡り廊下があります。

↑公共通路から直接、東京ガス本社ビルに入る渡り廊下がつながっている。↑
そこを入り口に向かって、どんどん進むと、途中に「特別警備実施中」と書かれた看板があります。さらに50mほど進むと、玄関があり、守衛が検問中です。

そこで当会は、玄関を一望できる場所で、カメラを向けようとしたところ、守衛がめざとく見つけて、「ここは撮影禁止だ」と大声で注意してきました。しかし、どこにも撮影禁止の文字はありません。オロオロしていると、「東京ガスの敷地内では写真撮影はダメだ」といわれました。では、渡り廊下の外に出ればよいかと思い、外に出ましたが、守衛はまだ怒った形相をしています。よくみると、そこは、東京ガスの建物の屋上になっているようです。慌てて、先ほどの「警戒」と書かれた看板のところに戻ると、その真下がちょうど東京ガスの建物と道路の境になっており、この外側なら、許してもらえそうです。しかし、相変わらず守衛の目が光っているので、怖くなって、やや離れた位置からズームで撮影しました。

↑怖い目でにらむ守衛さん。なんでも「敷地内で撮影するには、事前に総務部から撮影許可をもらわなければならない」のだそうです。撮影の目的から、日時、場所、角度など、いろいろ申請が必要なようです。このブログをチェックされて、東京ガスのCSRからクレームしてくれるかなあ。↑
■公道の真上に、専用の渡り廊下を設置できるほどの大企業なのに、施設内の写真撮影の禁止にこだわるのは、なぜでしょうか。おそらく、東京ガスの言行不一致に疑問をいだく関係者が多いため、そうした実態を慮って、無用な心配や懸念から過剰防護しているのではないでしょうか。
世界最大のガス会社を標榜する東京ガスに対しては、今後とも、正しいCSRやコンプライアンスの実践を促していきたいと存じます。当会が直面した東京ガスの本質については、このブログに記載された事実を通して、多くの皆さんに知っていただきたいと存じます。
【ひらく会情報部・高圧ガス導管敷設研究班】

↑岩井地区の県道に明けた縦穴の底部には配管済みの高圧ガス導管が見える。(9月5日撮影)↑

↑若宮橋右岸で実施中の、岩野谷地区における最後の配管接続作業。(9月5日撮影)↑
おそらく、岩野谷地区の道路交通規制は、今月中にほぼ解除される見通しですが、東京ガスからは、もう地区回覧用チラシによる工事予定の情報提供はなく、いったい道路の下で、いつまで、どんな工事をおこない、仮舗装された凸凹の道路がいつ本舗装されるのか、まるでわかりません。
また、高圧ガス導管工事が12月末に完了したあと、導管内の清掃や、内面処理、防錆措置、耐圧試験など、パイプラインの機能確認を行い、来年4月の運転開始となるのでしょうが、もはや、東京ガスはそうした予定についても、今後一切、地元住民には公表しないものと思われます。なぜなら、地元住民が切望している災害防止協定の締結には、まるで無関心だからです。
そうした中で、東京ガスの情報公開に消極的な体質が、またもや示されました。

↑東京ガス本社ビル全景。ガスパッチョの親しみやすさのイメージに惑わされないようにしたい。↑
■当会は、東京ガスから、平成21年8月1日付けで「上から目線」的書面が到来したので、平成21年8月6日付で、反論と再質問を兼ねた回答書を東京ガスに提出していました。東京ガスからの誠意ある回答を心待ちにしていたのですが、なかなか返事がありません。
そして、ちょうど1ヶ月が経過した平成21年9月7日付けで、次の内容の書面が送られてきました。いつもは、予めFAXで送信してくるのですが、今回は、書面での送付のみでした。
**********
平成21年9月7日
小川賢 様
東京ガス株式会社 群馬幹線建設事務所
平成21年8月6日付貴状に対する弊社見解
拝復 初秋の候、貴殿ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
さて、平成21年8月6日貴状について下記のとおり弊社見解を回答申しあげます。 敬具
記
弊社は平成21年7月31日付文書にて貴殿に対し『誠意あるご対応』を要望いたしましたが、同年8月6日付貴状から判断する限り、貴殿は弊社の意を汲み取っていただけていないものと認識し大変遺憾に感じております。
弊社は貴殿のご理解を賜るべく2年以上にわたり真摯に対応して参りましたが、見解の相違に属する部分については如何ともしがたく、これ以上の対応は控えさせていただきます。
なお、貴殿管理のホームページ上における、弊社員の顔写真の無断掲載及び弊社ホームページ掲載写真の無断転載ならびに弊社員を評し『ドロボーと大差のない』との記載等につきましては、一般常識に照らした良識あるご対応のほどを再度要望いたします。 以上
連絡先 渉外課 課長○○○○ 電話 027-324-5438
**********
■驚きました。当会のブログに対して、さまざまな視点でクレームをしてきた東京ガスに対して、誠意をもって当会の見解を書面で伝え、さらに、当会の見解に対する東京ガスの回答も要請していましたが、結局、東京ガスからは誠意ある説明責任をいただけないまま、「これ以上の回答は控えさせていただきます」として、見解の相違を埋める努力を放棄した内容の文章となっています。
そこで、CSRが機能しない東京ガスのため、仕方なく同社の群馬幹線建設事務所長に対して、次の書面を送付するとともに、FAXでも送信しました。東京ガスでは、高圧パイプの敷設工事が完了すれば、もう沿線住民には要はないのでしょうが、地元住民としては、今後、殆ど未来永劫、70気圧の超高圧ガス管が埋まった生活道路を使って、通勤、通学、買い物のため往来しなければならず、住居の目の前の生活道路下に敷設された高圧パイプと共存していかなければなりません。しかも、災害防止協定の締結にも東京ガスが応じないため、高圧ガス導管施設の運用や維持面での情報が入手できないので、将来への不安は尽きません。だから、東京ガスから、「これ以上の回答は控えさせていただきます」と、三行半を突きつけられても、沿線住民としては、今後とも東京ガスから誠意ある回答をいただける余地を残してもらわなければなりません。万一の事態を考慮して、ステークホルダーの住民としては、地元住民とのパイプの構築を、引き続き、東京ガスにお願いしていく必要があるからです。
そこで、次のレターを群馬幹線建設事務所長宛に、FAX及び郵送で送付しました。
**********
平成21年9月13日
東京ガス株式会社 群馬幹線建設事務所長 殿
〒379-0114安中市野殿980番地 小川賢
平成21年9月7日付貴状に対する弊コメント
拝啓 初秋の候、貴社いよいよご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、平成21年8月6日弊状について、平成21年9月7日付書面で、貴社見解をご連絡賜り厚く御礼申し上げます。貴見解について、下記のとおり、弊コメント申し上げます。 敬具
記
私は、貴社が当地において、天然ガス高圧導管敷設計画を立案し、その現地施工に際して、地元関係者のことをステークホルダーと見なしていただき、情報開示及び説明責任の重要性を重ねてお願いして来ました。
しかるに、誠に遺憾ながら、貴社の説明姿勢は高慢で消極的であり、地元として要望したルート変更にも一切応じていただけず、地元との災害防止協定についても、全く関心を示していただけませんでした。
日本におけるエネルギー転換において、今後、貴社の果たす役割が大きいことは十分承知をしており、そのため、貴社には、今後の天然ガスのネットワークの充実にむけた導管敷設の円滑な工事のためには、周辺住民への理解を得ることが、最重要な要素であることを、理解していただきたいと念じつつ、これまで、再三にわたり貴社に対して「誠意ある対応」を要請してきました。
しかし、結局、貴社は、地元住民の要望に真摯に耳を傾けることなく、地元に多大な迷惑と不信感を残したまま、今年12月中の工事完了と、来年4月の運用開始に向けて、既に、地元住民の迷惑など眼中にないご様子です。
また、私が何度もご質問してきた事項についても、誠意あるご回答をいただけないまま、今回の書面で、一方的に、「見解の相違に属する部分については如何ともしがたく、これ以上の対応は控えさせていただきます」との一文を寄せられたことは誠に残念です。
貴社では、そのような方針で今後は対応をお取りになられるようですが、私としては、今後とも貴社の設置した導管施設のすぐ近傍で生活を余儀なくされることから、今回の貴社の対応を風化させることのないように次代に継承するため、当会のブログも引き続き維持してゆきます。
また、貴社に対して、地元との災害防止協定の締結や、施設維持情報の開示など、懸案事項について、貴社のご理解を得るための努力を今後も惜しまない所存です。 以上
**********
■東京ガスでは、最近、大阪ガスや韓国のガス会社と一緒に、オーストラリアと30年間にわたる長期の天然ガス供給契約を締結しました。一方、群馬県の今回の群馬幹線Ⅰ期工事のあと、計画されているⅡ期工事については、現時点で、計画の実現性については白紙だといわれています。その理由は、沿線の大規模なガス消費者としての企業業績が、昨年秋のリーマンショックを契機として景気減速だとされています。
今回の安中市磯部の信越半導体から、高崎市下小塙町までの群馬幹線Ⅰ期工事では、途中に東邦亜鉛や、NSKなどの大口消費家がいたので、57億円もの工費を投じる気になったのでしょうが、一番宛にしていた東邦亜鉛との交渉が足踏み状態となると、このⅠ期工事の採算性に黄色信号が点くことになります。だから、Ⅱ期工事の着手に踏み切れないのかもしれません。なお、どっちにしても、安中市民がCO2削減に役立つクリーンエネルギーの恩恵にあずかれるのは、いつになるのかわかりません。
■東京ガスの体質について、わかりやすい事例を示します。当会では、東京ガスの本社の写真を読者の参考のために撮影しようとしたことがあります。JR浜松町駅で下車して、立派な廊下のような越線橋を渡ると、左手に東京ガス本社への渡り廊下があります。

↑公共通路から直接、東京ガス本社ビルに入る渡り廊下がつながっている。↑
そこを入り口に向かって、どんどん進むと、途中に「特別警備実施中」と書かれた看板があります。さらに50mほど進むと、玄関があり、守衛が検問中です。

そこで当会は、玄関を一望できる場所で、カメラを向けようとしたところ、守衛がめざとく見つけて、「ここは撮影禁止だ」と大声で注意してきました。しかし、どこにも撮影禁止の文字はありません。オロオロしていると、「東京ガスの敷地内では写真撮影はダメだ」といわれました。では、渡り廊下の外に出ればよいかと思い、外に出ましたが、守衛はまだ怒った形相をしています。よくみると、そこは、東京ガスの建物の屋上になっているようです。慌てて、先ほどの「警戒」と書かれた看板のところに戻ると、その真下がちょうど東京ガスの建物と道路の境になっており、この外側なら、許してもらえそうです。しかし、相変わらず守衛の目が光っているので、怖くなって、やや離れた位置からズームで撮影しました。

↑怖い目でにらむ守衛さん。なんでも「敷地内で撮影するには、事前に総務部から撮影許可をもらわなければならない」のだそうです。撮影の目的から、日時、場所、角度など、いろいろ申請が必要なようです。このブログをチェックされて、東京ガスのCSRからクレームしてくれるかなあ。↑
■公道の真上に、専用の渡り廊下を設置できるほどの大企業なのに、施設内の写真撮影の禁止にこだわるのは、なぜでしょうか。おそらく、東京ガスの言行不一致に疑問をいだく関係者が多いため、そうした実態を慮って、無用な心配や懸念から過剰防護しているのではないでしょうか。
世界最大のガス会社を標榜する東京ガスに対しては、今後とも、正しいCSRやコンプライアンスの実践を促していきたいと存じます。当会が直面した東京ガスの本質については、このブログに記載された事実を通して、多くの皆さんに知っていただきたいと存じます。
【ひらく会情報部・高圧ガス導管敷設研究班】