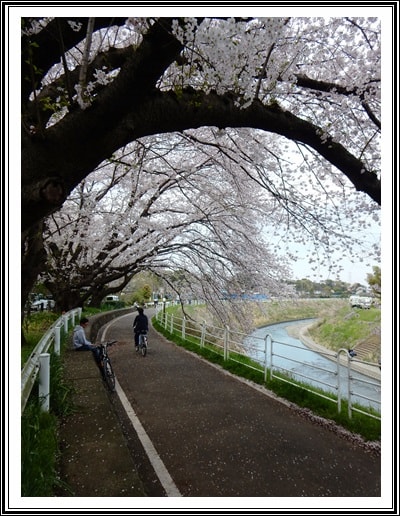人生の大きな分岐点となった人工股関節置換手術から間もなく1年9か月を迎えます。
先日の検診でも、全く問題なし、よほど激しいスポーツ(ラグビー、サッカー、柔道など人との激突が予想されるもの)以外は
何をやっても構わないとのこと
セントラルのジム内にある、台の上に乗ってスイッチを入れると、全身がブルブル震える機械
体幹を鍛えるようですが、長い間、これは無理だろうと躊躇していたのですが
今回聞いたところ、それも大丈夫だとのこと
もっともいまだに勇気がなくてやってないのですが・・・
手術をやったことを知らない人は、ぜったい気づかないくらい普通に戻りました。
もしかしたらバレーボールもできるんじゃないかと思うこともありますが
さすがにこれは、夫が絶対反対どころか、阻止することでしょう。
術後しばらく考えていたことは、ほとんどことごとく実行に移すことができたし
ほんとうにやってよかった、順調に来てよかったと、感謝の気持ちは何年経っても
忘れてはいけないと、決して当たり前ではないのだと謙虚に思っているのです。
先日の検診時にも、待合室でいろいろな症状の方にお会いしましたが
中には、なかなか思うようにならない方もいましたし、
交通事故で後天的に体が不自由になってしまった方に至っては何と言ったらいいものか
あまりにお気の毒で言葉も見つかりませんでした。
私が手術を受けた関西医大では、人工関節(膝も含む)置換手術、片方の場合は通常3週間
両方の場合は1ヶ月、の入院期間が決められています。
人によって、患者の自宅環境によって、転院という選択肢もありますし
自立するまで、しっかりとしたフォローがあります。
MIS(最小侵襲手術:Minimally Invasive Surgery)
初めて聞く方のほうが多いかと思います。
現在、多くの病院で取り入れている手術法です。
我が家から比較的近い専門病院でも、この方法が取り入れられていて、多くの患者さんが手術しているようです。
最少侵襲・・つまり、傷口が小さい、したがって治りも早い?
なんと術後5日で退院、もっともこれは全く問題のない人だけのようですが・・
私も以前、行ってみようかと迷った時期がありました。
なんといっても専門ですし、近いし、
でも飯田先生への思い入れのほうが勝って、結局行くことはありませんでした。
入院中も、大阪の人たちに「○○人工股関節センターって近いんじゃない?なぜそちらにしなかったの?」と
質問されたことがあります。
当時、詳しいことはわからなかったけど、どうしても納得がいかなくて、そちらに行く気持ちは起きませんでした。
病院、特に整形外科などは<年間術数 ××件>なんて数字が目につき、たくさんやっているところのほうが
いかにもいい病院なのでは?と思われがちです。
5日で退院と言うことは、それだけ新しい患者が入院できるということ
おのずと術数は多くなります。
この術後5日目、改めて自分に置き換えてみると、まだ車いす生活でした。
もちろん術後2日目からリハビリが始まりましたから、ベッド上にいることはなかったけど
トイレは車いすが入ることが条件でしたし、1週間目にようやく歩行器に頼って歩く練習を始めました。
そんなころに退院、自宅に帰る・・もう恐ろしくて考えただけでめまいがしそうです。
確かに傷口が小さいということは、回復も早いのかもしれませんが、それはあくまでも傷口だけのことで
人工関節の部分は全くいっしょです。
それでも何人もの医師と、大勢の患者がそれを取り入れているということは、それだけの結果が出ているから?
私は、症状が悪化してから、比較的短い期間に手術をしましたので、跛行はそれほどなく
術後、正しい姿勢で歩けるようになるのに時間はかかりませんでしたけど
長い間、痛みが続いていて、跛行のひどい人は術後、まっすぐ歩けるようになるまで、相当な時間を要するとか
手術も大事ですが、その後のリハビリの大切さを身を持って知った以上、5日間で退院と言うのは
どうしても納得できない
5日で退院して、その後のリハビリは?家での生活は?
1日も早く職場復帰しなければならない方、幼い子供さんを抱えた方
それぞれ事情はあるのでしょうが、何より心配な術後3か月、
ある医師のサイトから拝借しました。
股関節は「関節包」という強力な袋でカバー(補強)されていますが、
人工股関節に置き換える際にこの関節包を取り除くことが多いため、
手術後、関節包が自然に再生するまでの数ヵ月間(3 ヵ月程度)は、
支えがなくなるために脱臼しやすくなります
私も術後、医師を始め、看護師、理学療法士から何度も3か月、3か月としつこく言われたものです。
退院後の2か月は特に細心の注意を払って過ごしました。
先日、ある方から相談?というかお話を聞く機会があり、この病院の話になりました。
結論から言うと、病院を選ぶのはそれぞれの考えです。
ご自分が納得したならそれが一番だから、とお答えしました。
もちろん私は選びませんけど・・・
この件に関して、北海道のある病院のHPにこんな文章がありました。
<当院の股関節MIS(最小侵襲手術:Minimally Invasive Surgery)
最近、人工股関節全置換術においてMIS(Minimally Invasive Surgery)という言葉が流行っているようです。その意味は最小侵襲手術ということですが、はたして本当にそうなのか疑問をもっている股関節外科医は多いと思われます。
そもそも手術というのは安全に、正確に目的を達成することが何よりも大切なはずです。しかも人工関節手術の真価は10年、20年あるいはそれ以上の長きにわたる長期成績にあります。
私の考える最小侵襲とは筋肉、軟部組織の損傷、挫滅および出血量・合併症が少なく手術時間も短いことであり、決して皮膚切開が小さいことではないということです。MIS(6~8cm程度の皮膚切開)の報告をみても手術時間、出血量、合併症のどれをとってもとても最小侵襲とは思えません。逆に感染や脱臼・骨折などの合併症が多くなっているようです。皮膚切開が小さすぎると、無理やり皮膚を引っ張ったりするため裂創や挫滅創を作ってしまい、メスで切った少し大きめの切開創より治癒が悪くなるのは当然であります。小さな皮膚切開では手術に必要な視野を得るのが困難となるのは当然で、それを補うために特殊なレトラクター(皮膚や筋肉をよけるもの)を用いたりします。手術の道具を工夫するのはよいことですが、“MISでもできるように人工関節のデザインを変更する”などという考え方は大変危険な思想であり本末転倒はなはだしいという感じです。人工関節手術において最も大切なことは安全に、理想的な位置に確実に設置することであり、そのためにはある程度の大きさの皮膚切開が必要です。中身(人工関節の位置、角度、設置具合)が同じなら傷は小さいほうが良いのは当然ですが、その中身が同じというところがブラックボックスであり、MIS症例の術後XPでは理想的な位置とは程遠いものも散見されます。どんな位置に設置されても術後には痛みがとれて非常に楽になるのが人工関節でありますが、理想的な位置に設置されたものとそうでないものとでは、長期成績でのゆるみの出現率や再置換率にはかなり差が出ると思われます。もちろん皮膚切開をむやみに大きくすることには反対です。長期成績を犠牲にすることなく、合併症を増やすことがない範囲内で皮膚切開を小さくしていくことは当然のことですし、今までもそうしてきましたが、小さすぎる皮膚切開は“悪”であるということです。
繰り返しになりますが、手術には優先順位があるということです。まず第一に安全であること。第二に長期成績が安定していることであり、切開の大きさはその後にランクされるべき枝葉末節の事柄であるということです。ところがMISをアドバルーンにあげて宣伝した場合、皮膚切開が小さいということが第一の優先順位になり、安全性や長期成績が二の次になりかねないということが危惧されるわけです。
次に入院期間に関してですが、MISだと皮膚・筋・腱切離が少ないため早期リハビリが可能で入院期間が短いと強調されています。しかし、MISでいけるという患者さんは手術が比較的簡単な場合(変形も少なく、可動域もそれほど悪くない)ですので従来法でも早期リハビリは可能で入院期間は大差ないと思われます(当院にて従来法で施行した患者さんの多くは手術翌日より荷重歩行しています)。患者さんには傷しか見えませんので心理的な要素が大きいと思われます。一方MISではとても手術できない重症例(脱臼位や変形が強く股関節の動きが殆どない場合)では十分なリハビリが必要ですので当然入院期間が長くなります。
最後に関西医大の飯田寛和教授が人工関節に関する医学雑誌のなかで、整形外科医に向けて鳴らした警鐘の言葉を引用させていただきます。「現在のMISに対する熱気には、他の部分でのセールスポイントが枯渇してきたメーカーの宣伝や、施設基準設定(年間の人工関節の手術数が一定以上でないと手術点数が一部カットされる)などの圧力から症例集めのアドバルーンとなるといった背景を強く感じます。理論的に小切開、小侵襲が良くないはずはないわけですが、従来の術式に習熟していない術者が行き過ぎた小切開手術へなびきすぎると様々な弊害が生じる可能性があります。」(整形・災害外科 Vol.47 No.13 2004 から一部抜粋)
要するに、長期成績を犠牲にすることなく、合併症も少ないという大原則が守られて初めてMISという手技が成り立つのですが、現時点でははなはだ疑問であるといわざるを得ないということです。>
この文章を読んで、改めて、MISを受けた患者の何割がこのようなことを知っていたのか、疑問に感じます。
1ヶ月の入院期間、理学療法、作業療法、リハビリを受けたおかげで
家に帰っても安心して毎日を過ごすことができたこと、それは大変大切なことだったのです。
そして、今があるのです。
このところ、胸につかえていたことを書き留めました。
先日の検診でも、全く問題なし、よほど激しいスポーツ(ラグビー、サッカー、柔道など人との激突が予想されるもの)以外は
何をやっても構わないとのこと
セントラルのジム内にある、台の上に乗ってスイッチを入れると、全身がブルブル震える機械
体幹を鍛えるようですが、長い間、これは無理だろうと躊躇していたのですが
今回聞いたところ、それも大丈夫だとのこと
もっともいまだに勇気がなくてやってないのですが・・・
手術をやったことを知らない人は、ぜったい気づかないくらい普通に戻りました。
もしかしたらバレーボールもできるんじゃないかと思うこともありますが
さすがにこれは、夫が絶対反対どころか、阻止することでしょう。
術後しばらく考えていたことは、ほとんどことごとく実行に移すことができたし
ほんとうにやってよかった、順調に来てよかったと、感謝の気持ちは何年経っても
忘れてはいけないと、決して当たり前ではないのだと謙虚に思っているのです。
先日の検診時にも、待合室でいろいろな症状の方にお会いしましたが
中には、なかなか思うようにならない方もいましたし、
交通事故で後天的に体が不自由になってしまった方に至っては何と言ったらいいものか
あまりにお気の毒で言葉も見つかりませんでした。
私が手術を受けた関西医大では、人工関節(膝も含む)置換手術、片方の場合は通常3週間
両方の場合は1ヶ月、の入院期間が決められています。
人によって、患者の自宅環境によって、転院という選択肢もありますし
自立するまで、しっかりとしたフォローがあります。
MIS(最小侵襲手術:Minimally Invasive Surgery)
初めて聞く方のほうが多いかと思います。
現在、多くの病院で取り入れている手術法です。
我が家から比較的近い専門病院でも、この方法が取り入れられていて、多くの患者さんが手術しているようです。
最少侵襲・・つまり、傷口が小さい、したがって治りも早い?
なんと術後5日で退院、もっともこれは全く問題のない人だけのようですが・・
私も以前、行ってみようかと迷った時期がありました。
なんといっても専門ですし、近いし、
でも飯田先生への思い入れのほうが勝って、結局行くことはありませんでした。
入院中も、大阪の人たちに「○○人工股関節センターって近いんじゃない?なぜそちらにしなかったの?」と
質問されたことがあります。
当時、詳しいことはわからなかったけど、どうしても納得がいかなくて、そちらに行く気持ちは起きませんでした。
病院、特に整形外科などは<年間術数 ××件>なんて数字が目につき、たくさんやっているところのほうが
いかにもいい病院なのでは?と思われがちです。
5日で退院と言うことは、それだけ新しい患者が入院できるということ
おのずと術数は多くなります。
この術後5日目、改めて自分に置き換えてみると、まだ車いす生活でした。
もちろん術後2日目からリハビリが始まりましたから、ベッド上にいることはなかったけど
トイレは車いすが入ることが条件でしたし、1週間目にようやく歩行器に頼って歩く練習を始めました。
そんなころに退院、自宅に帰る・・もう恐ろしくて考えただけでめまいがしそうです。
確かに傷口が小さいということは、回復も早いのかもしれませんが、それはあくまでも傷口だけのことで
人工関節の部分は全くいっしょです。
それでも何人もの医師と、大勢の患者がそれを取り入れているということは、それだけの結果が出ているから?
私は、症状が悪化してから、比較的短い期間に手術をしましたので、跛行はそれほどなく
術後、正しい姿勢で歩けるようになるのに時間はかかりませんでしたけど
長い間、痛みが続いていて、跛行のひどい人は術後、まっすぐ歩けるようになるまで、相当な時間を要するとか
手術も大事ですが、その後のリハビリの大切さを身を持って知った以上、5日間で退院と言うのは
どうしても納得できない
5日で退院して、その後のリハビリは?家での生活は?
1日も早く職場復帰しなければならない方、幼い子供さんを抱えた方
それぞれ事情はあるのでしょうが、何より心配な術後3か月、
ある医師のサイトから拝借しました。
股関節は「関節包」という強力な袋でカバー(補強)されていますが、
人工股関節に置き換える際にこの関節包を取り除くことが多いため、
手術後、関節包が自然に再生するまでの数ヵ月間(3 ヵ月程度)は、
支えがなくなるために脱臼しやすくなります
私も術後、医師を始め、看護師、理学療法士から何度も3か月、3か月としつこく言われたものです。
退院後の2か月は特に細心の注意を払って過ごしました。
先日、ある方から相談?というかお話を聞く機会があり、この病院の話になりました。
結論から言うと、病院を選ぶのはそれぞれの考えです。
ご自分が納得したならそれが一番だから、とお答えしました。
もちろん私は選びませんけど・・・
この件に関して、北海道のある病院のHPにこんな文章がありました。
<当院の股関節MIS(最小侵襲手術:Minimally Invasive Surgery)
最近、人工股関節全置換術においてMIS(Minimally Invasive Surgery)という言葉が流行っているようです。その意味は最小侵襲手術ということですが、はたして本当にそうなのか疑問をもっている股関節外科医は多いと思われます。
そもそも手術というのは安全に、正確に目的を達成することが何よりも大切なはずです。しかも人工関節手術の真価は10年、20年あるいはそれ以上の長きにわたる長期成績にあります。
私の考える最小侵襲とは筋肉、軟部組織の損傷、挫滅および出血量・合併症が少なく手術時間も短いことであり、決して皮膚切開が小さいことではないということです。MIS(6~8cm程度の皮膚切開)の報告をみても手術時間、出血量、合併症のどれをとってもとても最小侵襲とは思えません。逆に感染や脱臼・骨折などの合併症が多くなっているようです。皮膚切開が小さすぎると、無理やり皮膚を引っ張ったりするため裂創や挫滅創を作ってしまい、メスで切った少し大きめの切開創より治癒が悪くなるのは当然であります。小さな皮膚切開では手術に必要な視野を得るのが困難となるのは当然で、それを補うために特殊なレトラクター(皮膚や筋肉をよけるもの)を用いたりします。手術の道具を工夫するのはよいことですが、“MISでもできるように人工関節のデザインを変更する”などという考え方は大変危険な思想であり本末転倒はなはだしいという感じです。人工関節手術において最も大切なことは安全に、理想的な位置に確実に設置することであり、そのためにはある程度の大きさの皮膚切開が必要です。中身(人工関節の位置、角度、設置具合)が同じなら傷は小さいほうが良いのは当然ですが、その中身が同じというところがブラックボックスであり、MIS症例の術後XPでは理想的な位置とは程遠いものも散見されます。どんな位置に設置されても術後には痛みがとれて非常に楽になるのが人工関節でありますが、理想的な位置に設置されたものとそうでないものとでは、長期成績でのゆるみの出現率や再置換率にはかなり差が出ると思われます。もちろん皮膚切開をむやみに大きくすることには反対です。長期成績を犠牲にすることなく、合併症を増やすことがない範囲内で皮膚切開を小さくしていくことは当然のことですし、今までもそうしてきましたが、小さすぎる皮膚切開は“悪”であるということです。
繰り返しになりますが、手術には優先順位があるということです。まず第一に安全であること。第二に長期成績が安定していることであり、切開の大きさはその後にランクされるべき枝葉末節の事柄であるということです。ところがMISをアドバルーンにあげて宣伝した場合、皮膚切開が小さいということが第一の優先順位になり、安全性や長期成績が二の次になりかねないということが危惧されるわけです。
次に入院期間に関してですが、MISだと皮膚・筋・腱切離が少ないため早期リハビリが可能で入院期間が短いと強調されています。しかし、MISでいけるという患者さんは手術が比較的簡単な場合(変形も少なく、可動域もそれほど悪くない)ですので従来法でも早期リハビリは可能で入院期間は大差ないと思われます(当院にて従来法で施行した患者さんの多くは手術翌日より荷重歩行しています)。患者さんには傷しか見えませんので心理的な要素が大きいと思われます。一方MISではとても手術できない重症例(脱臼位や変形が強く股関節の動きが殆どない場合)では十分なリハビリが必要ですので当然入院期間が長くなります。
最後に関西医大の飯田寛和教授が人工関節に関する医学雑誌のなかで、整形外科医に向けて鳴らした警鐘の言葉を引用させていただきます。「現在のMISに対する熱気には、他の部分でのセールスポイントが枯渇してきたメーカーの宣伝や、施設基準設定(年間の人工関節の手術数が一定以上でないと手術点数が一部カットされる)などの圧力から症例集めのアドバルーンとなるといった背景を強く感じます。理論的に小切開、小侵襲が良くないはずはないわけですが、従来の術式に習熟していない術者が行き過ぎた小切開手術へなびきすぎると様々な弊害が生じる可能性があります。」(整形・災害外科 Vol.47 No.13 2004 から一部抜粋)
要するに、長期成績を犠牲にすることなく、合併症も少ないという大原則が守られて初めてMISという手技が成り立つのですが、現時点でははなはだ疑問であるといわざるを得ないということです。>
この文章を読んで、改めて、MISを受けた患者の何割がこのようなことを知っていたのか、疑問に感じます。
1ヶ月の入院期間、理学療法、作業療法、リハビリを受けたおかげで
家に帰っても安心して毎日を過ごすことができたこと、それは大変大切なことだったのです。
そして、今があるのです。
このところ、胸につかえていたことを書き留めました。










 」
」







































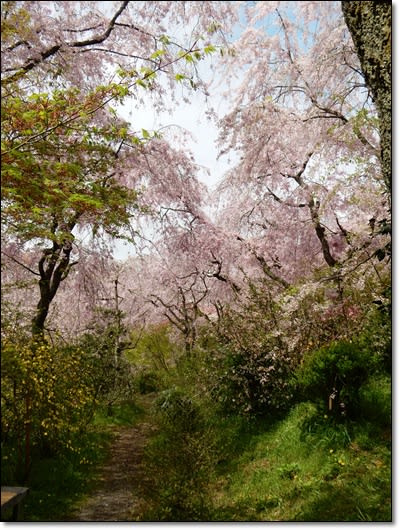



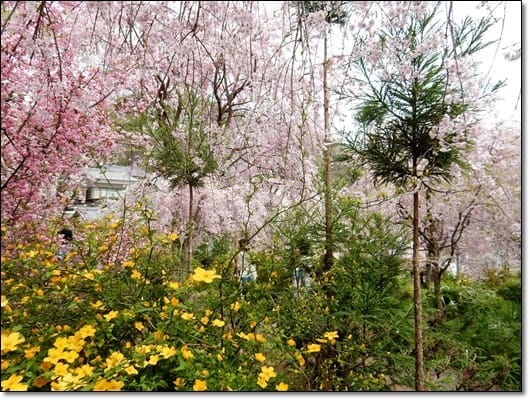

























 <おけいはん>というなんとも愛らしい名称で
<おけいはん>というなんとも愛らしい名称で





 >
>


































 ・・当日が来るのが怖かった。
・・当日が来るのが怖かった。 ヒック
ヒック