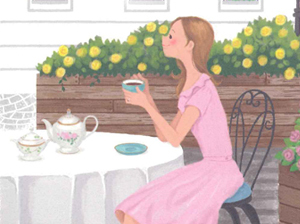5月の看護部・検査部便り
5月の看護部・検査部便り
皆様、こんにちは。
最近、
「点鼻薬(ブセレキュアスプレー)をしたのに、体温が上がらない。排卵している?」
というお声を何度かお聞きしたので、
今回は「排卵」についてお話ししたいと思います。
まず、
排卵とは、
20mmくらいまで育った卵胞の中から卵子が飛び出すことです。
体温が高温になるのは、
卵胞が排卵することによって黄体となり、ここから黄体ホルモンが分泌されるためです。
基礎体温は起床時の身体を動かす前の微妙な変化を捉えるものです。
その微妙な変化をもたらすのが黄体ホルモン。
しかし人間の身体は機械では無いので、
その微妙な変化を完全に正確に基礎体温上に反映させることができません。
ですから、
日々の0.2,3℃の変化や1,2日だけ妙に高かったり低かったり、よく分からなかったり…
これらを「異常」「おかしい」と考える必要はありません。
そのためにも、
当院では排卵を促すために点鼻薬(ブセレキュアスプレー)を使用しています。
排卵を促すサポート方法は2つあります。
1. HCG注射
卵胞を破裂される作用と黄体を形成する作用があり、
LHと同じような働きをします。
一般的には最大卵胞の大きさが18~20mmになった時点で、注射をします。
注射後、24~36時間後に排卵が起こります。
2. 点鼻薬(ブセレキュアスプレー)
この点鼻薬の作用は、
短期的に使用すれば下垂体ホルモン(LHとFSH)の分泌を助け、
長期的に使用すれば卵巣ホルモンの分泌を抑制します。
排卵直前に点鼻薬を短期的に使用することで、LHとFSHの急激な上昇が見られるようになり、
この現象をフレアーアップといい、これによって排卵が促されます。
5~36時間で排卵が起こります。
ブセレキュアスプレーは、
HCG注射よりも副作用が少なく、
排卵という大切な時期を逃さないようにするためのサポートとして使用致します。
また当院では、
タイミング・人工授精後に超音波検査と血液検査を行い排卵の確認も行っております。
不安な時、わからない時はその時にスタッフにお声かけ下さい。
季節の変わりめ、皆様、お身体には十分お気をつけ下さいね。
 とくおかLC看護部・検査部スタッフより
とくおかLC看護部・検査部スタッフより