2012年11月22日(木)
下田市郊外、ワンゲルハウスのKさんご夫妻に見送られ、8時43分林田バス停発
のバスに乗る。10分余りで伊豆急下田駅に着き、国際ウオーキングトレイルメンバ
ーは自然解散となった。
私は茅ヶ崎のIさんと、半日の下田観光をすることにした。まずは下田を上から見
ようと、寝姿山ロープウェイに乗る。先着していたやまさんご夫妻との4人だけで、
9時15分発に乗り、5分で山頂駅に着いた。

山頂は寝姿山自然公園になっていて、遊歩道で回遊できる。山頂駅の展望台からは、
石廊崎と同様に伊豆七島が遠望できるが、雲が多くて遠くの島は認識しにくい。
利島 新 島

眼下に、下田港を囲む須崎半島やみさご島、橋で渡れる犬走島などが見下ろせる。
神津島 犬走島

遊歩道沿いには、「三色のボタン」とも呼ばれるリトルエンジェルがたくさん植え
られ、見ごろになっている。東南アジアや南米原産のようで、初めて見る花だ。

ほかに、初冬の花、皇帝ダリアや、何色かのランタナ、ツワブキなども咲いている。
利島↓

下では暖かだったので、ロープウェイの下の駅、下田駅のコインロッカーにジャン
パーを入れてきたが、雲が広がり風が冷たくなった。

大岩の割れ目から幹の伸びた石割楠の横を過ぎ、いかり型の飾り物のある黒船展望
台に上がった。ここからも伊豆七島や下田港などの展望が素晴らしい。
大 島

さらに進むと、下田出身で日本最初の写真師、下岡蓮丈(しもおかれんじよう)ゆ
かりの下岡蓮丈写真館があるが、閉館していた。

遊歩道の最奥には、法隆寺夢殿のような愛染堂があり、鎌倉初期の仏師、運慶作と
いわれる愛染明王が安置されていた。

愛染明王は子宝や縁結びの神とされるのか、ハート型のそれらの願いを記した木札
がたくさん奉納されている。

愛染堂の横の斜面には、平安時代の作といわれる寝姿地蔵が、150体余り並んで
いた。

背後の伊豆急下田駅を見下ろす位置に、伊東~下田間の伊豆急行を昭和36(1961)
年に開通させた、五島慶太の記念碑が沿線町村会の手でつくられていた。

遊歩道を下り始める。黒船の警戒に当たるために設けられた見張所を復元した幕末
見張所のところには、当時の米国船に搭載されていたという、2門の大砲が下田港を
見下ろすように並ぶ。


山頂駅に戻って10時15分発のロープウェイで下り、下田の町並み散策へ。駅前
からマイマイ通りと呼ぶ中心街を、了仙寺(りょうせんじ)の方向に進み、まずは近
くの稲田寺(とうでんじ)に入った。

山門を入ってすぐ右の阿弥陀堂には、像高2.08m、平安後期の阿弥陀如来像が祭
られていた。

寺は、下田奉行伊沢美作守などの宿舎となり、安政の東海地震の津波後は、仮奉行
所になったという。
次は、唐人お吉の墓のある宝福寺へ。本堂の前に木造の坂本龍馬像が立ち、その右
手奥に唐人お吉記念館がある。

唐人お吉は17歳の時、心ならずもアメリカ総領事タウンゼントはリスのもとへ奉
公に上がり、その後、波乱に満ちた一生を終えた。館内には、お吉の一生を記した絵
物語などが展示されていた。
また、坂本龍馬については、この寺で土佐藩主・山内容堂(ようどう)に勝海舟が
謁見し、脱藩した龍馬の脱藩の許しを請い、認められたとのことで、その部屋が残さ
れていた。

墓地にはお吉の墓があるが、墓地には回らずに寺を出る。

道路際に1837年製のカノン砲などの並ぶ下田市民文化会館や、薩摩十八烈士の
墓があるという大安寺などの前を通過する。
近くの交差点際には、下田に多いなまこ壁の建物が並んでいた。

まいまい通りの南端まで進み、突き当たりの了仙寺に入る。了仙寺は、第2代下田
奉行今村伝四郎正長が、寛永12(1635)年に開基したとのこと。

嘉永7(1854)年3月、神奈川で日米和親条約が締結されて下田は開港され、
入港したペリー一行の応接所となり、5月には、日本側全権、林大学頭などとペリー
との間に和親条約付録下田条約を調印した場所として知られる。
本堂の左手背後に回ると、了仙寺横穴遺蹟があり、古墳時代に墓として利用されと
考えられ、数々の出土物があったようだ。

了仙寺前から左へ、平滑川沿いは「ペリーロード」と呼ばれ、柳が植えられ、なま
こ壁の家並みなどが続いている。ペリー提督は海兵隊を率いて、この先の鼻黒(現在
の下田公園下)から了仙寺まで行進した道筋だという。

流れにたくさんの魚が泳ぐ。路傍に出ていたおばあちゃんに聞くと、海の魚ボラだ
と教えてくれた。

二つ目の橋際には、安政元(1854)年建築↑で、もと海運業だった土佐屋が、
川が左折した向こう側には、伊豆石に囲まれた旧澤村亭↓が、いずれも重厚ななまこ
壁の古民家として残されていた。

旧澤村亭は公開されていたので入ってみることにする。建築は大正4(1929)
年、澤村家は下田町長や下田市議会議長を務めた家柄で、4年前に下田ガス社長の
澤村紀一郎氏が市に寄贈したという。

奥の土蔵には、下田出身の皮革工芸作家で、日展顧問や現代美術か協会副会長など
を歴任され、10年前に文化化勲章を受章された、大久保婦久子さんの皮革工芸品が
数点展示されている。

落ち着いたたたずまいの母屋の内部もひととおり回り、お茶をいただいて澤村亭を
出た。
正午近くなったのと雲が厚くなり気温が下がってきたので、その先の下田公園に行
くのは止め、駅に戻ることにする。
古いカノン砲の置かれた通りを北に向かう。すぐ近くに昭和湯と呼ぶ天然温泉の銭
湯があり、9時から営業していた。

次の角にあったなまこ壁の土藤(つちとう)商店は、明治20(1887)年創業
の酒屋さん。店内には、古く懐かしい看板がたくさん保存されていて、興味をそそら
れる。

さらに進むと、店の前にアジなどの生干しを並べて店が多く、ひもの横丁と呼ばれ
ている。今日は雲が多くてまだ干物は出来上がらないとのこと。その中の1軒で、冷
凍していたアジの干物を求めた。

昼食はそれぞれのお好みとすることにして、Iさんと別れる。往路で目を付けたそ
ば店が見つからず、駅近くのさぬきうどん店で昼食。ロープウェイの下田駅で預けた
荷物を取り出し、伊豆急下田駅発12時44分発熱海行きに乗る。Iさんも同じ列車
だった。
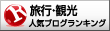 旅行・観光 ブログランキングへ
旅行・観光 ブログランキングへ

にほんブログ村
下田市郊外、ワンゲルハウスのKさんご夫妻に見送られ、8時43分林田バス停発
のバスに乗る。10分余りで伊豆急下田駅に着き、国際ウオーキングトレイルメンバ
ーは自然解散となった。
私は茅ヶ崎のIさんと、半日の下田観光をすることにした。まずは下田を上から見
ようと、寝姿山ロープウェイに乗る。先着していたやまさんご夫妻との4人だけで、
9時15分発に乗り、5分で山頂駅に着いた。

山頂は寝姿山自然公園になっていて、遊歩道で回遊できる。山頂駅の展望台からは、
石廊崎と同様に伊豆七島が遠望できるが、雲が多くて遠くの島は認識しにくい。
利島 新 島

眼下に、下田港を囲む須崎半島やみさご島、橋で渡れる犬走島などが見下ろせる。
神津島 犬走島

遊歩道沿いには、「三色のボタン」とも呼ばれるリトルエンジェルがたくさん植え
られ、見ごろになっている。東南アジアや南米原産のようで、初めて見る花だ。

ほかに、初冬の花、皇帝ダリアや、何色かのランタナ、ツワブキなども咲いている。
利島↓

下では暖かだったので、ロープウェイの下の駅、下田駅のコインロッカーにジャン
パーを入れてきたが、雲が広がり風が冷たくなった。

大岩の割れ目から幹の伸びた石割楠の横を過ぎ、いかり型の飾り物のある黒船展望
台に上がった。ここからも伊豆七島や下田港などの展望が素晴らしい。
大 島

さらに進むと、下田出身で日本最初の写真師、下岡蓮丈(しもおかれんじよう)ゆ
かりの下岡蓮丈写真館があるが、閉館していた。

遊歩道の最奥には、法隆寺夢殿のような愛染堂があり、鎌倉初期の仏師、運慶作と
いわれる愛染明王が安置されていた。

愛染明王は子宝や縁結びの神とされるのか、ハート型のそれらの願いを記した木札
がたくさん奉納されている。

愛染堂の横の斜面には、平安時代の作といわれる寝姿地蔵が、150体余り並んで
いた。

背後の伊豆急下田駅を見下ろす位置に、伊東~下田間の伊豆急行を昭和36(1961)
年に開通させた、五島慶太の記念碑が沿線町村会の手でつくられていた。

遊歩道を下り始める。黒船の警戒に当たるために設けられた見張所を復元した幕末
見張所のところには、当時の米国船に搭載されていたという、2門の大砲が下田港を
見下ろすように並ぶ。


山頂駅に戻って10時15分発のロープウェイで下り、下田の町並み散策へ。駅前
からマイマイ通りと呼ぶ中心街を、了仙寺(りょうせんじ)の方向に進み、まずは近
くの稲田寺(とうでんじ)に入った。

山門を入ってすぐ右の阿弥陀堂には、像高2.08m、平安後期の阿弥陀如来像が祭
られていた。

寺は、下田奉行伊沢美作守などの宿舎となり、安政の東海地震の津波後は、仮奉行
所になったという。
次は、唐人お吉の墓のある宝福寺へ。本堂の前に木造の坂本龍馬像が立ち、その右
手奥に唐人お吉記念館がある。

唐人お吉は17歳の時、心ならずもアメリカ総領事タウンゼントはリスのもとへ奉
公に上がり、その後、波乱に満ちた一生を終えた。館内には、お吉の一生を記した絵
物語などが展示されていた。
また、坂本龍馬については、この寺で土佐藩主・山内容堂(ようどう)に勝海舟が
謁見し、脱藩した龍馬の脱藩の許しを請い、認められたとのことで、その部屋が残さ
れていた。

墓地にはお吉の墓があるが、墓地には回らずに寺を出る。

道路際に1837年製のカノン砲などの並ぶ下田市民文化会館や、薩摩十八烈士の
墓があるという大安寺などの前を通過する。
近くの交差点際には、下田に多いなまこ壁の建物が並んでいた。

まいまい通りの南端まで進み、突き当たりの了仙寺に入る。了仙寺は、第2代下田
奉行今村伝四郎正長が、寛永12(1635)年に開基したとのこと。

嘉永7(1854)年3月、神奈川で日米和親条約が締結されて下田は開港され、
入港したペリー一行の応接所となり、5月には、日本側全権、林大学頭などとペリー
との間に和親条約付録下田条約を調印した場所として知られる。
本堂の左手背後に回ると、了仙寺横穴遺蹟があり、古墳時代に墓として利用されと
考えられ、数々の出土物があったようだ。

了仙寺前から左へ、平滑川沿いは「ペリーロード」と呼ばれ、柳が植えられ、なま
こ壁の家並みなどが続いている。ペリー提督は海兵隊を率いて、この先の鼻黒(現在
の下田公園下)から了仙寺まで行進した道筋だという。

流れにたくさんの魚が泳ぐ。路傍に出ていたおばあちゃんに聞くと、海の魚ボラだ
と教えてくれた。

二つ目の橋際には、安政元(1854)年建築↑で、もと海運業だった土佐屋が、
川が左折した向こう側には、伊豆石に囲まれた旧澤村亭↓が、いずれも重厚ななまこ
壁の古民家として残されていた。

旧澤村亭は公開されていたので入ってみることにする。建築は大正4(1929)
年、澤村家は下田町長や下田市議会議長を務めた家柄で、4年前に下田ガス社長の
澤村紀一郎氏が市に寄贈したという。

奥の土蔵には、下田出身の皮革工芸作家で、日展顧問や現代美術か協会副会長など
を歴任され、10年前に文化化勲章を受章された、大久保婦久子さんの皮革工芸品が
数点展示されている。

落ち着いたたたずまいの母屋の内部もひととおり回り、お茶をいただいて澤村亭を
出た。
正午近くなったのと雲が厚くなり気温が下がってきたので、その先の下田公園に行
くのは止め、駅に戻ることにする。
古いカノン砲の置かれた通りを北に向かう。すぐ近くに昭和湯と呼ぶ天然温泉の銭
湯があり、9時から営業していた。

次の角にあったなまこ壁の土藤(つちとう)商店は、明治20(1887)年創業
の酒屋さん。店内には、古く懐かしい看板がたくさん保存されていて、興味をそそら
れる。

さらに進むと、店の前にアジなどの生干しを並べて店が多く、ひもの横丁と呼ばれ
ている。今日は雲が多くてまだ干物は出来上がらないとのこと。その中の1軒で、冷
凍していたアジの干物を求めた。

昼食はそれぞれのお好みとすることにして、Iさんと別れる。往路で目を付けたそ
ば店が見つからず、駅近くのさぬきうどん店で昼食。ロープウェイの下田駅で預けた
荷物を取り出し、伊豆急下田駅発12時44分発熱海行きに乗る。Iさんも同じ列車
だった。
にほんブログ村

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます