今日は篆刻サークルの勉強会でした。
5月の月例競刻の講評を受けました。

5月の課題は「三餘」印の大きさ八分(約2、5cm)
以下、先生の講評です。

朱白同印の作、筆画を考慮して配置も適切である。
尚「三」の横画に切れ味に今少し鋭味があれば
安定感ある好印たり。

上と同じ朱白相関印。安定した作であるが
空間に今少し差をつけて動きを出したら
良かったか「三の字」丁寧な作といえる。

ゆったりと二字を配分して余白が美しい。
文字と辺縁の構成が実にうまい。明快の作である。

一見して辺縁に工夫を欠いているように思える。
古典に範を求めるべし。右字下部の表現に一考の
余地あり。

一字内に線の細太を用いての軽重の法による刻だが
今少しその特徴を出しきっていないように思える。
ただし、その意気やよし

よくできた朱文印である「三」の字画の空間の
取り方が絶妙。辺縁は重すぎず全体として
軽快の作となった。

文字の画数を考えてよく配分されており
よく出来た佳作である。欲をいえば落ち着き
すぎているので撃打変化をつけたい。辺縁一考。

白文の印篆作であるが「三」の下部に余裕の
空間をとることで印面に動きが出た細やかさが
ある。餘字の旁は下部伸展が良。

文字の周縁に広めに空間をとる事で文字に
締まりが出た。撃辺も程良く柔和さを感ず。

上下に配置したユニークな作。上の辺縁は
カットする大胆さあり、金文の「余」字を
巾広くみせるのもユニークである。
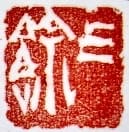
氏の独特の空間構成が新鮮である。「三」は
もう少し伸展した方が良いと思う。
辺縁やや削りすぎ?

辺縁が太く古趣のイメージあり「三」を上に
寄せて対角の承応の風味も少しあるが、やや
「三」字が小さく目立たない。

実に重厚感のある刀味である。特に「三」は
間合いを寄せることで良。旁の「余」字
縦画が曲がっているので留意のこと。

「三」の字を上部に寄せて下部に大きく朱の
重みを見せる。一種絵画的な技で氏の持ち味
十分作たり。「余」字に白部を大きくとり
一層朱色が鮮明。
斉白石の刻した「三餘」
Nさんが調べてきました。

「今回は『三』字をみなさんがどのように
刻してくるか楽しみでした」と先生。
「三」の字に変化をつけてきた人は少なかった。
「3本の線(三)を上に持っていくか下に
持っていくか、位置をずらすか、辺に
くっつけるか、いろいろあります」と先生。
先生が刻した参考印「渓雲」と「青渓」
「氵」の形見本。「氵(サンズイ)」の形も随分違う。


それにしても
「こんなに細い線(髪の毛ほど)どうしたら
刻せるのかしら」とみんな。
「太い印刀では刻せないね」
「印刀はせんの太さによって使い分けます」と先生
あまり詳しくは教えてくれませんでした。
このような細い線を刻すのは何個も刻してみると
いう事なのでしょう。
引き刀と押し刀ではどちらがいいのか?
押し刀はなかなか難しい。人それぞれですが、私は
引き刀で刻す。以前押し刀で刻してみたが滑ってしまって
上手く制御できなかった。
先月の月例競刻で「亀」とあるが判読不能と講評された
Kさんの作品、Kさんが補刀してきました。


これだったら「亀」と読めるかも。
6月の月例競刻提出作品の表を作り今日の勉強会終了。

5月の月例競刻の講評を受けました。

5月の課題は「三餘」印の大きさ八分(約2、5cm)
以下、先生の講評です。

朱白同印の作、筆画を考慮して配置も適切である。
尚「三」の横画に切れ味に今少し鋭味があれば
安定感ある好印たり。

上と同じ朱白相関印。安定した作であるが
空間に今少し差をつけて動きを出したら
良かったか「三の字」丁寧な作といえる。

ゆったりと二字を配分して余白が美しい。
文字と辺縁の構成が実にうまい。明快の作である。

一見して辺縁に工夫を欠いているように思える。
古典に範を求めるべし。右字下部の表現に一考の
余地あり。

一字内に線の細太を用いての軽重の法による刻だが
今少しその特徴を出しきっていないように思える。
ただし、その意気やよし

よくできた朱文印である「三」の字画の空間の
取り方が絶妙。辺縁は重すぎず全体として
軽快の作となった。

文字の画数を考えてよく配分されており
よく出来た佳作である。欲をいえば落ち着き
すぎているので撃打変化をつけたい。辺縁一考。

白文の印篆作であるが「三」の下部に余裕の
空間をとることで印面に動きが出た細やかさが
ある。餘字の旁は下部伸展が良。

文字の周縁に広めに空間をとる事で文字に
締まりが出た。撃辺も程良く柔和さを感ず。

上下に配置したユニークな作。上の辺縁は
カットする大胆さあり、金文の「余」字を
巾広くみせるのもユニークである。
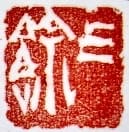
氏の独特の空間構成が新鮮である。「三」は
もう少し伸展した方が良いと思う。
辺縁やや削りすぎ?

辺縁が太く古趣のイメージあり「三」を上に
寄せて対角の承応の風味も少しあるが、やや
「三」字が小さく目立たない。

実に重厚感のある刀味である。特に「三」は
間合いを寄せることで良。旁の「余」字
縦画が曲がっているので留意のこと。

「三」の字を上部に寄せて下部に大きく朱の
重みを見せる。一種絵画的な技で氏の持ち味
十分作たり。「余」字に白部を大きくとり
一層朱色が鮮明。
斉白石の刻した「三餘」
Nさんが調べてきました。

「今回は『三』字をみなさんがどのように
刻してくるか楽しみでした」と先生。
「三」の字に変化をつけてきた人は少なかった。
「3本の線(三)を上に持っていくか下に
持っていくか、位置をずらすか、辺に
くっつけるか、いろいろあります」と先生。
先生が刻した参考印「渓雲」と「青渓」
「氵」の形見本。「氵(サンズイ)」の形も随分違う。


それにしても
「こんなに細い線(髪の毛ほど)どうしたら
刻せるのかしら」とみんな。
「太い印刀では刻せないね」
「印刀はせんの太さによって使い分けます」と先生
あまり詳しくは教えてくれませんでした。
このような細い線を刻すのは何個も刻してみると
いう事なのでしょう。
引き刀と押し刀ではどちらがいいのか?
押し刀はなかなか難しい。人それぞれですが、私は
引き刀で刻す。以前押し刀で刻してみたが滑ってしまって
上手く制御できなかった。
先月の月例競刻で「亀」とあるが判読不能と講評された
Kさんの作品、Kさんが補刀してきました。


これだったら「亀」と読めるかも。
6月の月例競刻提出作品の表を作り今日の勉強会終了。
















