先にご紹介した名和好子先生の
「きもの遊び」。
ゆるゆる着付けが魅力で、
「みなさん、キチキチに着すぎです。
まるで糊で固めたみたいに着ていらっしゃるけど、
あれ変ですよ」との言葉を何度も噛みしめる?
目を凝らして着付けのポイントを
見ていたら、
この方、着物の衽(おくみ)線が
合っていないんですね。
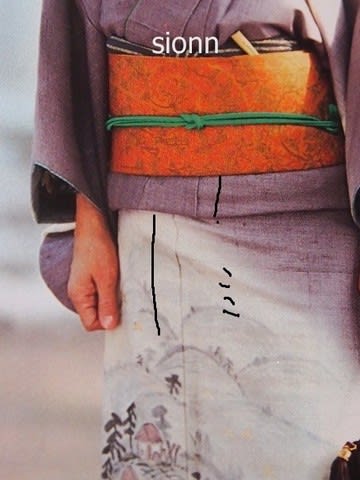
合わなくても特に気にしない
ということなのでしょうね。
不肖紫苑、最初に習った着付けの先生が
帝国ホテルで先生をなさっていた方のせいか、
結構うるさかった。
その後笹島先生の
「一人でできる着付け」(世界文化社)で
自学自習。
「衽合わせは布目を通してから~~」とか
結構詳しく説明してあったので、
「衽線は合わなくてはいけない」
と思いこんでいました。
ゆえに着付けが終わったあと、
上の線と下の線が合わないと、
無理やりずらして合わせたり~~(苦笑)。
衽線には苦労していました。
その結果、ほかの場所が~~、
ところが~~。
美容界の大御所名和先生、合ってない~~。

こちらも。
上半身ゆったり着たら、
下の線と合わなくても当然。
合うなら合うで良し、って感じ。
それに全部のきものがマイサイズではないので、
どうしてもズレは出るよね。
で、気になってほかの本を見てみました。
まずはやはりゆったり着付けの
上野淳美さんの
「日本のおしゃれ七十二候」(WAVE出版)

フォーマルでも合っていない。ほっ
ほかのきものももちろん~?
も一つ、今度はクロワッサンの
「着物の時間2」
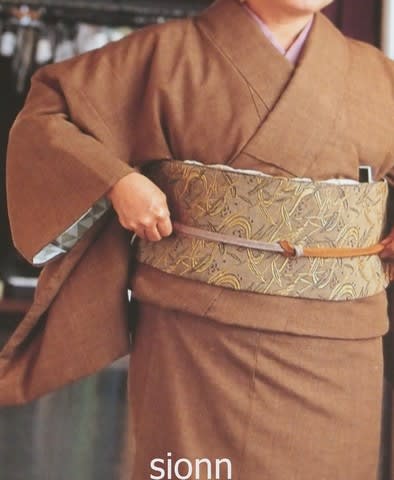
こちらは大久保信子先生の着付け。
大久保先生は雑誌のきもの写真は
「無理してキチキチ着ているだけよ」
と着付けの講座に行ったときに仰っていたなあ。
「脇線は無理に脇に来なくていいの」と。
この衽線、まっすぐつながっていないのを発見?して
気が抜けた。
今さらかい。
衽線、無理に合わせなくていいなら、
ほんと、もっと楽に着られるのよね。

衽、無理に合わなくていいとなれば、
娘にも楽に教えられる。
よかった
この衽線の件で、
「自分を縛っていたのは自分だ」と気づいた。
最初に習った「刷り込み」って大きい。
頭では「ゆったりのほうがいい」と思いながら、
見た目、やはり気にして、いる、いたのね。
私のなかにもいる「自分きもの警察」
でも、皆さまの教えのお陰で、
どんどん着付け楽になります。
いつも応援ポチ
ありがとうございました。
励みになります。

















