
「鉄の暴風」(沖縄タイムス社)やそれを元ネタにした大江健三郎氏の「沖縄ノート」(岩波新書)で、沖縄の「集団自決」は軍命令だった云われたことに疑問を持った作家の曽野綾子氏が沖縄取材の経緯を雑誌「正論」に書いている。
その後曽野氏の指摘により「鉄の暴風」は間違い部分を削除したが、誤報は一人歩きを始め「軍命令による集団自決」は教科書にも載った。
誤報が一人歩きをして教科書にまで載った例は「強制連行による従軍慰安婦」と全く同じケースである。
「鉄の暴風」と言うタイトルは「日本軍の住民虐殺」を印象つける言葉だという沖縄県民もいるくらいだ。
が、住民と軍に「鉄の暴風」とも言うべき無差別攻撃をかけたのは日本軍ではなくアメリカ軍である。
そんな自明の事実さえ、「日本軍は県民を虐殺したがアメリカ軍は助けてくれた」と言う「平和運動家」の言葉には陰が薄くなる。
直接の加害者に非難の目を向けるのではなく、日本軍を批判すると言う点では「広島・長崎の原爆被爆」と全く同じである。
◇
沖縄戦集団自決をめぐる歴史教科書の虚妄
作家 曽野綾子
「正論」平成15年9月号掲載
終戦直前の1945年春、沖縄本島への攻撃の直前に慶良間列島の島々が攻撃された。攻撃は主に艦砲射撃によって行われたが、その激しさは想像を絶するものであったという。
そうした激しい戦火のただ中にほうりこまれた慶良間列島のあちこちで、追い詰められた村民が集団自決をしたケースがあった。この人たちが、古い日本の教育と思想を受けた人々であったことは間違いない。
島民だけではない。当時まだ子供だった私をも含めて日本人のすべてが「生きて虜囚の辱めを受けず」という教育を受けていた。そうした軍国教育の片棒を担いだ大きな力は、文部省と教師たち、大手の新聞社であったことをここに明記して置かねばならない。
1971年の10月から、1972年の8月まで、私は文芸春秋社から発行されている月刊誌『諸君!』に、この慶良間列島中の渡嘉敷島で起きた村民の集団自決の調査報告を『ある神話の背景―沖縄・渡嘉敷島の集団自決』と題して連載した。
私がこの事件に関心を持ったのは、戦後四半世紀経ってからなのである。私はそれまでにも沖縄の旧女学生たちが、終戦間近の戦乱の沖縄で、軍と運命を共に けなげに働いていた状況に焦点をおいた『生贄の島』などを書いていたが、その取材の途中で、この島の悲劇のことも耳にしたのである。
渡嘉敷島は沖縄本島から30キロの沖合いに浮かぶ島である。1945年終戦の直前に、その島には陸軍の海上挺身第三戦隊の海上特攻部隊130人が駐屯していた。彼らの武器はおもちゃのような船であった。
先頃、北朝鮮の工作船が公開され、見る人は一様に「こんなオンボロ船で、ろくろく寝るところもなく乗組員を載せて・・・・・」と言ったが、工作船はまだしも鉄船である。
こちらはベニヤ板でできた長さ5メートル、幅1.5メートル、深さ0.8メートルの舟に、75馬力の自動車用エンジンを載せ、速力20ノットで夜陰に乗じて敵の艦船に接近し体当たりし、120キロの爆雷二個を爆発(三秒瞬発信管使用)させて沈没させるのが目的であった。
「三艇を一組として敵船腹にて爆破せしむるもので、隊員の生還は不可能である」となっていたのである。
この海上挺身第三戦隊を指揮する赤松嘉次元大尉はその時まだ25歳であった。私は1970年9月17日、大阪ではじめて氏に会ったが、氏はその後、1980年に逝去されている。
私が渡嘉敷島の事件に興味を持ったのは、その年の春に見たいくつかの記事がきっかけだったと記憶している。
つまり赤松元隊長とその部下たちが島の慰霊祭のために渡嘉敷島に渡ろうとして抗議団に阻止されたのである。結局、部下たちだけが慰霊祭に出席し、懐かしさを示す村人たちと歓談したが、赤松元隊長だけは島へ行くことを諦めた。
抗議団というのは、平和を守る沖縄キリスト者の会、歴史・社会科教育者協議会、日本原水爆禁止協議会沖縄県支部、日本平和委員会沖縄県支部、日本科学者協議会沖縄県支部、の連合体であった。
当時のジャーナリズムの中には赤松元隊長を悪の権化のように書くものが少なくなかった。その先鋒の一人が大江健三郎氏であった。1970年9月の奥付で、岩波新書から出版された氏の『沖縄ノート』には、赤松元隊長について次のような記述がある。
「・・・・・ その人間が可能な限り早く完全に、厭うべき記憶を、肌ざわりのいいものに改変したいとねがっている場合にはことさらである。かれは他人に嘘をついて瞞着するのみならず、自分自身にも嘘をつく。そのような恥を知らぬ嘘、自己欺瞞が、いかに数多くの、いわゆる『沖縄戦記』のたぐいを満たしていることか」
「慶良間の集団自決の責任者も、そのような自己欺瞞と他者への瞞着の試みを、たえずくりかえしてきたことであろう。人間としてそれをつぐなうには、あまりにも巨きい罪の巨塊の前で、かれはなんとか正気で生き伸びたいとねがう」
私は当時この文章を読んで、二つの感慨を持ったことを記憶する。
一つは人の罪をこのような明確さでなじり、信念を持って断罪する神の如き裁きの口調に恐怖を感じたということである。
もう一つの感慨は極めて通俗的なものであった。私はこの赤松元隊長という実在の人物がもしほんとうに告発されているような人物なら、ぜひ一度会っておきたい、と思ったのである。<略>
私は、自然にその関係の記事や書物を読むようになった。その代表の一冊は沖縄タイムズ社によって発行された『沖縄戦記・鉄の暴風』で、その中には、赤松元隊長がいったんは住民に向かって軍陣地に避難せよ、と言いながら、住民がその通りにすると、自分たちだけは安全な豪の中にあって住民を追い払い、翌日には自決命令を出したというものである。
『鉄の暴風』は次のように描く。
「轟然たる不気味な響音は、次々と谷間に、こだました。瞬時にして――男、女、老人、子供、嬰児――の肉四散し、阿修羅の如き、阿鼻叫喚の光景が、くりひろげられた。死にそこなった者は互いに棍棒で、うち合ったり、剃刀で自らの頚部をきったり、鍬で親しいものの頭を叩き割ったりして、世にも恐ろしい状景が、あっちの集団でも、こっちの集団でも同時に起こり、恩納河原の谷川の水は、ために血にそまっていた」
間もなく私は、第二資料とでも言うべき『慶良間列島、渡嘉敷島の戦闘概要』のコピイをもらった。事件の中心の部分は、次のように書かれていた。
「瞬間、手榴弾がそこここに爆発したかと思うと、轟然たる不気味な音は、谷間を埋め、瞬時にして老幼男女の肉は四散し、阿修羅の如き阿鼻叫喚の地獄が展開された」
「(死に損なった者は)剃刀で自らの頚部を切り、鍬や刀で親しい者の頭をたたき割るなど、世にもおそろしい情景がくり拡げられた。谷川の清水は、またたく間に血の流れと化し」
文章を長年書き続けて来た者の体験から言うと、これだけよく似ている表現は、必ずどちらかがどちらかを下敷きにして書いているものである。
そのうちに私は、第三資料にぶつかった。那覇在住の作家・星雅彦氏のエッセイによると、資料となるものは三つ年代順と思われる順に並べると、次のようになる、という。
第一が『渡嘉敷における戦争の様相』(渡嘉敷村、座間味村共編)で、当時の村長・古波蔵惟好氏と役所吏員防衛隊長・屋比久孟祥氏の記憶を辿って書いたもの、となっている。資料は琉球大学図書館にあるガリ版刷りで、書かれた日時の明記はなく、赤松元隊長が自決命令を出したという記録もない。
第二が『鉄の暴風』(沖縄タイムズ社編)。1950年(昭和25年)8月の日付があり、「自決命令が赤松からもたらされた」とある。
第三が『慶良間列島、渡嘉敷島の戦闘概要』(渡嘉敷島村遺族会著)で、出版は1953年(昭和28年)3月。「赤松隊長から、防衛隊員を通じて、自決命令が出された」となっている。
この三つの資料には、どれかを模写したような共通の文体と内容があることを炯眼の星氏は看破していたのである。
第一資料『渡嘉敷における戦争の様相』と第3資料の『慶良間列島、渡嘉敷島の戦闘概要』は、その自決の場面などには、偶然とはとうてい思えない多くの同一表現が見られる。
とりわけ私にとって決定的に思えたのは、この三つの資料が、米軍上陸の日、1945年3月27日を、どれも3月26日と一日間違って記載していることであった。
何しろ悲劇の始まった日なのだ。生き残った村民にとっては父母兄弟たちの命日の日である。それを三つの資料とも書き違って平気でいるということはないだろう。
これは、三つの資料共、直接体験者でない人々が、後年、伝聞証拠を元にして、前の資料を下敷きにしながら書いて行ったと言う証拠であろう。
私はその当時39歳であった。体力だけは充分であった。私は軍と村民側双方から話を聞くことにしたのである。<略>
敵の艦砲射撃が始まったとき、軍陣地内に逃げよ、という命令を聞いて集まった村民を、赤松元隊長が民間人を軍陣地内には入れられないとして追い返し、自分たちだけ安全な壕にいた、という一つの話を例に取ろう。
このことについて『鉄の暴風』は、赤松元隊長の副官であった知念朝睦氏がその時「悲憤のあまり、慟哭し」たと書いている。知念氏がその苗字が示す通り沖縄県人であったので、非常によく筋が通って読めたのである。
しかし赤松隊側に聞くと「軍陣地は攻撃目標になる危険なところでありますから、最初から民間人を入れるという考えはありません」と言い、知念氏は『鉄の暴風』の記載のでたらめさに憤慨し、かつまともに聞いて来ようともしない沖縄のマスコミに怒って、私に会うまで口を閉ざしたままであったという。
知念氏によると3月25日に特攻舟艇の出撃が不可能になり、初めて赤松隊は心ならずも「島を死守する」ことになった。その二日後の27日に、『鉄の暴風』の書くような「将校会議ができるような壕など全くありえない」と言う。
当時、村の有力者といえば、校長、村長、駐在巡査の三役だったが、私の幸運は当時の村長も、駐在巡査も健在だったことだった。
村長が「自分は自決命令を聞いていないが、駐在がそれを伝えて来た」言明したので、私とすれば駐在巡査に会えばよかったのである。
幸いにも元巡査の安里喜順氏は快く私に会ってくれ、赤松元隊長が自決命令を出したことを否定した。むしろ「あんたたちは非戦闘員だから、生きられる限り生きてくれ」と言ったと証言したのである。
その時に私は驚いたのだが、知念元副官と言い、安里元巡査といい、鍵を握る人物が現存していて、少しも面会を拒否していないのに、取材のために会いにきた沖縄側のジャーナリストは一人もなく、私より前に取材に来たのは「週刊朝日」の中西記者だけだという事実だった。
ついでに言うと、大江氏も渡嘉敷島にさえ取材に来てはいなかった。当時渡嘉敷島には民宿が一軒しかなかったが、私が当然のように大江氏の名前を出しても宿の人はぽかんとしていた。
結論を言うと、私ができる限りの当事者にあたっても、赤松元隊長が自決命令を出したという証拠はどこからも上がってはこなかったのである。
混乱は少なからずあった。もう少しこうすればよかった、という反省は赤松隊側からも出た。しかし西山の玉砕地と呼ばれる悲劇の土地に300人を越す遺体が集まっていたのを見た人はいなかった。
しかしそれを敢えて言わなかったのは、玉砕ということで遺族が年金をもらえれば、それでいいではないか、と思ったという。
私がこの調査をし終わって得た結論は、「赤松隊が自決命令を出さなかったという証拠はない。しかし出したという確実な証拠も全く見つからなかった」ということである。
赤松元隊長を糾弾しようとする多くのマスコミや作家たちは、私が私費でできた基本的調査さえせずに、事件の日にちさえも取り違えた記録を一つの日本史、あるいは日本人の精神史として定着させようとした。その怠慢か欺瞞かが、やっとはっきりしたのである。
人間は間違えるものだ、ということが、私の常日頃からの一つの思いでありこの事件の調査を終わった後も、それは変わらなかった。もし私があの渡嘉敷島の戦中戦後の困難の中におかれたら、私は考えられる限りの感情的な行動を取ったろう。そういう自覚の中では、渡嘉敷島の戦闘に生きたすべての人々は限りなく自然であった。
調査が終わった後、私は生涯沖縄に行くのをやめようと思っていた。この問題に関して、沖縄で発行されている二つの新聞が徹底して私を叩き続けたことを、私は忘れたかったのである。
沖縄の人たちは、この二つの新聞だけが地域を独占している限り、自由で公正な思想とニュースを受けることはないだろう、と感じたが、それも人のことだから、どうでもいい。
しかし何年か経った時、私はやむを得ぬ仕事で沖縄に行くことになり、新聞記者に会った。その中の一人が「赤松神話は曽野さんの調査で覆されましたが」と言った時、私は彼に答えた。
「あなたはどうしてそんなことを言えるのですか。明日にでも渡嘉敷島の土の中から、赤松隊の自決命令書が出てくるかもしれないではないですか。私たちはただ、今日までのところ自決命令が出たという証拠はなかった、ということを知っているだけです。どんなにどちらかに片づけたい事件でも、私たちは歴史の曖昧さに耐える勇気を持たなければならないんです。」
教科書にこの事件が日本軍の残忍さを証拠立てる事件として何の証拠もなく記載されることの恐ろしさは言うまでもないが、私はもう一つの側面を見落としてはならない、と思い続けて来た。
当時沖縄では「この類を見ない残酷な事件、強制された自決」は、日本人の恥の記録とすべきものだ、というふうに話す人がたくさんいたし、おそらく教科書の記載もそうなっているのであろう。<略>
自決した人たちの死は軍から強制されたものとすることに狂奔した。それは死者たちの選択と死をおとしめるものであろう。イスラエルと日本のこの違いはどこから来るのか。私はそのことの方に関心が深いのである。
≪編集部註≫
本稿に関係する歴史教科書の記述例は以下の通り(いずれも来春から使用される高校教科書)。
≪日本軍によって集団自決を強いられた人々・・・≫(実教出版・世界史B)
≪犠牲者のなかには、慶良間諸島の渡嘉敷島のように、日本軍によって「集団自決」を強要された住民や虐殺された住民も含まれており・・・≫(桐原書店・日本史B)
≪日本軍に「集団自決」を強いられたり・・・≫(三省堂・日本史A)
≪戦陣訓によって投降することを禁じられていた日本軍では、一般住民にも集団自決が強いられたり・・・≫(東京書籍・日本史B)











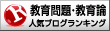


 銀の雨 (1977) 作詞、作曲/松山千春 歌/松山千春
銀の雨 (1977) 作詞、作曲/松山千春 歌/松山千春 ♪貴方と暮らした♪、・・・・・・・
♪貴方と暮らした♪、・・・・・・・




