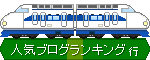夏休み期間後半に考えていたこと。
17日と18日にネットその他で配信された記事の中に、「大学卒業後数年は新卒扱い」にするべきであると、日本学術会議が提言をまとめたというものがあった。
それによれば、深刻な就職難で内定を得られずに卒業する大学生が増えているとして、就職活動で既卒者が不利にならないよう、卒業後数年間は新卒扱いとすることを企業側に求める提言を文部科学省に提出したということだった。ただ、単に新卒と見なせと要求するだけではどうにもならないようなので、学生が身に付けるべき知識や能力を、学問分野ごとに示す基準を作ることも提言した。
後者は文科省の言っている「学士力」と通じるものだろう。
考え方自体はもっともであると思う。でも、仮に卒業後2年、3年が「見なし新卒期間(僕が考えた言葉だ)」となる場合、誰がその人たちに就職関係の情報を配信するのだろう。わからないことが多いので、やっぱり難しくてもオリジナルを読むべきだと思い、日本学術会議のウェブサイトに行ってみた。トップページに「大学教育の分野別質保証の在り方について」というPDFがあったので、DL、プリントして読んでみた。読みたいことは、「第三部 大学と職業との接続の在り方について」にまとめてあった。
以下一部引用する。
個人の自助努力のみで雇用機会を確保することには限界があることから、(中略)、大学は、卒業後最低3年程度は在学生と同様にキャリアコンサルティングや就職斡旋の対象とするなど、卒業者の進路決定に対して支援を提供するべきである。また、大学と公共職業安定機関(ハローワーク)の連携や、民間事業者が行う職業紹介・派遣事業、さらに非営利組織などが行う無料職業紹介機能と大学とが就職斡旋について協力することで、就職できない若者の雇用機会のマッチング機能の充実を図ることも重要である。
大学は卒業後3年程度は在学生と同じケアをすべきであるとの意見のようだ。
この分のコストは誰が持つのかな。大学を卒業した新卒期間にある人は、ハローワークに行くのか、出身校に行くのか。ハローワークなみに大学が情報を収集整理し、OBOGに提供できるのだろうか。ハローワークに近づければその分コストがかかる。誰が負担するんだろう。
卒業時、就職できない人が、日本中の大学に平均的にいるわけではないことも、たぶん間違いないだろう。就職できなかった学生が多い大学は単年度で多いわけではなく、やっぱり毎年多いんじゃないかな。何となくこれも予測できることだと思う。毎年多い大学では、4年生は最大3学年上の卒業生と仕事を取り合うことになる。そして、その大学は就職できない「見なし新卒者」が減らない。
***** *****
この話は、提言にも書いてあるのだが、『本編では、医学等の強固な専門職業資格に直結した分野以外の分野、典型的には人文社会科学系の分野を念頭に論旨を展開している。』とあるように、いわゆるプロフェッショナル系ではなく、教養系の学部学科在籍者の就職問題を取り上げている。僕は本来大学はプロフェッショナル系、教養系それぞれ役割があり、大切であると思う。前者ばかりが尊ばれていくのであれば、そもそも大学の教養教育、リベラルアーツという考え方の否定で、いいことではない。それは専門学校に任せるべきかもしれない。もしくは職業系大学として、別のものにすべきなのかもしれない。ただ、現在の大学はそうはなっていない。だからこそ、教養系の学問をメインにしている学部学科学生の卒業後が、きちんとしていなければならないことは、ちょっと冷静に考えればわかる。
企業側の意見もわからなくはない。大学卒としての要求レベル、世界規模の競争を勝ち抜くための人材確保。ご意見ごもっともの感じもある。ただ、どうしても気になるのは、彼らの発想はいったいいつの大学生を大学生の基準としているのかということである。普通科卒業生の64%が大学生になる。すべての高卒者の54%が大学生になる時代の大学生のレベルは、現在採用担当をしている人たちの時代とはずいぶん違うことが、ホントに理解できているのだろうか。できていないような気がする。
ここ20年で大学の数、大学生の数、大学進学率がずいぶん変化した。平成になり、1991年の大学の教育課程の大綱化以降、大学は従来の大学とは違うものになった。少なくともこの時期以降の大学は、従前の大学とは違う可能性がある。それらがすべて大学として存在しているからわかりにくいとは思うが、大学全体がやはり様変わりしているのは、事実だと思うのだ。だから、そんな大学生がいらないならば、高校(特に専門系高校)や、専門学校に求人を回せばいい。でも、そうすぐには進学先は変わらない。何年もかけて、高校生の進路先が大学進学に徐々に変わったのだから、そう簡単には変わらない。やっぱり、大学生をきちんと取らなくちゃ行けないのだ。。。それには要求すべきものをきちんと大学に求めなければどうにもならないことだ。高いレベルを求めるならば、そうすべきだし、そうでないならばそうすべきなのだ。でも、そうはなっていない。企業がこんなレベルの大学生では取りたくないというのであれば、採らない。そうするしかないのかもしれない。後は外国人を雇用するか? ただ、どの企業もSONY、Nissan、Panasonicというわけにはならない。
やはり、大学生を採るしかないのだ。大学が作る人材は、全部がプロフェッショナル系ではない。で、どうしたらいいのだ。
こんなことをずっと毎日書き足していたら、22日こんなニュースが入ってきた。
新卒支援へ特命チーム 首相、試験的雇用など検討
菅首相は21日、寺田学首相補佐官をトップとする「新卒者雇用・特命チーム」を設置する方針を表明。
厳しさを増す若者の雇用対策に、菅政権が本格的に取り組む姿勢をアピールするのが狙いとみられる。
首相補佐官、文部科学、厚生労働、経済産業等関係府省の政務官らで構成。
今年四月に就職できなかった若者の就職支援や、来年の大卒者らの雇用を守るための具体策を検討する。
24日に初会合を開く。
25日、今度はテレビ朝日のニュースから
菅総理大臣:「当面、短期的な対策としては、1週間をめどに一つの方向を取りまとめて頂きたい」
特命チームでは、今年3月に卒業した学生や来年に卒業する学生に向けた就職支援・雇用確保など、中長期的な政策を省庁を横断して協議する。
特命チームでは、新卒者を試験的に採用した企業に助成金を出す「トライアル雇用」制度の拡充など、具体的内容を今月30日までにまとめる。
緊急対応策だなあ。
「トライアル雇用」は、3ヶ月試用期間と同じで、その後の雇用につながらないのであれば、補助金が出て行くだけにはならないか。
***** *****
考えがまとまらない。こんなに就職が大変なのに進学する。就職がないから進学せざるを得ない。大学や・短大に行っても、4年後、2年後。。。よくなっているだろうか。よくわからない。けど、進学の相談を受けて、考えられることをすべて考えて、資料を読み、生徒とや保護者と面談をする。どうしたらいいんだろう。
どうなるんだろう。
30日、こんなニュースがあった。
菅直人首相直属の雇用対策特命チームは30日午前、「新卒者や既卒者の雇用を確保するための緊急対策」を正式にまとめた。採用に積極的な企業への奨励金や学生支援態勢を強化し、9月初旬から直ちに取り組む。追加経済対策に盛り込まれることになったようだ。
こんな内容だ。
〇卒業後3年以内の既卒者を正社員として採用した企業
〇トライアル雇用(試験的採用)を行ったりする企業
これらに奨励金を創設。
〇キャリアカウンセラーを配置する大学を250校から500校にする。
〇ハローワークでも「大卒・高卒就職ジョブサポーター」を倍増させる。
新たな求人開拓により2万人の正社員就職を目指す。
〇「新卒者就職応援本部(仮称)」を設置する。
全都道府県労働局に国・地方・労使・学校の5者からなる本部を設置。
新卒者らが利用しやすい専門ハローワークの設置。
絵に描いた餅にならないようにしてもらいたい。明日から新学期だ。