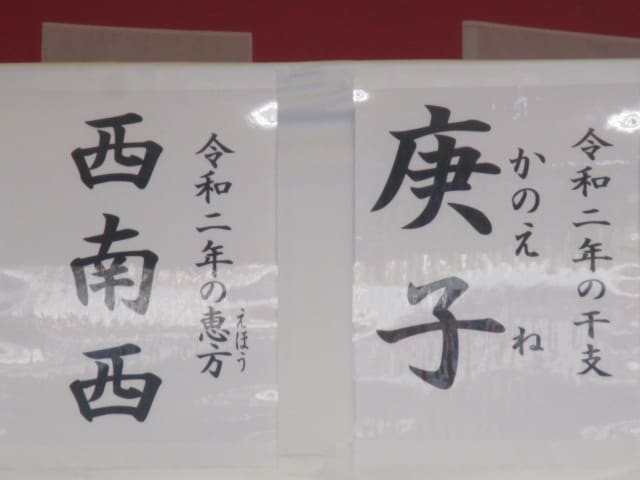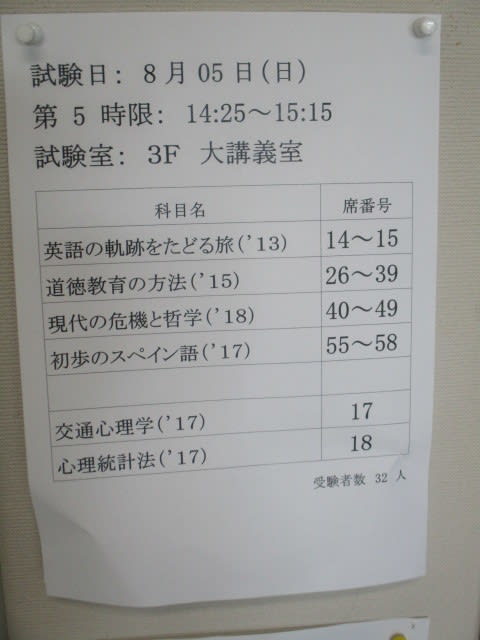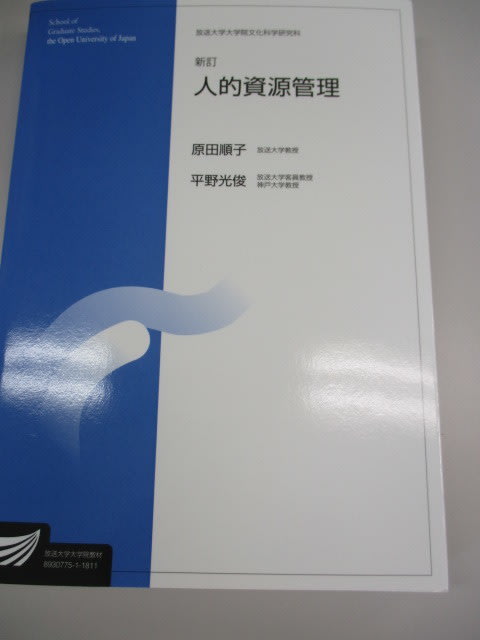放送大学から印刷教材が届きました。
ちょっとワクワク。
いつもの楽しい瞬間です。
一学期は「文学・芸術・武道にみる日本文化」を中心に学んでいきます。
担当は、魚住孝至放送大学教授。
もう一度、日本文化について、学び、考えていこうと思います。
来年度は、シラバスもかなり詳細になっています。
講義内容のポイント、授業の目標、履修上の注意まで説明されています。
学ぶ人に焦点を当てた、なかなか良い取り組みだと思います。
第1回 日本文化の基層(縄文・弥生・古墳時代)
日本列島は海に囲まれ、山と森が多く、四季がある自然環境の中で、縄文土器を生み出し用いた狩猟・漁撈・自然採集の文化が1万数千年以上も続いた。島国で異民族の支配がなかったので、自然を崇拝する感性は、文化の底流で続いていくことになる。2900年程前に北部九州から灌漑稲作が広まり、地域から国家へと統合が進んだ。中部高地の縄文遺跡と諏訪大社の関係を例として、日本文化の基層が形成される様を考える。
【キーワード】日本列島の自然環境、縄文文化、土器、土偶、自然崇拝、祖霊、弥生文化、古墳文化
執筆担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
放送担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
第2回 日本文化の基盤形成(飛鳥時代)
6世紀後半以来、大陸から漢字、仏教、律令制度などを導入して、文化と社会の文明化が図られた。大陸の様式を学びながら見事な仏像が制作され、寺院が建設される一方で、神社も作られた。神と仏への祈りの場が出来た。独自の神話や伝承歌謡が誦習されて『古事記』に記録されることになる。
【キーワード】漢字、仏教、律令制度の導入、仏像、寺院、神社、日本の神話、伝承歌謡
執筆担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
放送担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
第3回 古代の古典の成立(奈良時代)
8世紀初頭、平城京が造営され、中葉には全国の国分寺を統べる東大寺の大仏も建立された。『古事記』と『日本書紀』には神話も含む歴史が記録される一方、『万葉集』には、飛鳥時代以来、4期に分けられる4500首余りの歌が集められ、有名歌人だけでなく、伝承歌謡や無名の者、敗者、地方の者や防人の歌を今に伝えている。
【キーワード】平城京、東大寺、大仏、正倉院、『古事記』、『万葉集』
執筆担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
放送担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
第4回 国風化への転換(平安前期)
8世紀末、平安京に遷都し、律令外の官職も多く設けられ日本化が進んだ。仏教では天台宗や真言密教が加わるとともに、山林修行や神仏習合が進んだ。9世紀後半に誕生した平仮名、片仮名によって、日本語の表記が容易になった。10世紀初頭の平仮名表記の『古今和歌集』は、勅撰で花鳥風月の美の基準を定めることになった。
【キーワード】平安京、平安仏教、神仏習合、国風化、平仮名、『古今和歌集』
執筆担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
放送担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
第5回 王朝文化の展開(平安中期)
10世紀後半から摂関制度が確立した。天皇の后として入内する女性の教養を高めるため有能な女房たちが集められたが、彼女たちは和歌、日記、物語などを書くようになる。11世紀初頭に成立した『源氏物語』は男女の心理や宿命を描き、世界最古の小説と評される。同世紀半ばの平等院は、貴族の浄土への憧れを今に伝えている。
【キーワード】摂関制度、年中行事、女房、王朝文学、『源氏物語』、平等院
執筆担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
放送担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
第6回 武士の台頭の中での王朝古典主義(院政期)
11世紀末から院政期となるが、貴族文化の爛熟期でもある。「源氏物語絵巻」が院周辺で企画され、貴族文化を象徴するものとなる。武士が中央に進出し、その支配が進行したが、朝廷は勅撰和歌集を編んで古典主義を標榜した。貴族の凋落が露わになる中で藤原定家は『百人一首』を編んだほか、冷泉家に大量の古典籍を伝承している。
【キーワード】院政期、「源氏物語絵巻」、古典主義、藤原定家、『百人一首』、冷泉家
執筆担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
放送担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
第7回 中世の始まりと『平家物語』(鎌倉時代)
12世紀後半、武士の平氏が政権を握ったが、末には源氏が兵を挙げ合戦となる。平氏を滅ぼした源氏により鎌倉幕府が成立する。平氏の興亡を語る『平家物語』が語り物で広まった。個性的な仏像や似絵が作られ、庶民の救済を目指す鎌倉新仏教が生まれた。鎌倉末の『徒然草』は無常観を基にする美を表現した。
【キーワード】「平治物語絵詞」、源平合戦、『平家物語』、語り物、運慶、鎌倉新仏教、『徒然草』
執筆担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
放送担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
第8回 連歌と能楽-芸道論の成立(室町時代)
14世紀中期、鎌倉幕府は滅び、南北朝の動乱が続いたが、やがて室町幕府が確立する。この時期に和歌を何人かで分けて詠み連ねる連歌が展開した。貴族と武家の文化が融合する中で、能楽の世阿弥は夢幻能を作るとともに、芸を深めて生涯にわたる芸道論を著した。
【キーワード】連歌、寄合、足利義満、北山文化、世阿弥、『風姿花伝』、夢幻能
執筆担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
放送担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
第9回 連歌師と茶の湯-芸道の展開(戦国・統一期)
15世紀末、足利将軍の書院造りの部屋では唐物を鑑賞しながら茶の湯を喫した。戦国時代になると連歌師が、京都の伝統文化を地方へ伝播させた。町衆の間で展開した茶の湯は、やがて天下人によって政治的に利用されるが、千利休において侘び茶が大成し、江戸時代には瀟洒な数寄の美が展開する。
【キーワード】足利義政、東山文化、禅文化、連歌師、茶の湯、堺、千利休、茶室
執筆担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
放送担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
第10回 武芸鍛練の道-近世の武道(江戸初期)
17世紀初頭に江戸幕府が成立したが、士農工商の身分社会において武士は武芸を鍛練すべきとされた。将軍家の師範となった柳生宗矩が武芸流派の理論と教授法を典型的に示した。他方、宮本武蔵の『五輪書』は、日常生活にまで徹底する剣の鍛練を核とした武士の生き方を説いた。
【キーワード】士農工商、武芸流派、新陰流、上泉信綱、柳生宗矩、宮本武蔵、『五輪書』
執筆担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
放送担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
第11回 俳諧-近世の文学(江戸中期)
17世紀中期には古典文学が木版印刷によって刊行されるようになり、王朝文化のリバイバルが生じた。経済成長する時代にあって、俳諧が爆発的な人気を呼んだ。京の貞門、大坂の談林に続いて、松尾芭蕉において、俳諧は不易の文芸に高められた。彼の俳論は、和歌、連歌も貫く理念を語っている。
【キーワード】出版文化、俳諧、北村季吟、松尾芭蕉、「不易流行」、『おくのほそ道』
執筆担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
放送担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
第12回 浄瑠璃と歌舞伎-近世の芸能(江戸中・後期)
18世紀に入って、京・大坂・江戸の三都で大衆芸能が展開した。歌舞伎では役者の荒事や和事の芸が型になる。浄瑠璃は語り芸に三味線と人形が合体して発展した。近松門左衛門の脚本により庶民の生き様を描く世話物が生まれた。浄瑠璃と歌舞伎の代表的な作品を見る。
【キーワード】歌舞伎、浄瑠璃、近松門左衛門、世話物、『曽根崎心中』、『仮名手本忠臣蔵』
執筆担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
放送担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
第13回 伝統文化の熟成と幕府の終焉(江戸後期・幕末)
18世紀前後から日本の歴史の捉え直しが盛んになり、国学は古典文学を捉え直し、蘭学は西洋の近代文明を取り入れようとした。浮世絵は、流行を取り入れながら庶民の生活や自然を描くようになる。竹刀剣術は下級武士と豪農の間で流行し、やがて彼らが出世する一つのルートを開いた。幕末、歴史意識の高まりから尊王思想が強まり、国の独立の危機感から本格的な内戦を回避して幕府は倒れた。
【キーワード】『大日本史』、国学、本居宣長、蘭学、浮世絵、葛飾北斎、竹刀剣術、徳川慶喜、大政奉還
執筆担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
放送担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
第14回 近代化と伝統の再編成-文学・芸術・武道(明治・大正・昭和初期)
1868年の明治維新以降、新政府は西欧を範とした近代化を進めて伝統文化を否定した。明治22年に憲法が制定され、近代日本の社会が確立するが、伝統文化も文学・芸術・武道として再編成された。大正時代に入ると、西洋的な教養から伝統文化を捉え直す論や民芸などの運動も生じた。
【キーワード】廃仏毀釈、伝統の再編成、正岡子規、岡倉天心、嘉納治五郎、柔道、和辻哲郎、民芸
執筆担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
放送担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
第15回 戦後改革からグローバル時代へ(昭和後期・現代)
1945年以降、占領軍による戦後改革で伝統文化が否定された。7年後に独立を回復し、さらに高度経済成長する中で、日本文化は復活し禅文化など国際的にも広まっている。柔道は国際柔道連盟主導で競技化が著しくJudoになっているが、日本的な身心の修行法がもっと注目されるべきである。日本文化を縄文文化に遡って捉え直して、新たな可能性を探っていかなけばらない。
【キーワード】戦後改革、武道禁止令、国際柔道連盟、『禅と日本文化』、『弓と禅』、縄文文化の再発見、日本文化の捉え直し
執筆担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)
放送担当講師名:魚住 孝至(放送大学教授)