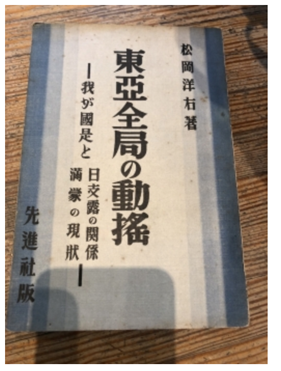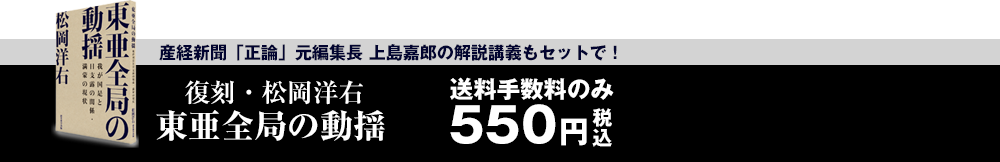9/6(日) 5:36配信
東洋経済オンライン
脳腫瘍が原因で夫の性格が豹変し、暴言・暴力がエスカレート。葛藤と孤独の果てに下した妻の決断とは?
子育てと介護が同時期に発生する状態を「ダブルケア」という。ダブルケアについて調べていると、子育てと介護の負担が、親族の中の1人に集中しているケースが散見される。
なぜそのような偏りが起きるのだろう。
連載第10回は、40代で脳腫瘍が発覚し、手術後、高次脳機能障害になり、性格が激変してしまった夫の介護と子育てをしながら公務員試験を受け、一家の大黒柱として働いてきた女性の事例から、ダブルケアを乗り越えるヒントを探ってみたい。
■夫に脳腫瘍が発覚
宮城県在住の新田夏美さん(仮名、48歳)は、18歳で非正規公務員として就職し、同じ職場で働いていた夫と出会い、23歳で結婚。約1年後には長女、その6年後には次女が誕生し、子育てと仕事で忙しいながらも、幸せに暮らしていた。
ところが2012年のゴールデンウィーク。家族で新田さんの実家へ帰省しようとしていたところ、車を運転していた夫が道を間違える。
「自宅から近く、普段からよく通る道だったので、少し嫌な予感がしました。ゴールデンウィーク明けには、仕事帰りに夫に買い物を頼んだのですが、忘れて帰ってきてしまい、『何かおかしい』と違和感を抱きました」
そして6月のある朝、夫は起き抜けに激しい目眩(めまい)を訴え、布団に突っ伏したまま15分ほど動けなくなる。
不安に思った新田さんはその翌日の夜、夫を伴い自宅近くの病院を受診。頭部CTを撮ったところ、脳腫瘍が発覚。
すぐに大学付属病院を紹介され、精密検査を受けると、腫瘍は6センチ大になっていた。
夫は10月に手術を受けることができたが、手術室に入る前までは穏やかで優しかった夫が、手術を境に性格が変わってしまっていた。
■高次脳機能障害に
手術から約1週間後のこと。病院の売店に夫と2人で行くと、夫は陳列棚に身体の左側をぶつけてしまう。すると棚にあった商品がバラバラと床に落ちた。
慌てて新田さんが商品を拾い始めたが、夫は顔色ひとつ変えず突っ立ったまま。
変に思った新田さんが「どうしたの?」と聞いても、「別に」と一言。新田さんが拾う様子を眺めているだけだった。
「夫は半月ほどで退院しましたが、手術前と比べるとこだわりが強く、怒りっぽくなり、物忘れが多くなりました。でも、当時高校2年だった長女も、小学5年だった次女も、まだ笑って済ませられる程度でした」
しかし2013年の1月、年末年始の休み明けから復職した夫は、手術前のように仕事ができなくなっていた。
当時、新田さんの夫は20人ほどの部下やパートのまとめ役だったが、職場へ行っても何をしていいかわからなくなっていたのだ。
失敗続きで自信をなくした夫は、次第にうつ状態になっていき、4月には精神科への通院を開始。
「夫はつねに怒っていて、私に食ってかかるようになりました。今思うと夫は、脳腫瘍の手術で『帯状回』という大脳辺縁系を手術したため、10月の時点で高次脳機能障害になっていたんだと思います。しかしこのときの私はまだ、高次脳機能障害という障害があることすら知りませんでした」
本当に夫は“うつ状態”なのか、疑問に思った新田さんは、ネットで夫の症状を調べ始める。
そして「高次脳機能障害」という後遺症があることを知り、市内にあるリハビリセンターで診てくれることがわかるとすぐ予約を入れ、6月中旬に受診した。
新田さんが今までの経過を簡単に話し、大学病院から借りたMRIの画像を見せ、認知機能を診るテストを終えると、医師は「高次脳機能障害で間違いないでしょう」と診断。
詳細な検査をすると、夫には記憶障害、注意障害、遂行機能障害、知能の低下(IQが項目によっては正常以下のボーダー域)、社会的行動障害(怒りっぽい、こだわりが強い)、左半側空間無視があることがわかり、障害者手帳の申請をしたところ、精神障害3級の手帳を交付された。
もともと夫は仕事好きで働く意欲が強かったため、医師の勧めで3カ月間仕事を休職し、就労支援を受けることに。
就労支援が終了すると、リハビリセンターの支援員が職場との調整に入り、障害者の夫ができる仕事を配慮してもらえた。
■脳腫瘍の再発
ところが2015年の春、MRI検査で脳腫瘍再発の兆候があり、7月には念のため入院してPET検査を受けることになった。
結果は再発確定。落ち込んだ夫は、「これ以上高次脳機能障害が進んで、自分のことが自分でできなくなるのは嫌だ」と手術を拒否する。
新田さんは、夫の意志を尊重するか、手術を受けるよう説得するべきか迷った。
「当時娘たちは大学2年と中学2年。まだまだ父親が必要な時期だと思い、手術を受けるよう説得しました。でも思い返してみると、夫が手術を受けないことにいちばん恐怖を覚えたのは私でした。夫が死んでしまうことへの恐怖。家族を1人で支えることへの恐怖。たぶん、1人で生きていくことが怖かったんだと思います」
夫は9月に手術を受け、生還。
退院後、抗がん剤の投与と放射線治療のため再入院。1カ月半で退院し、抗がん剤の維持療法に移行した。
11月、夫は言語聴覚士のリハビリを受けた。
リハビリ内容は、夫が座っている場所から2メートルぐらい離れた机の上の書類を取り、すぐ横の机の上に書類を置き、元の場所に戻る……という簡単なものだったが、夫はまったくできなかった。
イスから立ったところで立ち尽くし、言語聴覚士に促されて机の前に行くものの、何をしていいかわからず言語聴覚士のほうを見る。言語聴覚士に書類を隣の机に置くよう言われ、書類を持ち隣の机に置く。
しかし書類を置いたところで立ちすくみ、今度は新田さんのほうを見て、言語聴覚士から「席に戻ってください」と言われ、やっと席に戻る……といった具合に、連続した作業をすることができなくなっていた。
高次脳機能障害は、すぐにリハビリをすれば多少は回復することがあるため、大学病院を退院後はリハビリセンター付属病院に移り、2カ月間入院して生活支援のためのリハビリを受けたが、一度損傷を受けた脳はあまり回復することはなかった。
■地方公務員に転職
新田家はもともと共働きだった。夫が脳腫瘍になる前は、夫のほうが残業が多かったため、新田さんが家事育児を担っていた。
脳腫瘍が発覚したとき、新田さんがまず最初に襲われた不安は、生活のことだった。
当時はまだ長女が高校2年、次女が小学5年。新田さんはパート(非正規公務員)で働いてはいたものの、年収は200万円もない。
そこで新田さんは、収入を上げるために転職活動を開始。新聞に公務員試験の募集記事が載っているのを見つけ、即申し込みをする。
試験まで1カ月ほどしかなかったが、仕事後帰宅し、一通り家事を終えると、毎晩公務員試験の問題集を解いた。数学が苦手な新田さんは、高校生の長女に解き方を教えてもらった。
そしてみごと合格し、翌年、地方公務員(行政事務)に転職。
しかし、経済的な安定は得られても、パートタイムからフルタイムに働き方が変わったため、仕事の責任は重くなり、残業も増え、介護・育児と仕事の両立に悩む。
「私の父は11年前に亡くなっており、母や妹は心配はしてくれていますが、母は昔から体が弱く、病気がちなので頼れません。妹は2人の子どもがまだ小さく、育児でいっぱいいっぱいです。夫の親やきょうだいの協力はほぼ得られず……。
たった1人でダブルケアをこなす心身ともに苦しい状態が続き、ものすごく孤独でした。でも、介護も育児も仕事も待ってくれません。『誰か助けて!』といつも心の中で叫んでいました」
新田さん夫婦は当時40代。周囲に介護をしている人はおらず、ダブルケアのつらさに共感してくれる人はまったくいなかった。
「悩みを相談する相手はなく、さらに“娘たちの父親代わりにならなくては”というプレッシャーや責任も加わり、押し潰されそうになっていました」
娘たちの周囲にも、父親が病気で介護が必要な友だちはいない。家庭での悩みや愚痴を友だちや先生にも言えず、2人ともつらい気持ちを抱えていた。
■高次脳機能障害者の介護
脳腫瘍の手術前後は2回とも自宅療養がほとんどだったため、夫が家で家事をし、新田さんが外で働くという役割分担をしていた。
「高次脳機能障害者の介護はさまざまですが、夫の場合は、自分がしたことをすぐに忘れてしまうため、冷蔵庫を閉め忘れたら閉め、コンロの火を消し忘れたら消し、玄関のドアが開けっぱなしなら閉め、トイレの水を流し忘れたら流すなどの生活全般を見守り、できないことを助けることと、暴言・暴力に対応をすることが主な介護でした」
娘が家にいるときは娘が夫を見守り、何かトラブルがあればその都度対応し、新田さんが帰宅すると不在の間の夫の様子を伝えてくれた。
「主な介護者は私ですが、私は生活のために働かなくてはなりません。私が仕事で遅くなるときは、夫が何かをしでかさないように、娘たちが夫の見守り介護をしてくれました。本当は友だちと学校生活を謳歌してほしいのですが、父親の介護のために帰宅せざるをえない毎日です。こんなにつらく悲しいことはありませんでした」
自宅療養中に夫は、「家計を任せてほしい」と言い出した。新田さんは反対したが、高次脳機能障害になった夫は、怒り出すと手がつけられない。
仕方なく夫と新田さんの給料が振り込まれる新田家の銀行口座の通帳とカードを預けたところ、食費だけで月に10万円以上使ってしまう。冷蔵庫には同じものが何個もたまり、食べきれずに腐って捨てる……という悪循環に陥る。しかし家の通帳とカードを返すよう言うと、すごい剣幕で反論してくる。
またあるとき夫は、「買い物に行くのに新しい自転車が欲しい」と言って自転車を買ったが、鍵をかけることを忘れ、買った翌日に盗まれてしまう。
代わりに長女の自転車を借りたが、今度は自転車に乗ってきたことを忘れ、帰りは歩いて帰ってくる。夫が自転車をなくすたびに、新田さんは娘たちと自転車を探しに行った。
さらに、家の通帳とカードを握った夫は、新田さんにお金をほとんど渡してくれないため、化粧品や生理用品を買うこともままならない。そのうえ、大学生になった長女の教育費も「払いたくない」と言い始める。仕方なく新田さんの個人的な貯蓄を取り崩して長女に渡していたが、貯蓄も底を尽きる。
「『障害だから』と思い、数カ月は我慢をしていましたが、まるで経済的DVを受けているような状況に、ついに私の堪忍袋の緒が切れて、夫と大げんかになりました。そして夫の復職を機に、家の通帳とカードを返してもらいました」
夫は2016年6月、約1年ぶりに復職した。
■首絞め・羽交い締め・警察沙汰にも
ところが復職後、夫の暴言や暴力がエスカレートしていく。
朝起きたばかりの、脳や身体が元気なうちは比較的穏やかだが、仕事で疲れて帰宅する頃には暴言や暴力が激しくなる。
きっかけはいつもささいなことだ。例えば、次女が苦手なピーマンを残したら、「お前のしつけが悪いからだ!」と怒り出し、少しでも反論しようものなら、ひどいときは首絞め、羽交い締め、腕をつかんで振り回す、抱え上げて床へ落とすなどの暴力に及んだ。
暴言や暴力は、娘たちにも振るわれた。「塾へ行きたい」と言う長女に怒り、首を絞める。次女が夕食を残したことに怒り、背中に飛び蹴りする……。
「私たちは、数えきれないほどの暴言を浴びせかけられてきました。私には、お前のせいで脳腫瘍になった、お前は母親失格だ、俺を監視するな、お前と結婚して俺の人生台無しだ! など。
長女には、誰に学費を払ってもらってると思ってるんだ、お前みたいな女は結婚できんぞ、ちょっと勉強ができるからって調子乗るな! など。
次女には、お前はほんと勉強ができないな、お前は発達障害か、お前みたいなバカに塾行かせてやってんだ感謝しろ! など……。暴言だけでなく、対応に困る理不尽な要求もあり、1日働いて帰宅した後の介護は、精神的にも体力的にもキツくて困り果てています……」
夫は暴言や暴力をふるった後も、決して謝らない。夫は自分以外の人を思いやる気持ちや共感する力をなくしてしまっていた。
新田さんは、激高した夫に恐怖して警察を呼んだり、22時過ぎに近くの交番にパジャマのまま裸足で助けを求めたこともある。
子どもの前で夫婦げんかをし、警察が介入したことから、「子どもに対する精神的虐待」ということで、児童相談所の面談を受けたこともある。児童相談所から連絡があったときも夫は、「お前が警察に電話したせいだぞ!」「お前が娘を虐待したんだ!」と怒鳴った。
2017年4月。次女は高校生になったが、夫の高次脳機能障害は進み、精神障害者手帳は3級から2級になっていた。
■明るい未来は別居か離婚か現状維持か
そして2020年、長女は就職して一人暮らしを始め、次女は看護学生になり看護を勉強している。
8月のある日、やはりささいな口論から、夫は突然「別居したい! 離婚だ! 子どもは俺が育てる」と言い出した。
「夫が別居や離婚を望む理由は、『娘たちに暴言を吐くなんて母親として不適格だ!』というのです。確かに私は、夫の介護と仕事に追われ、娘たちの細かなことにまで手が回らなかったかもしれません。
とくに次女が思春期を迎えた頃は、何度か母娘げんかをしたこともありました。でも、早朝に起きて弁当作りから制服や体操服の洗濯、学校生活で必要な物を買いそろえ、おこづかいも渡してと、高校生として恥ずかしくないように、やれるだけのことはやったつもりです」
このときばかりは新田さんも、長年夫を支え、介護してきた努力が夫にまったく理解されていないとわかり、涙がこらえきれなかった。
夫はそれまでも何度か別居や離婚を口にしてきたが、障害者の夫1人で家を借りて暮らすのは難しいうえ、夫はすぐに忘れてしまうため、新田さんは相手にしなかった。
ところが、夫は自分で姉2人に電話し、夫の実家近くの喫茶店で会う段取りをつけてしまう。
「夫が姉たちに『俺はこいつにいじめられているから、離婚か別居がしたい』と切り出すと、『大事な弟なんだからちゃんと面倒見なさいよ!』『かわいそうな弟!』と義姉2人にののしられました。
でも、私は夫を約9年介護してきましたが、義姉たちは数年前、義母の介護に音を上げて、1年も経たずに施設へ入所させているうえ、私が助けを求めても、真剣に話を聞いてはくれませんでした」
新田さんvs義姉2人+夫で激しい口論になったが、見かねた下の義兄が間に入り、話し合いを仕切ってくれた。
夫はグループホームなどの見守りサービスがある施設に入るのが現実的だが、「見守りなんて要らない! 一人暮らしできる!」と渋る。新田さんは、「私も娘たちも、夫の一人暮らしのための保証人になんてならない!」と話は平行線。結局下の義兄に、「このまま別居か離婚をしたほうがいいのではないか?」と言われた。
新田さんは、その後も夫の希望どおりにしたほうがいいのか、自分が介護を続けたほうがいいのか考えた。しかし答えが出ないので、久々に母親に電話してみることに。
現在71歳の母親は、身体は弱いが頭はしっかりしている。新田さんが珍しく弱音を吐くと、母親は言った。
「あなたにまだ夫を愛する気持ちがあるなら、希望どおり別居してあげたら? それがあなたにできる最後の優しさじゃない? もし離婚するなら、姻族関係終了届を出して、義理のお家とは完全に縁を切りなさい。私があなたならとっくの昔に離婚してるでしょうけど、あなたは昔から我慢強いから……」
新田さんは、はっとした。
「『私は今まで何にこだわっていたんだろう?』と思いました。私は今まで夫を心配なあまり、『私が面倒を見なければ!』と思い込んでいて、夫にとっては重荷になっていたのかもしれません。『離婚したい』と言う人の介護をし続けるのも精神的にしんどいですし、1人で介護を続けることに限界を感じてもいます。
今、私にできることは、障害福祉サービスの手続きをし、夫が望む別居に向けて環境を整えて、夫が1人でも暮らしていけるようにすること。夫にも私にも希望が持てる未来につなぐことではないかと考え始めました」
■1人で抱え込まないために
新田さんは、障害福祉サービス利用のための手続きを進めた。しかし、「障害者数に対してサービスを提供できる事業所や人が少なく、順番待ちになるため、サービスを受けるまでかなり待つことになります」と言われる。「介護保険なら待ち時間が少ないので、旦那さんに高齢に起因する疾患がないか確認してみてください」とのこと。
障害者の福祉サービスは、高齢者の介護よりも整備が遅れているようだ。
「私の生きる支えになったのは、2人の娘でした。娘たちの父親だから、介護し続けられたのだと思います。高次脳機能障害の介護は人によって違いますが、夫の場合は暴言・暴力が激しく、感謝されることがほぼないため、介護の負担が重く感じます。
でも、親やきょうだいなど、周囲の人が介護している人のつらさ・苦しさを理解して、共感や感謝、ねぎらいの気持ちを持ってくれていたら、負担感は全然違ってくると思うのです」
ダブルケアの多くのキーパーソンは孤独だ。
「介護をしていて感じるのは、共感してくれる存在の大切さです。人とのつながり、地域とのつながりをもっと大切にすべきだったと今頃になって感じています。介護は長期戦です。私のように1人で抱え込んでいると、いずれ破綻します。1人で抱え込むのがいちばん危険です。今すぐにでも、信頼できる人に相談したり、福祉サービスを利用したり、周りの人の力を借りてください」
新田さんは、自分と夫と娘たちにとって明るい未来を模索している。
旦木 瑞穂 :ライター・グラフィックデザイナー