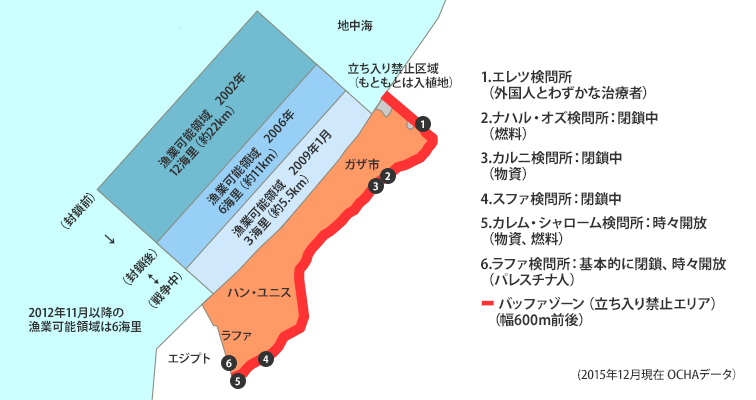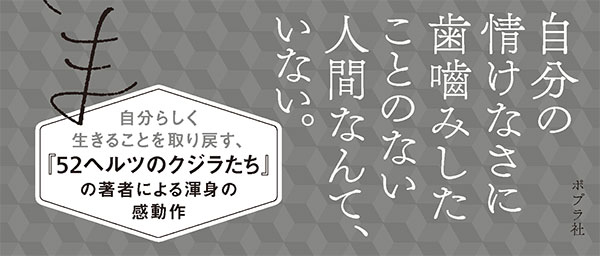53歳の彼が、国際連盟から「人間にとって最も大事だと思われる問題を取り上げ、一番意見を交換したい相手と書簡を交わしてください」と依頼され、選んだテーマがこの本のタイトルであり、その相手はフロイト。当時76歳だったフロイトは1917年に『精神分析入門』を刊行し、やはり名の知れわたった碩学であった。
時代はすでに全体主義の足音が聞こえはじめており、ナチ党の政権掌握は1933年1月。アインシュタインはユダヤ人(後にアメリカへ亡命)、フロイトもユダヤの血を引いている。
解説の養老孟司は、当時のアインシュタインにとって「ナチの勃興が焦眉の重大問題だった」と述べ、フロイトはその問題に気づいていないともみえるとしている。
アインシュタインは「人間を戦争というくびきから解き放つことはできるのか?」と問い、「人間の心を特定の方向に導き、憎悪と破壊という心の病に冒されないようにすることはできるのか?」と悩む。
また、「“教養のない人”よりも“知識人”と言われる人たちの方が、暗示にかかりやすいとも言えます」と。
これに対してフロイトは「人間から攻撃的な性質を取り除くなど、できそうにもない!」と明言する。戦争とは別のはけ口を見つけてやればよいと言い、エロス(愛)と破壊衝動をキーワードに問題解決に挑む。
そして、「文化」をヒントに彼なりの示唆深い解答を提示する。70年前の往復書簡。冷戦が終息し、地域紛争の多発で明けた21世紀に、このフロイトの解をいかに読み解けば良いのであろうか?
養老孟司の解説「脳と戦争」は往復書簡との関連性でみると、いまひとつ理解できない。「人の攻撃性が生得的であろうとなかろうと、人が見ている世界は所詮はヴァーチャルである」とし、「それならヴァーチャル世界で戦争をすればいい。攻撃性をそこで満足させればいいのである」と言う。しかし増加する内戦や地域紛争では、斧(おの)や自動小銃で殺戮を犯す“ヴァーチャル”とは言えない現実がある。
付録「戦争の世紀」は1898年の米西戦争以降の戦争を列挙しているが、その意義は不明。高校の歴史教科書の要約である。(澤田哲生)
ナチズムの嵐に消えた世紀の戦争論!世紀の変わり目の今、日本に甦る!一九三二年、国際連盟がアインシュタインに依頼した。「人間にとって最も大事だと思われる問題をとりあげ、一番意見を交換したい相手と書簡を交わしてください」とりあげた問題は、戦争。相手は、フロイトだった。
感想
フロイトの返信は非常に面白い。また養老先生の注釈が文化の差異をうまく解説してくれています。
政治家・学者連中に読ませる本
9・11のWTCのテロ発生から一年。またもや戦争という名の亡霊がはびこり始めたようである。ブッシュ親子はどうしてそんなに戦争がしたいのだろう。彼は言う、正義のために。でも正義ってなに?いったい誰のための正義?もちろん答えはアメリカのためである。その結果、どうしてわれわれを巻き込もうとしているのだろう?
そんな時だからこそ、20世紀最大の英知の会話が今ほど必要なときはないのではないだろうか。戦争は不可避であるのだろうか?遺伝子がそうさせているのだろうか?答えはNOであろう。言葉で考えた論理が、身体的表現として戦争を是認する。とくに、政治家・学者連中は自分の身には大きな身体的危害が及ばないから勝手に正義を論理だてる。自分がやばくなったら他国へ逃げるのに。もちろん、戦争に行かされるわれわれ一般人としては、彼らの論理には反対ではないか?
戦争に関する限り、頭で考えるのは止めにして、利己的な遺伝子的に、戦争反対と言おうではないか。
間違いなく人類史上最重要な書の1つ
人類史上、イエス・キリストに次ぐ有名人と言ってもさして無理のない二人が、人類に戦争を止めさせる方法について書簡を交わしたのですから、歴史的な出来事であり、もっと注目されて良いはずです。
もちろん、いかに天才とはいえ、このような難しい問題に簡単に答が出せるはずがありませんし、フロイト自体は非常に悲観的な見解を述べています。しかし、よく読むと、恐るべき貴重なヒントが提示されていると思います。
アインシュタインおよびフロイトについて、十分に知識を得てから読めば、更に価値の高さが理解できると思いますが、逆に、このシンプルな書簡から、この人類史上最高の賢者達に興味を持つこともあると思われます。そして、後者の場合にも本書は実に適切な書であると思います。
アインシュタインがただ科学の天才であるだけではないことには多くの方が同意すると思いますが、彼が選んだ最高の賢者は、ともすれば誤解され、あるいは、売名のために卑劣に彼を貶める輩が実に多いながら、例えばマスローにおいては「自分の仕事はフロイトの深い意味の探求」と言わせた、真の天才フロイトであったことも感慨深いと思いました。
80年前に書かれた書簡とは思えないくらいリアルです
提起されている問題が今でも解決されてないという現実
戦争が繰り返されている世界と向き合わなければならない
という現実、結局何も進歩していないという事なのか。
一読の価値あり、しかし物足りない
この本はアインシュタインが国連から「今最も大切なテーマについて誰を指名して意見を交換してもよい」という提案を受け、フロイトを選び、テーマに戦争を選んで交わされた2通に手紙をメインとした本である。後半は「二人の手紙の推測による解説」と「日本人の戦争にたいする意識」「世界で起きた戦争の時事」が書かれている。
ちなみにアインシュタインはルーズベルトに爆弾の開発を即す為に手紙を送ったのではない
「未来のエネルギー源としての研究。爆弾は作れると思うが今のところ無理だろう」という内容で、開発は彼には秘密で行われた。(ウィキペディア)
私の印象では、アインシュタインは「兵器よりヒトを恐れていて、自分の研究が悪用されることを推測している」 もしも彼が「爆弾を作れる」と確信していたらルーズベルトへの手紙はなかったかもしれないし、敵国よりも先に行くために送っていたかもしれない。
私はこの本から「開発した者と悪用する者のどちらが悪いのか?」という疑問を覚えた。
この本自体は面白い、戦争について考えるなら二人の手紙の内容は一読の価値があると思う。
が、物足りなさは否めない、これ以降に文通が続かなかったので仕方ないが・・・。
衝動理論のことはよくわかります
アインシュタインは言う。「人間には本能的な欲求が潜んでいる。憎悪に駆られ、相手を絶滅させようとする欲求が!」
これがフロイトへの問いかけであり、フロイトは精神分析学の衝動理論(エロスとタナトス)を引いて、「人間から攻撃的な性質を取り除くなど、できそうにない!」と答えながらも、文化の発展に一縷の希望を託す。
アインシュタインからのもう一通の手紙が欲しかったですね。いったいどんな意見をもったでしょう。中途半端な終わり方という感は免れません。養老先生の解説もいまひとつですし。
一番びっくりしたのは、アインシュタインが広島・長崎の原爆に強い憤りを覚えていたこと。自分の発見した理論があのような形になるなんて、原爆投下から13年前にこの手紙を書いていた頃は思いもよらなかったでしょうね。
知的な逡巡を味わう
アインシュタインとフロイトが戦争について書簡で意見を交換し合う!?
当時高校生だった私には大いに興味をそそられる作品でした。
両者の書簡ともよく戦争という話題について考え込まれた
とても丁寧なもので、読む価値は大いにあると思います。
ただ、フロイトは相変わらずというべきか独特の意見を展開していて
論理を外れる部分もあり、大学1年のとき論理学の授業でこの本を
論理的に批評するレポートを提出したほどでもあります。
とにかく、「ヒトはなぜ戦争をするのか?」という根本的であるにも
関わらずあまり深く考えない分野についての2大知識人の考察は一読
の価値ありだと思います。
友人などと読みあって考えあうのもいいでしょう。
ただ、牧場の少女カトリという作品中にあった、「嵐や吹雪と違って
戦争は人間が始めたものだから人間がやめさせる事ができるはずだわ」
という単純な考えも忘れたくないなー、と最後に蛇足な個人的付け足しです。
ちょっと期待はずれ
往復書簡!というわりに1往復しかしていない・・。
往復にはちがいないけどさあ・・というかんじ。
ただ内容は非常に濃いです。文庫で700円とかで読めたら
もっとよかったなー。