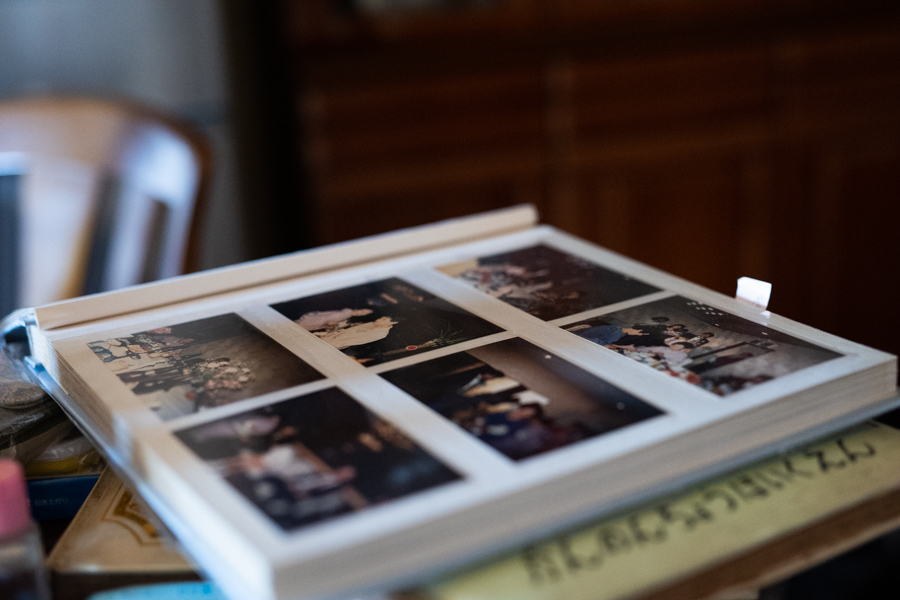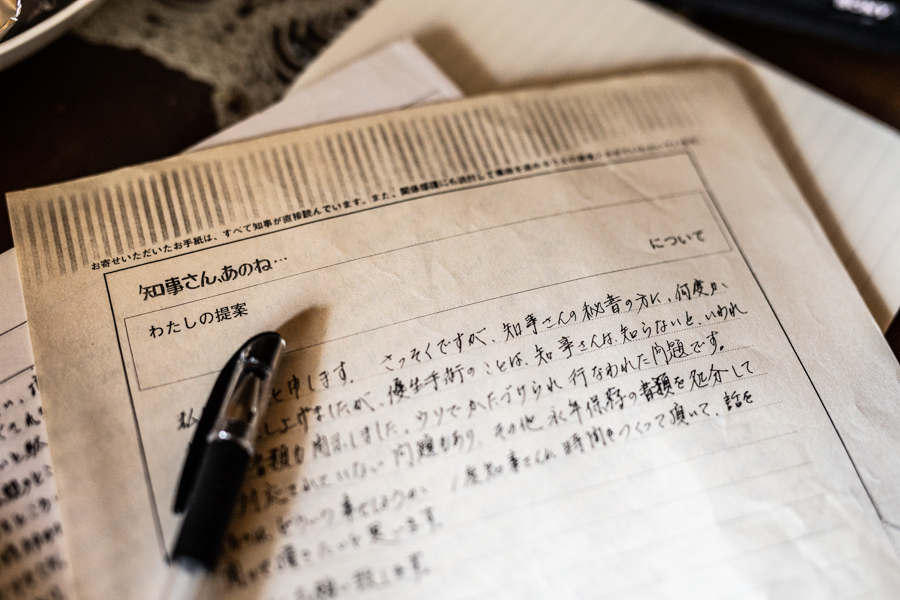アプリ限定 2024/10/09(水)

寛仁親王牌と全プロの深い関係
10月17〜20日に弥彦競輪場で開催される「寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント(GI)」。8月下旬に出場選手108名が発表された。
この大会は、1990年に日本で開催された「世界選手権自転車競技大会」において寛仁親王が名誉総裁を務めたことが由来となっている。近年は前橋競輪場か弥彦競輪場で開催されることが多く、過去には青森競輪場で開催されたこともある。
この大会のひとつの特徴として、5月末に高知で行われた「全日本プロ選手権自転車競技大会(以下「全プロ競技大会」)」における成績が考慮される。さっそく選考条件から見ていこう。
【寛仁親王牌 選考条件】※開催時S級在籍
(1) 開催時S級S班在籍者
(2) 寛仁親王牌で3回以上優勝した者(開催時S1在籍)
(3) パリ五輪自転車競技トラック種目代表選手
(4) 選考期間において2か月以上JCFトラック種目強化指定(S)に所属した者(開催時S1在籍)
(5) 選考期間における世界選トラック競技出場者
(6) 選考期間における世界選に準ずる国際大会トラック競技の1〜3位
(7) 選考期間におけるアジア選ケイリン及びスプリント1位
(8) 過去の五輪自転車トラック種目メダリスト(全プロ競技大会出場かつ開催時S1在籍)
(9) 2024年度全プロ競技大会各種目の1〜3位 (ケイリンは決勝出場者)
(10) 2024年度全プロ競技大会出場者で選考期間における平均競走得点上位者 (同点の場合は選考用賞金獲得額上位者)
(11) (1)〜(10)で108名に達しない場合は2023年度地区プロ大会出場者から平均競走得点を勘案し選手選考委員会が推薦した者
※選考期間は平均競走得点が2024年2月〜7月の6か月間、国際大会成績が2023年8月〜2024年7月の12か月間
自転車競技での成績に関する選考条件が多数含まれているが、今回の大会日程と「世界選手権自転車競技大会」の日程が重なっているため、太田海也らナショナルチーム勢の出場はない。
よって、今大会の選考のポイントは(9)(10)の全プロ競技大会出場者、成績上位者ということになる。
オールスター競輪(GI)に出場した選手のうち、寛仁親王牌の出場権を逃した選手(ナショナルチームを除く)は、北津留翼、武藤龍生、和田真久留など。和田は賞金14位、武藤は17位と上位だが、いずれも全プロ競技大会には出場していなかった。

また、昨年大会ファイナリストで弥彦競輪がホームバンクの諸橋愛も同様に、出場選手に名前がなかった。
全プロ競技大会の結果は
「全プロ競技大会」は新型コロナウイルスの影響で、2020年から2022年まで中止に。2023年に富山で4年ぶりに行われ、今年は高知500バンクで開催された。では今年の結果はどうだったのか、振り返ってみよう。
全プロトラック各競技上位者
| 出場種目 | 選手名(級班) | 所属地区 |
|---|---|---|
| スプリント | 1位 河端朋之(S1) 2位 雨谷一樹(S1) 3位 佐々木悠葵(S1) |
中国 関東 関東 |
| ケイリン | 1位 山口拳矢(SS) 2位 松井宏佑(S1) 3位 郡司浩平(S1) 4位 新山響平(SS) 5位 眞杉匠(SS) 6位 山田庸平(S1) 7位 荒井崇博(S1) |
中部 南関東 南関東 北日本 関東 九州 九州 |
| 1kmタイム トライアル |
1位 菊池岳仁(S1) 2位 新田祐大(S1) 3位 村田祐樹(S2) |
関東 北日本 中部 |
| チーム スプリント |
1位 久米康平(S1)、太田竜馬(S1)、島川将貴(S1) 2位 深谷知広(SS)、渡邉雄太(S1)、簗田一輝(S1) 3位 井上昌己(S1)、佐藤幸治(S2)、梅崎隆介(S2) |
四国 南関東 九州 |
| エリミネイション | 1位 小林泰正(S1) 2位 小林潤二(S2) 3位 舛井幹雄(A1) |
関東 関東 中部 |
| 4km個人 パーシュート |
1位 近谷涼(A1) 2位 渡辺正光(S2) 3位 梁島邦友(A1) |
中部 北日本 関東 |
| 4kmチーム パーシュート |
1位 角令央奈(A1)、原井博斗(S2)、橋本陸(A2)、上野恭哉(A1) 2位 近谷涼(A1)、重倉高史(A1)、吉川希望(A1)、南儀拓海(A2) 3位 新村穣(S2)、嶋津拓弥(S1)、堀内俊介(S2)、佐々木龍(S2) |
九州 中部 南関東 |
※太字の選手はS級=寛仁親王牌出場予定。佐藤幸治選手はあっせん停止のため不出場

上記からケイリン、スプリント、1kmタイムトライアル1位が初日メイン「日本競輪選手会理事長杯(日競杯/理事長杯)」に、ケイリン決勝2〜7位(失格除く)、スプリント2〜3位、同1kmT.T.2〜3位、チームスプリント1位が特選予選に出場できる。
寛仁親王牌出場選手の競走得点
寛仁親王牌出場正選手108名の平均競走得点は、109.08(熊本記念終了時点)。
参考までに、出場人数が同じ108名のGI全日本選抜は正選手の平均競走得点が109.87、GI高松宮記念杯競輪は110.80。全プロ競技大会で好成績を残したS級2班の選手も多く選ばれることから、寛仁親王牌の平均競走得点はやや低くなっている。

出場選手の中で100点を切っているのは渡辺正光、小林潤二、梅崎隆介の3名だ。いずれも全プロ競技大会で結果を残しての出場で、渡辺は4km個人パーシュート、小林はエリミネイション、梅崎はチームスプリントで上位に入った。
勝ち上がりを解説
寛仁親王牌は4日制のGIとなる。初日のシードレースは2種類あり、格上の「日本競輪選手会理事長杯(日競杯/理事長杯)」1レースと特選予選が2レース設けられている。
日競杯上位5名と特選予選上位2名が2日目メイン「ローズカップ」へ進む。ローズカップ出場選手は失格にならない限り準決勝に進出できる。
一次予選9レースでは二次予選2種類への勝ち上がりを競う。上位2着までが準決勝へ4着権利の「二次予選A」、3〜4着は準決勝へ2着権利の「二次予選B」へ進むことになる。2着権利は非常に厳しいため、シビアなレースとなりそうだ。
また日競杯6〜9着と特選予選3〜4着と5着のうち選考順位上位1名が二次予選A、特選予選下位は二次予選Bに回る。
準決勝以降は通常のグレードレース同様に、上位3名が決勝進出となる。4日制のGIということで、シード組はかなり有利に勝ち上がりを進めることができそう。一方で一次予選スタートの選手にとっては初日から緊張感が大きいだろう。
一発逆転グランプリもあり得る! 4日制GI
今回の寛仁親王牌の優勝賞金は昨年から200万円アップの4000万円。決勝3着までが1000万円を超える賞金が与えられる。また2日目ローズカップの1着賞金は114万3000円で、準決勝1着は80万5000円だ。

優勝者には年末のKEIRINグランプリ出場権が与えられる。賞金でのグランプリ争いも白熱しており、ボーダー上の選手は自身の勝ち上がりはもちろんのこと、出場権を争うライバルとの戦い方も意識してくるだろう。
熊本記念終了時の賞金ランキングでは、ボーダー上の6〜7000万円台に6名がひしめく接戦に。すでにグランプリの出場権を持った選手の優勝となれば、賞金争いの熾烈さに拍車がかかるだろう。

賞金ランキング19位の松浦悠士と25位の山口拳矢が“赤パン”を維持するためには寛仁親王牌か競輪祭、いずれかのGIを獲るしかない。2人とも日競杯からのスタートであるため、一発逆転のチャンスは十分ある。
競輪祭がシードなしのポイント制予選を含む6日制であることを考えると、ここで「獲りたい」と考えている選手が多いはず。激闘の4日間、競輪ファンの皆さんには初日から余すことなく楽しんでほしい。