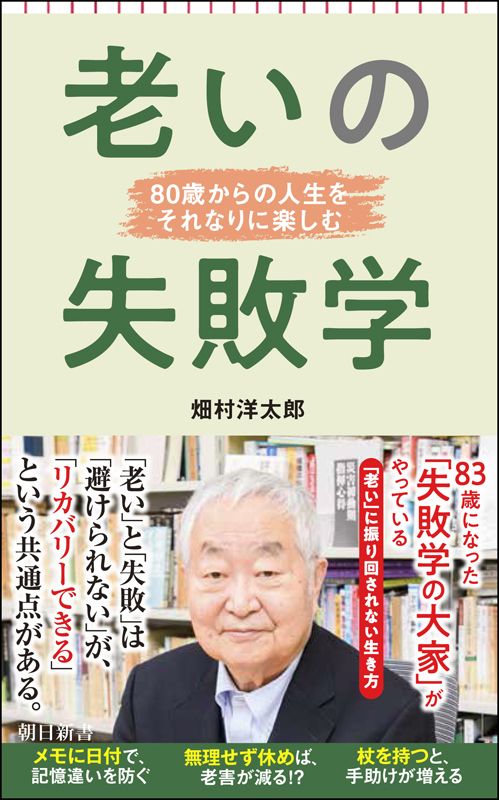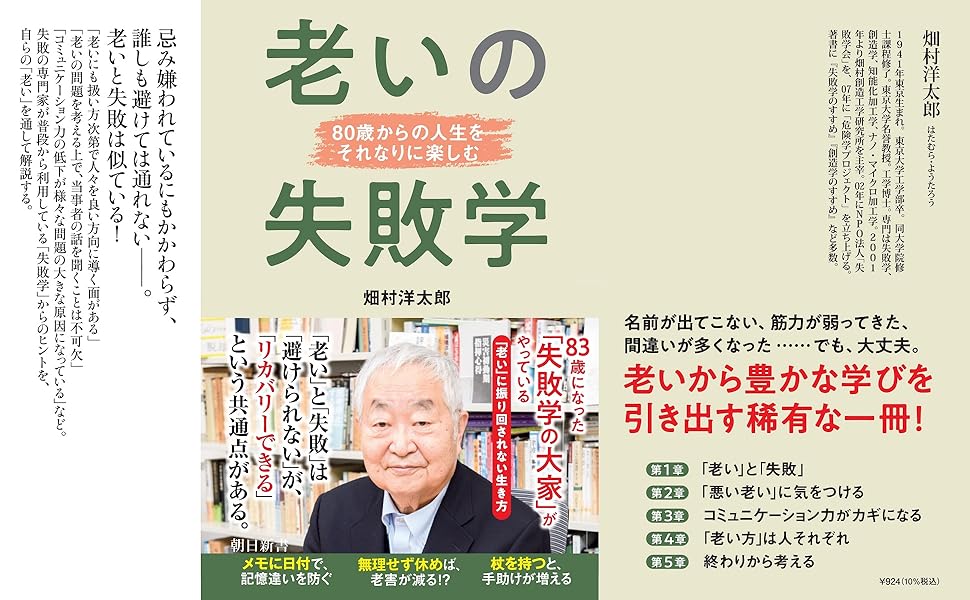久しぶりの取手競輪場へ向かう。
そして、競輪場正面門の左手奥の路地裏の食堂「さかえや」へ寄る。
知人が二人。
常連のお客さんたちは、既に皆さん帰宅していた。
珍しくママさんの娘さんが手伝いに来ていた。
8レースから車券は買わずにテレビ観戦し、最終レースのみ車券を買う。
実は、締め切られた車券が買えないレースがあったが、その予想が外れていた。
2-5 2-3 3-2の3連単が、4-3となる。
3000円失うところで、救われた。
そして12レースは?!
並び予想 3-8 6-1 2-4-7 9-5
| 予 想 |
着 順 |
車 番 |
選手名 | 着差 | 上り | 決ま り手 |
S / B |
勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 9 | 古性 優作 | 11.4 | 捲 | 捲上斬込む | ||
| ○ | 2 | 5 | 南 修二 | 3車身 | 11.5 | 差 | 挟まれ立直 | |
| ▲ | 3 | 8 | 平原 康多 | 1車輪 | 11.5 | 松浦弾き伸 | ||
| 4 | 7 | 佐藤 慎太郎 | 3/4車身 | 11.6 | 新田祐任せ | |||
| 注 | 5 | 1 | 松浦 悠士 | 1車輪 | 12.0 | 古性掬われ | ||
| × | 6 | 3 | 眞杉 匠 | 1車身1/2 | 11.9 | 捲り併され | ||
| 7 | 6 | 犬伏 湧也 | 3/4車身 | 12.4 | B | 新山潰して | ||
| △ | 8 | 4 | 新田 祐大 | 1/4車輪 | 11.9 | S | 新山かばい | |
| 9 | 2 | 新山 響平 | 8車身 | 12.9 | 犬伏叩かれ |
レースダイジェスト映像
| 2 枠 連 |
複 |
|
2 車 連 |
複 |
|
3 連 勝 |
複 |
|
ワ イ ド |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 |
|
単 |
|
単 |
|
戦い終わって
犬伏湧也のカマシを強烈なスピードで飲み込み一着の古性優作は「スタートが取れれば良いなと思ってたが二番目から。平原(康多)さんがカンナ削りをしてきたので眞杉(匠)の所に追い上げて勝負しようと。犬伏君がカマして新田(祐大)さんが切り替えると思ったが新山(響平)君を入れたので自分のタイミングで仕掛けました。最終二センターの所は内に入ったというより吸い込まれた感じ。松浦(悠士)君が落車しそうにもなっていたので松浦にも犬伏にも当たらないようにすり抜けた感じ」。
古性に離れた南修二だが最後はコースを見極めて追い込み二着。「しっかり離れないようにと思ってたが離れてしまった。スピードで離れましたね。レースになってなかったし着はおまけみたいなもの。次に古性君と連係する時は修正したい」。
三着に入った平原康多は「ヤバかった。眞杉君はかなり脚を使っての何十番手かだったのでさすがにきついかなと。でも諦めずに行ってくれて後は自分がどうするかの判断でした。古性君が内に入ったのが分からず自分は前だけ見て自分のコースをと。前回の調子なら眞杉君に離れていたと思うし、色々と試そうとやってきた事が今回良い方向に出たと思う」。
投票