日本のコンサートホールで見る(聞く)というのも、何か阿波踊りをサントリーホールで見物するような(そんなことは多分ないだろうけど)違和感を覚えるのだけれども、昨日(8/25)すみだトリフォニーで見たスアル・アグンはけっこう楽しめた。
スアルアグンの演奏は基本的に竹の打楽器が基本なのだが、時折管楽器も登場する。ガムランやケチャというのはポリリズムがリズムの基本なので、それなりのアンサンブル訓練が必要になってくるけれども、こうした地方(インドネシアやタイ、ベトナムといった地方)の音楽は、農耕(米作)する人間と神とのコミュニケ-ションを音楽で媒介することが主な役割。ガムランではあまりメロディやハーモニーは重要視されない。メロディやハ-モニ-で語る西洋音楽とは違い、リズムで話していかなければならないからこそ音楽が複雑なポリリズムになってくるのだろう。しかも、音楽そのものが神との対話なので、異界とのコミュニケーションを図るためにトランス(要するにハイになって「向こう」に行ってしまう状態)が絶対的に不可欠になってくる。
男性ばかりの14人の打楽器アンサンブルのリズムの中でメンバー数人が演奏中に突然憑衣状態になって舞台の上で次々に倒れこんでいった。そんなサマは昔のGSの「失神」状態にもある種似ているナと思った。
要するに、音楽の演奏というものには「トランス」が必要なのであって、それを簡単に起こさせてくれるこうした音楽が農耕民族の儀式の中で発展したのも頷ける。
じゃあ、GSも同じか?。
うん、多分同じだと思う。今のクラブ音楽だっていつもクスリがそこにつきものだ。クスリが必要なのは、このトランス状態が欲しいからだろう。ロックやジャズだって必ずクスリがそこにあるのは、音楽でトランスを起こす助けになるからこそ。
じゃあ、クラシック音楽はどうなの?と思われるだろうが、クラシック音楽というのは、基本的にキリスト教が作り出した音楽。キリスト教はこうしたトランス状態を異教として排除してきたのでそことは相容れない。映画「ダヴィンチ・コード」で自分の身体に鞭打っていた男の姿こそが「異教」そのものなのだ(鞭を打つのが修行なのではなく、このトランスを作り出すため)。
そう考えるとクラシックとクラシック音楽以外の音楽の違い(これが「正統と異端」という西洋文化の中で何百年も続いてきた大テーマにも関係してくる)が理解できるのだが、これは音楽が直接的に「何」と向き合っているかという問題と根本的に関わってくるので、ここで深いところまでは突っ込まないでおく。
それにしても、ふだん女性ばかりオーケストラで何十人も女性と向き合っている私としては、男性ばかりのアンサンブル(しかもコスプレで化粧をしている人たちだ)というのはとっても新鮮だった。
スアルアグンの演奏は基本的に竹の打楽器が基本なのだが、時折管楽器も登場する。ガムランやケチャというのはポリリズムがリズムの基本なので、それなりのアンサンブル訓練が必要になってくるけれども、こうした地方(インドネシアやタイ、ベトナムといった地方)の音楽は、農耕(米作)する人間と神とのコミュニケ-ションを音楽で媒介することが主な役割。ガムランではあまりメロディやハーモニーは重要視されない。メロディやハ-モニ-で語る西洋音楽とは違い、リズムで話していかなければならないからこそ音楽が複雑なポリリズムになってくるのだろう。しかも、音楽そのものが神との対話なので、異界とのコミュニケーションを図るためにトランス(要するにハイになって「向こう」に行ってしまう状態)が絶対的に不可欠になってくる。
男性ばかりの14人の打楽器アンサンブルのリズムの中でメンバー数人が演奏中に突然憑衣状態になって舞台の上で次々に倒れこんでいった。そんなサマは昔のGSの「失神」状態にもある種似ているナと思った。
要するに、音楽の演奏というものには「トランス」が必要なのであって、それを簡単に起こさせてくれるこうした音楽が農耕民族の儀式の中で発展したのも頷ける。
じゃあ、GSも同じか?。
うん、多分同じだと思う。今のクラブ音楽だっていつもクスリがそこにつきものだ。クスリが必要なのは、このトランス状態が欲しいからだろう。ロックやジャズだって必ずクスリがそこにあるのは、音楽でトランスを起こす助けになるからこそ。
じゃあ、クラシック音楽はどうなの?と思われるだろうが、クラシック音楽というのは、基本的にキリスト教が作り出した音楽。キリスト教はこうしたトランス状態を異教として排除してきたのでそことは相容れない。映画「ダヴィンチ・コード」で自分の身体に鞭打っていた男の姿こそが「異教」そのものなのだ(鞭を打つのが修行なのではなく、このトランスを作り出すため)。
そう考えるとクラシックとクラシック音楽以外の音楽の違い(これが「正統と異端」という西洋文化の中で何百年も続いてきた大テーマにも関係してくる)が理解できるのだが、これは音楽が直接的に「何」と向き合っているかという問題と根本的に関わってくるので、ここで深いところまでは突っ込まないでおく。
それにしても、ふだん女性ばかりオーケストラで何十人も女性と向き合っている私としては、男性ばかりのアンサンブル(しかもコスプレで化粧をしている人たちだ)というのはとっても新鮮だった。















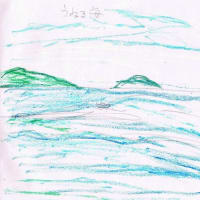


キッチンライヴ、受賞祝いの鈴木さんお連れしていきますよ~。ご紹介しますネ。がんばってください!
(あとbbs、ひらけません。)