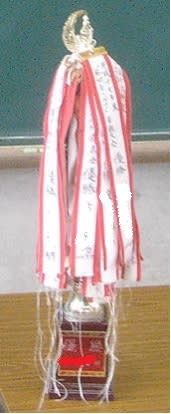なぜかと言うと、授業中は見えない子供の素顔が見えるからである。
・・・という理由もあるが、本当は、自分が子供達と遊ぶのが楽しいからである。
最近は、サッカーをすることが多い。
今日は、うれしいことがあった。
遊んでいる時、いいプレーを見たら、その場で褒めるようにしている。
「ナイスシュート」
「ゴール前のいい位置にいたね。だからシュートできたね。」
「今の守り、良かったよ。」「ボールとゴールの間に入ったから、相手はシュートしにくかったよ。」
「そのしつこさがいい!」
などと言っている。
今日は、褒めまくっていたら、次のように言われた。
「そうやって褒めている先生が偉い!」
そうやって見てくれる子がいるのがうれしい。