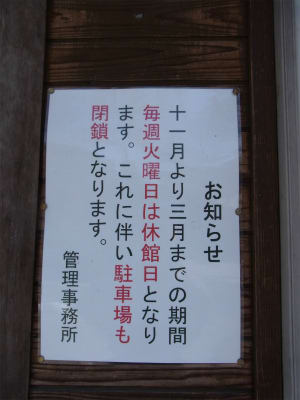5月25日(土)は、里山体験プログラム「川の生きものさがしとトンボの羽化の観察」で、小川町の兜川です。駐車場もトイレもない場所なので大人数では使えませんが、今年は定員20名のところ30名で受付終了となり、キャンセル待ちのご家族も9名と、今までで一番参加希望者が多くてちょっと心配しました。時期的に運動会と重なったりして、最終的にはキャンセル待ちのご家族もなくなり、23名に落ち着いてくれてよかったです。でも、来たかったのに来れなくなってしまった子どもたちは、かわいそうでしたね…。


ちょっと上流に堰があり、そのあたりは深くなっていますが、コイなんていたかなぁ…。3匹は泳いでいました。他の生きものたちがみんな食われちゃう…。
堰より下流は浅くて、小さな子どもたちでも安心して生きものさがしができます。かなりの数のアブラハヤの子どもたちが泳ぎまわっていましたが、これは追いかけても簡単には捕まりません。底のほうから&岸辺まですばやく網を入れるガサガサが基本です。川に入れる場合は上級者は足も使いますが、子どもたちは基本だけでも充分OK。この川で何も捕まらないなんていうことはあり得ません。あとは手数が多いか少ないかだけの問題です。まあ、水面近くだけパシャパシャやったり、トロ~んと網を入れていては、収穫も少ないけどね…。


羽化の途中でちょっと休憩中のシオカラトンボ。2枚目はプログラム終了後の同じ個体です。無事に羽化できてよかったですね。この日は「トンボの羽化の観察」もあるので、「川の生きものさがし」でガサガサする前にまず、アシスタントのあきらに羽化しているトンボを探してもらいました。


羽化したばかりのオジロサナエとシオカラトンボも見つけてくれましたね。アオサナエが川に産卵するシーンも見ることができました。


「川の生きものさがし」では、この2年生が一番いろいろと捕まえていたかな。アメリカザリガニやオニヤンマのヤゴも真っ先に見つけていたし、大きなサワガニまで! とりあえず生きもの系のキッズアシスタントの有力候補です。
サワガニはこの場所では初めて見つかったので、上流から流されてきたのでしょうか? アメリカザリガニはもうどこにでもいるけれども、指標生物としては「きれいな水」のサワガニも「大変汚れた水」のアメリカザリガニもいる川って、なんだかとっても不思議な感じがします。まあ、アメリカザリガニだって「大変汚れた水」でも生きられるというだけのことで、決して「きれいな水」が嫌いなわけじゃないんだろうけれども、風布川では見たことがないから、水温が低い所は苦手なのかな。
最後には、ヤゴの持ち帰り方や飼い方も含めて、新井さんに生きものの説明をしていただきました。


アブラハヤとギバチです。今回確認できた魚の仲間は6種類。アブラハヤがかなり多く、ギバチは4~5匹というところです。ギバチは関東と東北地方のみに分布する日本固有種で、環境省また埼玉県のレッドデータ上は絶滅危惧Ⅱ類だったでしょうか。
ギバチは昔、巾着田で捕まえたオタマジャクシサイズのものがあっという間に30㎝近くなって、60㎝の水槽で何年か飼っていたことがあります。エビが大好きで、ヌマエビやテナガエビを入れておいてあげるといつのまにか0匹になっていました。ナマズ系熱帯魚のエサも好きでしたね。背びれと胸びれに棘があって毒もあるっていうんだけれども、けっこう無造作につかんだりしていても、刺されたことはありません。ほんとなのかな?


ジュズカケハゼとモツゴ。いずれもあきらが捕まえてくれたものだけだったかな?
ジュズカケハゼはかなり見つかっていた年もありましたが、モツゴもいたのかぁ~。数では先のサワガニとアメリカザリガニとは逆ですが、風布川にいるアブラハヤと秋ヶ瀬や彩湖の池にいるモツゴが同居している川もなんだか不思議な感じです。


シマドジョウとホトケドジョウです。ホトケドジョウにはびっくり! これも上流から流されてきたものなのでしょうか? ドジョウの仲間もけっこう捕まっていたと思うけど、この1匹ずつしか写真は撮っていないので、あとはドジョウだったのかホトケドジョウだったのかわからない…。


スジエビと昔はヌカエビって呼んでいたヌマエビの仲間。エビの仲間はアメリカザリガニを加えて3種でした。写真は撮っていませんが、貝の仲間はカワニナとマシジミ(かな? にしとかないと外来種も増えているみたいなので…)、モノアラガイの3種です。


コシボソヤンマとオニヤンマのヤゴです。オニヤンマはこの夏羽化するサイズのものも何匹か見つかっていましたが、新井さんによると飼育して羽化させるのはけっこう難しいみたいですね。


オジロサナエ(小さいほうの2匹)&アオサナエとコヤマトンボ。他にもダビドサナエ・ヤマサナエ・コオニヤンマ・シオカラトンボ・ハグロトンボで、ヤゴは全部で10種です。新井さんがいるから種類もすぐにわかるんだけれどもね…。


サイズは計っていませんが、多分ヒメガムシのほうかな? 2枚目はヒラタドロムシの仲間の幼虫。
ヒルの仲間、泳ぐタイプのカゲロウやユスリカの幼虫も見つかっていて、確認できただけでも30種類近くの生きものが見つかったわけです。意識して探せば、水生昆虫はもっともっと種類が多いはずで、「川の生きものさがし」では一番おもしろい川かもしれません。子どもたちでもガサガサで魚の仲間がつかまえられる川も意外と少ないものです。


午後、送迎の方と希望者は、嵐山町のオオムラサキの森活動センターへ移動。テラスをお借りしてお弁当タイムです。たか爺はおにぎり片手運転で済ませちゃったけど…。
黒板には今年のチョウの確認状況が書かれています。オオムラサキの幼虫も大きく育っていました。2枚目は、ダイミョウセセリとハエトリグモの仲間。


樹液はまだほとんど出ていませんが、クヌギにはサトキマダラヒカゲが多かったですね。アカボシゴマダラも…。イボタノキには、コアオハナムグリがかなり集まってきていました。


今年初の「手乗り毛虫」です。マイマイガの幼虫ですね。http://wonderschool.iinaa.net/kemusitokodomo.htm
お弁当の後、ちょっと駆け足で1時間ほど蝶の里公園をお散歩。都幾川まで出てみました。川のほうは水が少なすぎて今年はいまひとつでしたが、川沿いのクワの木の実は摘めますからね。蝶の里公園内は昆虫も植物も採集禁止ですが、ここは園外なので食べ放題!?
ホタルも発生する細い流れでは、オニヤンマのヤゴやなぜか水中で羽化が始まっていたヤンマの仲間も見つかっていました。トビケラの幼虫も多かったですね。
たか爺としては兜川のホトケドジョウが気になるので、近いうちに改めて確認しに行きたいところですが、平日に1人で行ってもつまらないからなぁ…。今のところ空いている6月8日(土)の午後あたりに、キッズ会員対象の「ホトケドジョウさがし」でも臨時開催? でも、梅雨入りしちゃうとどうかなぁ…。「川の生きものさがし」では、風布川と巾着田の小川中心のワンダースクールですが、今年は兜川へも梅雨明けから夏休みの間に一度は行っておきたいところです。