■英国王のスピーチ/2010年イギリス・オーストラリア
■監督:トム・フーパー
■脚本:デヴィッド・サイドラー
■出演
コリン・ファース、ヘレナ・ボナム=カーター、ジェフリー・ラッシュ、ガイ・ピアース
■ストーリ
1930年代のイギリス。国王ジョージ5世の二男アルバート(のちのジョージ6世、コリン・ファース)は、吃音症のため満足にスピーチ一つできなかった。彼は、社交的で献身的な妻エリザベス(ヘレナ・ボナム=カーター)のすすめで、オーストラリア出身の平民な上に型破りな自称専門家ライオネル(ジェフリー・ラッシュ)の治療を受けることに。徐々に効果も表れ、王族相手にまったく臆しないライオネルとアルバートは、やがて友情で結ばれてゆく。そんな折、即位したばかりの兄エドワード8世(ガイ・ピアース)が、全国民を驚かせる決断をする。
■感想 ☆☆☆*
年末年始は深夜に映画がたくさん放送されるのも楽しみのひとつです。「見たい」と思ってた作品が満を持して登場する至福の季節です。そんなわけで「英国王のスピーチ」。ずっと見たいと思っていました。
見終えた一番の感想は、「望んでもいないのに、兄から国王を押し付けられた英国王ジョージ6世が気の毒でならないよ・・・」でした。けれど、「かわいそう」という気持ちが強いにもかかわらず、その気持ちと同じぐらい清々しさを感じた映画でもありました。
彼が国王という地位を押し付けられてしまったのは、ジョージ6世が強い責任感と信念を持っていたから。「兄の事情なんて知ったこっちゃない。」と押し返すこともできたはずなのに、彼はその選択肢を選ばなかったから。それは、国の未来を本気で憂い、国民の幸せを真剣に願っていたから。彼のそういった人柄と地道な努力がきちんと報われたから、私はこの映画を見て清々しさを感じるんだろうな、と思いました。
彼が努力を始めたのは、決して「国王になったから」ではない。即位前から「国王の一族として、その地位にふさわしくあるべき」と考え、自分の吃音症を治療しようと努力していた。そのことが彼の誠実さと生真面目さと、そして誇り高い人柄を端的に表していて、だからこんなにも応援したい、と思わせられるんだろうな、と思いました。
そして、同時に、だからこそ、本来ならもっと自由に生きられたはずなのに、と思わずにはいられないんだろうな、とも思いました。こんなにも誠実で生真面目な人が「第二次世界大戦直前」というイギリスが、そして世界各国がもっとも大きな危機を抱えていた時代に王位を継承せざるを得なかったことは、きっと歴史の流れに大きく影響しているはずで、彼ではなく、彼のお兄さんであるエドワード8世が国王になっていたら、まったく違う歴史になっていただろうな、と歴史の流れに思いを馳せました。
王位継承が決定し、彼は「こんなこと、一度も望んでいなかったのに。」と号泣します。思いもよらなかった王位継承に戸惑う彼の「王」ではなく「ひとりの人間」としての姿が非常に印象的な場面。そして、私はこの場面で、日本の皇族たちに思いを馳せずにはいられませんでした。私の勝手な思い込みや肩入れかもしれないけれど、彼らもこんなふうな葛藤を抱えてきたんじゃないかな、今も抱えているんじゃないかな、と思わずにはいられないのです。
「人は、その地位にふさわしい品性がついてくる」という言葉を聞いたことがあります。この映画で描かれるジョージ6世は、その地位にふさわしい品性を「自分の努力によって」培った人物でした。自分の努力に裏付けされているから、自分を信じることができる。自分を信じられるようになることで、人は変わることができる。それもまたひとつの事実だと思うのです。けれど、人を根っこのところで支えるのは自らの仕事に対する誇りや自信やだけではなく、自分を信じてくれる大切な家族や友人、自分の声に耳を傾けてくれる他者の存在なんだろうな、と思わせてくれるクライマックスでした。国王として、おずおずと始めた演説は、主治医ライオネルの誘導によって、少しずつ、少しずつ力強くなります。原稿を読む声に力が入り、感情が込められ、命が吹き込まれる。そんな自国の王のスピーチに対して真摯に耳を傾ける国民たち。その場面を見て、発信したメッセージが誰かに届く、ということは、すごくすごく幸せなことなんだな、と思いました。
またBGMがとても静かな曲調でこの場面の邪魔をまったくしていないのに、力強く心に染み入り、印象深かったなー。あまりに印象的だったので、ぐーぐる大先生に「この曲、なあに?」と確認したところ、ベートーベンの「交響曲第7番第2楽章」でした。なるほど・・・。ドイツへの宣戦布告のようなスピーチの場面であえてドイツ出身の作曲家、ベートーベンの曲。と色々、考えさせられました。
ラスト、彼と彼の主治医、ライオネルの友情が終生続いたことが字幕に記されてこの映画は終わりを迎えます。「終生続いた」、つまり、彼には家族以外にも心を許せる存在が終生いたのだとわかり、心から安心して映画を見終えることができました。
■監督:トム・フーパー
■脚本:デヴィッド・サイドラー
■出演
コリン・ファース、ヘレナ・ボナム=カーター、ジェフリー・ラッシュ、ガイ・ピアース
■ストーリ
1930年代のイギリス。国王ジョージ5世の二男アルバート(のちのジョージ6世、コリン・ファース)は、吃音症のため満足にスピーチ一つできなかった。彼は、社交的で献身的な妻エリザベス(ヘレナ・ボナム=カーター)のすすめで、オーストラリア出身の平民な上に型破りな自称専門家ライオネル(ジェフリー・ラッシュ)の治療を受けることに。徐々に効果も表れ、王族相手にまったく臆しないライオネルとアルバートは、やがて友情で結ばれてゆく。そんな折、即位したばかりの兄エドワード8世(ガイ・ピアース)が、全国民を驚かせる決断をする。
■感想 ☆☆☆*
年末年始は深夜に映画がたくさん放送されるのも楽しみのひとつです。「見たい」と思ってた作品が満を持して登場する至福の季節です。そんなわけで「英国王のスピーチ」。ずっと見たいと思っていました。
見終えた一番の感想は、「望んでもいないのに、兄から国王を押し付けられた英国王ジョージ6世が気の毒でならないよ・・・」でした。けれど、「かわいそう」という気持ちが強いにもかかわらず、その気持ちと同じぐらい清々しさを感じた映画でもありました。
彼が国王という地位を押し付けられてしまったのは、ジョージ6世が強い責任感と信念を持っていたから。「兄の事情なんて知ったこっちゃない。」と押し返すこともできたはずなのに、彼はその選択肢を選ばなかったから。それは、国の未来を本気で憂い、国民の幸せを真剣に願っていたから。彼のそういった人柄と地道な努力がきちんと報われたから、私はこの映画を見て清々しさを感じるんだろうな、と思いました。
彼が努力を始めたのは、決して「国王になったから」ではない。即位前から「国王の一族として、その地位にふさわしくあるべき」と考え、自分の吃音症を治療しようと努力していた。そのことが彼の誠実さと生真面目さと、そして誇り高い人柄を端的に表していて、だからこんなにも応援したい、と思わせられるんだろうな、と思いました。
そして、同時に、だからこそ、本来ならもっと自由に生きられたはずなのに、と思わずにはいられないんだろうな、とも思いました。こんなにも誠実で生真面目な人が「第二次世界大戦直前」というイギリスが、そして世界各国がもっとも大きな危機を抱えていた時代に王位を継承せざるを得なかったことは、きっと歴史の流れに大きく影響しているはずで、彼ではなく、彼のお兄さんであるエドワード8世が国王になっていたら、まったく違う歴史になっていただろうな、と歴史の流れに思いを馳せました。
王位継承が決定し、彼は「こんなこと、一度も望んでいなかったのに。」と号泣します。思いもよらなかった王位継承に戸惑う彼の「王」ではなく「ひとりの人間」としての姿が非常に印象的な場面。そして、私はこの場面で、日本の皇族たちに思いを馳せずにはいられませんでした。私の勝手な思い込みや肩入れかもしれないけれど、彼らもこんなふうな葛藤を抱えてきたんじゃないかな、今も抱えているんじゃないかな、と思わずにはいられないのです。
「人は、その地位にふさわしい品性がついてくる」という言葉を聞いたことがあります。この映画で描かれるジョージ6世は、その地位にふさわしい品性を「自分の努力によって」培った人物でした。自分の努力に裏付けされているから、自分を信じることができる。自分を信じられるようになることで、人は変わることができる。それもまたひとつの事実だと思うのです。けれど、人を根っこのところで支えるのは自らの仕事に対する誇りや自信やだけではなく、自分を信じてくれる大切な家族や友人、自分の声に耳を傾けてくれる他者の存在なんだろうな、と思わせてくれるクライマックスでした。国王として、おずおずと始めた演説は、主治医ライオネルの誘導によって、少しずつ、少しずつ力強くなります。原稿を読む声に力が入り、感情が込められ、命が吹き込まれる。そんな自国の王のスピーチに対して真摯に耳を傾ける国民たち。その場面を見て、発信したメッセージが誰かに届く、ということは、すごくすごく幸せなことなんだな、と思いました。
またBGMがとても静かな曲調でこの場面の邪魔をまったくしていないのに、力強く心に染み入り、印象深かったなー。あまりに印象的だったので、ぐーぐる大先生に「この曲、なあに?」と確認したところ、ベートーベンの「交響曲第7番第2楽章」でした。なるほど・・・。ドイツへの宣戦布告のようなスピーチの場面であえてドイツ出身の作曲家、ベートーベンの曲。と色々、考えさせられました。
ラスト、彼と彼の主治医、ライオネルの友情が終生続いたことが字幕に記されてこの映画は終わりを迎えます。「終生続いた」、つまり、彼には家族以外にも心を許せる存在が終生いたのだとわかり、心から安心して映画を見終えることができました。















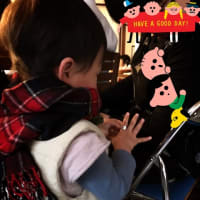




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます