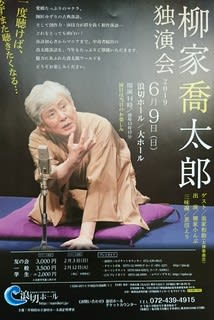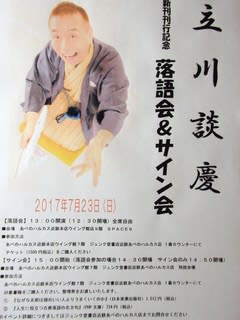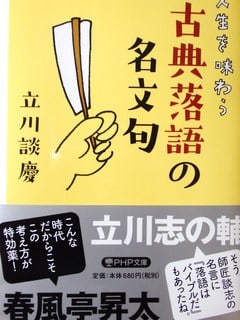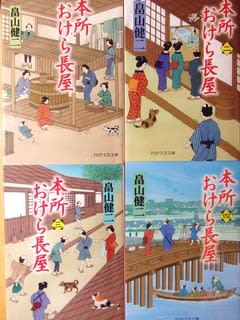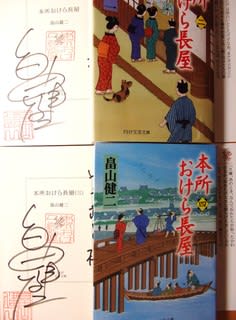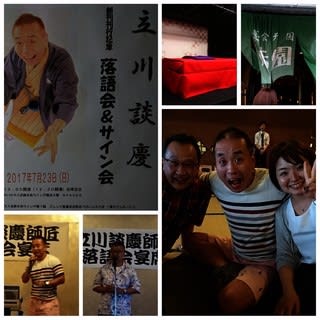入ると、1階の6分の1位の席が白い紐で座れないように確保されている。
東北の3校の中高校生の団体が間もなく入ってくるらしい。
入って来たら、皆さん拍手でお出迎えよろしく・・・・。
一、川柳川柳・・・・・・・・・・・「高校野球の入場行進曲」
いつもの、ジャズではなく、本日はスポーツのテーマ曲の紹介から・・・。
NHKのスポーツのテーマ曲の作曲は確か、古関裕而さん。
今、高校野球か、ゴルフの日本オープンとか由緒ある大会には使われているようですが。
大阪人では有名ですが・・・吉本新喜劇のオープニングのテーマ曲が
各放送局で違ったんですよ・・・
毎日放送、朝日放送、読売TV・・それぞれ懐かしいですな。
「高校野球の入場行進曲」、最近は、嵐はもとより、AKB48なんぞが登場。
でも、各選手によっては想い出の曲なんでしょうな。
川柳さん、覚えきれないと扇子書いてきたのを順に紹介。
まあ、川柳さんじゃないが、私も知らない曲ばかりでおました・・・。
二、三遊亭多歌介・・・・・・・「桃太郎」
今日は、学生さんが来られているので、解り易い噺をと「桃太郎」
これが最高、中堅さんがと思っていると多歌介さん、喬太郎さんより兄さん。
いいね、真打ちが語る、前座噺・・・・・東京の寄席の良さの一つですな。
ほんま、良かったですよ。
三、翁家和楽社中・・・・・・・「曲芸」
お爺ちゃんの和楽、お父さんの小楽、孫の小花、親子三代の曲芸。
三度目だが、構成はすべて同じ・・・。
本日、違ったのは、お父さんの小楽さんの出来・・・・刀剣投げで、落とす、落とす、落とす。
楽屋では、師匠の和楽さん、孫には甘そうだが、息子には厳しい叱咤が飛んでいそう。
やはり、曲芸、上手い下手より、その日の体調と張り詰めた気持ちが大切なんですな。
四、桃月庵白酒・・・・・・・・・「ざる屋(米揚げ笊)」
これも、解り易い「ざる屋」上方でいう、「米揚げ笊」。
白酒さんで・・・でおまっせ。 良ろしおますな・・・最高。
仕事を紹介され、尋ねながら笊屋に行くまでは割愛。
縁起を担ぐ商屋の前で売り声あげるところからたっぷり。
東京の噺家さん、どなたも覚える時はフルバージョンで、
でも寄席では、12~15分の持ち時間の中で完結させるのか。
同じ噺でも、ダイジェスト版で最後まで演じるのか、
お好きなところをたっぷり演じるのか、噺家さんのセンスが問われますな。
五、入船亭扇遊・・・・・・・・・「たらちね(延陽伯)」
続いて、扇遊さんの「たらちね」でっせ。
このあたりで、なぜか嬉しくなってしまった。
普段は、上方にある噺は上方の方が断然おもしろいと思っていたが、
真打、師匠連が演る噺の息と間の絶妙のもしろさ・・・・・。
工夫された、科白のいろいろ、今日は、東北の学生さんに感謝、感謝でおます。
六、柳家小菊・・・・・・・・・・・「粋曲」
これまた、小菊姐さんの粋な高座。
吉原であろうと、おめかけさんであろうと、いつものままで・・・。
あんた達わかる、今はわからなっくても、そのうちわかるようになるから・・・。
さあ、ついてこれるだけ、ついてきなさい・・・・。
この、色っぽさに、後ろに座った中高校生の男子生徒は
どんな顔をして聞いていたのか見てみたかったですな・・・・。
七、三遊亭金時・・・・・・・・・「禁酒番屋(禁酒関所)」
酒にまつわる噺だが、役人のぐでんぐれんぶりは上方の方が強烈か。
禁じられているものを破るというより、頓智比べみたいなもの。
商売では負けたが、頓智では勝った、酒屋の丁稚たち。
親旦那、溜飲を下げたが、もうこの手は使えませんな・・・。
八、三遊亭歌奴・・・・・・・・・「新聞記事(阿弥陀池)」
馴染みのある歌奴の名、先代が円歌を襲名して空跡になって40年。
6年前に、4代目歌奴として襲名。・・・・40年も空けてあったんですな。
この噺も、やはり、最初の阿弥陀が行けの仕込があって、
最後のサゲに、「それややったら、阿弥陀が行けと言いました」が聴きたいですな。
東京では、時間があればやはり、このサゲのフルバージョンの形もあるんでしょうな。
九、アサダ二世・・・・・・・・・「マジック」
アダチ龍光さんのお弟子さん。しゃべくりは、やはり似ている。
上手いのか、そうでないのか、あざやかさよりもお喋りで楽しませてくれる。
でも、師匠の名も空いたまま・・・・、落語家と違って色物は一代限りで複雑なんでしょうか
引田天功あたりの襲名も、最初は女性、それも小娘と思っていたが今や世界的マジシャン。
名は体をあらわすの例えのごとく、名前って大事ですよね。
十、桂文楽・・・・・・・・・・・・・「悋気の火の玉」
名跡、文楽の登場、九代目。
上方でも、なかなか出会えない噺。
「悋気の独楽」とよく似た設定。
旦那が本宅と妾宅の間を往ったり来たり。
女の嫉妬は怖いですが、怖さはこちらの方が上、
だって、火の玉になってからも、「ふん~」の焼もちセリフ。
モテるのと嫉妬は別もんみたい、張りあう相手に腹が立つんでしょうな・・・。
十一、三遊亭歌る多・・・・・「松山鏡」
凄い芸歴・・・喜多八さんやさん生さんより真打昇進が半年早くて先輩。
こちらの露の都一門が十八番だけに、女流落語家の「松山鏡」は違和感一切なし。
仕草やかわいさ全面に出した喋りにおおいに騙されるとこ・・・。
女性芸人さんの年って、解り難いですよね・・・・。
十二、ペペ桜井・・・・・・・・・「ギター漫談」
ギター漫談、何でもできます、リクエストを、客席から「ショパンのノクターン」
ええ、クラシックもできるのかと、21曲ある中から何をと期待させたが、
「夜想曲」と再び言う客に、「日本語で言ってよ」と、さっきから云われてるやん。
唄うのは、フランク永井、など流しの曲ばかり・・・・決して悪くはないが。
何でもできます、弾けますと、豪語したわりには尻すぼみの高座。
ノックダウンのペペ桜井さんでおました。
十三、林家正蔵・・・・・・・・・「読書の時間」
林家正蔵さん、「読書の時間」。
学校の読書会に、親父の本棚から借りてきたのが、司馬遼太郎の「竜馬がゆく」。
でも、カバーはそれだが、中身はエロイ本。
授業中、先生に当てられ皆の前で朗読。
修学旅行の生徒さんたち、大いに受けていたこと間違いなし。
自分たちの日頃の学校生活が落語になっているんだから・・・
感激ものでしょう・・・・・・・良い、思い出になってるんでしょうな。
高座を降りられたあと、後ろの席で若い男が連れの女の人に
これが自分で創った創作落語というもので・・・と知ったかぶりの声。
思わず、作者は、三枝さん、今の文枝さんでっせと云いたかったけど、
若いカップルの仲がおかしくなっても困るので、そこは大人、じっと我慢でおました。
十四、林家正楽・・・・・・・・・「紙切り」
紙切り、正楽さん、芸術の極み。
お題は「お花見」「弁慶」「チャップリン」。
「チャップリン」最高・・・・今度、リクエストと言われたら、勇気を持って言ってみよう。
十五、三遊亭歌之介・・・・・「龍馬伝」
正蔵さんが降りられてきて、正調「龍馬伝」をと、言われたので、
十八番の「龍馬伝」、でも三回目だと思うが今までで最高。
龍馬の生き方を述べながら、東北の震災にあった1階と2階の修学旅行の生徒に、
どんな苦難にも打ち勝って、「少年を大志を抱け」のメッセージを述べているような、
力の入った高座・・・・・良かったですな。
笑いがすべてですが、伝えたい対象が絞られた時の芸の力とは、
素晴らしいものがありますな・・・・。
でも、歌之助師匠の噺に感動、龍馬の様な立派な人になりたいというより、
落語家になりたい、師匠の弟子になりたいという者がでてきたらどうします。
生徒さんたちと同じく、感動を分かち合えた・・・
三遊亭歌之介さんの「龍馬伝」の一席でした。
浅草演芸ホール・平成二十六年四月中席(夜席)
2014年4月16日(水)
浅草演芸ホール
一、川柳川柳・・・・・・・・・・・「高校野球の入場行進曲」
二、三遊亭多歌介・・・・・・・「桃太郎」
三、翁家和楽社中・・・・・・・「曲芸」
四、桃月庵白酒・・・・・・・・・「ざる屋(米揚げ笊)」
五、入船亭扇遊・・・・・・・・・「たらちね」
六、柳家小菊・・・・・・・・・・・「粋曲」
七、三遊亭金時・・・・・・・・・「禁酒番屋(禁酒関所)」
仲入り
八、三遊亭歌奴・・・・・・・・・「新聞記事(阿弥陀池)」
九、アサダ二世・・・・・・・・・「マジック」
十、桂文楽・・・・・・・・・・・・・「悋気の火の玉」
十一、三遊亭歌る多・・・・・「松山鏡」
十二、ペペ桜井・・・・・・・・・「ギター漫談」
十三、林家正蔵・・・・・・・・・「読書の時間」
十四、林家正楽・・・・・・・・・「紙切り」
十五、三遊亭歌之介・・・・・「龍馬伝」
14-14-81
にほんブログ村に参加中。
クリックで応援、よろしくでおます。
↓↓↓
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村