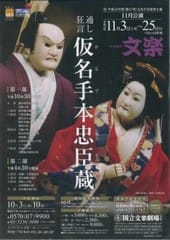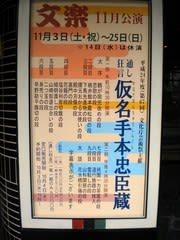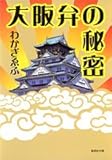新丸八寄席へ、今日は福井からのお客様をお誘いして、今里の居酒屋丸八へ。

詳細は、後日・・・・。
一、桂福丸・・・・・・・・・・・・・「金明竹」
ひと味違う、「金明竹」を聴かせてくれた福丸さん。
普通たて弁のところ、早口言葉を競うように早く言う方が多い中、
使いの方、最初は同業者と思うので、ちょっと早めに話すが、
丁稚さん、頼りなさ過ぎて理解していないようなので、
二回目の女将さんには、噛んで言うようにゆっくりと話すが、同じように解らぬ様子
三度目は、早く帰りたいのもあって苛立ちながら、ちょっと早めに・・・。
その微妙な、気持ちの焦りが各たて弁に現れていて、さすが京大、理論的ですな。
どっしりと、構えた「金明竹」、この噺の楽しみ方がまた一つ増えましたな。
お客様の、明城様のために、たて弁のセリフを・・・・・。
「わたい、松屋町の加賀屋佐吉方から参じましたんやが、先度、
仲買の弥一が取り次ぎました道具七品のうち、祐乗・光乗・宗乗、三作の三所物。
ならびに備前長船の則光。横谷宗、四分一こしらえ、小柄付きの脇差。
あら、柄前が鉄刀木(たがやさん)やとの仰せにございましたが、
埋もれ木やそぉにございまして木が違ぉておりますので、
この旨ちょっとお断りを申しあげます。ならびに、黄檗山金明竹、
寸胴切りの花活け。のんこの茶碗。古池や蛙飛び込む水の音、と申します
これは風羅坊芭蕉、正筆の掛け物でございまして。
沢庵禅師の一行物には隠元・木庵・即非、張り交ぜの小屏風。
こら、うちの旦那の檀那寺が兵庫にございましてな、
この兵庫の坊主のえらい好みまする屏風じゃによって、
表具へやって兵庫の坊主の屏風にいたしました。と、
かよぉお伝えを願いたいんで。」
それに、しても、これをペラペラとよう言いまんな。
丁稚やないけど、もういっぺん言うてぇと、思わず言いたくなる「金明竹」でおます。
ニ、桂壱之輔・・・・・・・・・・・「野晒し」
弾ける楽しさの「野晒し」。
全編、能天気で唄う、「骨ぅ~にぃ、サイサイ・・・スチャラカチャン」の音曲で、
いつも気持ちよくなれるのに、弾けない、弾けない。
壱之輔さんの、シャイの部分が見え隠れして、ちょっと乗りきれてない様子。
「スチャラカチャン、スチャラカチャン」と、壱之輔さんが気持ちよく唄っている
「野晒し」、もう一度聞いてみたいですな・・・・・。
三、笑福亭銀瓶・・・・・・・・・「宿題」
銀瓶さんの「宿題」、おもしろい。
三枝さんの作だが、今や多くの方が演られる「宿題」だが、
銀瓶さんのは、一味も二味も違う。
おやっさんの、問題への怒りぐあいが凄い・・・。
問題が解らないので誤魔化そうとしているのではなく、
聞いた瞬間、単純に問題の出題に怒り狂っている、
普通では困ったお父さんですが、こんなキャラクター好きですな。
さすが、繁昌亭大賞、受賞者の銀瓶さん、武生の奥さんの一言。
「銀瓶さん、華があるわ」の高座でおましたわ・・・。
四、笑福亭鶴二・・・・・・・・・「尻餅」
これまた、鶴二さんの世界。
おやっさんの、賃つき屋との一人二役をしながら楽しんでいる様子が、
また、それを演りながら愉しんでいる鶴二さんを観ていて、
こちらまで、しら蒸すの湯気と共に温かくなってくる。
叩く音は、餅の音、女房の尻を叩く音、いずれにしても幸せの音。
今年も、あとひと月、師走になりましたな・・・・。
第14回・新丸八寄席
2012年11月28日(水)午後6:30開演
今里・丸八
一、桂福丸・・・・・・・・・・・・・「金明竹」
ニ、桂壱之輔・・・・・・・・・・・「野晒し」
三、笑福亭銀瓶・・・・・・・・・「宿題」
四、笑福亭鶴二・・・・・・・・・「尻餅」

福井県武生市から、お泊りでこの丸八寄席に来られた、明城御夫妻。
打ち上げまで参加して頂き、ご満足されたんでしょうか。

鶴二さんの高校の先生、御一行さんに壱之輔さんと福丸さん。

皆さんにこやかな、ご贔屓の方々。
12-43-206
にほんブログ村に参加中。
クリックで応援、よろしくでおます。
↓↓↓・・・