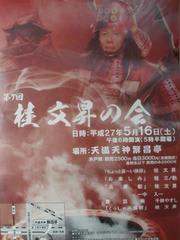☆☆☆☆
約一カ月前に、東京神保町の古本屋で買った本。
艶消しのハトロン紙に巻かれているのは、それなりの風情がある。
色んな本の合間に読んでいたのだが、じっくり過ぎて今日にてようやく完読。
全部で274の噺が、「梗概」「成立」「鑑賞」「藝談」「能書」に分けて説明されている。
特に興味のあるのが「藝談」・・・・・
その中でも先般亡くなられた米朝師匠の言葉を拾いだすと・・・・・。
「牛の丸薬」、季節感を大切にしたいはなしです。
「親子茶屋」、このハナシに使われる下座噺子の緩急、高低が大変重要でして
はなしの進展につれ、またその場面に応じて変化させねばなりません。
「景清」、ぐっと泣かせるところのあるはなしですが、あまり締め過ぎてもいけず、
変にくすぐってもいけません。笑いも涙もおのずから生じてくるもので
ありたい・・・・と思っています。
「蟇の油」、サゲは「煙草の粉を少々分けて下され」(タバコは血止めになる)
または「袂クソがあったらちょうだいしたい」(これも同じく血止めになるとされた)
・・・・いろいろあったのですが、今ではわかりにくいので、私はあっさりと、
「お立会いのうちに、血どめはないか」としています。
「口入屋」、明治時代の商家の構造をある程度知っていないと、
演るほうもやるにくいし、お聞き下さる方も面白味が薄れるのですが
そこをよく理解して頂くためにも、演者にちょっと配慮が要ります。
「鴻池の犬」、前半は人間の話で、後半はすっかり擬人化された犬の物語ですが、
そこの変化に不自然さがあってはイケません。いささか大層ないい方ですが、
犬に仮託して人生の運不運、有為転変・・・というものを暗示した作品かと
思って演じています。
「瘤弁慶」、この落語サゲ「されば、夜のこぶは見逃せぬ」は、今や説明が要る
ようになりました。夜間、昆布を見たらちょっとつまんで食べる、
「夜の昆布は見逃せん」等といって、よろこぶ、喜ぶ・・・という言葉の洒落に
過ぎませんが、花柳界や水商売では今でもある風習です。
「崇徳院」、瀬を早み岩にせかるる滝川の・・・・の歌を書くのも
扇子、短冊、色紙、いろんなやり方があるのですが、私は後の手掛かりが
何もないほうが良いと思って茶店の料紙に書くことにしたのですが、
これで別に差支えはないようです。
「てれすこ」、元来は「イカの乾したのをスルメといえあすな」・・・これがサゲです。
「抜け雀」、この話は桂文枝に教わりました。大体この「抜け雀」という落語は
桂派のネタで、二代、三代の文枝も得意にしたものでした。
私が教わったのでは、雀は室内を飛びまわるだけで、障子を開けるとバタバタと
絵に納まってしまうのですが、私は東京式に一ぺん戸外へ飛び出すことに
しました。
米朝さんの解説は誰のよりも長く、学術的で、
そして、今、上方で聴いているスタンダードでおます。
その恩恵に与って、ありがたいことでおます。
後ろに索引としてこの本で紹介されてない演目も題だけが書かれていますが
今や、上方落語の定番とも云えるのが沢山あります。
その題だけ列挙すると、「阿弥陀池」「家見舞」「いかけ屋」「池田の猪買い」
「犬の眼」「稲荷車」「馬の田楽」「お玉牛」「帯久」「お文さま」「鶴満寺」「勘定板」
「堪忍袋」「義眼」「京の茶漬」「「肝つぶし」「くしゃみ講釈」「稽古屋」「仔猫」
「米揚げ笊」「「鷺とり」「猿後家」「算段の平兵衛」「七段目」「七度狐」「指南書」
「宗論」「相撲風景」「ぜんざい公社」「高尾」「蛸芝居」「ちしゃ医者」「提灯屋」
「次の御用日」「つる」「手紙無筆」「天神山」「動物園」「豊竹屋」「「猫忠」「軒づけ」
「野崎詣り」「花筏」「鼻ねじ」「反対車」「東の旅」「平林」「べかこ」「堀川」「豆屋」
「桃太郎」「やかんなめ」「夢八」「欲の熊鷹」
上方の地名がでてくるもの、鳴り物が必要なもの、商家を扱ったもの、
浄瑠璃がらみのものなど、東京へ移し難かったんでしょうか・・・・
でもこの本の初版発行が25年前ですから、現在ではもっと変わってるんでしょうな。
まあ、東京落語を聞くには、バイブル的本で傍から離せませんな・・・。
にほんブログ村に参加中。
クリックで応援、よろしくでおます。
↓↓↓