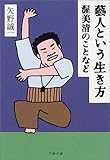今日は、久し振りにザビエル寄席へ。
会場は堺東の、町中の大きなホールに・・・。
サブタイトルが、三喬一門会と、喬若さんが一席になった変わりに、
ゲストにこごろうさん、そして師匠の三喬さんの出番・・・楽しみですな。

・・・・・500人弱の大入り満員・・・・喬若さん凄い人気・・・
一、笑福亭喬介・・・・・・・・・・・・・・「つる」
にこにこ顔で登場、携帯の電源切りのお願いのあと、
「落語、、やります」でスタート。
「つる」、米朝一門では、初期に習うネタと聞いているが
喬介さんの「つる」、・・・内容はいたってオーソドックスだが、無邪気さが満開。
どこまでが、演出で、どこまでが、素なのか、いつもながらに分らない噺っぷり。
でも、一見、頼りなさそうにうつる、その様子に、後の女性(そこそこの・・・)たちは、
かわいいの連発でしたで、中年のアイドルの位置、確保ですな。
二、笑福亭喬若・・・・・・・・・・・・・・「禁酒関所」
門番に、最初の丁稚の時は、「湯飲みの大きいやつを持ってまいれ」
次の丁稚の時は、「湯のみ、寿司やと同じやつ」
最後の時は、「どんぶり鉢を持ってまいれ」と、役人が言う。
落語とは、うまくできてますな。
最後の、小便をどんぶりで飲ます為に、フィルムを逆に回して作ったような噺。
喬若さんの酔いっぷり、若いだけに、まだまだ酔いが回ってない様子。
二升ものお酒、久しぶりだけに、もう少し、酔ってほしかったですな。
でも、この会の良さ、二席するだけに、この様に大ネタのご披露、うれしおます。
三、桂こごろう・・・・・・・・・・・・・・・・「七段目」
笑福亭の会に、桂で一人、アウェイ状態だが、力抜くことなく、孤軍奮闘。
ああ、こごろうさんの「七段目」・・最高でおます。
「あにさんの頼みとは、あにさんの頼みとは」のお軽の台詞に
「妹よ、われの命、この兄さんがもろうた」で、若旦那が、夢中になって
柄に手をやり、いままさに、刀を抜かんとする。
「あかん、あかん、抜いたら、あかん」という定吉の顔、こごろうさん、上手いな。
らくご道とか、こごろうの会など、三味線が入る事が少ないので、
こごろうさんの音曲噺、初めて聴いたような気がするが、
さすが、米朝一門、会場の大きさに合わせて、動きも多少大きめなのか。
この「七段目」・・・・しっかりとした中に、漫画チックなおもしろさ満載。
こごろうさんの、苦手なネタ、出来ぬネタなど無し・・・・・・
「遊山船」、「稽古屋」、「船弁慶」など、どんなんなのか、是非、聴いてみたいですな・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・金屏風の大舞台・・・・・・・・・・・・・・・・
四、笑福亭三喬・・・・・・・・・・・・・・「月に群雲」
三喬さん、出てくるなり、弟子の喬若がこんな立派な会を催すことができまして、
誠にありがとうございますと、まずは、師匠としてのご挨拶。
プログラムには、私がトリになっていましたが、自分の会だけに、喬若がトリをとって、
責任を果たすのも良いと、今日の出番を入れ替えて先に出てきましたと。
決して、次の仕事があるとかでは無くて・・・、良く言えば、麗しい師弟愛、
悪く言えば、いじめ、ですが・・・・と言いながら、心底、弟子の晴れ舞台・・
喜んでいられるようでしたな。
上方で、米團治と言えば、若旦那・丁稚と言えば雀々・、
三喬と言えば、泥棒ネタ・ですが・・・・よろしいか。
「転宅」、「子盗人」、「おごろもち盗人」、「へっつい盗人」、「仏師屋盗人」
「書割盗人」、「花色木綿」、拡大解釈で「一文笛」などがあるが・・
今日は・「月の群雲」・・(小佐田定雄作)でおました。
「月の群雲」・・・「花に風」の合言葉だけで、笑わす。
「金は天下のまわりもの」、「念ずれば救われる」「骨切って肉を断つ」
ことわざの間違い読みの連発・・・・・。
「七面観音」、「九百九十八手観音」、「六福人」とハンパ物の盗品が続き・・・、、
泥棒、合言葉(ことわざ)、仏像、の三大噺みたいなネタですな。
それだけの筋立てですのに、こんなおもしろい噺になるなんて、
三喬さんの(小佐田先生すいません)、話術に負うところ大いにありそうですな。
五、笑福亭喬若・・・・・・・・・・・・・・「野ざらし」
トリに出るなら、「禁酒関所」でも良かったかも・・・・。
「野ざらし」、喬若さんの、十八番だが、この500人のお客さん相手なら
もっともっと、弾けて、欲しかったでおます。
でも、堺の刃物会館からスタートの、ザビエル寄席。・・・・・今日の大会場は、
喬若さんの、人柄の良さと芸の大きさで、多くのファンができた証しですな。
これからも、多彩なゲストを迎え、ミニ独演会のつもりで
どんどん、新しいネタに挑戦してほしいですな。
第六回・ザビエル寄席
2010年6月13日(日)午後2:00開演
堺市総合福祉会館 大ホール
一、笑福亭喬介・・・・・・・・・・・・・・「つる」
二、笑福亭喬若・・・・・・・・・・・・・・「禁酒関所」
三、桂こごろう・・・・・・・・・・・・・・・・「七段目」
仲入り
四、笑福亭三喬・・・・・・・・・・・・・・「月に群雲」
五、笑福亭喬若・・・・・・・・・・・・・・「野ざらし」
・・・・・・・・・・・・・・・・三味線・・・・・・花登益子
 にほんブログ村
にほんブログ村