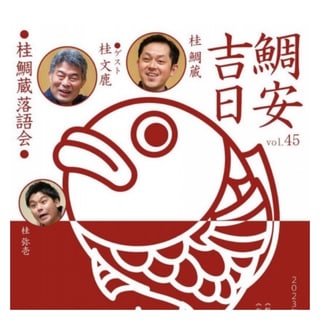鯛安吉日・桂鯛蔵落語会〜2023.11.29
今日は初めて鯛蔵さんの落語会へ。どんな落語が聴けるのか楽しみでおます。
良かったですな。重ための噺が三席聴けたのは幸せ。そういえば、「打飼盗人」が6回も「崇徳院」が16回目だが、笑福亭好きの私にとって案外出会いの少ない噺。そして、冬に怪談噺、文鹿さんの「主悦殺し」が聴けたのはラッキー、いつか出会いたいと思っていただけに、この年末に聴けるとは・・・。
他の一門さんの会にも、進んで足を運んで落語のリフレシュせんとあきまへんな。
一、桂弥壱・・・「狸の賽」
私も噺す「狸賽」だけに、興味深く聞かせてもらいました。私は最初に聴いた可朝さんのが頭に残っているだけに、あっさりと上品に北の割烹の味わいにとまどいながらも、さすが米朝一門と楽しませてもらいましたで・・・。
ニ、桂鯛蔵・・・「打飼盗人」
ご縁があって知り合った、鯛蔵さん。メインの会にお伺いしようと、この「鯛安吉日」なんと45回目の開催、じっくりと育ててこられた会なんですね。
まあ、盗みに入った盗人から質屋から道具や着物の金、米代までせびり取る。これだけの話術があるなら、他のどんな仕事でもできそうにおもいますが・・。主人公の部屋が案外こぎれいに見えるのは、やはり鯛蔵さんの上品さですか。
三、桂文鹿・・・「主悦殺し~真景累ヶ淵」
本日の秀逸。冬に怪談噺とは。文鹿さんの古典、癖がありながら骨太で好きでおます。失礼ながら厳つい文鹿さんに怪談噺はぴったりと合っているようで、是非七話まである「真景累ヶ淵」、全編聞かせて欲しいです。でもこれって圓朝21歳の時の作って凄い、すごくませてましたな。
四、桂鯛蔵・・・「崇徳院」
ネタおろししたてで二回目とか。「崇徳院」さん。私の好きな噺のひとつ。仁鶴さん、枝雀さん、ざこばさんで馴れ親しんだ落語。今日の鯛蔵さんの「崇徳院」を聞いていても、枝雀さんとざこばさんがチラチラ見え隠れするのは私だけでしょうか。
私が中学生で初めて覚えた一首、「瀬を早み岩にせかるる滝川の・・・」これって今の私の短歌かじりにつながっているんでしょうか。
和歌がでてくる落語は「ちはやふる」「崇徳院」「鶴満寺」「鼓ヶ滝」あたりですか、どうしても和歌自体が噺になった「ちはやふる」か「鼓ヶ滝」、をやはり噺してみたいですな。
鯛安吉日・桂鯛蔵落語会
2023年11月29日(水)午後7時開演
動物園前・動楽亭
一、桂弥壱・・・「狸の賽」
ニ、桂鯛蔵・・・「打飼盗人」
三、桂文鹿・・・「主悦殺し~真景累ヶ淵」
中入り
四、桂鯛蔵・・・「崇徳院」