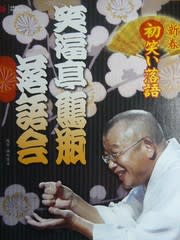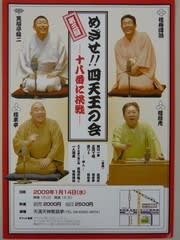フジコ・ヘミング、魂のピアニスト
~フジコ・ヘミング著~
新潮文庫・476円
☆☆☆
「間違ったっていいじゃない。機械じゃないんだから。」
「ひとつの物差しでしか音楽を計れない。
こころで音楽を聴くことのできる人が少ないのだ。」
「確かにピアニストの場合は、出す音がすべてかもしれない。
ポンと、音を出すだけで、ふだんの自分が、人間性が、全部出る。
出す音が、自分の内面を雄弁に語る。」
「だから、それはとてもこわいことだ。」と
芸術家の悩み、舞台への恐怖が随処に語られる。
落語家さんも同じ、話す機会が増えれば増えるほど、悩みも増える。
「私のピアノには、魂があるといわれた。
その言葉に、とっても感激している。
これまで何度かつらい経験をしてきたけれど、
それでも何とかピアノを続けることができたのは、
こうしてわたしの音楽に共感してくれる人がいたからだ」、と。
仲間や聴衆のあたたかい声援に感謝し。
「こんなことを自分からいったりするのは恥ずかしいのですが
わたしはいつも自分の才能を信じていました」と。
芸術家としての、過剰とも思える自信をも漲らせる。
芸を極める人の孤独感が心の叫びとして伝わります。
ピアノ曲を聴きながらの読書、お勧めします。
真ん中にある、30ページもの、絵日記はとってもかわいいです。
私はこれを見て買ったのですが・・・・・・。
~フジコ・ヘミング著~
新潮文庫・476円
☆☆☆
「間違ったっていいじゃない。機械じゃないんだから。」
「ひとつの物差しでしか音楽を計れない。
こころで音楽を聴くことのできる人が少ないのだ。」
「確かにピアニストの場合は、出す音がすべてかもしれない。
ポンと、音を出すだけで、ふだんの自分が、人間性が、全部出る。
出す音が、自分の内面を雄弁に語る。」
「だから、それはとてもこわいことだ。」と
芸術家の悩み、舞台への恐怖が随処に語られる。
落語家さんも同じ、話す機会が増えれば増えるほど、悩みも増える。
「私のピアノには、魂があるといわれた。
その言葉に、とっても感激している。
これまで何度かつらい経験をしてきたけれど、
それでも何とかピアノを続けることができたのは、
こうしてわたしの音楽に共感してくれる人がいたからだ」、と。
仲間や聴衆のあたたかい声援に感謝し。
「こんなことを自分からいったりするのは恥ずかしいのですが
わたしはいつも自分の才能を信じていました」と。
芸術家としての、過剰とも思える自信をも漲らせる。
芸を極める人の孤独感が心の叫びとして伝わります。
ピアノ曲を聴きながらの読書、お勧めします。
真ん中にある、30ページもの、絵日記はとってもかわいいです。
私はこれを見て買ったのですが・・・・・・。