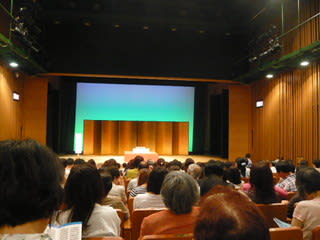東京の柳亭市馬さんとの初出逢い。
江戸落語の粋さに、期待ですな。

・・・・・・・・かっこいいな・・梅團治さん・一枚看板・・・・・・・・・・・・
一、桂梅團治・・・・・・・・・・・・・・・「子ほめ」
トップに出るのは、久しぶりですが、今回満員御礼でございます。
まことに、市馬さん効果で、早々とチケットぴあ販売分が完売。
凄いですな。
市馬さんは、今後東京の落語界を支えていく方。
私は、家族でさえ、ささえるのが、精一杯ですが。
今日は、たっぷり江戸落語を堪能して貰いたいと、
ゲストの市馬さんを立てながら、二人会の意気込みを語る。
噺は「子ほめ」・・梅團治さんの子ほめ。良かったですな。
間抜けな主人公ではなく、べんちゃらのひとつもいうて、
ただ酒にありつけたいということで。
呑みたい一心で、人の話など聞く耳をもたないのが、
ストレートでおもしろい。
まずは、梅團治さんの「子ほめ」が聴けだけでも、得した気分ですな。
二、柳亭市馬・・・・・・・・・・・・・・・「かぼちゃ屋」
上方落語でいう、「みかん屋」。・・大阪弁に慣れている私には、
数段、みかん屋の方がおもしろい。
長屋の賑やかさなくて、ものさびしい。
みかんは衝動買いはあるかも知れないが
かぼちゃの衝動買いは如何なものか。
その日、長屋全部がかぼちゃ料理とは、気持悪いでっせ。
元々は、どちらの噺か。・・長屋噺は、上方に限りますな。
凄い・・えこひいき。
三、桂梅團治・・・・・・・・・・・・・・・「宇治の柴舟」
私の隣に坐った男性、今日初めて繁昌亭に来ましたと。
「ええ、小屋ですな。」
「まあ、大きさも丁度よろしく、二階席でも充分楽しめまっせ」と
小屋主みたいに、誉め言葉を述べる。
その方が、終わったあとで、「崇徳院と思いましたわ」の一言。
ほんま、若旦那の悩みとやらを聞くのは「千両みかん」もあるけど
「宇治の柴舟」と「崇徳院」は最初のところ、瓜二つですな。
惚れたのが、生身の女性ではなく、絵の中の女性。
まさに、究極の恋患いでおますなが。
プログを見ていると、梅團治さん、
鉄道写真に、この若旦那以上に、恋患いですな。
仲入り
四、桂梅團治・・・・・・・・・・・・・・・「寝床」
最初に、お断りしときますが、私の寝床は、短いです。
今日初めて聞く人は、是非他の人のも聴いてください。
本来、そこそこ長いネタです。
いきなり、「久七、・・・・どうやった、すると町内の皆さんは、
誰も来られんということか。」というと、
客席から、思わずああなんと大胆なという笑い。
でも、その後は、最後の定吉のくだりまで、一切の手抜き無しの
ノーカット版。・・・・・・・・・・・・・おもしろい。
実は、大好きな鶴二さんの寝床も、このバージョン。
噺家さん、縮めたり、伸ばしたり、、今日の梅團治さんの「寝床」
時間は短いが、中身は濃縮の味わいでしたな。
五、柳亭市馬・・・・・・・・・・・・・・・「百川」
梅團治さんの、好きなものを語っている時の顔はよろしいな。
私は実は無趣味・・・・・・いや、昭和歌謡が好きで・・・と。
三橋美智也の最初のヒット曲「おんな船頭唄」を客席の期待に
応えて歌ってくれる。・・・伸びのある、いい声。
与太郎、与次郎、与三郎と、一字違いでアホから若旦那まで大違い。
与太郎の説明しているようで、最後のさげの複線、にくいですな。
噺は、百川に勤める百兵衛が、言葉足らずで、河岸の若い衆と
「主人家の抱え人」を、「四神剣の掛けない人」とトンチンカンの勘違い
江戸言葉に馴れない私は、一度こちらの言葉に変換するので
素直に笑いに入れない。
サゲは、「かめもじ」、と、「かもじ」、の一字違いと。
最初の、仕込が生きてくる・・・。
語り口、品の良さは最高。
江戸落語は、やはり上方にはない人情噺、武家噺なら素直に入れるが
私には、今日の二席は、チョット違和感ありましたな。
本日は、市馬さんより、梅團治さん。
江戸落語より、上方落語が
私の笑いの壷にはあいましたな。
でも、もっともっと、江戸の、噺家さんに、
こちらで会えるような企画、大いに増やして欲しいですな。
第3回・桂梅團治のこれ独演会
2009年7月26日(日)午後6:30開演
天満天神繁昌亭
一、桂梅團治・・・・・・・・・・・・・・・「子ほめ」
二、柳亭市馬・・・・・・・・・・・・・・・「かぼちゃ屋」
三、桂梅團治・・・・・・・・・・・・・・・「宇治の柴舟」
仲入り
四、桂梅團治・・・・・・・・・・・・・・・「寝床」
五、柳亭市馬・・・・・・・・・・・・・・・「百川」
09-54-249
江戸落語の粋さに、期待ですな。

・・・・・・・・かっこいいな・・梅團治さん・一枚看板・・・・・・・・・・・・
一、桂梅團治・・・・・・・・・・・・・・・「子ほめ」
トップに出るのは、久しぶりですが、今回満員御礼でございます。
まことに、市馬さん効果で、早々とチケットぴあ販売分が完売。
凄いですな。
市馬さんは、今後東京の落語界を支えていく方。
私は、家族でさえ、ささえるのが、精一杯ですが。
今日は、たっぷり江戸落語を堪能して貰いたいと、
ゲストの市馬さんを立てながら、二人会の意気込みを語る。
噺は「子ほめ」・・梅團治さんの子ほめ。良かったですな。
間抜けな主人公ではなく、べんちゃらのひとつもいうて、
ただ酒にありつけたいということで。
呑みたい一心で、人の話など聞く耳をもたないのが、
ストレートでおもしろい。
まずは、梅團治さんの「子ほめ」が聴けだけでも、得した気分ですな。
二、柳亭市馬・・・・・・・・・・・・・・・「かぼちゃ屋」
上方落語でいう、「みかん屋」。・・大阪弁に慣れている私には、
数段、みかん屋の方がおもしろい。
長屋の賑やかさなくて、ものさびしい。
みかんは衝動買いはあるかも知れないが
かぼちゃの衝動買いは如何なものか。
その日、長屋全部がかぼちゃ料理とは、気持悪いでっせ。
元々は、どちらの噺か。・・長屋噺は、上方に限りますな。
凄い・・えこひいき。
三、桂梅團治・・・・・・・・・・・・・・・「宇治の柴舟」
私の隣に坐った男性、今日初めて繁昌亭に来ましたと。
「ええ、小屋ですな。」
「まあ、大きさも丁度よろしく、二階席でも充分楽しめまっせ」と
小屋主みたいに、誉め言葉を述べる。
その方が、終わったあとで、「崇徳院と思いましたわ」の一言。
ほんま、若旦那の悩みとやらを聞くのは「千両みかん」もあるけど
「宇治の柴舟」と「崇徳院」は最初のところ、瓜二つですな。
惚れたのが、生身の女性ではなく、絵の中の女性。
まさに、究極の恋患いでおますなが。
プログを見ていると、梅團治さん、
鉄道写真に、この若旦那以上に、恋患いですな。
仲入り
四、桂梅團治・・・・・・・・・・・・・・・「寝床」
最初に、お断りしときますが、私の寝床は、短いです。
今日初めて聞く人は、是非他の人のも聴いてください。
本来、そこそこ長いネタです。
いきなり、「久七、・・・・どうやった、すると町内の皆さんは、
誰も来られんということか。」というと、
客席から、思わずああなんと大胆なという笑い。
でも、その後は、最後の定吉のくだりまで、一切の手抜き無しの
ノーカット版。・・・・・・・・・・・・・おもしろい。
実は、大好きな鶴二さんの寝床も、このバージョン。
噺家さん、縮めたり、伸ばしたり、、今日の梅團治さんの「寝床」
時間は短いが、中身は濃縮の味わいでしたな。
五、柳亭市馬・・・・・・・・・・・・・・・「百川」
梅團治さんの、好きなものを語っている時の顔はよろしいな。
私は実は無趣味・・・・・・いや、昭和歌謡が好きで・・・と。
三橋美智也の最初のヒット曲「おんな船頭唄」を客席の期待に
応えて歌ってくれる。・・・伸びのある、いい声。
与太郎、与次郎、与三郎と、一字違いでアホから若旦那まで大違い。
与太郎の説明しているようで、最後のさげの複線、にくいですな。
噺は、百川に勤める百兵衛が、言葉足らずで、河岸の若い衆と
「主人家の抱え人」を、「四神剣の掛けない人」とトンチンカンの勘違い
江戸言葉に馴れない私は、一度こちらの言葉に変換するので
素直に笑いに入れない。
サゲは、「かめもじ」、と、「かもじ」、の一字違いと。
最初の、仕込が生きてくる・・・。
語り口、品の良さは最高。
江戸落語は、やはり上方にはない人情噺、武家噺なら素直に入れるが
私には、今日の二席は、チョット違和感ありましたな。
本日は、市馬さんより、梅團治さん。
江戸落語より、上方落語が
私の笑いの壷にはあいましたな。
でも、もっともっと、江戸の、噺家さんに、
こちらで会えるような企画、大いに増やして欲しいですな。
第3回・桂梅團治のこれ独演会
2009年7月26日(日)午後6:30開演
天満天神繁昌亭
一、桂梅團治・・・・・・・・・・・・・・・「子ほめ」
二、柳亭市馬・・・・・・・・・・・・・・・「かぼちゃ屋」
三、桂梅團治・・・・・・・・・・・・・・・「宇治の柴舟」
仲入り
四、桂梅團治・・・・・・・・・・・・・・・「寝床」
五、柳亭市馬・・・・・・・・・・・・・・・「百川」
09-54-249