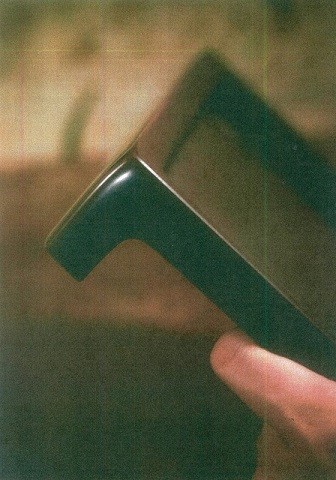『自然の不思議・樹木のこと 7(どんぐりは1万余年の縄文時代を支えた)』
『「どんぐり背比べ」より『どんぐりの種類比べ』の方が相応しい)』
『ヒトのためにも、クマのためにも、縄文人が護ってきた「1万余年続いた縄文人の生活の
知恵」、「ムラ(村)・ハラ(原)・ノハラ(野原)と「自然混交林」を護っていきたい』。
 ウエブ情報から引用
ウエブ情報から引用
先日(2022/09/28)日経新聞文化蘭で、宮国晋一氏の『どんぐりはオンリーワン「同じ種でも木によっては多彩、根気強く観察25年」』を拝見しました。 すぐに思い出したのは二点;
- 縄文人は定住で『採集・狩猟・漁労で農耕(田畑)なし』に対して、古代エジプトは定住で『農耕(田畑)あり』)があった)ことから、1万余年も続いた縄文時代と木の実・どんぐりのこと。 縄文時代の日本は「広葉樹林」が広まり、そこから収穫できるどんぐりは供給量が多く、縄文人の食文化に大いに貢献したとも考えらえています。
- 熊はドングリを飽食すれば豊富な脂肪が身体に着き、その後、木の穴などで冬眠します。 そして冬眠の間にメスのクマは1~2頭の子グマを産みます。
でも、ナラ類の結実にはほぼ一年ごとに豊作と凶作の周期があります。 またブナは5年またはそれ以上の間隔でしか豊作になりません。ドングリに依存する冬眠前のクマは、凶作の年には窮乏生活を送ることになります。 時には人里に現れるケースが多発しています。
どんぐりは形も大きさもほぼ一様で差がないので、背比べをしても優劣が決められないことから、『どんぐりの背比べ』とは、どれもこれも似たり寄ったりで、抜きん出た者がいないことのたとえです。 『どんぐり』は漢字で『団栗』と書く、『背比べ』は『背競べ』とも書きます。 日本語は詩歌・文学には素晴らしい言語です。
宮国晋一氏のエッセイ『どんぐりはオンリーワン「同じ種でも木によっては多彩、根気強く観察25年」』からの抜粋・引用です。
『コロンとした丸い形、細長い形、指の先ほどの小サイズ――。 秋の公園で地面に落ちているどんぐりをじっくり観察してみると、驚くほど多様な形をしている。 一見別の種類に見えて、実は同じ種類の場合も多い。 そんな個性の豊かさに引かれて、25年間収集を続けている。
どんぐりとはブナ科の果実の俗称で、コナラやクヌギなど、国内に22種が存在する。 だが、同じ種でも木ごとにつける実は多様で何百、あるいは何千と種類がある
野山に自生する木には、単調で似た形の実がなる場合が目立つ。 一方、公園や緑地に生えている木は、それぞれ全く異なる形状をしたどんぐりをつけることが多いようだ。 なぜ、場所にとってこんな違いが生じるのか。 私は人間が木を選別してきたことが関係していると考えている。』
人のためにも、クマのためにも、縄文人が護ってきた『1万余年続いた縄文人の生活の知恵』・『ムラ(村)・ハラ(原)・ノハラ(野原)』と自然混交林を護っていきたいものです。
(記事投稿:2022/10/19、#588)