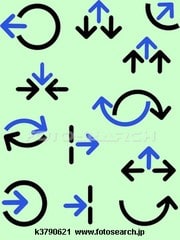科学・技術は、政治に引きずられるとあまりよい働きをしない。
政治家は、科学・技術をあらゆる手を使って利用しにかかる。
思想・評論を仕事にする人たちも同じようなことをしたがる。
思想の科学などというあまり意味のわからない標題の雑誌さえ出ていたことがある。
科学という呼び名が、科学とは無関係のところで出版産業の材料にも使われていた事例である。
科学・技術が、政治や産業を支える役割が薄められて、お雇い科学、ご用達技術に堕していくと、やることのどこかに隙間ができる。
そして、天変地異に遭うと防ぎえた程度を超える被害をこうむってしまう。
そのことに政治家とお雇い科学者は、口をそろえて「想定外」という。
いったん事故が起きた後でなれば、どこをどうしておけばよかったのかは、科学者の知恵を借りて技術者が結論付けられることである。
その場合には、検討過程での政治家や思想関係者は口出し無用なのである。
なんでも政治主導などと、できもしないことを言ってえらそうに口を出すから間違いが起こる。
なぜ間違うのか。政治や思想には必ず偏りがあるもので、宇宙万般に公正な政治や思想などありえないからである。