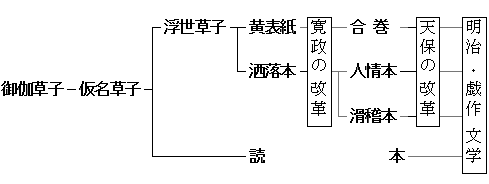江戸金よしよし。
(江戸は金遣い(きんづかい))(4進法(よんしんほう)・銭4貫文(しかんもん))
[ポイント]
1.江戸は金遣い(きんづかい)で、金銀貨は4進法で、1両は銭4貫文だった
[解説]
1.全国的に通用する貨幣を安定して供給することは、幕府の重要な役割であった。同じ規格・品質の金・銀の貨幣は、徳川家康が1600(慶長5)年ころから金座・銀座で大量につくらせた慶長金銀が日本で初めとされる。金座は江戸と京都(のち江戸のみ)におかれ、後藤庄三郎(生没年不詳)(のち後藤家が世襲)のもとで小判・一分金などの計数貨幣が鋳造された。また銀座はまず伏見・駿府におかれ、のちに京都・江戸に移されて、丁銀や豆板銀などの秤量貨幣を鋳造した
2.三貨の換算率は江戸時代前半までは、金1両=銀50匁(1700年からは60匁)=銭4貫文。しかし、実際はその時の相場で動く変動制であった。金貨の単位は1両=4分=16朱の4進法。銭は10進法。
3.江戸では金貨が流通(金遣い)したが、上方(大坂)では主として銀貨が流通(銀遣い)した。この地域的違いに加え、金・銭は計数貨幣であるのに対し銀は重さを量る秤量(しょうりょう)貨幣であったため、日常的に三貨の間で両替(りょうがえ)商による両替が必要であった。たとえば江戸から大坂に行く場合、現代で日本からアメリカに行くような不便さがあった。そこで田沼意次は三貨を金に一本化して貨幣制度の安定をはかるために計数銀貨、南鐐二(弐)朱銀を発行。この銀貨は8枚で(2朱×8=16朱)1両とされた。
〈2015早大・文
問5 下線b金・銀・銭に関する記述として、誤っているものを1つ選べ。
ア 金座は江戸と京都に置かれたが、のち江戸だけになった。
イ 金座は代々後藤家が管轄した。
ウ 金貨の単位は両・分・朱だが、天保一分銀は銀貨である。
エ 江戸は主に金遣い、大坂は主に銀遣いであった。
オ 当時は正金銀が流通していたので、紙幣を発行する藩はなかった。」
(答:オ× ※金銀産出量が不足し、それを藩札発行で補った)〉
〈2014文教大学・全学部
問4 下線部(c)江戸時代の貨幣制度は様々を問題点を抱えておりに関連して述べた文として最も適切なものはどれか。次の中から一つ選べ。
1.大名にも紙幣発行権が認められており、藩札は藩の領域を越えて全国に流通した。
2.江戸では主に銀貨が流通し、大坂では主に金貨が流通した。
3.貨幣は都市では流通するが、自給自足の農村には浸透しなかった。
4.金貨と銀貨の交換率に決まりはあったが、実際はその時の相場で取り引きされた。
問5 下線部(d)金貨・銀貨・銭貨の単位と特徴について述べた次の文中の空欄[ア~イ]に入る語句の組み合せとして最も適切なものはどれか。次の中から一つ選べ。
金貨は両・分・朱を単位とする[ ア ]進法の貨幣であるが、銀貨は貫・匁などを単位とする[ イ ]貨幣、銭貨は貫・文を単位とする10進法の貨幣であった。
1.ア-2、イ-計数
2.ア-2、イ-秤量
3.ア-4、イ-計数
4.ア-4、イ-秤量」
(答:問4→4 ※1×藩内のみに流通、2×江戸金・大坂銀、3×農村にもじわじわ浸透)、問5→4)〉
〈2012明大・商学部
Ⅲ 以下の文章は近世前後の貨幣史とその関連事項について記したものである。文章内における(a~e)の【 】に入る最も適切な語句を1~5から選び、また[1~5]の空欄に入る最も適切な語句を漢字で記入しなさい。
中世までの貨幣は中国からの輸入銭(宋銭・明銭)や粗悪な私鋳銭などが使用されており、そのために円滑な流通が阻害され、それぞれの交換比率に不具合が生じていたことはよく知られている。それゆえ織豊政権は全国規模の経済政策の実施に向けて金銀の採掘、精錬、鋳造を標準化する努力を払わなくてはならなかった。秀吉は、佐渡相川、但馬生野などの主要鉱山を直轄化したうえで、貨幣鋳造を試みた。京都の彫金家、
(a)【(1)後藤徳乗 (2)小堀遠州 (3)荒木田守武 (4)本阿弥光悦 (5)酒井田柿右衛門】(1550~1631)に命じて1588年に造らせたという天正大判などがそれである。ただし、この段階の貨幣は政権の交代もあり、全国市場を統一する貨幣としての地位を確立することはなく、実際に全国規模の貨幣制度が確立するのは織豊政権の基本的な貨幣政策を引き継いだ徳川氏の手によることとなる。
全国的に通用する同じ規格の金・銀の貨幣は、1601年に整備された金座・銀座で鋳造された。金座は江戸と京都におかれ、小判、1分金などを鋳造した。銀座は最初伏見、駿府におかれ、のち京都と江戸に移されて丁銀、豆板銀などを鋳造した。金貨は両、分、朱の単位でそれぞれが
(b)【(1)2 (2)3 (3)4 (4)8 (5)12】進法で数えられる計数貨幣であったが、銀貨は目方を計る[ 1 ]貨幣であった。銭は江戸や各地の民間請負の銭座などで寛永通宝の1文銭・4文銭などを銅や鉄で鋳造した。しかしながら、慶長大判などは流通貨幣というよりは、公儀の賜与や大名の贈答のための性格が強かったという。また、以上の金・銀・銭の三貨の交換は変動相場制によっていたため、はなはだ複雑であった。また、国際的には銀本位が規準となっていたうえ、東日本経済が金決済、西日本経済は銀決済という仕組みが定着してしまい、国内金融市場はつねに変動する価値に翻弄されていた。
とくに元禄期の好況期にはその拡大された経済にみあった通貨の増発が必要となったため元禄の改鋳が行われたが、金銀の減産傾向と、銀の国外流出、両貨のアンバランスなどの要因から金銀貨は大幅に悪鋳されたものとなった。1695年、当時勘定吟味役であった[ 2 ](1658~1713)の上申を受けて綱吉によって発行された元禄小判は、慶長小判が金含有率84%であったのに対して同比率がわずか57%でしかなく、銀貨についても同様に銀含有率が80%から64%に関連している。このように貨幣価値が大きく下落すると庶民はインフレのさらなる激化に苦しむこととなった。また、両貨の改悪の度合いとしては金貨のほうが大きかったこともあり、元禄金をきらって銀貨に対する需要が高まり、銀貨が払底することで銀相場は高騰した。幕府は事態に対応するために金銀比価の改定を行い、さらに宝永期には定量を減じた乾字小判などを発行し、金銀比価および東西の相場安定を目指したが成功することはなかった。
これに対して正徳~享保期の貨幣改鋳は悪貨にかえて良貨をつくることを目的としていた。幕府は新井白石の建策にもとづいて1714年、正徳貨幣の改鋳を開始し、同時に銀座の粛清を断行した。家康時代への復古の理念は貨幣政策にもおよび、享保期にかけて発行された小判は慶長小判とほぼ同様の定量と品位を回復した。しかしながら旧貨の通用禁止令によって物価が新貨により表示されるようになると景気は急激に後退した。茅場町に私塾を開き、聖人の道を明らかにした『弁道』という著書で経世論を説いた[ 3 ](1666~1728)などの学者もこの幣制改革による通貨縮小策が行き過ぎであって、貨幣の品位、定量を落としても貨幣数量を確保する必要があることを説き、幕府は再び悪貨の改鋳を通じた景気の安定策を繰り返していくこととなる。
他方、この時期は領国通貨(藩札)が一般化したことでも知られている。幕府は1730年には1707年以来の札遣い停止令を解除し、藩札の再発行を許すこととなった。藩札はその後、貨幣流通量の不足を補い、領国経済の商品流通の結節点となっていった。そもそも藩札は1661年に
(c)【(1)福井 (2)郡山 (3)広島 (4)尼崎 (5)久留米】藩で最初に発行されたといわれている。江戸初期から経済の中心として栄えていった畿内、伊勢の有力商人の私札の流通に対応するため、藩が紙幣を発行したと解釈されている。
田沼時代には、商工業者の組織化政策、あるいは専売制の実施など、各地で発展しつつあった商品生産・流通からもたらされる富を財政の補強のために使おうとする経済政策が展開した。貨幣政策でもそれまでの三貨を金に一本化して貨幣制度の安定をはかるために計数銀貨の発行を実施した。これは田沼意次が老中に就任する直前に発行された明和
(d)【(1)五分 (2)五貫 (3)五両 (4)五匁 (5)五朱】銀の政策意図を踏襲したもので、金銀の相場により変動する貨幣制度を強制的に安定させる目的をもっていた。ただ、この貨幣は鋳造数が少なかったうえ、取り扱いもかさばって使いにくかったため、1772年、97%の純度を持つ[ 4 ]銀を発行した。この銀貨
(e)【(1)2 (2)3 (3)4 (4)8 (5)12】枚で金1両に相当する計算になった。幕府は同貨幣の流通を公金貸付制度と一緒に実施することで成功に導き、天明期には流通の安定基盤が確保されたといわれている。
しかしながら江戸後期にかけては、幕府の財政はさらなる逼迫状況に陥り、文政、天保期には貨幣の悪鋳に財政危機の打開という目的がこめられていくが、不安定な金融状況は続き、開国によってその状況はさらに悪化の一途をたどった。金の銀に対する相対価値の低さから、外国人が銀貨を日本に持ち込んで日本の金貨を安く外国に持ち帰る事態が進展したのである。これは、おもにスペイン系中南米諸国で鋳造されていたメキシコ銀などのいわゆる[ 5 ]銀を日本の天保1分銀と交換し、そしてさらにそれを日本の金貨と交換する手法によった。幕府は金貨の品位を大幅に引き下げた万延小判を鋳造してこの事態を回避しようとしたが、これにより物価高騰がおこり、下級武士や庶民の生活は著しく圧迫され、討幕のうねりの一つの底流となったといわれている。」
(答:a1、b3、c1、d4、e4、1秤量、2荻原重秀、3荻生徂徠、4南鐐二朱、5洋)〉
〈2012同志社大学・文経済
問ク.1600年から改鋳が開始され、1695年の元禄改鋳まで最も長期間使用された金銀貨幣を総称して何というか、その名称を記せ。
問ケ.江戸時代を通じて幕府はしばしば貨幣の改鋳を行った。次の1~4の金銀の改鋳を年代順に並べよ。
1.正徳金銀 2.天保金銀
3.元文金銀 4.安政金銀」
(答:ク慶長金銀、ケ1→3→2→4)