・小林秀雄
読書に習熟するとは、耳を使わずに話を聞く事であり、文字を書くとは、声を出さずに語る事である。それなら、文字の扱いに慣れるのは、黙して自問自答が出来るという道を、開いて行く事だと言えよう。
・本は、必ずしも通読する必要はない。苦しいときも、悲しいときも、日々、近くに置いて思うように読めばよい。
・たった一つの言葉が、人間を暗闇から救い出してくれることがある。そればかりか、生きる意味とは人生の言葉と呼ぶべきものとめぐり逢うことのようにすら思う。
闇を照らす言葉は、信頼できる人の口から発せられることもあったが、縁のない人から語り出される場合もあり、書物のなかから飛び出してくる、そんな日もあった。
悲しみの底にあるとき、光となったのは「かなしみ」という言葉だった。「かなしみ」を生きながら、「かなしみ」とは何であるかを知らない。そう感じたとき人生の扉が少し開いた。
「かなしみ」を確かに感じている。だが、「かなしみ」が何であるかが分からない。そうしたことは私たちの人生に幾度かあるのではないだろうか。誤解を恐れずにいえば、人は、「かなしみ」を生きるとき、もっとも強く幸福を感じることさえある。
・詩人茨木のり子
私の詩が、入試に使われたことが何度かあり、試験が終わってから入試問題が送られてきて、キャッ! と叫ぶことがある。試験問題だからすべて事後で、否も応もない。自分の詩でありながら、設問になんら答えられず、0点間違いなし。これに答えなければならない受験生たちに、まったく同情する。
・「劫初」(ごうしょ)
・とにかく、よく物を失くす。注意力が足りないからなのか、それに留まらない何か大きな欠陥があるからか、知命も近い年齢になってくると、こうした癖を直したくても直せないと思い、諦めている。
・イギリスの詩人ミルトン
心というものは、それ自身一つの独自の世界なのだ、――地獄を天国に変え、天国を地獄に変えうるものなのだ。
・虚無を感じるのは、私たちの人生に意味がないからではないだろうか。今感じているよりも深く、生きる意味を感じるようにも、人生が求めているのではあるまいか。
・逢うためには、どうしても、時の助力がなくてはならない。むしろ、時が、出会いを出逢いに変じるのだろう。
・人は、本当に後悔していることを他者には容易に語らない。他者だけでなく、自分でもそれを直視しようとしない。そうした心のありようをドストエフスキーが見事に言い当てている。
どんな人の思い出のなかにも、だれかれなしには打ちあけられず、ほんとうの親友にしか打ちあけられないようなことがあるものである。また、親友にも打ちあけることができず、自分自身にだけ、それもこっそりとしか明かせないようなこともある。さらに、最後に、もうひとつ、自分にさえ打ちあけるのを恐れるようなこともあり、しかも、そういうことは、どんなにきちんとした人の心にも、かなりの量、積もりたまっているものなのだ。いや、むしろ、きちんとした人であればあるほど、そうしたことがますます多いとさえいえる。
・問題は、失敗と成功の二者択一にあるのではなく、そのあいだに潜む、「と」の世界にある。小さな幸福を、いかにして「と」の世界に探し当てることができるかにあるのではないだろうか。思ったりもする。
・哲学者のショーペンハウアーは近代人が陥りがちな多読をいさめるようにこう記している。
読書は、他人にものを考えてもらうことである。本読む我々は、他人の考えた過程を反復的にたどるにすぎない。習字の練習をする生徒が、先生の鉛筆書きの線をペンでたどるようなものである。
・・・彼が私たちを誘おうとしているのは読書という習慣ではなく、読書を通じた思索の営みだ。
・フランクル『夜と霧』
かつてドストエフスキーはこう言った。「わたしが恐れるのはただひとつ。わたしがわたしの苦悩に値しない人間になることだ」
苦悩はいつか必ず、人を真の幸福へと導く翼になる、そう彼らは信じているのである。
・21歳から22歳にかけて、こころを病んでいた。実社会に出て働くのが怖くて、自分という小さな世界に閉じこもる日々が続いた。そんなある日、師である井上洋治神父を囲む『新約聖書』の勉強会があり、そこでやるかたない自分の心情を神父に語ったことがある。独りよがりの長い話だったが、私の言葉が切れると彼は、深みから何かを照らし出すようにこう語った。
「君の苦しみは君の苦しみだから、ぼくは、それが何であるか、ほんとうのところは分からない。しかし、君が苦しんでいるのはよく分かる、それは、君に生きることが始まった合図、人生が始まった合図なのではないのだろうか」
そう話したあと彼は、生きるとは、プールで泳ぐことではなく、ひとり小さな舟で海に漕ぎ出すようなものではないだろうか、とも言った。
プールは大きさが決まっていて、急に深くなることも、波もない。そこは消毒されていて人間以外の生き物もいない。しかし、海には同じ深さのところなどないし、そこには無数の生き物がいる。波の大きさも一定ではなく、その上にいるとき、私たちはいるも揺れ動いている。
人生に確実な答えなど存在しないことは皆、知っている。しかし、揺れ動く中で人は、生きるための確かな手ごたえを感じられるようになってくる。確かな、とは絶対に間違いがないことを指すのではない。その人が、わが身を賭してもよいと感じるに十分な感覚を指す。
それは言葉との関係においても同じで、あるときから多くの言葉を知ることよりも、自分にとってかけがえのない言葉の深みを治してみることの方がよほど大切なことに気が付く。
さまざまな段階を経るなかで、同じ言葉の意味に大きく変わってくる。むしろ、一つの言葉に世界の深みへと通じる扉を見出すようになっていく。「祈り」という言葉は、私にとってそうした意味の深みを感じさせてくれるイチゴになっている。
感想;
若松英輔さんの本は2冊目ですが、温かみを感じます。
言葉の重み、大切さ、自分を助けてくれる言葉を見つけることはとても大切なように思います。











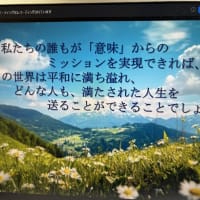

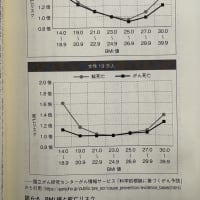

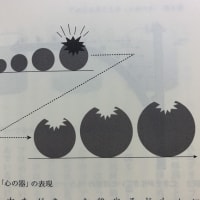
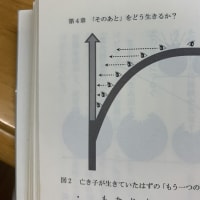



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます