・生きるとは、人生とは何かを問うことではなく、人生からの問いに応えることだと『夜と霧』の著者ヴィクトール・フランクルは言った。人生は、答えを出すことを求めない。だが、いつも真摯な対応を求めてくる、というのである。
・『小岩井農場』宮沢賢治作
もうけつしてさびしくはない
なんべんさびしくないと云ったとこで
またさびしくなるのはきまつてゐる
けれどもここはこれでいいのだ
すべてさびしさと悲傷とを焚いて
ひとは透明な軌道をすすむ
・邂逅の歓びを感じているのなら、そのことをもっと慈しんでよい。勇気を出して、そう語り出さなくてはならないのだろう。
あなたに出会えてよかったと伝えることから始めてみる。相手は目の前にいなくてもよい。ただ、心のなかでそう語りかけるだけで、何かが変わり始めるのを感じるだろう。
・哲学を意味するギリシア語フィロソフィアは、『叡知を愛する』ことを意味した。
・改めて考えると不思議だが、情愛と共に人生の道を生き抜こうとする者は皆、力を伴った徳を具えている。私はこれまで何人もそうした無名の叡知の人に出会ってきたように思う。
・詩集『白い木馬』ブッシュ孝子作
暗やみの中で一人枕をぬらす夜は
息をひそめて
私をよぶ無数の声に耳をすまそう
地の果てから 空の彼方から
遠い過去から ほのかな未来から
夜の闇にこだまする無言のさけび
あれはみんなお前の仲間達
暗やみを一人さまよう者達の声
沈黙に一人耐える者の声
声も出さずに涙する者達の声
この女性は、いわゆる詩人ではなかった。ガンのため逝ったのは28歳のときだった。亡くなる五か月ほど前のある日、突然、言葉があふれる経験をして以来、彼女はノートに詩を書き続けた。書きつけた言葉が、おのずと詩になったという方がよいのだろう。
・「言葉」(『考えるヒント』小林秀雄著)
悲しみに対し、これをととのえようと、肉体が涙を求めるように、
悲しみに対して、精神はその意識を、その言葉に求める。
涙が頬をつたう。それは何ものかが、言葉を探す準備が整ったことを知らせている、というのである。
・考えるとは、安易な答えに甘んじることなく、揺れ動く心で、問いと生きてみることだ。真に考えるために人は、勇気を必要とする。考えることを奪われた人間はしばしば、内なる勇気を見失う。
・詩集『点滴ポール 生き抜くという旗印』岩崎航作
(筋ジストロフィーを発症して以来、ベッドの上で毎日を送っている。)
ここにいる そこにもいる
目の前にいる普通の人こそ
知られざる
勇者であること
わたしは生きて知りました
「光」
どんな
微細な光をも
捉える
眼を養うための
くらやみ
「絶望のなか」
絶望のなかで見いだした希望、苦悶の先につかみ取った「今」が、自分にとって一番の詩だ。
そう心から思えていることは、幸福だと感じている。
ここに勇気の文字は記されていないが、読む私たちはそれを感じる。勇気とは、語り得る何かではなく、試練を生きる者の生涯によって体現されるものなのかもしれない。
・師について
2014年の3月8日に師が逝った。井上洋治神父である。彼はカトリックの司祭で、優れた神学者、思想家でもあった。
神父の役割は、イエスの言葉を人々に届けることである。彼は日本人に西洋の神学を押し付けるのではなく、日本人の心に直接響く言葉を探した。イエスに関する知識ではなく、イエスの心を伝えたい、そのことを、心から心に伝えたい、としばしば語った。
師とめぐり会ったのは19歳のときだった。この出会いから人生は明らかに位相が変わった。当時そう感じたのではない。師が亡くなり一年が経ち、今更ながらそう思うのである。
世に言う師とは、どう生きるかを教えてくれる存在であるかもしれないが、私の師は違った。彼が教えてくれたのは、生きるとは何かということだった。人生の道をどう歩くのではなく、歩くとはどういう営みであるかを教えてくれた。
もう25年以上前になる。学生時代の終わり頃ノイローゼになった。医師がカルテに「神経症」と書いたのをはっきり覚えている。自分が造った小さな世界に逃げ込んでしまい、出ることができなくなっていた。原因は、はっきりしている。働くのが嫌だったのである。働かなくてもよい環境にいたのではない。むしろ逆だった。
どうしてそう思い込んだのか、ものを作る会社に勤めなくてはならないと思い込んでいた。特殊な技能も資格もない。製造業の会社に勤務するとなればきっと営業職で、下戸で、歌うこともまったく苦手な自分は、耐えがたい辛酸をなめるに違いないと思ったらとたんに、世にでるのが怖くなった。比喩ではない。部屋から出られなくなった日々も少なからずあった。
当時、師は、多忙の時間を割いて、若者と新約聖書を読む集いを設けてくれていた。集いといっても同席していたのは師をふくめて5人で、今から思うとなんと贅沢な時間だったのかと思う。
ある日その場で、出口を失ってどうにもならない心情を、そのまま吐露した。
聖書のどこを読んでも自分は光を見つけられない。そればかりか自分が救われないことだけがはっきりしてくる。その語り、矛盾したことが述べられている箇所を挙げ、数十分にわたってひとりで話し続けた。すると、だまって聞いていた師が、こう言ったのである。
「今日は、とてもすばらしい話を聞かせてもらいました。ありがとうございます。しかし、ひとつだけ感じたことがある。信仰とは頭で考えることではなく、生きてみることではないだろうか。知ることではなく、歩いてみることではないだろうか」
この一言が私を変えた。その日からゆっくりと病は癒え始め、しばらくして、文章を書くようになった。病がなければ、こうして言葉をつむぐ仕事に就くこともなかっただろう。
生前、神父を師と呼んだことはなかった。師と呼ぶには、私が彼に弟子だと認められなくてはならない。師弟の関係は、弟子の敬意が深いだけでは成り立たないのである。
だが今、彼を師と呼ぶのは亡くなる一月前、没後の出版を託され、原稿を預けられたからだ。また、師が最後に読んだ著述が、雑誌に掲載された私の『イエス伝』であることを亡くなったあとに聞かされたからでもある。彼の遺稿には、こんな一節がある。
宗教は考えて理解するものではなく、行為として生きて体得するものです。たとえてみれば、山の頂上にむかって歩んでいく道であるといえましょう。人は二つの道を同時に考えることはできても、同時に歩むことは決してできません。(『遺稿集「南無アッパ」の祈り』
・人生の意味は、生きてみなくては分からない。素朴なことだが、私たちはしばしば、このことを忘れ、頭だけで考え、ときに絶望してはいないだろうか。
・哲学者 池田晶子著『あたりまえなことばかり』
死の床にある人、絶望の底にある人を救うことができるのは、医療ではなくて言葉である。宗教でもなくて、言葉である。
・『ミラノ霧の風景』須賀敦子著(処女作)
「いまは霧の向こうの世界に行ってしまった友人たちに、この本を捧げる」
彼女が愛したサバ(イタリア北東部の街トリエステで活動した詩人)の詩
石と霧のあいだで、ぼくは
休日を愉しむ。大聖堂の
広場に憩う。星の
かわりに夜ごと、ことばに灯がともる
人生ほど、
生きる疲れを癒してくれるものは、ない
(須賀敦子『コルシア書店の仲間たち』より)
・『苦海浄土』石牟礼著
私たちは、この作品を読むことを通じてでも、きよ子と彼女の母親の悲願に応えることができる。(母親は石牟礼に、水俣病の原因となった有機水銀を排出した企業であるチッソに向けて、いや、世の人々に向けて、きよ子のような人間がいたことを告げる言葉を書いてくれないかと懇願する。)
読むことには、書くこととはまったく異なる意味がある。書かれた言葉はいつも、読まれることによってのみ、この世に生を受けるからだ。比喩ではない。読むことは言葉を生みだすことなのである。
・『クリスマス・キャロル』チャールズ・ディケンズ著
ご主人には、わたしたちを幸福にも不幸にもするだけの力があるんです。ご主人のやり方しだいで、わたしたちの仕事は、軽くもなり、重荷にもなります。楽しみにもなれば、苦しみにもなるんです。ご主人のその力は、言葉とか顔つきといった、一つ一つは、ささいなことにあるのであって、数え上げて合計を出そうたって、できやしません。だけど、どうです? それによって与えられる幸せは、一財産を積んだって買えないくらい大きいんですからね。
・コトバが心に届くとき、人は何かに抱きしめられたように感じる。誰の人生にも幾度かは必ず、こうした出来事が訪れる。そしてその感触は忘れられることはあっても、生涯消えることはないのである。
・画家の岸田劉生
「自分は時として、自分の孤独に淋しさを感ずる事がある。他の個性と自分の性格との差別をそこから意識する事によって自分は或る淋しさをほんとうに味う事がある」
「しかし、自分はこの自分の孤独を感ずる事の外に、自分の存在を感ずる事の出来ないものである。そうして、自分の生存と意志に権威と祝福とを感ずるのである。人間は孤独をつかんでからでなければ真の生活を創め得ない事を自分は真に感ずるものである」
人生には、孤独を生きてみなければどうしても知り得ないことがある。孤独を感じるとき、もっとも近くに自己を感じる。ここで述べられている人生の秘密との遭遇は、私が、「私」になる道程に欠くことができない。さらに、人が真に他者と出会うのも孤独を生きる道程においてだというのである。
孤独の経験は、わたしたちを孤立させるのではない。むしろ、他者と結びつく契機となる。それはいつしか、私たちを人類という場に導くことがある。
「孤独とは、人類としての自分と自然との意志の調和を本当に感じる事である。自然が人類として自分を生んだという真正の自覚が孤独である。少なくとも人間は孤独になるのほか本統(ほんとう)に自然を見る事は出来ない。本統に人類に交渉する事は出来ない」と岸田はいう。ここでの人類とは無限に広がる複数の人間よりも、人間であることの、時空を超えたつながりを指す。人類には亡き者たちも含まれる。私の孤独は、人類の孤独でもある。
・孤独はときに、情愛の発露となる。人は、孤独を生きることによってはじめて、自らの内部に、それまで感じ得なかった愛惜の炎を見出すことがある。
・孤独は、悲嘆に始まる経験であると同時に、それは生きる力をもたらし、深みから私たちの人生を祝福するというのである。
・河合隼雄
治療者は、クライエント(心理療法を受ける人)と一対一で会う。眼前にいる人は、日常生活のなかで、ある試練に直面している。現代社会には同様の日々を送っている人物は少なくない。この人物もそのうちの一人だと考えることもできる。しかし、自分にはそう思えない。とのクライエントに向き合うときも、必死に今を生き抜こうとする人類の代表者として会う。
・誰かを愛しむことは、いつも悲しみを育むことになる。なぜなら、そう思う相手を喪うことが、たえがたいほどの悲痛の経験になるからだ。宿った情感が豊かで、また、相手を深く思えばと思うほど、訪れと悲しみも深くなる。
・神谷美恵子
愛し、そして喪ったということは、いちども愛したことがないよりも、よいことなのだ。
感想;
ここで紹介した箇所はほんの一部です。
生きる上での孤独や不安、時には苦しみにさえ感じる様々な湧き出す感情。
その感情をコントロールできずに、その感情に右往左往している。
時には、その感情のまま選択すべきでない選択もしてしまう。
でも、その孤独や感情をそのまま包み込んで、そしてそれがとても大切な意味あるものであると諭してくれているようでした。
悲しみが深いということは、それを深く愛したことでもある。
愛情が強くなればなるほど喪う悲しみも大きくなる。
しかし、それを恐れて愛さないよりも、愛する方が人生がすばらしいと、多くの人生の先輩が遺してくれた言葉がそれを教えてくれています。
この本に出てきた多くの人の中に、自分が読んだ本もいくつかありました。
感動を覚える本はあるていど同じなのかもしれないと思いました。
井上洋治神父の生き方/考え方に惹かれ何冊か読みました。
井上洋治神父のことを教えて下さったロゴセラピーの仲間、人を通してさらに広がりを感じます。
自分が読める本の量は限られています。
でも、この本のように、著者が読み感動された本や言葉の紹介が、無限の広がりを持っているように感じます。
気になった本を読むことにより、その広がりはさらに広がっていくようです。
お薦めの本です。
若松英輔
・『小岩井農場』宮沢賢治作
もうけつしてさびしくはない
なんべんさびしくないと云ったとこで
またさびしくなるのはきまつてゐる
けれどもここはこれでいいのだ
すべてさびしさと悲傷とを焚いて
ひとは透明な軌道をすすむ
・邂逅の歓びを感じているのなら、そのことをもっと慈しんでよい。勇気を出して、そう語り出さなくてはならないのだろう。
あなたに出会えてよかったと伝えることから始めてみる。相手は目の前にいなくてもよい。ただ、心のなかでそう語りかけるだけで、何かが変わり始めるのを感じるだろう。
・哲学を意味するギリシア語フィロソフィアは、『叡知を愛する』ことを意味した。
・改めて考えると不思議だが、情愛と共に人生の道を生き抜こうとする者は皆、力を伴った徳を具えている。私はこれまで何人もそうした無名の叡知の人に出会ってきたように思う。
・詩集『白い木馬』ブッシュ孝子作
暗やみの中で一人枕をぬらす夜は
息をひそめて
私をよぶ無数の声に耳をすまそう
地の果てから 空の彼方から
遠い過去から ほのかな未来から
夜の闇にこだまする無言のさけび
あれはみんなお前の仲間達
暗やみを一人さまよう者達の声
沈黙に一人耐える者の声
声も出さずに涙する者達の声
この女性は、いわゆる詩人ではなかった。ガンのため逝ったのは28歳のときだった。亡くなる五か月ほど前のある日、突然、言葉があふれる経験をして以来、彼女はノートに詩を書き続けた。書きつけた言葉が、おのずと詩になったという方がよいのだろう。
・「言葉」(『考えるヒント』小林秀雄著)
悲しみに対し、これをととのえようと、肉体が涙を求めるように、
悲しみに対して、精神はその意識を、その言葉に求める。
涙が頬をつたう。それは何ものかが、言葉を探す準備が整ったことを知らせている、というのである。
・考えるとは、安易な答えに甘んじることなく、揺れ動く心で、問いと生きてみることだ。真に考えるために人は、勇気を必要とする。考えることを奪われた人間はしばしば、内なる勇気を見失う。
・詩集『点滴ポール 生き抜くという旗印』岩崎航作
(筋ジストロフィーを発症して以来、ベッドの上で毎日を送っている。)
ここにいる そこにもいる
目の前にいる普通の人こそ
知られざる
勇者であること
わたしは生きて知りました
「光」
どんな
微細な光をも
捉える
眼を養うための
くらやみ
「絶望のなか」
絶望のなかで見いだした希望、苦悶の先につかみ取った「今」が、自分にとって一番の詩だ。
そう心から思えていることは、幸福だと感じている。
ここに勇気の文字は記されていないが、読む私たちはそれを感じる。勇気とは、語り得る何かではなく、試練を生きる者の生涯によって体現されるものなのかもしれない。
・師について
2014年の3月8日に師が逝った。井上洋治神父である。彼はカトリックの司祭で、優れた神学者、思想家でもあった。
神父の役割は、イエスの言葉を人々に届けることである。彼は日本人に西洋の神学を押し付けるのではなく、日本人の心に直接響く言葉を探した。イエスに関する知識ではなく、イエスの心を伝えたい、そのことを、心から心に伝えたい、としばしば語った。
師とめぐり会ったのは19歳のときだった。この出会いから人生は明らかに位相が変わった。当時そう感じたのではない。師が亡くなり一年が経ち、今更ながらそう思うのである。
世に言う師とは、どう生きるかを教えてくれる存在であるかもしれないが、私の師は違った。彼が教えてくれたのは、生きるとは何かということだった。人生の道をどう歩くのではなく、歩くとはどういう営みであるかを教えてくれた。
もう25年以上前になる。学生時代の終わり頃ノイローゼになった。医師がカルテに「神経症」と書いたのをはっきり覚えている。自分が造った小さな世界に逃げ込んでしまい、出ることができなくなっていた。原因は、はっきりしている。働くのが嫌だったのである。働かなくてもよい環境にいたのではない。むしろ逆だった。
どうしてそう思い込んだのか、ものを作る会社に勤めなくてはならないと思い込んでいた。特殊な技能も資格もない。製造業の会社に勤務するとなればきっと営業職で、下戸で、歌うこともまったく苦手な自分は、耐えがたい辛酸をなめるに違いないと思ったらとたんに、世にでるのが怖くなった。比喩ではない。部屋から出られなくなった日々も少なからずあった。
当時、師は、多忙の時間を割いて、若者と新約聖書を読む集いを設けてくれていた。集いといっても同席していたのは師をふくめて5人で、今から思うとなんと贅沢な時間だったのかと思う。
ある日その場で、出口を失ってどうにもならない心情を、そのまま吐露した。
聖書のどこを読んでも自分は光を見つけられない。そればかりか自分が救われないことだけがはっきりしてくる。その語り、矛盾したことが述べられている箇所を挙げ、数十分にわたってひとりで話し続けた。すると、だまって聞いていた師が、こう言ったのである。
「今日は、とてもすばらしい話を聞かせてもらいました。ありがとうございます。しかし、ひとつだけ感じたことがある。信仰とは頭で考えることではなく、生きてみることではないだろうか。知ることではなく、歩いてみることではないだろうか」
この一言が私を変えた。その日からゆっくりと病は癒え始め、しばらくして、文章を書くようになった。病がなければ、こうして言葉をつむぐ仕事に就くこともなかっただろう。
生前、神父を師と呼んだことはなかった。師と呼ぶには、私が彼に弟子だと認められなくてはならない。師弟の関係は、弟子の敬意が深いだけでは成り立たないのである。
だが今、彼を師と呼ぶのは亡くなる一月前、没後の出版を託され、原稿を預けられたからだ。また、師が最後に読んだ著述が、雑誌に掲載された私の『イエス伝』であることを亡くなったあとに聞かされたからでもある。彼の遺稿には、こんな一節がある。
宗教は考えて理解するものではなく、行為として生きて体得するものです。たとえてみれば、山の頂上にむかって歩んでいく道であるといえましょう。人は二つの道を同時に考えることはできても、同時に歩むことは決してできません。(『遺稿集「南無アッパ」の祈り』
・人生の意味は、生きてみなくては分からない。素朴なことだが、私たちはしばしば、このことを忘れ、頭だけで考え、ときに絶望してはいないだろうか。
・哲学者 池田晶子著『あたりまえなことばかり』
死の床にある人、絶望の底にある人を救うことができるのは、医療ではなくて言葉である。宗教でもなくて、言葉である。
・『ミラノ霧の風景』須賀敦子著(処女作)
「いまは霧の向こうの世界に行ってしまった友人たちに、この本を捧げる」
彼女が愛したサバ(イタリア北東部の街トリエステで活動した詩人)の詩
石と霧のあいだで、ぼくは
休日を愉しむ。大聖堂の
広場に憩う。星の
かわりに夜ごと、ことばに灯がともる
人生ほど、
生きる疲れを癒してくれるものは、ない
(須賀敦子『コルシア書店の仲間たち』より)
・『苦海浄土』石牟礼著
私たちは、この作品を読むことを通じてでも、きよ子と彼女の母親の悲願に応えることができる。(母親は石牟礼に、水俣病の原因となった有機水銀を排出した企業であるチッソに向けて、いや、世の人々に向けて、きよ子のような人間がいたことを告げる言葉を書いてくれないかと懇願する。)
読むことには、書くこととはまったく異なる意味がある。書かれた言葉はいつも、読まれることによってのみ、この世に生を受けるからだ。比喩ではない。読むことは言葉を生みだすことなのである。
・『クリスマス・キャロル』チャールズ・ディケンズ著
ご主人には、わたしたちを幸福にも不幸にもするだけの力があるんです。ご主人のやり方しだいで、わたしたちの仕事は、軽くもなり、重荷にもなります。楽しみにもなれば、苦しみにもなるんです。ご主人のその力は、言葉とか顔つきといった、一つ一つは、ささいなことにあるのであって、数え上げて合計を出そうたって、できやしません。だけど、どうです? それによって与えられる幸せは、一財産を積んだって買えないくらい大きいんですからね。
・コトバが心に届くとき、人は何かに抱きしめられたように感じる。誰の人生にも幾度かは必ず、こうした出来事が訪れる。そしてその感触は忘れられることはあっても、生涯消えることはないのである。
・画家の岸田劉生
「自分は時として、自分の孤独に淋しさを感ずる事がある。他の個性と自分の性格との差別をそこから意識する事によって自分は或る淋しさをほんとうに味う事がある」
「しかし、自分はこの自分の孤独を感ずる事の外に、自分の存在を感ずる事の出来ないものである。そうして、自分の生存と意志に権威と祝福とを感ずるのである。人間は孤独をつかんでからでなければ真の生活を創め得ない事を自分は真に感ずるものである」
人生には、孤独を生きてみなければどうしても知り得ないことがある。孤独を感じるとき、もっとも近くに自己を感じる。ここで述べられている人生の秘密との遭遇は、私が、「私」になる道程に欠くことができない。さらに、人が真に他者と出会うのも孤独を生きる道程においてだというのである。
孤独の経験は、わたしたちを孤立させるのではない。むしろ、他者と結びつく契機となる。それはいつしか、私たちを人類という場に導くことがある。
「孤独とは、人類としての自分と自然との意志の調和を本当に感じる事である。自然が人類として自分を生んだという真正の自覚が孤独である。少なくとも人間は孤独になるのほか本統(ほんとう)に自然を見る事は出来ない。本統に人類に交渉する事は出来ない」と岸田はいう。ここでの人類とは無限に広がる複数の人間よりも、人間であることの、時空を超えたつながりを指す。人類には亡き者たちも含まれる。私の孤独は、人類の孤独でもある。
・孤独はときに、情愛の発露となる。人は、孤独を生きることによってはじめて、自らの内部に、それまで感じ得なかった愛惜の炎を見出すことがある。
・孤独は、悲嘆に始まる経験であると同時に、それは生きる力をもたらし、深みから私たちの人生を祝福するというのである。
・河合隼雄
治療者は、クライエント(心理療法を受ける人)と一対一で会う。眼前にいる人は、日常生活のなかで、ある試練に直面している。現代社会には同様の日々を送っている人物は少なくない。この人物もそのうちの一人だと考えることもできる。しかし、自分にはそう思えない。とのクライエントに向き合うときも、必死に今を生き抜こうとする人類の代表者として会う。
・誰かを愛しむことは、いつも悲しみを育むことになる。なぜなら、そう思う相手を喪うことが、たえがたいほどの悲痛の経験になるからだ。宿った情感が豊かで、また、相手を深く思えばと思うほど、訪れと悲しみも深くなる。
・神谷美恵子
愛し、そして喪ったということは、いちども愛したことがないよりも、よいことなのだ。
感想;
ここで紹介した箇所はほんの一部です。
生きる上での孤独や不安、時には苦しみにさえ感じる様々な湧き出す感情。
その感情をコントロールできずに、その感情に右往左往している。
時には、その感情のまま選択すべきでない選択もしてしまう。
でも、その孤独や感情をそのまま包み込んで、そしてそれがとても大切な意味あるものであると諭してくれているようでした。
悲しみが深いということは、それを深く愛したことでもある。
愛情が強くなればなるほど喪う悲しみも大きくなる。
しかし、それを恐れて愛さないよりも、愛する方が人生がすばらしいと、多くの人生の先輩が遺してくれた言葉がそれを教えてくれています。
この本に出てきた多くの人の中に、自分が読んだ本もいくつかありました。
感動を覚える本はあるていど同じなのかもしれないと思いました。
井上洋治神父の生き方/考え方に惹かれ何冊か読みました。
井上洋治神父のことを教えて下さったロゴセラピーの仲間、人を通してさらに広がりを感じます。
自分が読める本の量は限られています。
でも、この本のように、著者が読み感動された本や言葉の紹介が、無限の広がりを持っているように感じます。
気になった本を読むことにより、その広がりはさらに広がっていくようです。
お薦めの本です。
若松英輔











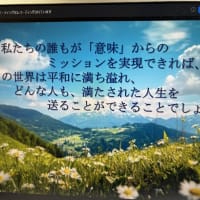

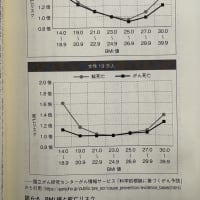

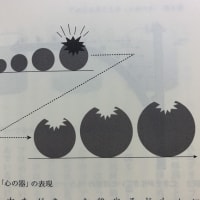
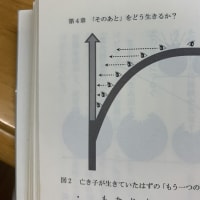



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます