◎ 浅原才市・・・
船大工であった才市は長年九州で働いていたが、晩年に故郷に戻り、下駄作りと販売業を営む。そして商売で得た利益を各地の災害や寺院に寄付した。才市は若い頃より普段の生活はつつましかったが、福祉や仏法のためには、生涯、惜しみなく献金を行なったのである。故郷には 才市が大正12年(1923)に新築した二階建ての家は、現在も保存されている。中には、生前使っていた大工道具等が展示してある。
NHK 信心の華 妙好人を語る 楠 恭著より














写真はご門徒さんの庭にできた綿花です。
3本植えたらできました。と言ってくださいました。
貴重な綿花です。
観賞に植えられたようです。大坊守も懐かしいと以前植えていたことを思い出したようです。
初めて見ましたという門徒さんもおられました。
私が高校のとき テレビで見た映画「風と共に去りぬ」のなかで広い農場の綿花を取り入れるシーンを見たような・・・
その時 学校の裏にあった富士紡績会社に父親が勤める友人から綿花の種をいただき 庭へ植え収穫したことがあります。エジプト綿だったかと思います。種も小さいが綿も小さく小ぶりでした。直径5cm程、種を綿から外すのが大変でした。
でも写真の綿はとても大きくすごいです。直径10cm
住職が「布団でも作ったら!」一同爆笑
晴れたときに採り入れなければ 綿が重く汚れるんでしょうね~
この種を来年5月に蒔いてみます・・・忘れなければの話
 花が綺麗なようです。
花が綺麗なようです。
ホクトの枕を作ってあげたい・・・・


船大工であった才市は長年九州で働いていたが、晩年に故郷に戻り、下駄作りと販売業を営む。そして商売で得た利益を各地の災害や寺院に寄付した。才市は若い頃より普段の生活はつつましかったが、福祉や仏法のためには、生涯、惜しみなく献金を行なったのである。故郷には 才市が大正12年(1923)に新築した二階建ての家は、現在も保存されている。中には、生前使っていた大工道具等が展示してある。
NHK 信心の華 妙好人を語る 楠 恭著より














写真はご門徒さんの庭にできた綿花です。
3本植えたらできました。と言ってくださいました。
貴重な綿花です。
観賞に植えられたようです。大坊守も懐かしいと以前植えていたことを思い出したようです。
初めて見ましたという門徒さんもおられました。
私が高校のとき テレビで見た映画「風と共に去りぬ」のなかで広い農場の綿花を取り入れるシーンを見たような・・・
その時 学校の裏にあった富士紡績会社に父親が勤める友人から綿花の種をいただき 庭へ植え収穫したことがあります。エジプト綿だったかと思います。種も小さいが綿も小さく小ぶりでした。直径5cm程、種を綿から外すのが大変でした。
でも写真の綿はとても大きくすごいです。直径10cm
住職が「布団でも作ったら!」一同爆笑
晴れたときに採り入れなければ 綿が重く汚れるんでしょうね~
この種を来年5月に蒔いてみます・・・忘れなければの話
 花が綺麗なようです。
花が綺麗なようです。ホクトの枕を作ってあげたい・・・・




























 幸せを感じてるみたいでした。
幸せを感じてるみたいでした。


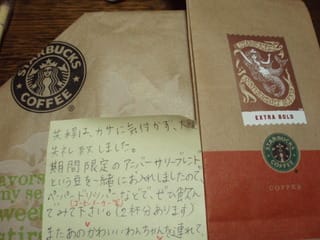

 あら~すみません 私こそ・・・ボケ・・・
あら~すみません 私こそ・・・ボケ・・・ 「何という種類ですか?滅多にいないですね~」
「何という種類ですか?滅多にいないですね~」 感謝するひとときでした。
感謝するひとときでした。


 私こそ 佐々木小次郎風斜めがけの傘
私こそ 佐々木小次郎風斜めがけの傘 にしなければ・・・・
にしなければ・・・・






 を買おうとなりまして・・・
を買おうとなりまして・・・

 文句なし 安さにビックリ(北海道では超高級品でしたが鎌倉は1800円) 買った
文句なし 安さにビックリ(北海道では超高級品でしたが鎌倉は1800円) 買った 直径30cm
直径30cm 住職の重い 思い・・・・
住職の重い 思い・・・・















 ねじり鉢巻でしあげました。
ねじり鉢巻でしあげました。









 のために 自ら去って木に託すんですね 偉いですね
のために 自ら去って木に託すんですね 偉いですね

 母曰く「一生に1本だけって言われたんよ~わたしゃ5年で賞味期限切れるからいいのよ」と笑いながら言う
母曰く「一生に1本だけって言われたんよ~わたしゃ5年で賞味期限切れるからいいのよ」と笑いながら言う










 美味しいですね~
美味しいですね~



