
前回に紹介した昔の船着場「下浜」の裏山沿いには
昔から保津の船頭衆が住む集落があります。
昔の船頭はこの裏山を下って、仕事場の着船場に
通っていたそうです。
この裏山には今も船頭達が通っていた細い路が
残っております。
地形が急な傾斜地になっていることから、曲がりくねった
階段状の坂道が続きます。
その中間地点に差し掛かると、路横に古い小さな祠が見えてきます。
この祠を保津の人達は「水神さま」と呼んでおります。
代々保津の船頭は、この路を通って出勤、家路にと
毎日往復する際、必ず「水神」さまに手を合わせて
いたそうです。
出勤の時は一日の運航の「安全」を祈願し、
帰り道には「安全運航できたことへの「感謝」の
気持ちで御参りしていたのです。
門構えも鳥居も何もない小さな祠しかない「水神」さまですが
保津の船頭の守り神として、強い精神的な支えなっていたのでしょう?
その路を歩いてみると、当時の船頭衆が棹を肩に
担げながら通勤する姿、その途中で「水神」さまに
手を合わし御参りする姿が目に浮かんできます。
代々先人の船頭さんの支えとなり、守られてきた「水神」さまには
はっちんの所属する第三支部が毎年、愛宕講の日(1月23日)の朝から
お供え物を持って御参りする慣わしになっており、当時の船頭の
思いを偲んでおります。
*写真の小さな祠が「水神」さまです。その横にある
小さな路が昔の船頭が仕事に通う時、使っていた
路です。現在は行き交う人の姿も稀となっている
ようで、寂しい限りです。
昔から保津の船頭衆が住む集落があります。
昔の船頭はこの裏山を下って、仕事場の着船場に
通っていたそうです。
この裏山には今も船頭達が通っていた細い路が
残っております。
地形が急な傾斜地になっていることから、曲がりくねった
階段状の坂道が続きます。
その中間地点に差し掛かると、路横に古い小さな祠が見えてきます。
この祠を保津の人達は「水神さま」と呼んでおります。
代々保津の船頭は、この路を通って出勤、家路にと
毎日往復する際、必ず「水神」さまに手を合わせて
いたそうです。
出勤の時は一日の運航の「安全」を祈願し、
帰り道には「安全運航できたことへの「感謝」の
気持ちで御参りしていたのです。
門構えも鳥居も何もない小さな祠しかない「水神」さまですが
保津の船頭の守り神として、強い精神的な支えなっていたのでしょう?
その路を歩いてみると、当時の船頭衆が棹を肩に
担げながら通勤する姿、その途中で「水神」さまに
手を合わし御参りする姿が目に浮かんできます。
代々先人の船頭さんの支えとなり、守られてきた「水神」さまには
はっちんの所属する第三支部が毎年、愛宕講の日(1月23日)の朝から
お供え物を持って御参りする慣わしになっており、当時の船頭の
思いを偲んでおります。
*写真の小さな祠が「水神」さまです。その横にある
小さな路が昔の船頭が仕事に通う時、使っていた
路です。現在は行き交う人の姿も稀となっている
ようで、寂しい限りです。















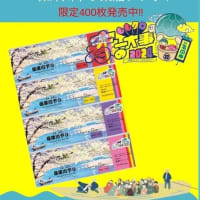

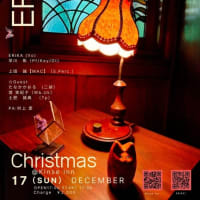



PS.風邪が流行っています。実はここ何日間ポラリスもダウンしておりました。はっちんさんもくれぐれもお体を大切に…毎回龍二様のことばかりの投稿ですいません。