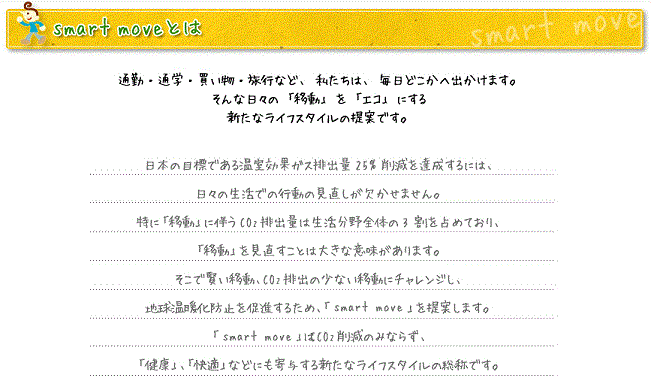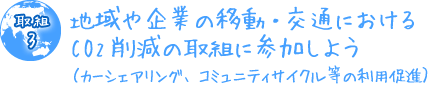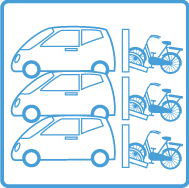■■【経営コンサルタントの独り言・環境】 発送電分離完全自由化をどのように進めていくべきか 7/7

2005年2月16日に「京都議定書」が発行しましたが、グローバルに見回しても一向に地球温暖化への気運が高まっていません。それどころか、自国の事情を背景に、自国擁護の動き優先で、一向に温暖化防止への動きが見られません。
環境への関心は、地球全体で意識を高めなければ、異常気象などが改善されません。

◆ 電力自由化はメリットを発揮するのか? 7/7
NHKの嶋津八生解説委員が電力自由化について解説していましたので、その解説をベースに私見をご紹介します。
◇第一回 世界一高額な電力料金
◇第二回 日本政府の電力自由化案
◇第三回 送配電会社と民間放送ネットワークの類似
◇第四回 発送電分離完全自由化の真の理由
◇第五回 発送電分離自由化の意義
◇第六回 発送電分離自由化のマイナス面
◇ 発送電分離完全自由化をどのように進めていくべきか
まずは政府のリーダーシップが必要です。
政府は、各電力会社が原発の運転停止によって経営が悪化し、資金調達に困難をきたしている現状の改善に向け、経営安定化に対しての支援策を早期に明確化して、電力会社や国民に示すべきです。
嶋津解説委員によりますと「政府が原子力の再稼働を保証する」と明言していませんが、電力自由化は原発の再稼働問題と微妙に絡み合いながら進んでいくという見解です。
日本の電力供給は、中長期的に原発の比率が低下し、一方で出力が一定しない不安定な電源である再生可能エネルギーの比率が高まっていくでしょう。その結果、安定供給が難しくなっていく傾向は避けがたいです。
ニューヨークやカリフォルニアではっせいしたようなブラックアウト(大停電)を絶対に避けなければなりません。いかに安定供給を確保しつつ、自由化を進めていくのか、用意周到な準備のもとでの完全自由化推進が最大の課題と考えます。 <完>
◆ 電力自由化はメリットを発揮するのか? 6/7
NHKの嶋津八生解説委員が電力自由化について解説していましたので、その解説をベースに私見をご紹介します。
◇第一回 世界一高額な電力料金
◇第二回 日本政府の電力自由化案
◇第三回 送配電会社と民間放送ネットワークの類似
◇第四回 発送電分離完全自由化の真の理由
◇第五回 発送電分離自由化の意義
◇ 発送電分離自由化のマイナス面
それでは、自由化により電気料金は値下がりするのでしょうか?
現状、電力業界は、原発の代わりに、コスト高を承知でLNGや石油火力をフル稼働させています。試算によると年間3兆円もコストが余計にかかるけいさんです。赤字の各電力会社の値上げも認められました。
新規参入の新電力会社なら、安い電力を提供できるという見通しは実はないのです。なぜなら発電に用いるエネルギー源であるLNGやシェールガス・オイルなどの安価での輸入まだ先の話です。
競争が促進されれば、値上がり幅がある程度抑えられる可能性はありますが、発電会社の体力低下にも繋がります。効果もそれほど期待できないでしょう。
ここで電力自由化のマイナス面を、嶋津解説委員の見方をみてみましょう。
私と同様に、電力会社の経営基盤の弱体化が最大の懸念材料と見ています。
原発の再稼働の見通しがなかなか立っていません。しかも安全規制面から今後、原発の廃炉に追い込まれ経営基盤が揺らぐような電力会社が出てくることも懸念されます。社債の発行など電力会社の資金調達の環境は悪化し、設備投資を難しくする恐れが出てきています。
発送電分離を前提にして、電力会社が資産を分割し、送電部門の別会社化を迫る自由化は、経営悪化に拍車をかけることは必定でしょう。
株価など資産価値が低下したところで、海外の投資ファンドが算入してくることは目に見えてきます。利益優先で、ユーザー無視な経営が行われるでしょう。 <続く>
◆ 電力自由化はメリットを発揮するのか? 5/7
NHKの嶋津八生解説委員が電力自由化について解説していましたので、その解説をベースに私見をご紹介します。
◇第一回 世界一高額な電力料金
◇第二回 日本政府の電力自由化案
◇第三回 送配電会社と民間放送ネットワークの類似
◇第四回 発送電分離完全自由化の真の理由
◇ 発送電分離自由化の意義
嶋津解説委員は、発送電分離完全自由化の意義について次のように解説しています。
1.一般的には、競争が促進されれば電力料金は下がるはずです。
2.家庭でも好きな電力会社から買えるようになると言う消費者の選択権が広がるというメリットはあります。
3.新規参入者が増えることが期待されます。マンション業者が、販売したマンションへの電力の販売を手掛けるといった動きも出てきそうです。発電部門でも、例えば製鉄会社の神戸製鋼所が、内陸部の栃木県でガス火力発電所の建設を進めると言った、あたらしい動きが出始めています。
4.競争が促進されれば、新しい技術革新が刺激され、日本経済の成長力の強化に繋がると言う期待もあります。
自由化されることにより、電力会社間に競争が生まれます。それにより、効率化に向けての努力もせざるを得ません。新しいエネルギー資源開発に取り組む企業が算入してくるでしょう。送電システムについても、環境問題先進国である日本ですから、革新的な考え方が生み出される可能性もでてきます。それをグローバルに展開する企業が出てきて欲しいですね。 <続く>
◇ 発送電分離完全自由化の真の理由
NHKの嶋津八生解説委員が電力自由化について解説していましたので、その解説をベースに私見をご紹介します。
◇第一回 世界一高額な電力料金
◇第二回 日本政府の電力自由化案
◇第三回 送配電会社と民間放送ネットワークの類似
◇ 発送電分離完全自由化の真の理由
発送電分離に関する法律が大企業偏重など不充分な内容で、自然エネルギーを供給する電力会社から自由に電力を買う事ができないことに対して、小規模な個人などで風力や太陽光といった自然エネルギーを使うことを希望する家庭などから多いに不満が出てきました。
今回、政府が電力の完全自由化に向かうことになった原点は福島第一原発の事故にあることは想像がつきます。何かことが起こらないと動かないのが日本の政府や御役人です。
事故を起こした東京電力に対する激しい批判が起きる中で「東電は売れる資産はすべて売って賠償や復旧に取り組め。発送電分離して送電設備も売ればよいではないか」という議論が持ち上がりました。
原発の再稼働によって電力の供給の安定化をめざす政府としては、こうした世論の厳しい空気を無視することができなくなって、ようやく神輿を上げたのです。前回、宿題として残されていた発送電分離を含む完全自由化に改めて取り組むことにならざるを得なくなったのです。 <続く>
◆ 電力自由化はメリットを発揮するのか? 3/7
NHKの嶋津八生解説委員が電力自由化について解説していましたので、その解説をベースに私見をご紹介します。
前回は、日本の電気料金は先進国で最も光学であることを紹介しました、今日は日本政府がどのように電力自由化を進めようとしているのか、嶋津解説委員の解説をご紹介します。
◇第一回 世界一高額な電力料金
◇第二回 日本政府の電力自由化案
◇ 送配電会社と民間放送ネットワークの類似
発送電分離が確立すると、各地域に作られる送配電会社は地域内に安定的に電力供給することが求められます。
そのために新電力の発電設備から供給される電力についてもすべて目配りした上で、基本的に域内の電力の需要と供給が一致するように、需給の安定に努めることになります。そして地域送電会社を全国レベルで統括し、全体の需給安定を図るのは、この「広域系統運用機関」ということになります。
テレビの民間放送局がネットを作るように、他の地域送電会社との連携が必要となります。
嶋津解説委員の解説に戻りましょう。
電力自由化のこれまでの経緯をたどりますと、日本も実は1990年代から世界的に自由主義の経済学が全盛を極め、電力の自由化を進めてきているのですね。自由化を進め競争を促進すれば、消費者や企業は安い電力を買う事が出来るようになるという論理からです。
その結果、大口ユーザーは、地元の電力会社ではなく、入札によって、一番安い価格を提示した新電力から買うことができるようになりました。しかし、現実には地域電力会社の競争力が強く新電力の獲得シェアはわずか4%程度にとどまっているのです。
家庭用などの小口のユーザーに対しては自由化が見送られ、選択の余地はありません。ただし、売電ができるようになったことは、ソーラー発電などを促進する一助になりました。 <続く>
◆ 電力自由化はメリットを発揮するのか? 2/7
NHKの嶋津八生解説委員が電力自由化について解説していましたので、その解説をベースに私見をご紹介します。
前回は、日本の電気料金は先進国で最も光学であることを紹介しました、今日は日本政府がどのように電力自由化を進めようとしているのか、嶋津解説委員の解説をご紹介します。
◇ 日本政府の電力自由化案
電力自由化をめぐる政府の基本方針では、5年後から7年後を最終ゴールに、電力の小売りの完全自由化、発送電の分離を目指すとしています。
ただそのゴールをいきなり目指すのではなく、改革を3段階にわけ、電力制度を定めた電気事業法も順次改正し、段階的に自由化を進めていくとしています。
第1段階として、2年後の2015年をめどに全国の電力の広域的な需給計画を立て、地域をまたいだ電力の需給調節に責任を持つ「広域系統運用機関」がつくられます。
第2段階の2016年をめどに電力の小売りの全面自由化が実施され、家庭も含めて、どこの電力会社からでも電気が買えるようになります。
第3段階は、2018年から2020年をめどに、料金規制の撤廃―つまり家庭用の電気の料金についても、各電力会社が自由に決めた値段で売ることができる。逆に消費者の立場からすれば、各電力会社の提示する多様な料金メニュを見比べて選べるようになります。
私見では、あまりにもテンポが遅すぎるように思えます。
第3段階に入ってようやく、既存の電力会社は、それぞれが社内に持っている送電部門を切り離して別会社を作るという、いわゆる発送電分離が実施されるのです。 <続く>
◆ 電力自由化はメリットを発揮するのか? 1/7
NHKの嶋津八生解説委員が電力自由化について解説していましたので、その解説をベースに私見をご紹介します。
◇ 世界一高額な電力料金
戦後、日本の電力供給体制は国営から民間へと経営が移されました。しかし、経費が高まれば、それを価格に転嫁できるという仕組みから、先進国では世界で最も高い電力を日本国民は使わされています。
福島第一原発自己では、東電の古い体質が浮き彫りになりました。電力料金を上げるのは「義務」であるという暴言さえ発せられました。しかし、それがあまり話題にならなかったことも不思議なことです。
大手電力会社による「地域独占」と、「発送電一貫体制」の弊害が、欧米の「電力の自由化」動向で目覚めさせられた感じで、日本政府も要約動き始めました。
「電力システムに関する改革方針」がようやく閣議決定し、電気事業法が改正の方向に向かった動き出しました。 <続く>