二つの火山の重なりがつくりだした豪快な千畳敷。

西海国立公園のなかでも指折りの絶景。

嵯峨ノ島(嵯峨島)は五島列島のなかでも流罪に使われた、離島の中の離島。

江戸時代よりずっと以前に京都から流されてきた公家が「嵯峨島」と名付けたと伝わる。
**
11月21日午後、福江島の貝津港から連絡船に乗った。

来訪者は片道880円

十五分ほどの航海だが中ほどでけっこう揺れた。

周囲9㎞ほどのひょうたん型をした島は男岳・女岳二つの火山の噴火で出来た。
島でひとつだけになってしまった集落に、島唯一の自動販売機がある。

「ちょっと前まで女岳のふもとにキリスト教徒の集落がもうひとつあったんですが…、島の人口は住民台帳で90人ですが実質50人ほどと言われています」

港と逆の海岸に冒頭写真の千畳敷がある。
 十分ほど歩けばもう海。
十分ほど歩けばもう海。



細い階段降りて千畳敷に出る。

びゅ~びゅ~海風にさらされる千畳敷の上。

足元に注意して歩いてゆくと、

「これは越えられないな」と思う海食洞(海が削った洞窟)に出た。が…
 「もうちょっと行くと火口が見える場所があるんですよ」と、橋のようになった部分を超えるNさん。
「もうちょっと行くと火口が見える場所があるんですよ」と、橋のようになった部分を超えるNさん。
え!行くんですか

「こまさんもこんね(小松さんも来ない?)」↓

全員で行きましょうとは言えない場所だ。が、どんな場所かはお伝えしたい。

小松、代表して超えました。

火口エリアを覗いてきます。

落っこちたくはない穴を横目にしばらくいくと

赤く高い崖がみえた。

↑なるほど、火口が波に削られて断面図のように半分になっていたのだ。
※「五島の島旅」に上から見た写真がありました
噴火の時に飛んできた石がそのまま地層につきささっている。



「日本にもこんなところがあるのですね」

離島で離島にやってきただけのことはある場所でした。

西海国立公園のなかでも指折りの絶景。

嵯峨ノ島(嵯峨島)は五島列島のなかでも流罪に使われた、離島の中の離島。

江戸時代よりずっと以前に京都から流されてきた公家が「嵯峨島」と名付けたと伝わる。
**
11月21日午後、福江島の貝津港から連絡船に乗った。

来訪者は片道880円

十五分ほどの航海だが中ほどでけっこう揺れた。

周囲9㎞ほどのひょうたん型をした島は男岳・女岳二つの火山の噴火で出来た。
島でひとつだけになってしまった集落に、島唯一の自動販売機がある。

「ちょっと前まで女岳のふもとにキリスト教徒の集落がもうひとつあったんですが…、島の人口は住民台帳で90人ですが実質50人ほどと言われています」

港と逆の海岸に冒頭写真の千畳敷がある。
 十分ほど歩けばもう海。
十分ほど歩けばもう海。


細い階段降りて千畳敷に出る。

びゅ~びゅ~海風にさらされる千畳敷の上。

足元に注意して歩いてゆくと、

「これは越えられないな」と思う海食洞(海が削った洞窟)に出た。が…
 「もうちょっと行くと火口が見える場所があるんですよ」と、橋のようになった部分を超えるNさん。
「もうちょっと行くと火口が見える場所があるんですよ」と、橋のようになった部分を超えるNさん。え!行くんですか

「こまさんもこんね(小松さんも来ない?)」↓

全員で行きましょうとは言えない場所だ。が、どんな場所かはお伝えしたい。

小松、代表して超えました。

火口エリアを覗いてきます。

落っこちたくはない穴を横目にしばらくいくと

赤く高い崖がみえた。

↑なるほど、火口が波に削られて断面図のように半分になっていたのだ。
※「五島の島旅」に上から見た写真がありました
噴火の時に飛んできた石がそのまま地層につきささっている。



「日本にもこんなところがあるのですね」

離島で離島にやってきただけのことはある場所でした。




















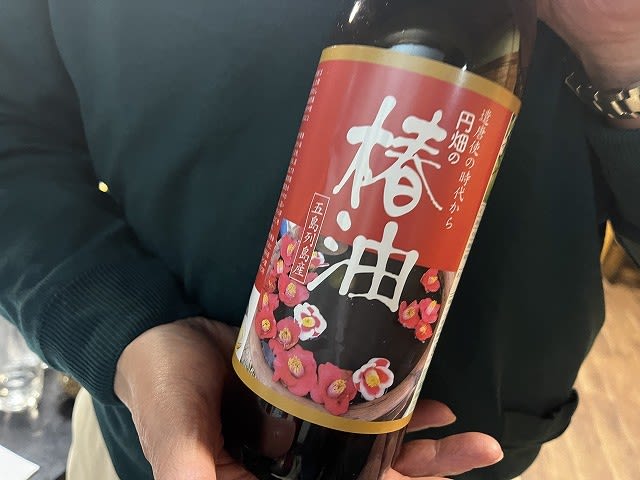

































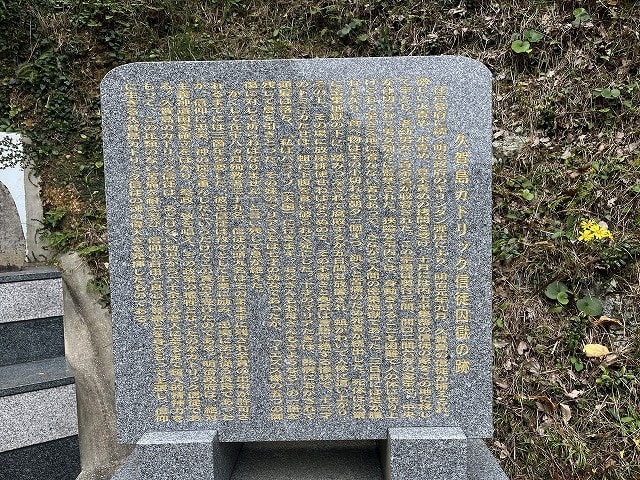















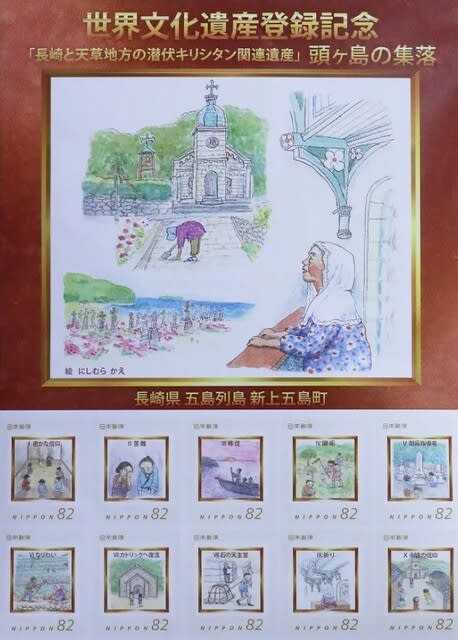





































 /a>
/a>























