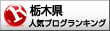先週オーナーが火入れをした炭窯の竹炭作りの結果報告です。
炭窯が開いていて、すでに竹炭を取り出した後でした。
炭窯の上に乗っている竹炭は、炭窯の燃やし口の近くにセットした竹たちで、
炭焼きの工程で燃えてしまい、灰になりかけの竹炭です。

今回出来た竹炭は、段ボールの中に入れられていました。
オーナーが、そのうちの1本を青竹を二つに割って作った台に乗せて、

「こんなのを玄関などの置物として、売れるのではないか・・・・・・」って、
はたして、買い手がつくのだろうか・・・・
ちなみに今回の竹炭作りに使用した竹は、
切ってから1年以上放置していたものを使用した為に油が抜けてしまったので、
竹酢液は、ほとんど採れなかったとの事でした。
13:20 高谷オカリナの里に着くと、オーナーが竹炭作りをしていました。
朝8:00頃に炭窯に火入れをしてからずっと、火の番をしているとの事でした。
今日は、風が強いので、煙突の煙が暴れています。

13:30 煙突内の温度は、100℃まで上がって来ました。
自分は、ダルマストーブに火を入れて、暖まりながら、ギターの練習をしていました。
15:30 過ぎ、地元の方が集まって来たので、オーナーも交えての、お茶会になりました。
16:30 炭窯の煙突の煙の色が変わって来たとの事で、炭窯の燃し口と煙突に蓋をしました。

あとは、自然冷却するのを待って、窯出しするだけです。
来週には、竹炭作りの成果が報告出来ると思います。
乞うご期待です!
炭窯の煙突部分の補修をしました。
オーナーが、以前から準備していた竹炭を焼こうと、午前中に窯に火を入れたところ、
煙突から出る煙はイマイチで、焚き口の方に煙が逆流してきたとの事でした。
原因は、煙突の下側に水(竹酢液)が溜まっていて煙突の気道が塞がっていた為です。
と言う訳で、竹炭作りは中断して、お昼過ぎから煙突の補修となった訳であります。
オーナーと安藤要さんで、炭窯の煙突側の囲いを外し詰まった土を取り除いていきます。

あらかた土を取り除いたら煙突の付根のボックスが見えて来ました。

ボックスの下の所にドリルで穴を開けると、水(竹酢液?)が大量に出て来ました。

ボックスの下に、排水用の穴を開けたいので、サンダーでボックスの側面をカットします。

その後、ボックスの下に排水用の穴を開けたら、元通りに埋め戻します。
その後、炭窯に火を入れ確認したところ、煙突からは勢いよく煙が出て、
焚き口の燃やした薪から、薪窯を通って、正常な気流になったという事です。
ちなみに、自分は所用の為、途中で帰ってしまったので写真も記事も中途半端です・・・・・・
あしからず・・・
昨日、オーナーが竹炭作りをしたそうです。
今回で6度目の竹炭作りになります。
と言う訳で、今日は窯の蓋を開けて、竹炭の出来栄えを確認しました。
まずは炭窯の蓋を開ける為に、蓋の上にかぶせてある土を取り除きます。
土は乾いているので、スコップを入れるだけで凄い土埃が出ます。

土埃の中から炭窯の蓋が見えて来ました。
蓋を開けたら、竹炭が見えて来ました。

竹炭の出来栄えは、11月6日(日)の「どまんなかフェスタ佐野」で、
野上木工クラブの木工製品と一緒に展示販売されますので、お楽しみに!
ちなみに、今回の竹炭作りですが、乾燥した竹を使った為に、
採れた竹酢液は、いつもの半分以下だったそうです。
オーナーが先週に引き続き、東二さんが採取してきた山蛭2匹で、竹酢液の効果検証をしました。
先週は、原液をスプレーでかけての実験でしたが、今回は原液を10倍に薄めて山蛭にかけてみました。
結果は、即死とは行きませんでしたが、だんだん動きが鈍くなってきて、5分後には固まってしまいました。

次に、4倍に薄めた竹酢液を山蛭にかけてみました。オーナーらくらくフォンで撮影しながらの実験です。

結果は、山蛭はあっという間に縮こまって、2分後には動かなくなりました。
気を良くしたオーナーは、この竹酢液の商品化をしようかと考えています。
商品名は「竹酢液」ではなくて、「山ヒルコロリ」にしようと考えています。

今日は、百舌さんが、「竹酢液の使い方・効用」についての資料を持って来ていただきました。
「竹酢液」結構使い道ありそうです。
東二さん、オーナー、百舌さんが何をやっているのかと言うと・・・
東二さんが、別荘のイワナハウスで山蛭を採って来たというので、
以前、竹炭焼きの時に採れた竹酢液を使ってちょっとした実験をしているところです。
実験と言っても簡単なもので、山蛭に竹酢液をスプレーで吹きかけたらど~なるかって事です。
結果は、スプレーを吹きかけた瞬間、山蛭は固まってしまい即死でした。

オーナーがらくらくフォンで動画を撮っていたので、興味のある方は見せてもらってください。
この結果には、イワナハウスに行くたびに山蛭にたかられて困っていた東二さん大満足でした。
但し、今回は竹酢液の原液をスプレーしたので、
今後はどのくらい希釈しても大丈夫なのか検証する必要があります。
この実験結果に気を良くしたオーナーは、早速在庫の竹酢液を、
500mlのペットボトルに詰め替えていました。

でもネットで調べたら、この竹酢液は大分タール分が多いので、
良質な竹酢液とは言えない事が判明しました。
まぁ山蛭退治や、作物の虫よけに使う分には問題ないのですが・・・
人体に使うには、タール分を取り除く作業が必要だと思われます。
高谷オカリナの里に到着すると、ウメェ~、ウメェ~とヤギのメーメーちゃんが鳴いていました。

その奥のそば畑では、オーナーが耕運機っで畑を耕しているところでした。
新い池の山裾には、24日の深夜に降った雪が解けずに残っていました。

ガレージのシャッターを開けて、ダルマストーブに火を入れて、
ギターを弾きながら寛いでいると、作業を終えたオーナーがやって来て、
先週焼いた竹炭の窯出しを始めました。
まずは、炭窯の上の土をスコップで取り除きます。

蓋が出てきたところで、蓋を開けると・・・・・・

竹炭が出て来ました。焚き口の方の竹は灰になっていますが・・・

前回焼いた時よりも大分歩留まりが良いとの事です。
キウイの蔓で作った台に竹炭をのせてみました。

「アケビの蔓でもやってみたら・・・」と安藤要さんの提案で、
オーナーは、アケビの蔓を採って来て、台作りを始めました。

早速、出来たアケビの蔓の台に竹炭をのせたら、なんだか良い感じだったので、

「玄関や、トイレに飾っておくのもいいね」
「これを、地域の物産展なんかに出したら売れないだろうか・・・」
「そう言えば、竹酢液も一斗缶でふたつ出来たので、これを蒸留して売れないだろうか・・・」
って、希望は膨らむばかりでした。
13:30 昨日館林下町夜市で使った道具を戻しに高谷オカリナの里に着くと、
オーナーが竹炭作りをしていました。
今回で5度目の竹炭作りになります。
前回は、12:00に火を入れて温度が上がったのが、1:00になってしまったので、
今回は、8:30に火を入れたという事でした。
13:40現在、煙突の温度は約60℃です。

前回の経験から行くと火を入れてから3時間で80℃まで上がったのですが、
今回は、17:30を過ぎても75℃までしか上がって来ません。
強い風が吹いているからなのでしょうか・・・
この分だと、オーナーは前回に引き続き深夜まで火入れをする事になりそうです・・・
オーナーの竹炭作りその後の経過報告です。
19:30 煙突の温度が100℃まで上がったので、夕食をとりに自宅に戻りました。
20:30 炭窯に戻ると、煙突の温度は85℃まで下がってしまったそうです。
それから、しばらく窯を焚き続けて、ようやく150℃になったので、
焚き口を5cm開けて自宅に戻ったそうです。
翌朝、炭窯に行ってみると窯が真っ赤になっていて、
煙突の温度計が振り切れていて、
ピザ窯の温度計を入れてみたら、500℃を超えていたという事です。
ここで焚き口と煙突をふさいで、窯の温度を下げて行きます。
窯の温度が下がって、窯を開けてみたら、窯の中の竹の半分以上が灰になっていたそうです。

窯の温度の上がり過ぎが原因だと思われます。
でも、出来上がった竹炭は、なかなか質の良い竹炭だったようです。
オーナーいわく、備長竹炭だそうです。
13:20 高谷オカリナの里に到着すると、オーナーが竹炭作りをしていました。
今回で4回目の竹炭作りになります。

12:00 炭窯に火を入れたという事でしたが・・・
13:25 煙突からは、白い煙がモクモク出ていますが煙突の温度は50℃にもなっていません。

14:00 65℃になったところで、竹酢液を採取する一斗缶を煙突にセットしました。

15:17 煙突の温度がやっと80℃まで上がり、煙が白から黒っぽい色に変って来ました。

今回の竹炭作りには、オーナーのこだわりがあります。
良い竹酢液を採取するために、薪は使わずに、竹だけで焼き上げるというのです。

薪を使うと、タールが混じってしまうのではないかと言う、オーナーのこだわりです。
でも薪とは違い竹はすぐに燃えてしまうので、ほとんど窯に付きっきりになるのが難点です。
17:50 周囲は暗くなってしまったのに、煙突の温度はまだ85℃までしか上がっていません。

120℃になれば、焚き口をふさいで次の工程に行けるのですが・・・・・・
それはもう少し時間がかかりそうです。
この続きは、後日報告したいと思います。
秋晴れの高谷オカリナの里に着くと、オーナーが炭窯に火を入れて、
竹炭作りをしていました。

7:30頃に火入れをして、それからずっと火の番をしていたそうです。
13:00現在、煙突の中の温度は85℃、煙突からは勢いよく煙が出ています。

今回で通算3回目の炭焼きになりますが、前回と違う所は煙突の構造です。
これまで煙突の先端だった所に、ブリキの一斗缶が設置されて、
その脇から横に煙突が伸びています。

そして一斗缶の底の部分からはビニールホースが下がっていて、
その先には、ペットボトルが置いてあります。
ペットボトルにたまっているのは、竹酢液(ちくさくえき)です。
17:00現在で、煙突の温度は140℃まで上昇しました。

この時点で、約7リットルの竹酢液が採取出来ました。
オーナーの竹炭作りは、まだまだ続きます。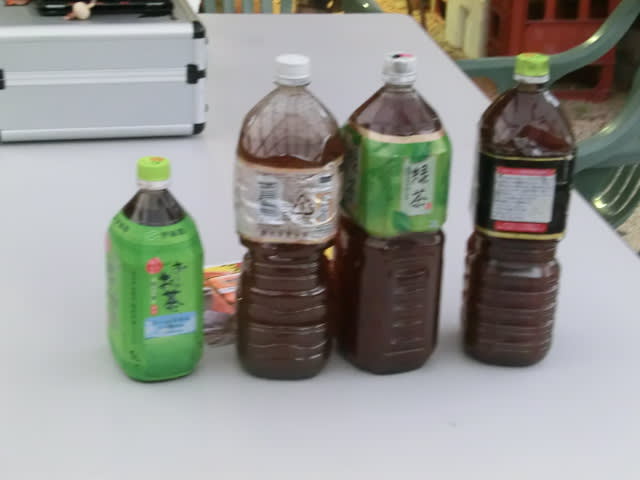

ちなみに、今回焼いた竹炭は、
11月1日に佐野市田沼グリーンスポーツセンターで開催される、
どまんなかフェスタ佐野の木工クラブのブースで、展示販売する予定です。
オーナーが炭窯から竹炭を取り出していました。
以前ブログで紹介しましたが、竹炭作り2度目の挑戦でした。

実は先週の定期演奏会の時に、火入れをしていたのです。
1度目は焼き方不足で上手くいきませんでしたが、
今回は、窯を改良して、煙突の出口の温度が200℃になるまで焼いたという事でした。
はたして出来栄えの方は・・・・・
手前側の竹炭は焼き過ぎでほとんど灰になっていましたが、
出口側の竹炭は結構良い感じで焼けていました。

焼いた竹の3分の1がNGと言う状態でした。
竹炭を取り出して行くうちに解かった事ですが、結構ひび割れが多い感じでした。

オーナーの見解だと、焼を辞めて温度を下げる段階での急激な温度変化が原因との事です。
取出した竹炭の何本かを、水で洗ったり、ぬれタオルで汚れを落としたりして、
東二さんのシャープナーを借りて適当な長さに切りテーブルに並べてみました。

しばらく眺めていると、ピシッピシッと音がして、何個かの竹炭にひび割れが入ってしまいました。

竹炭の用途が、消臭用・展示用・その他?とイマイチはっきり見えて来ませんが、
次回の竹炭作りに期待をしたいと思った次第であります。