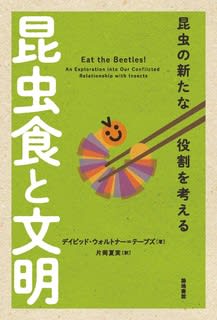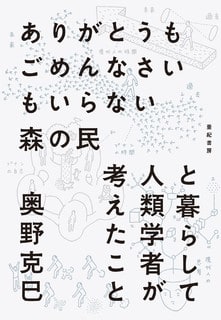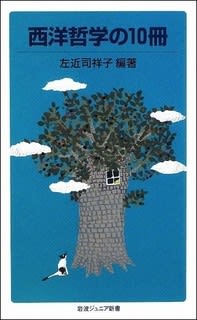佐藤健太郎 「世界史を変えた新素材」読了
「歴史を変えた“新”素材」というタイトルなのだが、読み始める前はこれからの歴史を変えるような新素材の紹介なのかと期待していたのだが、確かに「変えた」という過去形の物語であった。
しかしながら、読んでいると、きっとそうだったんだろうなと思うようなところはある。
ただ、素材が歴史を変えたというよりも素材を生産する技術が歴史を変えたというほうが正しいのではないだろうか。
鉄について興味深い書かれ方をしていて、「人間は鉄を利用して文明を発展させてきたというより鉄の性質に沿って文明が発展してきた。」そう言えるだろうけれどもそれは大量生産がもたらした変革ではなかっただろうか。
金や、陶器(陶器が素材と呼べるかどうかは別にして。)、絹といった素材は量産できない貴重さが人の欲望をかきたてて世界の情勢を変えたというところは納得できるが、これとて、輸出品として量産した国(日本もそうなのだろうが)が国力を蓄え、世界へのかかわりを変えてきたという意味でははやり素材もしかりだが、はやり技術が世界を変えてきたと僕は思うのだ。
しかしながら、釣りの世界ではやはり素材がその歴史を変えてきたと言ってもいいのではないかと思う。まあ、釣り師は使うだけでそれを作らないから技術革新は横に置いといてというだけかもしれないが・・。
僕の世代ではすでにナイロン糸は普通にあったのでそれは除くとしてこれが釣りを変えてきたというものを取り上げると、蛍光塗料、カーボンロッド、PEライン、GPS、GPSは素材ではないけれどもこの四つは確かに釣りの世界を劇的に変えたのではないだろうか。
蛍光塗料なんてとうの昔からあったじゃないかと思われるかもしれないが、ぼくが幼稚園くらいのころは、棒ウキはただ白いだけで、クジャクの羽を白く塗っただけのものだった。そういえば、もう、クジャクの羽も釣具屋で見なくなった。父親が使うチヌ釣り用の玉ウキも黒か茶色をしていた。髙松の長屋のようなところにあった釣具屋さんで父親はそれを買っていた。小学生になったころに、父親が蛍光塗料の玉ウキ(木製からセルロイド?に変わっていた。発泡ウキはもう少し後に出てくる。)を買ってきて、「よ~見えるど~。」と言っていた。
カーボンロッドはその細さと軽さに驚いた。高くてなかなか変えずに、グラスより少し軽い、ポリグラスの竿というのがあって父親は僕にそれを使わせてくれた。我が家にやってきた最初のカーボンロッドは、オリムピックの「世紀」というやつであったが今の竿から比べるとかなり持ち重りがしたけれどもそれでも軽かった。このブログを始めたころはまだ使っていたのではないだろうか。田辺の磯で、「にいちゃん、えらい古い竿、使ってんな~。」と言われた思い出がある。
PEラインとGPSは僕だけでなく船で釣りをする人はすべて、これがないともう、釣りにならないのではないだろうか。ウチにはまだ、びしま糸があるけれどもあれを加太で使えと言われると絶対無理だと思うのだ。父親が船を買った頃、これを使わされたけれども、まったく底が取れなかったことを覚えている。ただ、これを使った釣りはものすごく面白いらしいのでひそかにいつかは挑戦してみようかと思っているのである。
これからは情報の時代だということで、この本にも磁石がもたらした、紙から磁気媒体そしてシリコン化合物へという記録の変革について書かれている。情報も変革の波に乗って世の中を変えてゆくのだろうが、製品としての素材はどういうふうに世界を変えてゆくだろうか。
現代はまだ、鉄の時代だそうだ。鉄というのは地球の重さの30%を占めていて、地表付近で人間が利用できる範囲にも、クラーク数という値で4.7%、ランクで第4位だそうだ。そういうことで当分は鉄が中心の時代が続くはずだそうだ。その先には何があるのだろうか?
カーボンナノチューブという素材が実用化されると地球と宇宙を結ぶ軌道エレベーターができるそうだ。宇宙がグッと近くなる。コンピューターの心臓部はシリコンだから、鉄の次は炭素とケイ素の時代が待っているということか。
しかし、どうだろう、そんな時代を待たずに、世界は情報だけが残るだけになって、そういう、インフラを構成するような素材は必要なくなっていたりしないのだろうか。
美空ひばりをAIで復活させるというドキュメントが放送されていたけれども、それを見ていると、もう、過去も未来も現在もいっしょくたになって仮想の世界だけが残るのではないかと思えてきた。
と、いうことはケイ素だけの時代になるのだろうか。このケイ素は、原子の周期表では同じ列のひとつ下にあったということを初めて知った。(受験勉強では大体カルシウムくらいまでしか覚えないのだ。)ということは炭素とケイ素はよく似た性質であるということだ。知能の主役が炭素化合物(=人間)からケイ素化合物にとって代わるということはあながち空想ということでもないのかもしれない・・。知らんけど・・。
「歴史を変えた“新”素材」というタイトルなのだが、読み始める前はこれからの歴史を変えるような新素材の紹介なのかと期待していたのだが、確かに「変えた」という過去形の物語であった。
しかしながら、読んでいると、きっとそうだったんだろうなと思うようなところはある。
ただ、素材が歴史を変えたというよりも素材を生産する技術が歴史を変えたというほうが正しいのではないだろうか。
鉄について興味深い書かれ方をしていて、「人間は鉄を利用して文明を発展させてきたというより鉄の性質に沿って文明が発展してきた。」そう言えるだろうけれどもそれは大量生産がもたらした変革ではなかっただろうか。
金や、陶器(陶器が素材と呼べるかどうかは別にして。)、絹といった素材は量産できない貴重さが人の欲望をかきたてて世界の情勢を変えたというところは納得できるが、これとて、輸出品として量産した国(日本もそうなのだろうが)が国力を蓄え、世界へのかかわりを変えてきたという意味でははやり素材もしかりだが、はやり技術が世界を変えてきたと僕は思うのだ。
しかしながら、釣りの世界ではやはり素材がその歴史を変えてきたと言ってもいいのではないかと思う。まあ、釣り師は使うだけでそれを作らないから技術革新は横に置いといてというだけかもしれないが・・。
僕の世代ではすでにナイロン糸は普通にあったのでそれは除くとしてこれが釣りを変えてきたというものを取り上げると、蛍光塗料、カーボンロッド、PEライン、GPS、GPSは素材ではないけれどもこの四つは確かに釣りの世界を劇的に変えたのではないだろうか。
蛍光塗料なんてとうの昔からあったじゃないかと思われるかもしれないが、ぼくが幼稚園くらいのころは、棒ウキはただ白いだけで、クジャクの羽を白く塗っただけのものだった。そういえば、もう、クジャクの羽も釣具屋で見なくなった。父親が使うチヌ釣り用の玉ウキも黒か茶色をしていた。髙松の長屋のようなところにあった釣具屋さんで父親はそれを買っていた。小学生になったころに、父親が蛍光塗料の玉ウキ(木製からセルロイド?に変わっていた。発泡ウキはもう少し後に出てくる。)を買ってきて、「よ~見えるど~。」と言っていた。
カーボンロッドはその細さと軽さに驚いた。高くてなかなか変えずに、グラスより少し軽い、ポリグラスの竿というのがあって父親は僕にそれを使わせてくれた。我が家にやってきた最初のカーボンロッドは、オリムピックの「世紀」というやつであったが今の竿から比べるとかなり持ち重りがしたけれどもそれでも軽かった。このブログを始めたころはまだ使っていたのではないだろうか。田辺の磯で、「にいちゃん、えらい古い竿、使ってんな~。」と言われた思い出がある。
PEラインとGPSは僕だけでなく船で釣りをする人はすべて、これがないともう、釣りにならないのではないだろうか。ウチにはまだ、びしま糸があるけれどもあれを加太で使えと言われると絶対無理だと思うのだ。父親が船を買った頃、これを使わされたけれども、まったく底が取れなかったことを覚えている。ただ、これを使った釣りはものすごく面白いらしいのでひそかにいつかは挑戦してみようかと思っているのである。
これからは情報の時代だということで、この本にも磁石がもたらした、紙から磁気媒体そしてシリコン化合物へという記録の変革について書かれている。情報も変革の波に乗って世の中を変えてゆくのだろうが、製品としての素材はどういうふうに世界を変えてゆくだろうか。
現代はまだ、鉄の時代だそうだ。鉄というのは地球の重さの30%を占めていて、地表付近で人間が利用できる範囲にも、クラーク数という値で4.7%、ランクで第4位だそうだ。そういうことで当分は鉄が中心の時代が続くはずだそうだ。その先には何があるのだろうか?
カーボンナノチューブという素材が実用化されると地球と宇宙を結ぶ軌道エレベーターができるそうだ。宇宙がグッと近くなる。コンピューターの心臓部はシリコンだから、鉄の次は炭素とケイ素の時代が待っているということか。
しかし、どうだろう、そんな時代を待たずに、世界は情報だけが残るだけになって、そういう、インフラを構成するような素材は必要なくなっていたりしないのだろうか。
美空ひばりをAIで復活させるというドキュメントが放送されていたけれども、それを見ていると、もう、過去も未来も現在もいっしょくたになって仮想の世界だけが残るのではないかと思えてきた。
と、いうことはケイ素だけの時代になるのだろうか。このケイ素は、原子の周期表では同じ列のひとつ下にあったということを初めて知った。(受験勉強では大体カルシウムくらいまでしか覚えないのだ。)ということは炭素とケイ素はよく似た性質であるということだ。知能の主役が炭素化合物(=人間)からケイ素化合物にとって代わるということはあながち空想ということでもないのかもしれない・・。知らんけど・・。