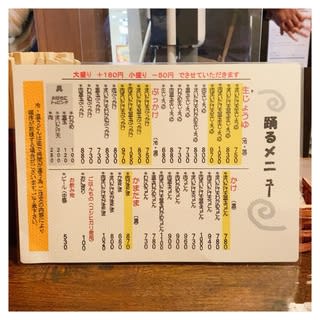OSAKA CLASSIC 2022・①~2022.09.04
今日は、「OSAKA CLASSIC 2022」のオープニングコンサートに行ってきました。会場は中央公会堂、二階席後列から二列目の天井桟敷のような席でしたが、行ってみると会場は小さくそしてオーケストラが客席に下りてきてるので、実質800人ぐらいで二階でも間近で楽員の動きがよく見えて最高。
久しぶりの大阪フィル。こんなに弦が艶やかとは、そして木管も魅力、でも一番は大植英次さんのエネルギシュな指揮。まさに音を楽しむ、魂を愉しむ、音が鳴り響く空間にわが心を泳がすこの時、とてもやすらぎを感じました。
ドボルザークの八番は私の好きな交響曲の一つ。思い出の演奏になりました。
そしてアンコール曲の常動曲を聴いて、次々替わるソリストに拍手を繰り返しているうちに、不覚にも涙が沸きだしそうになりました。
歳をとると、ちょっとしたことに感動しますな。でもクラシックもやはり良いもので、これからは機会見つけてコンサートにもいちょかみしたいですな。
OSAKA CLASSIC 2022・①
2022年9月4日(日)12:00開演
大阪市中央公会堂・大集会場
一、J.シュトラウスⅡ世・喜歌劇「こうもり」序曲
二、ドボルザーク・交響曲 第8番 ト長調 作品88
三、J.シュトラウスⅡ世・常動曲 op257
指揮:大植英次
管弦楽:大阪フィルハーモニー交響楽団
②、大阪市中央公会堂・大集会場
1918年、丁度100年前に建てられたレトロな公会堂。
③、大阪市中央公会堂・大集会場
④、OSAKA CLASSIC 2022~2022.09.04
⑤、ごまめのCD・J.シュトラウスⅡ世
この中で一番のお気に入りは、ウィーン・ヴィルトゥオーゼンの小編成のものです。各パートのメロディとハーモニーが良く際立って聞え、夜にもワルツという時に最高です。
⑥、ごまめのCD・ドボルザーク・交響曲 第8番 ト長調 作品88
私の数あるCDの中で、録音の面からも好きな5枚のうちに入るCANYONのこのCD。このチェコフィルの音色が最高、途中のティンパニーの音に感動しています。