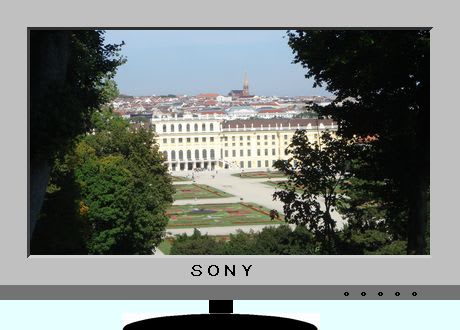◇吾妻渓谷の新緑を楽しむ
昔の職場の仲間7人で群馬県吾妻渓谷の小さい山「王城山」を登った。何しろ
昭和30年代に入って一緒に働いた仲間なので、みんな70歳台。若いころは甲斐
駒、白馬、北岳、谷川岳などそれなりにきつい山に登ったが、近年は歩く時間は
せいぜい1日4~5時間。降りたところに温泉があるコースを選定するのが多くな
った。
今回はJR吾妻線に乗って「長野原草津口」という駅で降りて「川湯温泉駅」方向
に少し戻ったところから登る「王城山」(1,122m)。登山口が既に海抜600m近い
ので、標高差は500mくらいだろう。
このあたりはダム紛争で有名な「八ツ場ダム」建設地点で、すでに堰堤本体工事
に先立ち、道路・鉄道の付け替え工事、水没集落の移転先地の建設工事などが
進んでいて、あちこちでブルの音などがする。

長野原草津口駅から見た吾妻川
王城神社の少し手前に登山口があり緩やかな山道をつづれ織りの登る。落ち
葉が10センチくらい積もっていて、まるで絨毯の上を歩いているようで歩きにく
い。
新緑が目にまぶしい。



王城山神社 登山口(宮原口)
ダムの付け替え道路、トンネルが見えてきた。湖水面はすぐそこまで来るわけ
だ。

付け替え道路
小さい山ではあるが、つづら折りの道でどんどん高度を上げる。道に獣の足
跡が残っている。イノシシか。



三合目 四合目 六合目
きつい傾斜の道を一気に登り切ると八合目(中棚尾根)。
右に行くと三角点(王城山古城)を通って王城山へ。ただし危険な尾根(ロープ
で転落防止をした崖)を通る。
左に行くと山腹を捲く形で王城山に行くがやはり転落防止用のロープが張って
ある。
どうせ危険なら三角点を通って行こうと右に道を取る。
蟻の戸渡りという表現がある。昔長野県戸隠山で右も左も絶壁、4~50センチ
の岩尾根を這うようにして登ったことがあるが、それに比べたら危険度は低いが
細かい砂状の道でかえって危険な気がする。



危険な尾根 崖 三角点から下界を
なんと三角点の祠のそばに鯉のぼりがたてられていた。
山の鞍部には多分山菜採りの基地・山小屋が。



鯉のぼり 山つつじ 山菜小屋
王城山山頂は登山口にあった王城山神社の奥の院ということであったが、なん
と小さな祠か。

道の途中で笹の花が咲いているのを見た。笹の花が咲くのは100年に一回。
その年は凶作になる。と聞いたことがある。はたして本当か。

笹の花
登りに2時間半、下りは1時間。大した山歩きではないが、昨年の山梨県西沢
渓谷歩きから1年ぶりの山登りで、みんなバテ気味。特に下りになると膝が笑っ
てしまい苦労していた。
時間は4時を過ぎた。王城神社まで宿の車に来てもらって「川原湯温泉」に向
かった。
(「川原湯温泉は次回へ」)
昔の職場の仲間7人で群馬県吾妻渓谷の小さい山「王城山」を登った。何しろ
昭和30年代に入って一緒に働いた仲間なので、みんな70歳台。若いころは甲斐
駒、白馬、北岳、谷川岳などそれなりにきつい山に登ったが、近年は歩く時間は
せいぜい1日4~5時間。降りたところに温泉があるコースを選定するのが多くな
った。
今回はJR吾妻線に乗って「長野原草津口」という駅で降りて「川湯温泉駅」方向
に少し戻ったところから登る「王城山」(1,122m)。登山口が既に海抜600m近い
ので、標高差は500mくらいだろう。
このあたりはダム紛争で有名な「八ツ場ダム」建設地点で、すでに堰堤本体工事
に先立ち、道路・鉄道の付け替え工事、水没集落の移転先地の建設工事などが
進んでいて、あちこちでブルの音などがする。

長野原草津口駅から見た吾妻川
王城神社の少し手前に登山口があり緩やかな山道をつづれ織りの登る。落ち
葉が10センチくらい積もっていて、まるで絨毯の上を歩いているようで歩きにく
い。
新緑が目にまぶしい。



王城山神社 登山口(宮原口)
ダムの付け替え道路、トンネルが見えてきた。湖水面はすぐそこまで来るわけ
だ。

付け替え道路
小さい山ではあるが、つづら折りの道でどんどん高度を上げる。道に獣の足
跡が残っている。イノシシか。



三合目 四合目 六合目
きつい傾斜の道を一気に登り切ると八合目(中棚尾根)。
右に行くと三角点(王城山古城)を通って王城山へ。ただし危険な尾根(ロープ
で転落防止をした崖)を通る。
左に行くと山腹を捲く形で王城山に行くがやはり転落防止用のロープが張って
ある。
どうせ危険なら三角点を通って行こうと右に道を取る。
蟻の戸渡りという表現がある。昔長野県戸隠山で右も左も絶壁、4~50センチ
の岩尾根を這うようにして登ったことがあるが、それに比べたら危険度は低いが
細かい砂状の道でかえって危険な気がする。



危険な尾根 崖 三角点から下界を
なんと三角点の祠のそばに鯉のぼりがたてられていた。
山の鞍部には多分山菜採りの基地・山小屋が。



鯉のぼり 山つつじ 山菜小屋
王城山山頂は登山口にあった王城山神社の奥の院ということであったが、なん
と小さな祠か。

道の途中で笹の花が咲いているのを見た。笹の花が咲くのは100年に一回。
その年は凶作になる。と聞いたことがある。はたして本当か。

笹の花
登りに2時間半、下りは1時間。大した山歩きではないが、昨年の山梨県西沢
渓谷歩きから1年ぶりの山登りで、みんなバテ気味。特に下りになると膝が笑っ
てしまい苦労していた。
時間は4時を過ぎた。王城神社まで宿の車に来てもらって「川原湯温泉」に向
かった。
(「川原湯温泉は次回へ」)