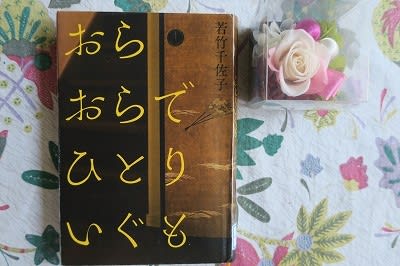◇『思い出の作家たち(谷崎・川端・三島・安部・司馬)』
著者:ドナルド・キーン 2019.2 新潮社 刊(新潮文庫)

2012年に日本国籍を取得したドナルドキーンと交流のあった作家5人について
著した文学論。
谷崎潤一郎と川端康成は年が離れすぎていて年少の崇拝者という立場であったし、
三島由紀夫と安部公房はまさに親友であり、司馬遼太郎は知遇を得たのは彼らより数
年遅く友人であるが、まぎれもなく恩人でもあると前書きにある。
このようにこの本はいわゆる作品評論や作家論ではなく、交友を通じてキーンの直
感で得られた彼らの性格や作品の生まれた背景を率直に記したエッセイである。
割腹自殺した三島から届いた手紙の暗示的な内容などが実に生々しい。
前書きで著者が述懐しているように、メモや日記をつける習慣がなかったキーンは
「もし日記が残っていたら自著『日本文学の歴史』(近代・現代篇)よりも彼らの知
られざる逸話を披露できたであろう」と言っている。
川端が受賞したノーベル文学賞は実は何かの行き違いがあって、実は『金閣寺』で
世界的に知られていた三島の筈であったとか。話にかなりの信頼度があり興味深い。
<谷崎潤一郎>
谷崎は『刺青』1911で文壇に登場した。『独探』1915に強くみられる西洋崇拝熱は、
『痴人の愛』1925をピークに、関東大震災で関西に住まいを移してからは日本の伝統
美に回帰し、『蓼食う虫』1929、『蘆刈』1931、『春琴抄』1933などを経て「源氏
物語」1939、『細雪』1942で完結する。谷崎は言う「私の近頃の願ひは、封建時代
の女性の日本の女性の心理を、近代的解釈を施すことなく、昔のままに再現して、しか
も近代人の感情と理解に訴へるように描き出すことである。」(昭和7年)
著者キーンは谷崎の作品の顕著な特徴は、書くことそのものへの専心にあるとする。
彼の小説は告白的でなく、いかなる哲学も主張せず、倫理的でも政治的でもないが、文
体の大家の手で豪華なほど精緻に作られているというのである。
<川端康成>
新感覚派である川端康成。『伊豆の踊り子』大正15年(1926)『雪国』昭和10年
(1935)『千羽鶴』昭和34年(1959)などの翻訳で知られ、1968年ノーベル文学賞
を受賞(1972)した。しかし三島由紀夫の自裁(昭和45年10月)の2年後、昭和47年
(1972)逗子の自宅で自殺した。
川端は、作家は政治や社会の参加者(アンガージュマン)たれと強いられることが何
より苦痛だったという(『文学的自叙伝』)。関東大震災や広島原爆被災に当たっても、
終始冷静な受け止め方をしたため世間的には冷淡であるなどと誤解を受けた。意外なこ
とに日本の伝統に深く浸りながら歴史小説は一つも書かなかった。
著者キーンは言う。「川端は西洋と東洋との間を行きつ戻りつしていた。『雪国』は
古典文学のどの作品からと特定するのはむつかしいが、全体的な印象としては平安文学
を思わせる。・・・『雪国』の終わり方は、日本のあらゆる伝統的な芸術作品と同様、
じらすように曖昧で、申し分なく美しい」
<三島由紀夫>
昭和45年(1970)の作家三島由紀夫の割腹という衝撃的な自決が世間を驚かせた。
著者は彼の死は、ある特種な美学にささげられた人生が必然的に行き着いた極点である
とみている。
彼が死の直前に著者にあてた手紙には「ずっと以前から文士としてではなく武士とし
て死にたいと思っていた」と書いてあったという。
彼が最期に当たり詠んだ辞世の句2首は無数の武士や軍人が呼んだ辞世の詩歌の言葉と
心象の寄せ集めである喝破する。
彼の作品の特徴は日本を初め西洋の古典を熟知し、古典の中に着想の示唆を求め、現
代の物語に翻案した。『潮騒』もギリシャの恋愛小説『ダフニスとクロエ』を下敷きに
しているという。
<安部公房>
著者キーンは、日本の作家の中でとりわけ親しかった安部公房を「風変わりで驚嘆に
値する友人であることを誇りに思う」という。
東京で生まれたものの、すぐに満州にわたり幼少期を過ごした安部は、日本への憧憬
と同時に日本からの疎外感を覚えて、土地への愛着を憎み世界主義者のような考えを終
生貫いた。戦後一時共産党に入党したのも社会主義思想的というよりも世界的連携に関
心を持ったのかもしれない。あらゆる形の国家主義と国家への帰属意識を嫌い、そのあ
げく『砂の女』をはじめ多くの小説・戯曲で、名前は物語を煩瑣にするからといって登
場人物も単に男、女と呼ぶのである。
後年戯曲と舞台表現に小説と同等の比重を置いた。
<司馬遼太郎>
著者キーンは、司馬の歴史小説は過去から復活させた実在の人間たちと彼らが生きた
時代のドラマに命を吹き込んだ。然し日本人が覚える感動は外国人には容易には理解で
きないため翻訳も少なく、ノーベル賞候補にもならないと解説する。 また司馬の作品
の翻訳を困難にしているのは彼の文体であり、彼の文体の特質は熟練の翻訳者をもって
しても大部分は伝達不可能であると言い切っている。
日本人の、彼の小説やエッセイに対する崇拝は、司馬その人への崇拝と深い係わりが
あるとする。彼は現代日本人が心に抱く英雄像そのものだったとする。
キーン自身、司馬は「日本とは、日本人とは」と問い続けた立派な英雄で、彼と親し
くなれたのは稀有な恩恵だったと最大限の賛辞を捧げている。
また彼の作品で誰で絵も気が付く特徴「脱線」についても好意的である。
「余談であるが…」と断りながら、彼がある出来事から何を連想したかを読者に伝える
ので、脱線は歓迎される。まさに司馬は自著の登場人物であったのである。
本書は200ページに満たない著作であるが、貴重な内容の本である。