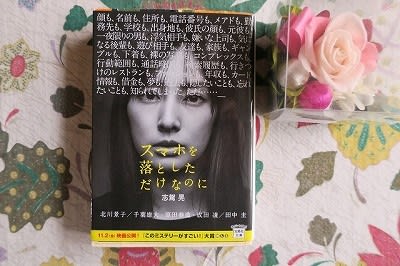◇ 『百年の旅』 著者:立野 正樹
2018.11 彩流社 刊
この著作は立野正樹氏の文芸評論である。
氏はこれまでもにいくつかの作品に関し、その舞台となった地を旅し、直接作品の背景
となった歴史的風物などに触れることによって、作者の真に意図するところを肌でくみ取
ろうとする姿勢をとって来たように思う。 著者は、第一次世界大戦と第二次世界大戦の
狭間の20年間の小説は、多かれ少なかれ戦争の「回想」であり、経験知と喪失感が分かち
がたく結びついたまま反映させられている。とする(本文19p)。
この度の『百年の旅』は、主として『武器よさらば』の舞台となったスイスとイタリア
の旅を通じて、「作品外の現実」ないし伝記的事実としてのイタリア戦線を巡り、作者が
考察した戦争の幻滅感と、戦場での恋愛という二つの経験的要素も視野に置いて著した評
論である。
著者は現在の激戦地の風景を見ながら作者が経験し描いた光景を脳裏に描き、幻影を見
る(p71pなど)。
第一部は ヘミングウェイについては「カポレットからの退却」の舞台イゾンツォ川を。
第二部は ラドヤード・キプリングの息子ジョン・キプリングの戦死した(と信じられ
ている)北フランスの「フランドル」を。
第三部は カロッサの『ルーマニア日記』、『処刑の森』を取り上げ、作品の舞台とな
ったギメシュ渓谷を訪れた。
振り返れば、ピエール・ルメートルの『天国でまた会おう』も、第一次世界大戦後、第
二次世界大戦との狭間が単に「長い週末」(E・S・フォスター)にあって、当時のヨーロ
ッパを覆った失望と不安感を題材に取り上げた作品といえるだろう。戦闘で重度の負傷を
追った兵士の生き様をドラマチックに描くことによって、戦死した兵士を英雄としてもて
はやしながら、生きて帰った復員兵には冷たい戦後のフランス社会に対し痛烈な一矢を報
いた作品なのである。作者ルメートルは第二次大戦後の生まれであり、戦闘場面は多分想
像力の産物ではあろうが、戦争への幻滅感に共通性がある。
(以上この項終わり)