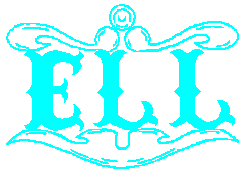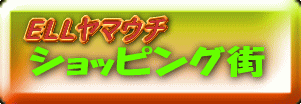日々のパソコン案内板
【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)
【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】
【PDFの簡単セキュリティ】
【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】
【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】
【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】
【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】
【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】
【手書きで書くように分数表記する方法】
【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】
【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】
【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】
高速道路が建設される時・・・
将来のおいて、償還できたときには通行料金を無料にするという話でしたが、
ここにきて、この話を見直して、利用者は払い続けていかなくてはならなくなりそうです。
そりゃ、道路の老朽化の維持管理というものが必要なのは理解できます・・・がっ、
それではお聞きしたい・・・
計画した段階において、メンテナンスがいずれ必要になることを
誰も気が付かなかったということでしょうか?
気が付いていても、「まあ、先の話やから、今は言う必要なない」
「国民に向けて、将来無料にするんや!」などとええかっこだけで計画されてんでしょうか?
同じ日本人として、日本人の一番嫌いなところは・・・
このように結論を延ばし延ばしにしてしまう所だと思います。
兎に角、今後において、如何していくのが良いのか、
慎重に話し合い検討して頂きたいと思いますね。
今朝は、国交省の基本方針についての記事を転載してみようと思います。
~以下、1月28日読売新聞朝刊より抜粋~
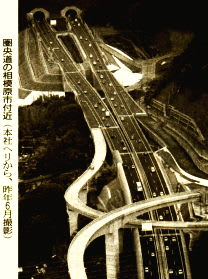

しかし、有識者会議は、人口減に加え、厳しい財政事情で公共事業費の大きな伸びが期待できない中で道路網を維持するには、既存の道路をより効率的に使うことを優先する必要があると考えた。
道路の渋滞を減らすことは、日本経済の活力を高めるためにも重要だ。国交省の調べでは、1人当たりの年間約100時間の乗車時間のうち、渋滞によって余計にかかる時間が約40時間に上っているとの試算もある。
このため、有識者会議は改革の目玉として、首都圏の高速道路の料金制度の見直しを打ち出した。先ず2016年度から距離に応じた料金に統一する。その上で20年をめどに、混雑に応じてルートごとに料金に差をつける制度に移行する。都心の道路を高く、比較的すいている圏央道などを安くして、利用者が郊外の道路を使うことを促す。。
国交省は、高速道路の利用をより効率よくするために、今後普及させる予定の「高度道路交通システム」を活用する考えだ。
自動料金収受システム(ETC)搭載車と情報をやり取りできるようにし、事故や渋滞などの情報をドライバーに送って迂回を促したり、渋滞が起きやすい場所や時間を細かく把握し、料金制度に反映させたりすることを想定している。
将来的にはETCの義務化も検討する。現金払いを維持するには、人件費などでETC車の約5倍の費用が必要とされ、高速道路の料金を下げる効果も期待できるからだ。
さらに、国道などの一般道で、大型車から料金を徴収することも検討する。
現在は一般道の維持管理に税金を使っているが、大型車の通行は道路の老朽化につながりやすく、通行料金として負担してもらう必要があるとの考えだ。
ただ、利用者の負担増につながるだけに、慎重な検討が必要だ。利用者のメリットと費用負担のバランスをどうとっていくかが課題となる。
将来のおいて、償還できたときには通行料金を無料にするという話でしたが、
ここにきて、この話を見直して、利用者は払い続けていかなくてはならなくなりそうです。
そりゃ、道路の老朽化の維持管理というものが必要なのは理解できます・・・がっ、
それではお聞きしたい・・・
計画した段階において、メンテナンスがいずれ必要になることを
誰も気が付かなかったということでしょうか?
気が付いていても、「まあ、先の話やから、今は言う必要なない」
「国民に向けて、将来無料にするんや!」などとええかっこだけで計画されてんでしょうか?
同じ日本人として、日本人の一番嫌いなところは・・・
このように結論を延ばし延ばしにしてしまう所だと思います。
兎に角、今後において、如何していくのが良いのか、
慎重に話し合い検討して頂きたいと思いますね。
今朝は、国交省の基本方針についての記事を転載してみようと思います。
~以下、1月28日読売新聞朝刊より抜粋~
渋滞緩和へ高速料統一
道路 効率利用に転換
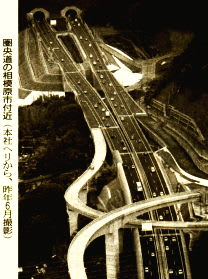
国交省基本方針
ETC義務化検討
国土交通省の有識者会議が、首都圏の高速道路の料金体系を抜本的に見直す方針を打ち出した背景には、人口減や道路の老朽化が進む中、新しく道路を造るよりも、既存の道路をより効率良く利用できるようにすることが重要だとの判断がある。料金の見直しを通じて都心の渋滞を緩和させ、経済活動をしやすくして東京の国際競争力の強化につなげる狙いもある。
(山本夕記子)

■ 年間40時間
戦後の道路行政は、道路を増やすことで全国各地の利便性を高めてきた。しかし、有識者会議は、人口減に加え、厳しい財政事情で公共事業費の大きな伸びが期待できない中で道路網を維持するには、既存の道路をより効率的に使うことを優先する必要があると考えた。
道路の渋滞を減らすことは、日本経済の活力を高めるためにも重要だ。国交省の調べでは、1人当たりの年間約100時間の乗車時間のうち、渋滞によって余計にかかる時間が約40時間に上っているとの試算もある。
このため、有識者会議は改革の目玉として、首都圏の高速道路の料金制度の見直しを打ち出した。先ず2016年度から距離に応じた料金に統一する。その上で20年をめどに、混雑に応じてルートごとに料金に差をつける制度に移行する。都心の道路を高く、比較的すいている圏央道などを安くして、利用者が郊外の道路を使うことを促す。。
国交省は、高速道路の利用をより効率よくするために、今後普及させる予定の「高度道路交通システム」を活用する考えだ。
自動料金収受システム(ETC)搭載車と情報をやり取りできるようにし、事故や渋滞などの情報をドライバーに送って迂回を促したり、渋滞が起きやすい場所や時間を細かく把握し、料金制度に反映させたりすることを想定している。
将来的にはETCの義務化も検討する。現金払いを維持するには、人件費などでETC車の約5倍の費用が必要とされ、高速道路の料金を下げる効果も期待できるからだ。
■ 償還主義
中長期的な課題は、高速道路の料金を建設費の返済が終わったら無料にする「償還主義」の見直しだ。利用者が料金を払い続けるようにし、老朽化が進む道路の維持管理費を確保するためだ。さらに、国道などの一般道で、大型車から料金を徴収することも検討する。
現在は一般道の維持管理に税金を使っているが、大型車の通行は道路の老朽化につながりやすく、通行料金として負担してもらう必要があるとの考えだ。
ただ、利用者の負担増につながるだけに、慎重な検討が必要だ。利用者のメリットと費用負担のバランスをどうとっていくかが課題となる。