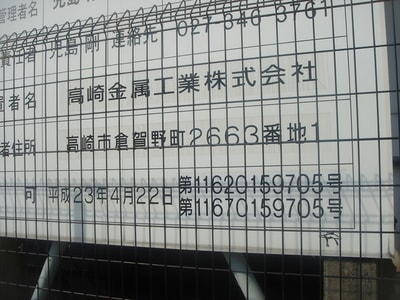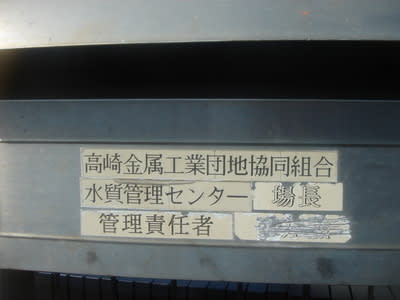■岩野谷地区で㈱環境資源が進めている大規模な廃棄物最終処分場設置計画について、これを阻止すべく、岩野谷区長会主催による「新山地区産業廃棄物処分場建設計画についての意見交換会」が5月26日(土)午後7時から、岩野谷公民館で開催されました。地区内の団体、個人など合計50名ほどの代表者や住民が集まり、2時間に亘り熱心なトークが交わされました。

↑熱心な討議を重ねた意見交換会。通常は平日でも週末でも午後7時からの会合がある場合には公民館長や職員は不在なのが通常だが、なぜか今回は市長への忠誠心が人一倍の公民館長が事務室の明かりを灯けて公民館の事務所にたむろしていた。岡田市長に会合の出席者の情報を伝達して、ゴマスリをするつもりらしい。↑
地元市議の司会・進行で開催された意見交換会には、各地区の区長ら8名をはじめ、市議、県議、大谷地区の処分場反対有志、水利組合幹部、自然保護団体関係者、子ども会関係者、民生委員、その他多くの住民が意見を述べました。
冒頭に地元区長会の代表区長から挨拶がありました。依田代表区長からは、「3月10日の出前講座以降、区長会としていろいろ活動をしてきた。一昨日、岡田市長に面談し、この件で、意見書を出した。市長から文書をもらい、その返事もした。その後、出前講座に出ていただいた、県議や市議らにも本件に関して回答要請をだした。その回答はまだ来ていないので、5月8日に再度参集をお願いした。岩井県議は都合で来られなかったが、12名の議員がある真理約2時間討議した。その結果、共通の認識が一致したということで、市長に意見を具申した。その結果は、さびしいことに、市長は過去の細かいことについての言及しかなく、最後に市長に“では今後どうすればよいのか”と聞いたところ“見識のある区長さんたちだから、よく考えて行動してください。ただし足元をよく見てね”と言われた。“では、今後どうすべきか”ときくと、市長は“県の庭で大会を開くくらいの気持ちだ”と言われた。約1時間弱、市長室で話した。その時感じたのは、富岡のアスベスト処分場計画では環境庁まで大量の署名を提出するというし、富岡市長は“皆さんが投票してくれたので私は皆さんと一緒です”という温かい気持ちを示している。ところが安中市長は“見識のある区長さんだから”という発言だった。20年5月2日付で安中市長は反対意見書を出しているが、たった一行だけ。市長に関係資料を持参したが、見もせず、置いていけとも言わず、本当に地元出身の市長なのかと、非常にさびしい気持がした。しかし、これとは別に、この処分場計画にはきちんと対処したい。今日、大澤知事が“水は大切だ”と新聞で主張している。これからは水問題だ。利根川流域でも会社がちょっと汚染物質を出しただけで、あのとおり。ここでも要らぬ業者が来て、水を止めてしまったら大変なことになる。水のことはなんとかしなければならない。この一点で行動している。至らぬところが多々あるかもしれないが、情報もどんどん寄せてもらい、我々のことも聞いてもらいたい。こころは一致なので本日も皆さんの意見を出していただきたい」と挨拶がありました。
続いて、3月10日の県の出前講座以降の動きについて、茂木県議から報告がありました。同県議からは「100名以上が集まった3月10日の集会が大きなポイント。これをきっかけに大谷地区に9ヘクタールを超える大規模サンパイ計画があることを知った。この計画は平成18年7月に事前虚偽書が県に出された。それから6年が経過したが、事前協議が行われてきた。地元の安中市にも情報が県からきて、県と市と事業者の間で手続が進められた。業者は設置許可申請を県に出す。本来は国が許認可をするが法律により県が許認可をする。それが事前協議。安中市も平成18年7月に連絡を受けているので計画内容は知っている。県と市で意見書のやり取りが何回も行われている。安中市の意見は、本来は地元住民を代表して、地元意見をまとめて出すというのが基本的な意見書だが、安中市の場合は庁内協議で廃棄物処分場は新規を認めないので市は反対、というたった一行の意見書を県に何度も出してきたという経緯がある。地元住民がどのような意見を持っているのか、どういう不安を持っているのかという情報は県の方に伝わっていなかったのが実情。その後合意書の取得手続きがあったが、平成22年6月に、地元の高橋区長の時に反対署名1915名を集め、知事室で副知事が受理した。そのとき、県は初めて地元で反対があるのかと知った。それ以降、県と皆さんの間の情報共有に尽くしてきた。その結果、ようやく県も情報を出すようになって来た。事前協議が終了したら今度は設置許可の本申請に入る。こうなるとトントンと進んで着工に至ってしまう。今年になり事前協議が最終段階にあるということを今年に入って県から言われた。区長に相談してどうしようかと話した。それまでは市長が反対しているし(大丈夫だろう)、ということで情報錯そうもあったが、1月末に県から“事前協議も最終段階ですよ。反対署名があったのでお知らせする”ということだった。なんとか住民の皆さんに知らせる必要があるため、出前講座の開催を3月10日に企画していただいた。私も皆さんの声を聞いて、しっかりと県に対して届けていきたい」と語りました。
次に3月10日以降、各団体の行動について参加者の共通認識にするため、まず岩野谷区長会の取り組みについて、代表区長から説明がありました。「区長会としては、3月10日は少し早いと思ったが実態を知って、これは大変だと思った。高橋前区長会長のときに署名活動を提案したのも私だったが、市長が反対しているからということで動きが緩んだ。その後、いろいろ動きがありこれは大変だとして、書類上は12月23日で終了し、あとは、いろいろ法律関係で、水利権について白紙で調べるだけという状況だった。おりから郷原のサンパイ中間処理施設問題もあり、その後、出前講座を受けてすぐ市長に意見書を提出した。そこに反対という文章があるのでそれを読んで市長に出した。その後市長から区長会に返事が来た。その後、個人的に市長に意見した。このような県への意見書ではだめですよと。市長は市子連総会時に、私に“あれじゃ、賛成と同じだ”などと発言があり驚いたこともある。県議や市議とも相談し、討議を重ね、いずれにしても今後よい成果を聞かせてもらいたい為に、住民の熱い熱意を背景にいろいろ区長会で話をしつつ現在に至っている。本日は全体の意見交換で要約を聞きつつ区長会としても詰めていきたいと思う」と述べました。
続いて前区長会長で、岩野谷みんなの命と自然を守る会の会長から挨拶がありました。「私がやった以降はいま依田会長から説明があったが、それ以前について説明したい。平成21年5月19日に県に行って大谷のサンパイ場計画の事情を聞きに行った。その後同年12月9日に高崎市労使会館でみたけ町の元町長の後援会があり、講演後私から岩野谷地区の処分場問題について現況発表をした。その後、署名運動を始めることになり、平成22年2月に着手した。6月7日に締め切りだったが、1915名の反対署名を提出できた。当時の地元の成人人口の実に72.5%に上った。知事が不在だったため、稲山副知事に渡した。新聞社5社、群馬TVが取材に来た。同年6月8日に報道された。同12月21日に学習会を開催し、集まったカンパで建設反対の旗を設置することで決定。平成23年に2回に分けて旗を立て、平成24年1月22日には隣の高崎市吉井町奥平地区の観音山雁行川流域について学習会に参加し、大谷地区のサンパイ問題について現状発表を行った」と説明。
その後、大谷地区の水利組合の幹部から報告がありました。副会長からは「新山地区に管理型の13品目が捨てられる最終処分場計画を聞いて驚いた。大谷の水利組合としては、事前協議規定の第22条ロとして放流地点の下流概ね500m以内の農業者等の利用者、または当該事業者の団体の長の合意が必要だということが求められている。これを調べたところ、業者は全員から合意をもらっていると言うが、実際にはまだ合意していない人がいることがわかり、業者のいうことは事実誤認。または当該団体の長の印鑑だが、平成21年1月13日に、当時の組合長が環境資源と、組合員の同意を得ずに同意書を作成して、そしてその合意書を既に県に提出していたことが判明。そのため、今年の2月21日、この合意書を無効とする組合員、全会員43名のうち39名の署名捺印入り要請書を県庁で、茂木県議の紹介で今井前組合長から、山口環境森林部長に手渡し、水利組合の合意書の無効化をお願いした。そして3月10日の県の出前講座に至った。その後、今月の5月6日、この水利組合の臨時総会を上組公会堂で開催し、そこで元組合長が環境資源と交わした合意書の撤回を環境資源に申し入れることになった。そして、元組合長も合意撤回を申し入れてくれということで、元組合長が環境資源に出向いたところ、“これまで使った費用、3億5千万円を支払えば撤回してやる”と言われて帰って来た。それで5月中旬、水利権の合意書の撤回を環境資源に申し入れるに当たり、組合員43名中39名の署名捺印をもらい、5月21日(月)、環境資源の処分場の反対陳情書を、高橋市議の紹介で、我々組合長はじめ8名で市役所に出向き、現組合長から奥原市議会議長へ反対陳情書を手渡した。そして、同じ日に、地元岩井の碓氷川の橋のところにある環境資源の事務所に8名が乗り込み、同社の鬼形社長に水利権の合意撤回の文書を手渡そうとしてが受け取りを拒否された。そのため、その内容を口頭で説明してきた。文書は受け取ってもらえなかった。そのような実情で、今後、なんらかの手段を尽くして、撤回文書を渡すことを考えている最中である」と発表。
司会の市議によれば、6月5日から市議会が始まるのでその中で審議されることになっているとのことです。
その後、大谷の長坂地区の有志グループとして行動を起こしている代表者から「3月10日の県の出前講座に参加し、岩野谷地区の大勢の人たちがサンパイ建設計画に反対しているという事実を知り、建設予定地に済む我々が行動を起こすべきだということに気付いた。まずは3月10日の出前講座の内容について地元住民に知ってもらうことからスタートした。そこで、住民は“こんなに大規模なものとは知らなかった。最初の説明会とは全く違う。反対するにはどうすればよいか”と多くの意見が出た。これまで地元ではほかにの何か所か計画が出ていて、どの計画に判をおしたか、また親が押したようだが今は世代交代していて反対の立場で、昔の判で押されて今の世代は反対ということ。それで反対するにはどうすればよいか、といろいろ意見が出た。今まで当地区はサンパイに狙われやすいところだった。これからは変えていきたい。そして今までのことは全て白紙にして、これからのことを考えようと言うことになった。まずは賛成か反対かを考えた。協議の結果、反対して同意撤回書を皆に書いてもらった。3月19日に県議、市議が同行して、40名の同意撤回書を県に届けた。地元も行動しているということを皆さんにも知ってもらいたいと思い意見を述べさせていただいた。よろしくお願いしたい」と力強い言葉がありました。
続いて岩野谷の水と緑を守る会の会長で、県の市民オンブズマンの当会代表から発言があった。「このような場で、サンパイ場の件でコメントさせていただけるということについて感謝申し上げる。岩野谷には既にサイボウ環境の処分場がある。これは平成3年から安定5品目でサンパイ計画だったが、平成5年から一般廃棄物処分場としてスタートした。今日は同志も見えているが、たった3名でこの問題について取り組んできた。10年以上前には地区に何度もチラシを配布したこともあるが、覚えていない人もいるかもしれない。なぜこの問題にとりくんだかというと、隣の上奥平地区の関係者にも聞いたが、“ひとつできると、つるべ式にどんどんできてしまう。だから最初の計画は絶対に阻止する”という気持ちで取り組んできた。平成7年のタゴ事件発生のころに事前協議にはいり、平成11年頃事前協議が終わり、その後、(行政相手に事業の差止めのため)徹底的に裁判を起こし、計15件ほど最高裁までたたかったが、全て敗訴した。それと公文書偽造作成行使についても県警、検察に告発したが、結局司直のゆがんだ判断に阻まれ、これもカラ振りに終わった。そして平成19年4月にサイボウがご存じの通り営業を開始した。こちらは一般廃棄物という触れ込みの処分場だが、しかし入れているものについて誰も知らないのでサンパイでもイッパイでもわけのわからない状態にある。今回、今の話だと、平成18年7月に事前協議が出たという。この時期はサイボウの我々の最後の裁判の決着と符合する。業者はこのサイボウの経緯をみて、事前協議を出した。それから、私のブログにも詳述しているが、今年の4月14日、私は長坂の公民館に行ってどんな連中がこの計画を推進しているのか、顔を出した。見覚えのある顔にびっくりした。サイボウの処分場で暗躍した人物がそこにいたからだ。サイボウの計画で、中核的にありとあらゆる手段を講じて推進した御仁。詳しくは私のブログを見てほしい。結果だけいうと、国も県も市も、処分場を作らせたがっている。この話は、この中の参加者の誰かが当然このあと業者に通報するだろうが、“処分場の手続は前例主義だから、それに則ってやれば県は絶対にノーと言えない”と私の前でその人物は言った。先日、県に行った時、サイボウの残土の件で報告したが、その際、2番目のサンパイ場、これはイッパイとサンパイが一緒になっている。行ってみればサイボウと同じやり方。その時、県の担当者は、私の前でこういった。“行政手続法がある。外形的に書類が整っていれば、決められた期限内に通さざるを得ない”と言っている。我々は3人で平成2年から平成19年まで頑張った。同志もここに居る。しかし、2番目の計画は村中かかってもなかなか止められない。最初止めるにはたった3名で14年要した。手続の時間を伸ばせた。しかし、一旦最初の(処分場)が、できるめどが立てば、業者が全部見ているから、つるべ式に、芋づる式に次から次に出てくるわけだ。今回の皆さまの努力には本当に関心する。これがなぜ最初の計画の時に、このような行動がとれなかったのか、つくづく残念でならない。しかし、“ればたら”の話をしても仕方がない。当会はこれまで培った経験知見を惜しみなく皆さんに伝えるつもりなのでよろしく」と述べた。
その後、参加団体の紹介として、岩野谷の環自連の会長が「先程大谷の人が言った通り親のときは賛成で、現在の世代が反対というのは事実だ。ある委員がいうには、“もう遅いですよ”と言われたことがある。前もみないろいろ反対したがだめだった。いま、小川さんがやっていた平成7、8年ごろがその時だったかなと思う。それでも、今の子どもがそういう考えなので、変えていければと思うので協力したい」と挨拶した。
そのあと、岩子連会長が「私もできれば将来の子どもたちのことを考えており、未来を考えればぜひ反対していただきたい。そのためには岩子連としても最大限協力したい」と述べた。
続いて岩野谷の民生委員会長が「私も反対署名をした。こういう場は初めてだが、乳幼児委託訪問から高齢者までネットワークがある。この経験を生かして、もしお手伝いできるようであれば協力させていただきたい」と挨拶。
次に、岩野谷の青少推の会長で、岩野谷のみんなの命と自然を守る会の事務局担当から「やはり岩野谷の自然をきちんと守り子どもたちがその中で遊べる環境作りが我々の責任だと思う。頑張ってゆくのでよろしく」と挨拶。
岩井地区の水利組合の清水代表が参加予定だったが体調不良のため、「処分場計画に反対の立場なので、みなさんによろしく」とのメッセージが紹介されました。
次に、岩野谷地区の農業委員から「岩井川流域の農業を守るためには、いろいろな負担材料のあるサンパイ場には絶対反対。農業委員会としても反対の立場なので皆さんによろしく」とのメッセージが寄せられました。
この後、参加者の間で熱心な討議が続けられた。今後、どう行動して、住民の意思を貫いていくかということが重要なので、初めにこの点について協議を行いました。
区長会長からは、「最も大事なのは水。サイボウの件もあるが、どこまで踏ん張れるか。自分一人ではどうにもならないが、踏ん張れるだけは踏ん張る。大谷の水の源に計画されたサンパイ場から出る汚染水は、大谷をはじめ岩井の田んぼにも影響がでる。なんとしても水を守るため、これを阻止したい。連携し、いいアイデアを出してほしい。意見書などを出したい。それには市議、県議に役所に日参いただくことになろう。まず水の問題。皆さんの智恵を借りたい」と発言がありました。
区長会長の発言の中の「意見書」について、県議から「事前協議は県と業者と市にも意見を聞きながら進められる。この中に、市が住民の意見をまとめて、生活環境の保全上、どのような不安や疑問や心配があるかということを意見として出せる。市が住民の意見をまとめて出すのが意見書。これまで市が県に出した意見書はたった1行しかない。県に確認したところ、市が“反対”というだけの意見ではなく、生活環境面で住民の意見を市が吸い上げて届けるのが、市が出せる意見書なので、それを出すように県から働きかけをしている。しかし市からは、同じように1行しか意見を出していないという経過がある。3月10日の説明会の後、その時市長から説明会のやり取りのなかで“どういうことなんだ?”という質問が来たということで、その打合せを5月8日に、市長に返事しなければいけないということで、参加した市会議員4名と県議2名(岩井県議は欠席したが事前コメントあり)で打ち合わせたが、最後に住民の意見が出せないだろうかという意見が出た。それを代表区長から県に確認してほしいと言われて、確認したところ、事前協議は最終段階だが、住民の意見を受け入れるので意見があれば出してほしいということを区長に伝えてほしい、という経緯がある。これが、本日の協議の背景にあると思う。これから住民の意見という形で、県は事前協議の中で、これを受けると言っている。ぜひ住民の意見を県に出してもらいたいと思う。同時に、意見書は事前協議の中で出せる。それに何らかの対応を採るということで一つのステップとなるため、この意見への対応ができれば事前協議が終わるということにもなる。岩野谷の住民の意見を出すことは必要。ただし、それにより、手続の過程が進むという可能性もあり、両刃の剣とも言えるため、慎重に対応したい」と補足説明がありました。
その後、この件で討議が続きましたが、結局、意見書を出すことが参加者の総意として確認されました。意見書を出せる範囲について、参加者から質問が出ました。これについて、生活環境の影響する範囲ということで、地域でいうと、岩野谷地区ということで了解されました。
また、安中市が群馬県からの要請に対して、出してきた意見の実態について報告がありました。それによると、条例第10条の審査項目として、県の土地利用対策会議(庁内38課で構成)で討議するために必要な次の項目が必要だと言うことです。
①災害発生のおそれはないか?
②土地の利用状況上、開発は可能か?
③公共施設・公益的施設の整備の見直しはあるか?
④用水確保の見通しはあるか?
⑤公害は防止できるか?
⑥地域への貢献度はどうか?
⑦開発事業者の資力、信用は担保されているか?
⑧保護すべき文化財は存在しないか?
これらの項目について、本来、安中市は現地を調査し、地元住民の意見をまとめ、県に対して意見を言うことができるわけです。しかし、このような見地からの意見を県は安中市へ求めたが回答がなかったというから呆れてしまいます。
実際に、安中市の岡田市長が県に上げた意見書は延べ5回に亘りますが、いずれも「市の基本方針から、最終処分場の構想は認めることができない」というたった1行の簡単な内容だけでした。これでは、県も安中市の住民の意見が分からない、と言い張れるわけです。一方、業者側はほくそ笑んでいることでしょう。
■一方、大規模土地開発事業の規制等に関する条例による事前協議では、次の報告が県議からありました。それによると、「事業者が廃棄物処理規定による地検者等の合意を取得したことから、平成21年12月に事前協議を受理して手続が開始された。その後役2年間に亘り、土地利用対策会議(庁内38課で構成)で審査し、計4階の指摘事項の通知とそれに対する事業者からの回答書の提出が行われた。また、安中市長をはじめとする関係市町村に意見照会をしたが、安中市長は当初から一貫して「市の基本方針から最終処分場の構想は認めることができない」という意見を出している。この安中市長の意見は、条例に規定する項目に関しての意見ではないため、平成22年9月、安中市長に対して県から再度意見照会を行ったが、安中市長の意見は“事業そのもの”に反対ということだけで、条例の審査項目に対して回答していなかった。現在、土地量対策会議からの指摘事項もなくなり、大規模土地開発事業審査会に諮問できる段階となっている」ということです。
この件については、別紙の参考資料にさらに詳しい経緯が示してあります。
その他、マスコミの活用、新山の溜池及びその周辺に本格的な看板を設置したり、岩井川沿いで自然環境のよさをアピールするイベントの開催、テレビ局への取材申し入れなど、さまざまな提案や提言が出されました。
また、大人だけではなく、今後影響をずっと受けることにもなりかねない子どもたちからの素直な意見書も出せるのかという意見があり、これも採択されました。
そして、まずは区長会で意見書を出すと共に、今日の参加者した方々はもとより、参加できなかった住民の意見も区長会がとりまとめて、行政に届けることを確認し、最後に、参加者一同で、一致協力し、団結して、地域に降りかかった未曽有の危機に対して断固として排除してゆくように、区長会を中心に対応してゆくことが決議されました。
【ひらく会・情報部】

↑熱心な討議を重ねた意見交換会。通常は平日でも週末でも午後7時からの会合がある場合には公民館長や職員は不在なのが通常だが、なぜか今回は市長への忠誠心が人一倍の公民館長が事務室の明かりを灯けて公民館の事務所にたむろしていた。岡田市長に会合の出席者の情報を伝達して、ゴマスリをするつもりらしい。↑
地元市議の司会・進行で開催された意見交換会には、各地区の区長ら8名をはじめ、市議、県議、大谷地区の処分場反対有志、水利組合幹部、自然保護団体関係者、子ども会関係者、民生委員、その他多くの住民が意見を述べました。
冒頭に地元区長会の代表区長から挨拶がありました。依田代表区長からは、「3月10日の出前講座以降、区長会としていろいろ活動をしてきた。一昨日、岡田市長に面談し、この件で、意見書を出した。市長から文書をもらい、その返事もした。その後、出前講座に出ていただいた、県議や市議らにも本件に関して回答要請をだした。その回答はまだ来ていないので、5月8日に再度参集をお願いした。岩井県議は都合で来られなかったが、12名の議員がある真理約2時間討議した。その結果、共通の認識が一致したということで、市長に意見を具申した。その結果は、さびしいことに、市長は過去の細かいことについての言及しかなく、最後に市長に“では今後どうすればよいのか”と聞いたところ“見識のある区長さんたちだから、よく考えて行動してください。ただし足元をよく見てね”と言われた。“では、今後どうすべきか”ときくと、市長は“県の庭で大会を開くくらいの気持ちだ”と言われた。約1時間弱、市長室で話した。その時感じたのは、富岡のアスベスト処分場計画では環境庁まで大量の署名を提出するというし、富岡市長は“皆さんが投票してくれたので私は皆さんと一緒です”という温かい気持ちを示している。ところが安中市長は“見識のある区長さんだから”という発言だった。20年5月2日付で安中市長は反対意見書を出しているが、たった一行だけ。市長に関係資料を持参したが、見もせず、置いていけとも言わず、本当に地元出身の市長なのかと、非常にさびしい気持がした。しかし、これとは別に、この処分場計画にはきちんと対処したい。今日、大澤知事が“水は大切だ”と新聞で主張している。これからは水問題だ。利根川流域でも会社がちょっと汚染物質を出しただけで、あのとおり。ここでも要らぬ業者が来て、水を止めてしまったら大変なことになる。水のことはなんとかしなければならない。この一点で行動している。至らぬところが多々あるかもしれないが、情報もどんどん寄せてもらい、我々のことも聞いてもらいたい。こころは一致なので本日も皆さんの意見を出していただきたい」と挨拶がありました。
続いて、3月10日の県の出前講座以降の動きについて、茂木県議から報告がありました。同県議からは「100名以上が集まった3月10日の集会が大きなポイント。これをきっかけに大谷地区に9ヘクタールを超える大規模サンパイ計画があることを知った。この計画は平成18年7月に事前虚偽書が県に出された。それから6年が経過したが、事前協議が行われてきた。地元の安中市にも情報が県からきて、県と市と事業者の間で手続が進められた。業者は設置許可申請を県に出す。本来は国が許認可をするが法律により県が許認可をする。それが事前協議。安中市も平成18年7月に連絡を受けているので計画内容は知っている。県と市で意見書のやり取りが何回も行われている。安中市の意見は、本来は地元住民を代表して、地元意見をまとめて出すというのが基本的な意見書だが、安中市の場合は庁内協議で廃棄物処分場は新規を認めないので市は反対、というたった一行の意見書を県に何度も出してきたという経緯がある。地元住民がどのような意見を持っているのか、どういう不安を持っているのかという情報は県の方に伝わっていなかったのが実情。その後合意書の取得手続きがあったが、平成22年6月に、地元の高橋区長の時に反対署名1915名を集め、知事室で副知事が受理した。そのとき、県は初めて地元で反対があるのかと知った。それ以降、県と皆さんの間の情報共有に尽くしてきた。その結果、ようやく県も情報を出すようになって来た。事前協議が終了したら今度は設置許可の本申請に入る。こうなるとトントンと進んで着工に至ってしまう。今年になり事前協議が最終段階にあるということを今年に入って県から言われた。区長に相談してどうしようかと話した。それまでは市長が反対しているし(大丈夫だろう)、ということで情報錯そうもあったが、1月末に県から“事前協議も最終段階ですよ。反対署名があったのでお知らせする”ということだった。なんとか住民の皆さんに知らせる必要があるため、出前講座の開催を3月10日に企画していただいた。私も皆さんの声を聞いて、しっかりと県に対して届けていきたい」と語りました。
次に3月10日以降、各団体の行動について参加者の共通認識にするため、まず岩野谷区長会の取り組みについて、代表区長から説明がありました。「区長会としては、3月10日は少し早いと思ったが実態を知って、これは大変だと思った。高橋前区長会長のときに署名活動を提案したのも私だったが、市長が反対しているからということで動きが緩んだ。その後、いろいろ動きがありこれは大変だとして、書類上は12月23日で終了し、あとは、いろいろ法律関係で、水利権について白紙で調べるだけという状況だった。おりから郷原のサンパイ中間処理施設問題もあり、その後、出前講座を受けてすぐ市長に意見書を提出した。そこに反対という文章があるのでそれを読んで市長に出した。その後市長から区長会に返事が来た。その後、個人的に市長に意見した。このような県への意見書ではだめですよと。市長は市子連総会時に、私に“あれじゃ、賛成と同じだ”などと発言があり驚いたこともある。県議や市議とも相談し、討議を重ね、いずれにしても今後よい成果を聞かせてもらいたい為に、住民の熱い熱意を背景にいろいろ区長会で話をしつつ現在に至っている。本日は全体の意見交換で要約を聞きつつ区長会としても詰めていきたいと思う」と述べました。
続いて前区長会長で、岩野谷みんなの命と自然を守る会の会長から挨拶がありました。「私がやった以降はいま依田会長から説明があったが、それ以前について説明したい。平成21年5月19日に県に行って大谷のサンパイ場計画の事情を聞きに行った。その後同年12月9日に高崎市労使会館でみたけ町の元町長の後援会があり、講演後私から岩野谷地区の処分場問題について現況発表をした。その後、署名運動を始めることになり、平成22年2月に着手した。6月7日に締め切りだったが、1915名の反対署名を提出できた。当時の地元の成人人口の実に72.5%に上った。知事が不在だったため、稲山副知事に渡した。新聞社5社、群馬TVが取材に来た。同年6月8日に報道された。同12月21日に学習会を開催し、集まったカンパで建設反対の旗を設置することで決定。平成23年に2回に分けて旗を立て、平成24年1月22日には隣の高崎市吉井町奥平地区の観音山雁行川流域について学習会に参加し、大谷地区のサンパイ問題について現状発表を行った」と説明。
その後、大谷地区の水利組合の幹部から報告がありました。副会長からは「新山地区に管理型の13品目が捨てられる最終処分場計画を聞いて驚いた。大谷の水利組合としては、事前協議規定の第22条ロとして放流地点の下流概ね500m以内の農業者等の利用者、または当該事業者の団体の長の合意が必要だということが求められている。これを調べたところ、業者は全員から合意をもらっていると言うが、実際にはまだ合意していない人がいることがわかり、業者のいうことは事実誤認。または当該団体の長の印鑑だが、平成21年1月13日に、当時の組合長が環境資源と、組合員の同意を得ずに同意書を作成して、そしてその合意書を既に県に提出していたことが判明。そのため、今年の2月21日、この合意書を無効とする組合員、全会員43名のうち39名の署名捺印入り要請書を県庁で、茂木県議の紹介で今井前組合長から、山口環境森林部長に手渡し、水利組合の合意書の無効化をお願いした。そして3月10日の県の出前講座に至った。その後、今月の5月6日、この水利組合の臨時総会を上組公会堂で開催し、そこで元組合長が環境資源と交わした合意書の撤回を環境資源に申し入れることになった。そして、元組合長も合意撤回を申し入れてくれということで、元組合長が環境資源に出向いたところ、“これまで使った費用、3億5千万円を支払えば撤回してやる”と言われて帰って来た。それで5月中旬、水利権の合意書の撤回を環境資源に申し入れるに当たり、組合員43名中39名の署名捺印をもらい、5月21日(月)、環境資源の処分場の反対陳情書を、高橋市議の紹介で、我々組合長はじめ8名で市役所に出向き、現組合長から奥原市議会議長へ反対陳情書を手渡した。そして、同じ日に、地元岩井の碓氷川の橋のところにある環境資源の事務所に8名が乗り込み、同社の鬼形社長に水利権の合意撤回の文書を手渡そうとしてが受け取りを拒否された。そのため、その内容を口頭で説明してきた。文書は受け取ってもらえなかった。そのような実情で、今後、なんらかの手段を尽くして、撤回文書を渡すことを考えている最中である」と発表。
司会の市議によれば、6月5日から市議会が始まるのでその中で審議されることになっているとのことです。
その後、大谷の長坂地区の有志グループとして行動を起こしている代表者から「3月10日の県の出前講座に参加し、岩野谷地区の大勢の人たちがサンパイ建設計画に反対しているという事実を知り、建設予定地に済む我々が行動を起こすべきだということに気付いた。まずは3月10日の出前講座の内容について地元住民に知ってもらうことからスタートした。そこで、住民は“こんなに大規模なものとは知らなかった。最初の説明会とは全く違う。反対するにはどうすればよいか”と多くの意見が出た。これまで地元ではほかにの何か所か計画が出ていて、どの計画に判をおしたか、また親が押したようだが今は世代交代していて反対の立場で、昔の判で押されて今の世代は反対ということ。それで反対するにはどうすればよいか、といろいろ意見が出た。今まで当地区はサンパイに狙われやすいところだった。これからは変えていきたい。そして今までのことは全て白紙にして、これからのことを考えようと言うことになった。まずは賛成か反対かを考えた。協議の結果、反対して同意撤回書を皆に書いてもらった。3月19日に県議、市議が同行して、40名の同意撤回書を県に届けた。地元も行動しているということを皆さんにも知ってもらいたいと思い意見を述べさせていただいた。よろしくお願いしたい」と力強い言葉がありました。
続いて岩野谷の水と緑を守る会の会長で、県の市民オンブズマンの当会代表から発言があった。「このような場で、サンパイ場の件でコメントさせていただけるということについて感謝申し上げる。岩野谷には既にサイボウ環境の処分場がある。これは平成3年から安定5品目でサンパイ計画だったが、平成5年から一般廃棄物処分場としてスタートした。今日は同志も見えているが、たった3名でこの問題について取り組んできた。10年以上前には地区に何度もチラシを配布したこともあるが、覚えていない人もいるかもしれない。なぜこの問題にとりくんだかというと、隣の上奥平地区の関係者にも聞いたが、“ひとつできると、つるべ式にどんどんできてしまう。だから最初の計画は絶対に阻止する”という気持ちで取り組んできた。平成7年のタゴ事件発生のころに事前協議にはいり、平成11年頃事前協議が終わり、その後、(行政相手に事業の差止めのため)徹底的に裁判を起こし、計15件ほど最高裁までたたかったが、全て敗訴した。それと公文書偽造作成行使についても県警、検察に告発したが、結局司直のゆがんだ判断に阻まれ、これもカラ振りに終わった。そして平成19年4月にサイボウがご存じの通り営業を開始した。こちらは一般廃棄物という触れ込みの処分場だが、しかし入れているものについて誰も知らないのでサンパイでもイッパイでもわけのわからない状態にある。今回、今の話だと、平成18年7月に事前協議が出たという。この時期はサイボウの我々の最後の裁判の決着と符合する。業者はこのサイボウの経緯をみて、事前協議を出した。それから、私のブログにも詳述しているが、今年の4月14日、私は長坂の公民館に行ってどんな連中がこの計画を推進しているのか、顔を出した。見覚えのある顔にびっくりした。サイボウの処分場で暗躍した人物がそこにいたからだ。サイボウの計画で、中核的にありとあらゆる手段を講じて推進した御仁。詳しくは私のブログを見てほしい。結果だけいうと、国も県も市も、処分場を作らせたがっている。この話は、この中の参加者の誰かが当然このあと業者に通報するだろうが、“処分場の手続は前例主義だから、それに則ってやれば県は絶対にノーと言えない”と私の前でその人物は言った。先日、県に行った時、サイボウの残土の件で報告したが、その際、2番目のサンパイ場、これはイッパイとサンパイが一緒になっている。行ってみればサイボウと同じやり方。その時、県の担当者は、私の前でこういった。“行政手続法がある。外形的に書類が整っていれば、決められた期限内に通さざるを得ない”と言っている。我々は3人で平成2年から平成19年まで頑張った。同志もここに居る。しかし、2番目の計画は村中かかってもなかなか止められない。最初止めるにはたった3名で14年要した。手続の時間を伸ばせた。しかし、一旦最初の(処分場)が、できるめどが立てば、業者が全部見ているから、つるべ式に、芋づる式に次から次に出てくるわけだ。今回の皆さまの努力には本当に関心する。これがなぜ最初の計画の時に、このような行動がとれなかったのか、つくづく残念でならない。しかし、“ればたら”の話をしても仕方がない。当会はこれまで培った経験知見を惜しみなく皆さんに伝えるつもりなのでよろしく」と述べた。
その後、参加団体の紹介として、岩野谷の環自連の会長が「先程大谷の人が言った通り親のときは賛成で、現在の世代が反対というのは事実だ。ある委員がいうには、“もう遅いですよ”と言われたことがある。前もみないろいろ反対したがだめだった。いま、小川さんがやっていた平成7、8年ごろがその時だったかなと思う。それでも、今の子どもがそういう考えなので、変えていければと思うので協力したい」と挨拶した。
そのあと、岩子連会長が「私もできれば将来の子どもたちのことを考えており、未来を考えればぜひ反対していただきたい。そのためには岩子連としても最大限協力したい」と述べた。
続いて岩野谷の民生委員会長が「私も反対署名をした。こういう場は初めてだが、乳幼児委託訪問から高齢者までネットワークがある。この経験を生かして、もしお手伝いできるようであれば協力させていただきたい」と挨拶。
次に、岩野谷の青少推の会長で、岩野谷のみんなの命と自然を守る会の事務局担当から「やはり岩野谷の自然をきちんと守り子どもたちがその中で遊べる環境作りが我々の責任だと思う。頑張ってゆくのでよろしく」と挨拶。
岩井地区の水利組合の清水代表が参加予定だったが体調不良のため、「処分場計画に反対の立場なので、みなさんによろしく」とのメッセージが紹介されました。
次に、岩野谷地区の農業委員から「岩井川流域の農業を守るためには、いろいろな負担材料のあるサンパイ場には絶対反対。農業委員会としても反対の立場なので皆さんによろしく」とのメッセージが寄せられました。
この後、参加者の間で熱心な討議が続けられた。今後、どう行動して、住民の意思を貫いていくかということが重要なので、初めにこの点について協議を行いました。
区長会長からは、「最も大事なのは水。サイボウの件もあるが、どこまで踏ん張れるか。自分一人ではどうにもならないが、踏ん張れるだけは踏ん張る。大谷の水の源に計画されたサンパイ場から出る汚染水は、大谷をはじめ岩井の田んぼにも影響がでる。なんとしても水を守るため、これを阻止したい。連携し、いいアイデアを出してほしい。意見書などを出したい。それには市議、県議に役所に日参いただくことになろう。まず水の問題。皆さんの智恵を借りたい」と発言がありました。
区長会長の発言の中の「意見書」について、県議から「事前協議は県と業者と市にも意見を聞きながら進められる。この中に、市が住民の意見をまとめて、生活環境の保全上、どのような不安や疑問や心配があるかということを意見として出せる。市が住民の意見をまとめて出すのが意見書。これまで市が県に出した意見書はたった1行しかない。県に確認したところ、市が“反対”というだけの意見ではなく、生活環境面で住民の意見を市が吸い上げて届けるのが、市が出せる意見書なので、それを出すように県から働きかけをしている。しかし市からは、同じように1行しか意見を出していないという経過がある。3月10日の説明会の後、その時市長から説明会のやり取りのなかで“どういうことなんだ?”という質問が来たということで、その打合せを5月8日に、市長に返事しなければいけないということで、参加した市会議員4名と県議2名(岩井県議は欠席したが事前コメントあり)で打ち合わせたが、最後に住民の意見が出せないだろうかという意見が出た。それを代表区長から県に確認してほしいと言われて、確認したところ、事前協議は最終段階だが、住民の意見を受け入れるので意見があれば出してほしいということを区長に伝えてほしい、という経緯がある。これが、本日の協議の背景にあると思う。これから住民の意見という形で、県は事前協議の中で、これを受けると言っている。ぜひ住民の意見を県に出してもらいたいと思う。同時に、意見書は事前協議の中で出せる。それに何らかの対応を採るということで一つのステップとなるため、この意見への対応ができれば事前協議が終わるということにもなる。岩野谷の住民の意見を出すことは必要。ただし、それにより、手続の過程が進むという可能性もあり、両刃の剣とも言えるため、慎重に対応したい」と補足説明がありました。
その後、この件で討議が続きましたが、結局、意見書を出すことが参加者の総意として確認されました。意見書を出せる範囲について、参加者から質問が出ました。これについて、生活環境の影響する範囲ということで、地域でいうと、岩野谷地区ということで了解されました。
また、安中市が群馬県からの要請に対して、出してきた意見の実態について報告がありました。それによると、条例第10条の審査項目として、県の土地利用対策会議(庁内38課で構成)で討議するために必要な次の項目が必要だと言うことです。
①災害発生のおそれはないか?
②土地の利用状況上、開発は可能か?
③公共施設・公益的施設の整備の見直しはあるか?
④用水確保の見通しはあるか?
⑤公害は防止できるか?
⑥地域への貢献度はどうか?
⑦開発事業者の資力、信用は担保されているか?
⑧保護すべき文化財は存在しないか?
これらの項目について、本来、安中市は現地を調査し、地元住民の意見をまとめ、県に対して意見を言うことができるわけです。しかし、このような見地からの意見を県は安中市へ求めたが回答がなかったというから呆れてしまいます。
実際に、安中市の岡田市長が県に上げた意見書は延べ5回に亘りますが、いずれも「市の基本方針から、最終処分場の構想は認めることができない」というたった1行の簡単な内容だけでした。これでは、県も安中市の住民の意見が分からない、と言い張れるわけです。一方、業者側はほくそ笑んでいることでしょう。
■一方、大規模土地開発事業の規制等に関する条例による事前協議では、次の報告が県議からありました。それによると、「事業者が廃棄物処理規定による地検者等の合意を取得したことから、平成21年12月に事前協議を受理して手続が開始された。その後役2年間に亘り、土地利用対策会議(庁内38課で構成)で審査し、計4階の指摘事項の通知とそれに対する事業者からの回答書の提出が行われた。また、安中市長をはじめとする関係市町村に意見照会をしたが、安中市長は当初から一貫して「市の基本方針から最終処分場の構想は認めることができない」という意見を出している。この安中市長の意見は、条例に規定する項目に関しての意見ではないため、平成22年9月、安中市長に対して県から再度意見照会を行ったが、安中市長の意見は“事業そのもの”に反対ということだけで、条例の審査項目に対して回答していなかった。現在、土地量対策会議からの指摘事項もなくなり、大規模土地開発事業審査会に諮問できる段階となっている」ということです。
この件については、別紙の参考資料にさらに詳しい経緯が示してあります。
その他、マスコミの活用、新山の溜池及びその周辺に本格的な看板を設置したり、岩井川沿いで自然環境のよさをアピールするイベントの開催、テレビ局への取材申し入れなど、さまざまな提案や提言が出されました。
また、大人だけではなく、今後影響をずっと受けることにもなりかねない子どもたちからの素直な意見書も出せるのかという意見があり、これも採択されました。
そして、まずは区長会で意見書を出すと共に、今日の参加者した方々はもとより、参加できなかった住民の意見も区長会がとりまとめて、行政に届けることを確認し、最後に、参加者一同で、一致協力し、団結して、地域に降りかかった未曽有の危機に対して断固として排除してゆくように、区長会を中心に対応してゆくことが決議されました。
【ひらく会・情報部】