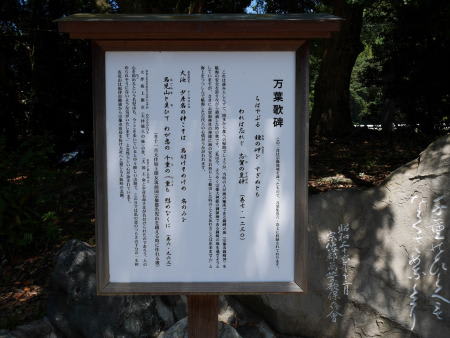ゆいレール 「 那覇空港駅 」


以前、那覇空港駅から首里駅までの往復を掲載していましたが、
動画が中国語に文字化けしたり、掲載できなくなっているので、
再度、那覇空港駅から首里駅往復を掲載します。
沖縄民謡をアレンジした車内音楽をお楽しみ下さい。
那覇空港駅から赤嶺駅の間は、航空自衛隊那覇基地があり、
道路沿いにはレンタカー屋さんが点在する。
那覇空港が出発点となる 「 ゆいレール 」 の
那覇空港駅 ⇒ 赤嶺駅 間の車内メロディーは、
「 花の風車 ( はなぬかじまやー ) 」 である。
『 花の風車 』
花ぬ風車や 風連りてぃ廻る
チントゥン テントゥン マンチンタン ウネタリ シュヌメー ウミカキレー
我んや友達連りてぃ 今どぅ我ね戻る
チントゥン テントゥン マンチンタン ウネタリ シュヌメー ウミカキレー
垣ぬ葉ぬ露や あがい太陽 ( てぃだ ) 待ちゅる
チントゥン テントゥン マンチンタン ウネタリ シュヌメー ウミカキレー
( 意味 )
花の風車は 風を連れて廻る
私は友達を連れて 今戻って来ました
石垣の葉に付いた露は 太陽が昇るのを待っています
風車 ( カジマヤー ) というのは、アダンの葉で作った玩具で、
花模様にぐるぐる回る風車を風に向けて遊びながら唄う。
カジマヤーは風車の字をあてているが、本来は〈風に舞うもの〉の意味である。
古くは、沖永良部では 「 かじゃもーやー 」 と呼んでいた。
沖縄では、十字路のことを 「 カジマヤー 」 というが、
この風車も十字形をしている。
普段は、沖縄の童唄であるが、沖縄では97歳の生誕祝いをカジマヤーと呼び、
風車をかざし祝座で唄い踊るならわしがある。
最近では車によるパレードもあり、
童心にかえり新しい人生の出発も込めて地域あげて祝っている。
伊江島の 「 門口池小堀 」 と、
沖永良部島の 「 余多打原 」 は異名同曲といわれている。