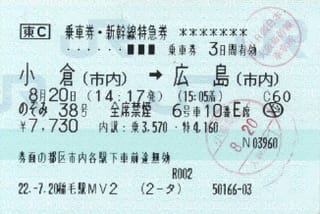6.リベンジ-小野田線本山支線の123系と残念なEF30
昨日の木次線の完乗と共に、
去年のリベンジとして今回どうしても挑戦したかったのが、
小野田線本山氏支線の完乗と終点の長門本山の駅取材である。
小野田線は宇部線居能から山陽本線小野田までと、
雀田から分岐し長門本山までを結ぶ支線の13.9kmの地方交通線である。
雀田と長門本山を結ぶ支線は本山支線と呼ばれ、
朝晩にしか列車の設定のないため長門本山はある意味、秘境駅の一つとなっている。
雀田を06:59に出て長門本山に07:04に到着、07:10に出て07:15に雀田に到着、
07:25に折り返して07:30に再び長門本山に到着する。
この列車は宇部新川行きとなり、長門本山に到着する列車は16:36着までない。
去年来た時には雀田からの列車がなかったため、
雀田から長門本山までは初めての体験となる。
1両編成の123系は荷物車を改造したため、
前後のドアの間にロングシートが設置されたシンプルな造りである。
小野田から123系に乗り、雀田で別の123系に乗り換えて終点まで行く。
長門本山は単式ホームに簡単な屋根の着いたベンチ、それに便所という、
最低限の設備の無人駅である。

本山支線は単線で距離が短いため交換駅もなく、
1両の列車が雀田から往復するだけである。
長門本山で乗ってきた列車を見送り、付近を散策して、
07:30に再び123系が到着するのを待ってこれに乗り込む。
この列車はそのまま宇部新川まで行き、ここで駅取材する。
更に宇部新川から宇部岬行きの列車に乗り込み、終点で駅取材。
この列車は105系2両と123系1両が連結されていた。
宇部岬から新山口まで行き、ここで山陽本線の下り列車を待つことにする。
遠くでは快速「SLやまぐち号」に充当される蒸気機関車も見えていた。
今回、小野田から雀田、雀田から長門本山、
そして折り返して居能経由で宇部新川まで行き、
更にその先宇部線を新山口まで行ったこととなり、
小野田線完乗を達成し、宇部線は居能-新山口間を乗車したこととなった。
新山口からは117系で下関まで行き、ここから415系に乗り換えて門司へ。
門司から門司港に行くために813系に乗り換えるが、
この時気動車使用の観光列車「みすず潮騒号」を見掛けるが撮影は出来ず。
門司駅から徒歩圏内にある平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線の九州鉄道記念館に行き、
ここでやまぎんレトロラインひとり2回きっぷ500円を購入する。
これは一人で1日2回まで乗ることの出来るきっぷで、
結果的に往復券として利用で来る。
平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線はかつての使われていた貨物線を流用した観光鉄道で、
無蓋車を改造し、島原鉄道で活躍していた2両のトロッコ列車の前後に、
南阿蘇鉄道でトロッコ列車に使用されていたディーゼル機関車を連結した列車で、
機関車を前後に連結することで機回りの必要がなく、
単線区間を原則的に前後するだけの運行である。
今回は子の観光列車に乗ることが目的というよりも、
終点の関門海峡めかりに隣接する和布刈公園の静態保存されている、
EF30型電気機関車1号機とオハフ33形488号客車が目当てであった。
しかし実際のEF30型は静態保存というには劣化がひどく、
またほとんど手入れしていないために、
電気機関車の形をしたアルミニウムの塊がそこに置かれているという感じで、
かつて関門トンネルで活躍した名機としての威厳は既にない。

鉄道にあまり関心のない人たちによって管理されると、こういうことになるのだろう。
それはそれで仕方のないことかも知れないが、もう少し何とかならないものだろうか。
オハフ33形は車内を休憩室、喫茶室として利用しているようである。
因みに「和布刈」は「めかり」と読む。
ここでこれらの保存車両を取材し、
再び平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線で九州鉄道記念館まで戻る。