2021年5月4日(火)
わが所沢市は5月12日(水)まで、「まん延防止等重点措置」対象の埼玉県内15市
のひとつで、不要不急の外出自粛が求められているが、今日はゴールデンウィーク最後の
好天の予報なので、3密とは縁の無さそうな隣の狭山市内へのウオーキングに出かけた。
西武新宿線の下り電車で新狭山駅に下車し、9時52分に北口をスタートする。


駅前から真っ直ぐ北西に伸びる「すかいロード」を進み、交通量の多い国道16号線に
出て北東へ。

川越狭山工業団地の西端にある、ロッテの工場前から延びる細いY字路に入る。
すぐ近くの逆Y字路の入口に「大山道標」と呼ばれる石造りの道標がある。

左側には「左大山道」、右側面は「はんのう子ノごんげんみち(飯能 子ノ権現道)」、
正面には「南無阿弥陀仏」と刻まれていて、寛政5(1793)年の建立という。
ちなみに大山とは、相模国(神奈川県伊勢原市)の大山(おおやま)のこと。大山は古
代から信仰の対象となっていて、「大山詣り」として江戸の人口が100万人の時代に年
間20万人もの参拝者が訪れたと言われているようだ。
武甲山

折り返して進む飯能方面への道は「赤間川通り」と呼び、少し進むと右手の展望が開け、
秩父のシンボル武甲山↑、さらに右手↓には外秩父の堂平山や笠山などが望まれる。
堂平山 笠山

少し下り道となり、背後の新緑の大木が見えたところに小さな石仏が立っていた。


「いぼ神様」と呼ぶ三面六臂(さんめんろっぴ)の馬頭観音像で、安永8(1779)
年の造立のよう。傍らにその説明パネルがある。

すぐ先の交差点際高台には、八雲神社が祭られていた。

八雲神社の創立は正徳5(1715)年で、当時は牛頭(ごず)天王を祭っていたよう。
明治5(1872)年に近隣の5社を合祀して八雲神社と改め、村社になったという。
道路を挟んだ南側は、尖塔が目につく西武学園文理小である。

その先、赤間川通りは三面コンクリート張りの赤間川に沿って南西へと進む。

次の十字路の手前、南東側台地上は奥富神社である。

明治初期の西南の役から日清及び日露戦争、大正年間の青島攻略やシベリア出兵、満州
事変、上海事変、太平洋戦争までの戦において、奥富から出征して戦死された英霊100
余柱を祭る神社で、社殿は昭和28(1953)年5月に完成したようだ。

境内のモミジなどの新緑が気持ち良い。
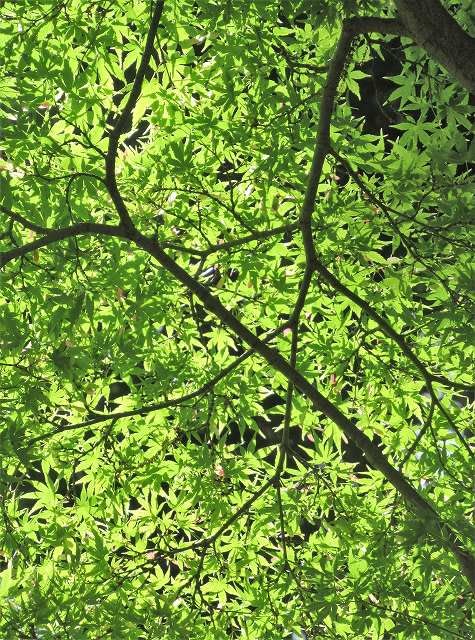
少し進んでから思い出し、そばの西方(にしかた)自治会館まで戻って背後に回ると、
「西方の石仏群」と呼ぶ古い石仏が10体余り並んでいた。

一番大きくて目につく如意輪観音は正徳6(1716)年の造立。右手でほお杖をつく
姿から歯痛に効くとして信仰されているようだが、本来は六道にあって苦しむ衆生を救う
仏らしい。

そばの交差点で赤間川通りに分かれて北西に少しで、西方集落の中心にある広福寺へ。

独特の山門は2階に鐘楼を持つ竜宮造りの鐘楼門。完成は文化2(1805)年とか。
幕末には、尊皇攘夷に身を捧げた清川八郎など多くの勤王の志士たちが、この山門をく
ぐったとも言われているという。

山門を入った右側には紅梅の古木↑があり、徳川三代将軍家光が鷹狩りの際の休息の折、
その美しさを賞賛して「御詞乃梅」(おことばのうめ)と言われ、そばの井戸は家光にお
茶を入れたことから「梅ノ井」といわれたと伝えられているよう。



境内は緑が豊富でシャクナゲも咲き、本堂南東側一角では回遊する池にコイが泳ぐ。



墓地に抜ける西側には不動明王、釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩など13仏が並ぶ。


借用したトイレの前には元禄年間(1688~1704)建立の宝篋印塔(ほうきょう
いんとう)が、本堂前には武蔵国十三仏霊場のお地蔵さんが立っていた。

道路を挟んだ西側は奥富小で、門の横に二宮金次郎像が目に入る。

奥富小の南から西側一帯は広々とした田園地帯で、正門前からその中を南南西に延びる
幅広い通りを進む。

耕されてはいるがまだ水入り前の田んぼが多い。その一角の小麦畑では、もう穂がいっ
ぱい延びていた。


大岳山

西側には奥多摩から奥武蔵、外秩父にかけての山並みが望まれ、奥多摩の大岳山、秩父
の武甲山、外秩父の堂平山や笠山などが認識できた。
武甲山

堂平山 笠山

道の中ほどを過ぎて2本の高圧送電線が横切り、道路が右カーブする辺りには色鮮やか
なツツジが咲いていた。

右カーブしてすぐの右手、豊富な鎮守の森には梅宮神社が祭られている。

梅宮神社は、平安時代に嵯峨天皇の第二皇子で武蔵守の源朝臣が五穀豊穣を願い、承和
5(838)年に京都の梅宮神社から分社されたという古社。

2月に開催される「梅宮神社の甘酒祭り」は、県指定の無形民俗文化財のよう。
京都の梅宮神社から分社された頃から始まったと伝えられ、関東には珍しい頭屋制と呼
ぶ饗宴形式の祭りで、2月10日の宵宮祭りと翌11日の大祭の儀式が行われるという。

境内中央の拝殿は開け放たれていて、天井や背後などが望まれる。正面上部に並ぶ古い
掲額からは、当社の歴史の一端がしのばれる。




木彫に飾られた本殿は覆い屋で守られ、境内は豊富な新緑に覆われていた。



一の鳥居の横では明日の端午の節句を前に、こいのぼりが風をはらんで泳いている。


南側から望む鎮守の森。 〈続く〉
 アウトドアランキング
アウトドアランキング

にほんブログ村
わが所沢市は5月12日(水)まで、「まん延防止等重点措置」対象の埼玉県内15市
のひとつで、不要不急の外出自粛が求められているが、今日はゴールデンウィーク最後の
好天の予報なので、3密とは縁の無さそうな隣の狭山市内へのウオーキングに出かけた。
西武新宿線の下り電車で新狭山駅に下車し、9時52分に北口をスタートする。


駅前から真っ直ぐ北西に伸びる「すかいロード」を進み、交通量の多い国道16号線に
出て北東へ。

川越狭山工業団地の西端にある、ロッテの工場前から延びる細いY字路に入る。
すぐ近くの逆Y字路の入口に「大山道標」と呼ばれる石造りの道標がある。

左側には「左大山道」、右側面は「はんのう子ノごんげんみち(飯能 子ノ権現道)」、
正面には「南無阿弥陀仏」と刻まれていて、寛政5(1793)年の建立という。
ちなみに大山とは、相模国(神奈川県伊勢原市)の大山(おおやま)のこと。大山は古
代から信仰の対象となっていて、「大山詣り」として江戸の人口が100万人の時代に年
間20万人もの参拝者が訪れたと言われているようだ。
武甲山

折り返して進む飯能方面への道は「赤間川通り」と呼び、少し進むと右手の展望が開け、
秩父のシンボル武甲山↑、さらに右手↓には外秩父の堂平山や笠山などが望まれる。
堂平山 笠山

少し下り道となり、背後の新緑の大木が見えたところに小さな石仏が立っていた。


「いぼ神様」と呼ぶ三面六臂(さんめんろっぴ)の馬頭観音像で、安永8(1779)
年の造立のよう。傍らにその説明パネルがある。

すぐ先の交差点際高台には、八雲神社が祭られていた。

八雲神社の創立は正徳5(1715)年で、当時は牛頭(ごず)天王を祭っていたよう。
明治5(1872)年に近隣の5社を合祀して八雲神社と改め、村社になったという。
道路を挟んだ南側は、尖塔が目につく西武学園文理小である。

その先、赤間川通りは三面コンクリート張りの赤間川に沿って南西へと進む。

次の十字路の手前、南東側台地上は奥富神社である。

明治初期の西南の役から日清及び日露戦争、大正年間の青島攻略やシベリア出兵、満州
事変、上海事変、太平洋戦争までの戦において、奥富から出征して戦死された英霊100
余柱を祭る神社で、社殿は昭和28(1953)年5月に完成したようだ。

境内のモミジなどの新緑が気持ち良い。
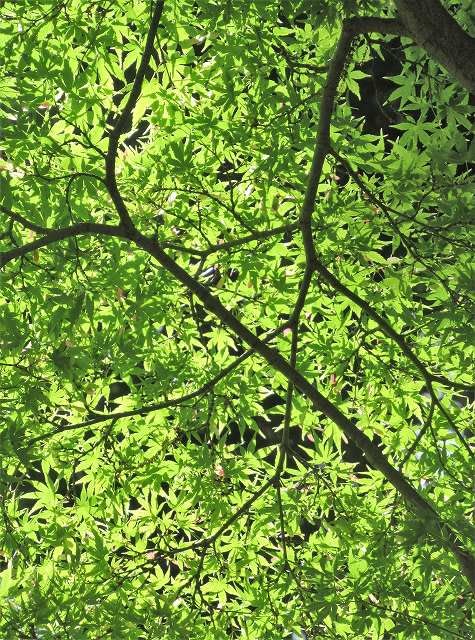
少し進んでから思い出し、そばの西方(にしかた)自治会館まで戻って背後に回ると、
「西方の石仏群」と呼ぶ古い石仏が10体余り並んでいた。

一番大きくて目につく如意輪観音は正徳6(1716)年の造立。右手でほお杖をつく
姿から歯痛に効くとして信仰されているようだが、本来は六道にあって苦しむ衆生を救う
仏らしい。

そばの交差点で赤間川通りに分かれて北西に少しで、西方集落の中心にある広福寺へ。

独特の山門は2階に鐘楼を持つ竜宮造りの鐘楼門。完成は文化2(1805)年とか。
幕末には、尊皇攘夷に身を捧げた清川八郎など多くの勤王の志士たちが、この山門をく
ぐったとも言われているという。

山門を入った右側には紅梅の古木↑があり、徳川三代将軍家光が鷹狩りの際の休息の折、
その美しさを賞賛して「御詞乃梅」(おことばのうめ)と言われ、そばの井戸は家光にお
茶を入れたことから「梅ノ井」といわれたと伝えられているよう。



境内は緑が豊富でシャクナゲも咲き、本堂南東側一角では回遊する池にコイが泳ぐ。



墓地に抜ける西側には不動明王、釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩など13仏が並ぶ。


借用したトイレの前には元禄年間(1688~1704)建立の宝篋印塔(ほうきょう
いんとう)が、本堂前には武蔵国十三仏霊場のお地蔵さんが立っていた。

道路を挟んだ西側は奥富小で、門の横に二宮金次郎像が目に入る。

奥富小の南から西側一帯は広々とした田園地帯で、正門前からその中を南南西に延びる
幅広い通りを進む。

耕されてはいるがまだ水入り前の田んぼが多い。その一角の小麦畑では、もう穂がいっ
ぱい延びていた。


大岳山

西側には奥多摩から奥武蔵、外秩父にかけての山並みが望まれ、奥多摩の大岳山、秩父
の武甲山、外秩父の堂平山や笠山などが認識できた。
武甲山

堂平山 笠山

道の中ほどを過ぎて2本の高圧送電線が横切り、道路が右カーブする辺りには色鮮やか
なツツジが咲いていた。

右カーブしてすぐの右手、豊富な鎮守の森には梅宮神社が祭られている。

梅宮神社は、平安時代に嵯峨天皇の第二皇子で武蔵守の源朝臣が五穀豊穣を願い、承和
5(838)年に京都の梅宮神社から分社されたという古社。

2月に開催される「梅宮神社の甘酒祭り」は、県指定の無形民俗文化財のよう。
京都の梅宮神社から分社された頃から始まったと伝えられ、関東には珍しい頭屋制と呼
ぶ饗宴形式の祭りで、2月10日の宵宮祭りと翌11日の大祭の儀式が行われるという。

境内中央の拝殿は開け放たれていて、天井や背後などが望まれる。正面上部に並ぶ古い
掲額からは、当社の歴史の一端がしのばれる。




木彫に飾られた本殿は覆い屋で守られ、境内は豊富な新緑に覆われていた。



一の鳥居の横では明日の端午の節句を前に、こいのぼりが風をはらんで泳いている。


南側から望む鎮守の森。 〈続く〉
にほんブログ村














